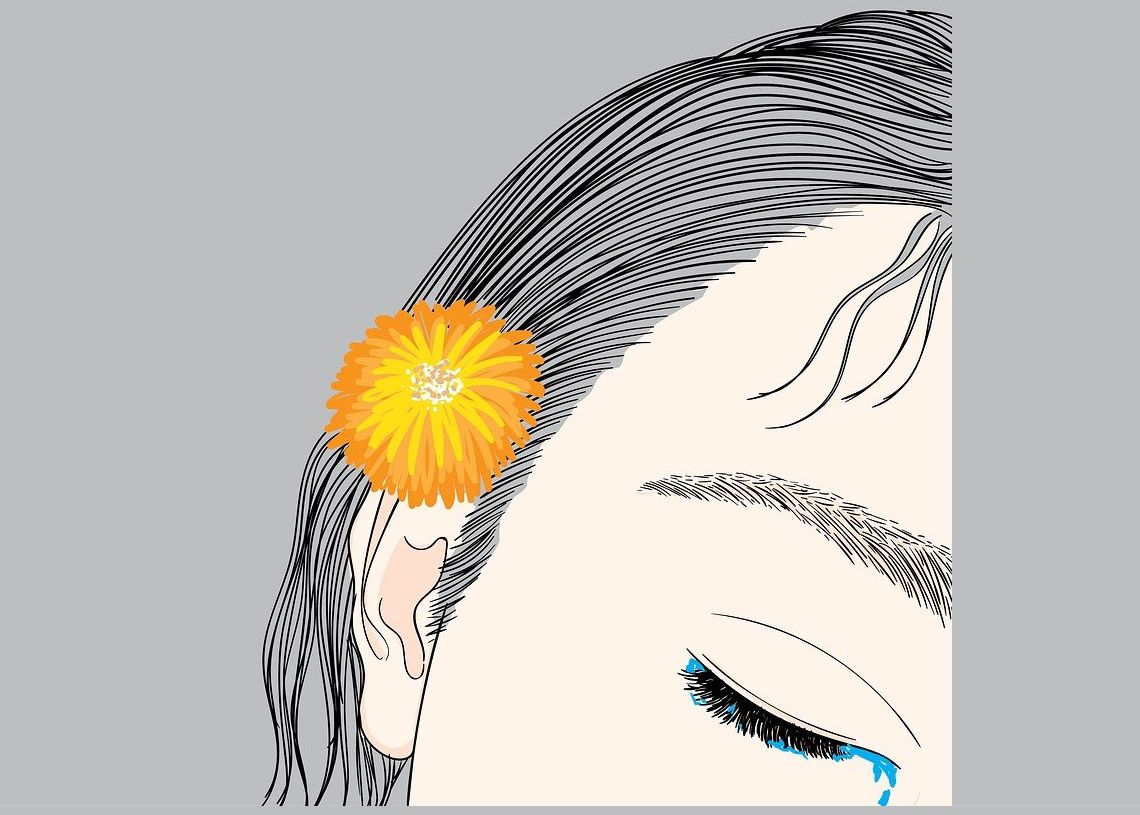
I knew
第一幕:エキストラ1
私はいつも誰かの人生の脇役だった。
沢山いる仲間達と、バカみたいな話でバカになって大笑いする。誰も私の中身なんて見ていないし、周りの人間はみーんな、自分にしかキョーミがない。でもそれが普通。私も周りの人間にキョーミはないし、その人の中身なんてどうでもいい。みんながみんな、自分が主役だと思っているけど、実際は誰かの脇役なのだ。"親友"だという子の恋を陰で嘲笑してる隣のこの子も、煙草を吹かしながら彼氏の愚痴を言ってるあの子も、ぜーんぶ誰かの人生の脇役に過ぎない。
でもそんな中でも最初から主役に生まれついた人はいる。
誰からも愛されて、周りを圧倒的に支配出来る人。
そういう人の恋人になれば、私も主役になれる気がしてた。
そんな映画やドラマの中でしか存在しないような人はいないと思っていたけど、主役級の男は本当に存在していると知ったのは、友達と遊びに行ったクラブだった。
彼に彼女がいることは知っていたし、それでもいいと言い寄ったのは私の方からだ。
いつものクラブに顔を出せば、そこに彼の姿があった。
灰谷竜胆――。
この六本木で夜な夜な遊んでる人間なら、彼のことを知らない人はいないはずだ。
このクラブのオーナーである蘭さんと、弟の竜胆。この街は彼ら灰谷兄弟のものだから。
存在を知った時からずっと憧れていた。美しいけれど、冷たい印象のする蘭さんよりも、竜胆の方が人懐っこくて話しやすい。だから少しずつ、彼に近づいた。
最初は挨拶から。そして次はさり気なく彼の好きな音楽の話を振る。
「このアーティストの〇〇って曲を探してて…」
「あーそれならオレ、持ってるわ。貸してやろーか?」
「え、嘘。嬉しい!」
「ここのバーテンに預けとくわ」
最初はこんなやり取りと距離感から始まった。
次はお礼と称してお酒をおごり、一緒に飲む時間を作ってもらう。ここまで来たら、後は簡単だった。お互い泥酔するまで飲み明かして、そういう空気を私は作った。お酒をわざと自分の服に引っ掛け、竜胆に介抱させる。その後、初めて関係を持ったのは彼のクラブ内にあるスタッフ用の休憩所だった。
ドアのカギをかけたけど、スタッフが戻って来たらおかしいと思われる。いつ誰が来るかも分からないスリルを、彼は楽しんでるようだった。
あれから三か月。未だに私は竜胆と関係を続けてる。
「やっぱり、ここにいたー」
私と彼が最初に関係を持った休憩所へ顔を出すと、竜胆が気怠げな目を向けてきた。竜胆がここにいるのはクラブのスタッフに確認済み。いつも一緒の蘭さんが、珍しく今夜は来ていないことも。
「おー。来てたん?」
「さっきね。私にもお水ちょーだい」
ソファに凭れてミネラルウォーターを飲んでいる彼の膝の上に跨り、肩に手をかけると「ん」と言ってボトルを渡された。私はそれを受けとって、水を口へ含む。そのまま竜胆の唇を塞いで口内の水を流し込めば、彼は素直にゴクンと飲み込んだ。水で濡れたくちびるを舐める仕草がエロいなあと思う。
「何…シたいの?」
私の腰を撫でながら竜胆が薄く笑った。
「そうじゃないけど…」
「オマエの彼氏、相変わらず満足させてくんねえのかよ」
「それはそれでいいの。可愛いから」
一方的に遊びの女扱いをされるのは嫌だから、しつこく口説いてきてた男を敢えて彼氏にした。
竜胆は女にモテるから遊ぶ女にも慎重だし、あまり重そうな女には一切手を付けないのは確認済み。だから好きだなんて死んでも言えない。更には竜胆にそれを悟られてはいけない。面倒くさい女認定をされ、こんな関係さえ終わってしまうに違いない。そんな未来が容易く想像できる。彼にとって、私はひたすらに軽くなければいけない。
「フーン、ビッチだなー相変わらず」
竜胆は鼻で笑うと、自分の膝を少しずつ開いていく。そうすることで、跨っている私の足も、ゆっくりと開いていった。ミニスカートが徐々に捲れて太腿が剥き出しになっていく。
彼氏なんかよりも、竜胆の綺麗な瞳に見つめられると、彼のことしか考えられなくなる。竜胆の言うように、私は最低のビッチだ。それでも私は竜胆が欲しくてたまらなかった。
そんな自分に呆れていると、竜胆が眼鏡を外して私の顔を覗き込むように近づけてきた。竜胆のくちびるが私のくちびるに押し付けられて、視界いっぱいに彼の淡いバイオレットが揺れている。竜胆は挑発するみたいに私と目を合わせたまま、くちびるを啄んでくる。私もそれに応えると、竜胆の瞳がかすかな熱を灯して、口内に彼の舌が入ってきた。そのまま口蓋をざらりと舐められて背中をゾクゾクとしたものが走る。でもそれはすぐに離れていった。
「…オマエ、タバコ吸った?」
竜胆がその鋭い瞳を僅かに細めた。確かに私はさっき一口だけ煙草を吸ってしまったかもしれない。迂闊だった。
ごめん、と呟けば「匂いついたらどーすんだよ」と言いながらも、竜胆の手が背中から服の中へ入ってくる。片手でブラのホックを外し、もう片方の手でキャミソールの肩紐を下げられると、私の胸は一気に無防備になった。
「もう乳首硬くなってんじゃん。期待してた?」
「…ちょ、引っ張らないでよ…破けちゃう」
キャミソールを下げようと指で引っ掛けた竜胆が、力いっぱい下げるから慌てて手を止めると、彼の目がスッと細められた。
「じゃあ自分から脱げばー?」
不機嫌そうな低音の声が私の鼓膜を震わせ、途端に冷たいものが背中を走る。
私を蔑んでいるかのような竜胆の瞳の色に喉の奥が痛くなった。こうなってしまうと、私は彼に逆らえない。言われるままに自らキャミソールを脱ぎ、胸を晒した。両手で胸を強く揉みしだかれ、快感とは程遠いのに私の口から甘い吐息が漏れてしまう。完全に竜胆の支配下に堕ちる瞬間だ。
「自分だけ気持ち良くなってんのずるくねえ?」
竜胆がこう言ってくる時はオレのも触ってという合図だ。さっきから下腹部に当たってる彼の昂ぶりを感じて、そこへすぐに手を伸ばす。
竜胆は舌で私の胸を辱めながら私の腰を抑えつけ、もう片方の手をスカートの中に侵入させてきた。私は私で竜胆のズボンのファスナーを下ろすと、下着を押し上げているものへと触れる。そのまま軽く撫でて手を中へ侵入させると、先端が少しだけ湿っていた。それを感じた時、私の理性はぶっ飛んでしまった。竜胆が欲しくてたまらない。でもそんな素振りは見せたら終わりだ。とことん軽い女を演じなければ、竜胆とこんな風に抱き合えない。
だって――竜胆の本命は別にいるんだから。
「何?もう挿れてほしーの?」
熱心にしごいていたせいで、私の熱が伝わってしまったらしい。本当はそこまで好きな行為でもないけど、相手が竜胆だと自ら強請ってしまうほどに欲しくなるんだから不思議だ。
「…挿れて欲しい」
「えっろ」
乳首をきゅっと強くつままれ、思わず背中がしなる。つい握る力が強くなって、竜胆も切なげな声を洩らした。
「でもさーあんま時間ないから、今日は口で出させて」
「…わかった」
竜胆はこんな場面でも頭は冷静だ。チラっと時計を確認して現実を突きつけてくる。
「今日、彼女が出張から帰ってくんだよね」
彼女、と聞いて心臓が痛いほどに跳ねた。こんな状況でそんな話を聞かされて、私にどう応えて欲しいんだろう。そんな思いを抱えたまま、私は彼の膝から下りて足の間へ顔を埋めていく。
竜胆の彼女は、どこかの出版社の編集者をしているともっぱらの噂で、だけど誰もその女の正体を知らない。以前、このクラブが紹介された雑誌を扱ってる出版社というとこまでは突き止めたけど、記事を書いた人、カメラマン、どちらも男だった。もしかしたらアシスタント的な子だったのかもしれない。
だから皆、竜胆の彼女の名前すら知らない。竜胆は決して彼女の名前を口にしようとはしないからだ。それだけ彼女を守って、遊びの女達が彼女に辿り着かないようにしてる。それほど大事に想っているくせに、竜胆はこうして私のような女と浮気をするんだから矛盾してると思う。それもこれも、忙しい彼女になかなか会えない寂しさを紛らわせているからだと、私も薄々分かってきたけれど。
竜胆が人で溢れてる自分の店に来てお酒を飲むのも、きっとそのせい。
「――あ?…あー…電話…」
フロアの方から響いてくる低音が、かすかに届く室内に、けたたましいくらいの音量でケータイが鳴った。竜胆の声に焦りの色が交じったことで、私はすぐに顔を上げた。
「ちょ、もういいわ」
口でしようとしてた私の肩をグイっと押すと、竜胆はズボンの乱れをすぐに直してケータイ片手に休憩室を出て行く。この瞬間、彼の脳内から私は綺麗さっぱり削除されたらしい。
彼は付き合いも広く、色んな業種の友達もいる。それ故に彼のケータイが頻繁に鳴るのはいつものことだ。でも女といる時は着信が来ても無視する事が多い。クラブにいると聞こえないからと、うるさいほどの音量で鳴るケータイをチラっと見ては、相手を確認するだけで手にとらないこともある。それはかけてきた相手が遊びの女の時だけ。そんな竜胆を見るたび、私は竜胆の隠れた冷たさを思い知らされる。私のかける電話に出ない時、竜胆はあんな顔をしてるのかと嫌な想像すらしてしまう。するだけ無駄だし空しいだけなのに、考えずにはいられないのだ。
閉じられたドアを見つめながら、今の電話は誰からなんだろうと考えていた。
どこか慌てたようにも感じたことで、胸の奥がざわりとする。気づけば私は乱れたキャミソールを着直して、ドアノブに手をかけていた。
そっとドアを押し開けば、廊下奥の方から竜胆の声が聞こえてくる。彼は話すのに夢中なのか、ドアが開いたことに気づいていない。フロアから流れてくるミュージックと、ドンドンと地響きのような重低音で、小さな音は聞こえないのかもしれない。
私はドアを少しだけ開けたまま、耳をすませて竜胆の声にだけ集中した。
人気のない廊下に竜胆の笑い声が響く。随分と楽しそうな嬉々とした声だった。
「えー?いいよ。迎えに行くって。うん…マジで。疲れただろ?出張なんて。ああ…あ、そろそろ着きそう?ならオレも今すぐ出るわ。ああ…だから気にすんなって。オレも早くに会いたいし…うん。じゃあ――」
その会話をどうにか耳が拾った時、私は思わず息を飲んだ。
これは――彼女に違いない。
私という遊びの女といる時は、他の女からの電話には出ない。だから今、私を放置してまで出たという時点で、男からだと思っていた。でも今聞いた名前は間違いなく女であり、出張、という言葉で気づいた。
――今日、彼女が出張から帰ってくんだよね。
竜胆はハッキリそう言ってたのを思い出し、私は唇を噛んだ。
そもそも竜胆にとって私は何者でもないんだと分かってはいた。いたけど、でもあんなに優しいトーンで女と話す竜胆を、私は見たことがない。あんなに甘い声で名前を呼ばれたという顔すら知らない女が心底憎らしいと思った。
でも悲しいことに、竜胆と何度キスをしても、セックスをしても、私は今の彼女以上の存在にはなれないのだ。