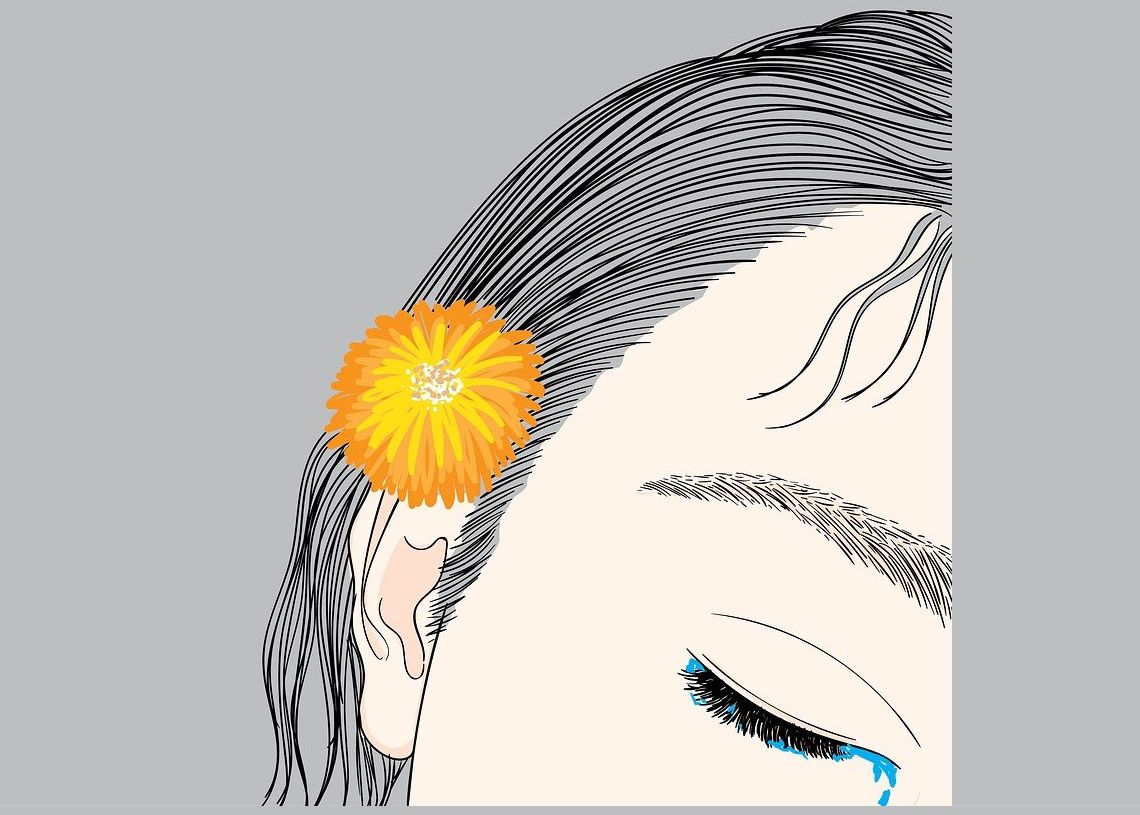
I knew
第十三幕:暗雲
宿泊した旅館の温泉は凄く素敵だった。屋根付きの露天風呂の周りは竹林で囲まれ、昼間に降り出した雨も絵になるような景色が広がっている。普段、都会で働いていると、こういった自然の空気が癒しになったりして、忙しかった日々の疲れが綺麗に流されていくようだ。
「ハァ~気持ちいいなぁ…」
晴れていれば星空を堪能できたかもしれないけど、雨音を聞きながら入る温泉もなかなか悪くない。こんな天気だからか、わたし以外の客はいないし、この空間を独り占めしているなんて贅沢な気分になった。
「うーん…まだ入ってたいけどそろそろ出ないと逆上せちゃうかな」
だいぶ体が温まったことで、わたしは後ろ髪を引かれる思いで湯から上がった。雨で外気は冷えてるけど、それすら感じないほど体はポカポカしている。脱衣所で体を拭いて浴衣と羽織りを着込むと、設置されているドライヤーで髪を乾かしながら、火照った自分の顔を鏡で見た。
「あー…真っ赤になちゃった…」
メイクもしてないのに頬はリンゴのように赤くて笑ってしまう。そこでふと、こういう場合、薄くでもメイクをした方がいいのか悩んだ。彼氏と初めての旅行で、しかも最初の夜。当然、少しは意識してしまう。
これまで竜ちゃんには我慢してもらってる状態で、竜ちゃんも強引にわたしを抱こうとはしなかった。だからこそ、この旅行で…と決心したのに、いざ来てみると思ってた以上に緊張してくる。といって、もし竜ちゃんとそういう空気になったなら、もう拒むつもりはなかった。まだ少し怖いけど、でもそれ以上に竜ちゃんが好きだから。
(ケーコ先輩にも下着を選んでもらったし、一応、そういう流れになっても大丈夫なはず…)
浴衣の下に身に着けた下着を思い出しながら軽く深呼吸をする。全てを曝け出すのは不安ではあるけど、竜ちゃんは経験豊富そうだし任せておけば大丈夫…なんて考えてから少しだけ悲しくなった。竜ちゃんや蘭ちゃんはモテるし、環境が環境だけに異性に対して奔放だったのは想像できる。蘭ちゃんは今もそういう感じだし。でも竜ちゃんもわたし以外の人とそういう関係になったりしたことがあるんだよなぁと考えるだけで、腹の奥から重苦しいものがこみ上げてきてしまう。これが嫉妬…という感情なのは分かっている。そんな過去に嫉妬したって意味がないってことも。でも竜ちゃんがわたしの知らない女の子に触れたと想像するだけで、自分でも抑えきれないくらいに不快な気分になるんだから、人の心は不思議だ。
「うわ…結構長風呂しちゃったな…竜ちゃんもう出てるよね…」
髪を乾かし終えて手荷物を抱えると、ケータイで時間を確認した。普段はこんなに長風呂じゃないけど、やっぱり温泉となるとつい油断してしまう。けど早く部屋に戻ろうと歩きかけた時だった。手にしていたケータイが鳴った。てっきり竜ちゃんかと思ったら、表示されていたのはまさかの蘭ちゃん。ちょっと驚きながらも電話に出た。
「もしもし。蘭ちゃん?」
『おー。今、旅館か?』
「うん。ちょうど温泉から上がったとこ。どうしたの?」
竜ちゃんにじゃなく、わたしに連絡してくるなんて珍しいと思って尋ねると、蘭ちゃんは『いや、それがさー。竜胆のケータイ繋がんねーんだけど、今一緒か?』と苦笑交じりで訊いてきた。
「竜ちゃんも温泉入りに行ったけど、多分もう部屋にいると思うよ」
『マジ?じゃあ電池切れか…?ずっとかけてんだけど急に留守電になったし』
「そっか。何か用事?わたし、伝えようか」
旅行中と知ってて何度も電話をかけたのなら何か急用かと思った。だから何の気なしに言ってみると、蘭ちゃんはどこか慌てたように『いや、いいよ』と言い出した。
『アイツにオレに電話するよう言ってくれるだけでいいわ』
「そう?じゃあ蘭ちゃんに電話してって伝えておくね」
『ああ、頼むな。――…そうそう。旅行はどんな感じ?』
ふと蘭ちゃんが思いだしたように訊いてきた。そこで蘭ちゃんも何気に来たがってたことを思い出す。
「すんごく楽しいよ!昼間はあちこち観光に行って、さっき旅館に入ったんだけど、お部屋も素敵でお風呂も最高。今度、蘭ちゃんも一緒に来ようね」
『そうだな。まあが楽しそうで良かったよ。明日も観光すんだろ?』
「うん。明日はドライヴがてら、観光地以外も回る予定なの」
『そっか。思う存分、楽しんでこいよ』
「ありがとう。お土産期待しててね」
わたしの言葉に蘭ちゃんは笑いながら『楽しみにしてるわ』と言って電話を切った。後ろでは数人の笑い声が聞こえてきてたから、もしかしたら天竺の仲間と今夜は飲み明かす予定なのかもしれない。蘭ちゃんも意外と寂しがり屋なんだよね、と思いながら苦笑が漏れる。
「いけない…わたしも戻らなくちゃ」
再びケータイの時間が目に入って、わたしはすぐに脱衣所を飛び出した。
△▼△
「え?兄貴から電話?」
が部屋に戻って来てから、温泉の感想なんかを話してたら、急に彼女が「あ、そうだ」と思い出したように兄貴から電話があったことを伝えてきた。オレに電話が繋がらないからって、わざわざにまでかけてくるなんておかしい。咄嗟にそう思ったオレはちょっとだけ悪い予感がした。さっきから何度もかかってきてた電話。単に兄貴がオレとの邪魔をしようと、酔っ払ってかけてきたものだとばかり思っていたが、彼女にまで言伝を頼むとなると、大事な用だったのかもしれない。でもに旅行を楽しんで来いよと言った話を聞く限り、緊急を要する感じでもない。じゃあ何で兄貴はわざわざオレに連絡しろなんて言ってくるんだろう。
「竜ちゃん…?どうしたの?」
「…え?」
少しの間、考えこんでいたらしい。が不思議そうにオレの顔を覗き込んでいた。
「いや…兄貴からの電話スルーしちゃったから、どう言い訳しようか考えてた」
咄嗟に出た返しにしてはリアリティがあったようだ。彼女は「大丈夫だよ。電池切れだって言えば」と笑っている。
「だな…。あー…じゃあ、ちょっと電話してきていい?」
「え?ここでかければいいのに」
「いや、そうなんだけど、仕事の話かもしんねーし…ちょっとロビーでかけてくるよ」
「あ、そうか。うん。じゃあビール飲みながら待ってる」
は冷蔵庫から缶ビールを取り出してグラスに注いでいる。それを見てホっとしつつ、悪いなと声をかけて部屋を出た。兄貴の話がどういった内容のものか分からない状態じゃ、の前で電話をするのは得策じゃない。から聞いた感じじゃ、兄貴も今はイザナくん達と飲んでいるんだろう。オレの予想通り、ただの酔っ払いの電話ならいいんだけど。そう思いながら電話をかけると、まさかのワンコールで兄貴が出た。
『竜胆?今、部屋からか?』
「いや…旅館のロビーまで出てきた。どうした?急用?」
てっきり電話に出なかったことを怒り出すかと思えば、やけに真剣な声で訊かれて胸の奥がざわついた。兄貴は『は?』と続けるから、部屋だよと応えると、兄貴はホっと息をついたようだった。その反応からして彼女に聞かれたらマズい話だと分かる。
「何…?何かヤバい話?」
『まあな…実は今日の夕方、家にクラブの客が来たんだよ』
「…は?客?」
余計な前置きなく言われ、一瞬何のことか分からなかった。家に客が訊ねてきたことはないからだ。
「客って――」
『ほら、オマエのファンだとか公言して毎日通って来てた子いたろ。ギャルっぽい感じの』
「……あー…アイツか」
兄貴の説明で一人、頭に浮かんだ。うちの店は常連は多いが、毎日通ってくる人間はそれほど多くはない。その中でギャルっぽい女と言えば、一人だけ心当たりがある。通ってくれてるから一度、声をかけて酒を奢った女だ。その後、彼女は酔っ払ってオレに気がある素振りを見せながら誘ってきた。オレも酔ってたし、据え膳食わぬはの精神で手をつけて以来つきまとってきたが、この旅行前に切ったはずだ。
「え、アイツが何で…?」
『オマエに連絡がつかないからって家に来たんだよ。ったく…適当に遊んだ女でもちゃんと切れ』
兄貴は少しイラついてるようだった。そりゃそうだろう。これまで家に尋ねてきた客なんかいなかったし、まして遊びの女が来ることもなかった。あの女がそこまでするタイプだとも思わなかった。完全にオレの誤算だ。
「悪い…この前、もう会わないって言ったんだけどさ。そもそも二人きりで会ったの三回くらいだし」
『あの様子じゃ納得してねえな。オレも二度と家に来るなって言っておいたけど、ああいうヤバそうな女は何すっか分かんねえし、オマエ、ちゃんとアフターケアはしとけ』
「分かった…アイツにはオレからもキツく言っておくわ」
オレがそう断言したことで兄貴も安心したのか『には絶対にバレんじゃねえぞ』と釘を刺してから電話は切れた。
「バレんじゃねえぞ…か。オレだって知られたくねえよ…」
溜息交じりでロビーのソファに座りこむと、深い溜息が漏れた。がいるのに他の女に手をつけてたなんて絶対にバレたくない。調子がいい考えかもしれねえけど。
ただ改めてオレは最低なことをしてきたんだと実感した。と出会う前の生活を急に変えることも出来ず、初めて好きな子が出来たというのに、昔と同じようなノリで寄ってくる女に手をつけた自分にウンザリする。
「バカか、オレは…」
こういう事態を招くことがあると想定しておくべきだったし、そもそも失いたくない存在が出来た時点で遊びなんかスッパリ止めるべきだったのに。
「あ、竜ちゃん。お帰り!蘭ちゃん、何だって?」
重苦しい気分で部屋に戻ると、が笑顔で出迎えてくれた。風呂上りの上にビールを飲んで、ほんのりと頬が赤い。その可愛らしい笑顔を見て、オレは自然に頬が綻んだ。
を失いたくない――。
心の底からそう感じて、オレは彼女を思い切り抱きしめた。
「竜ちゃん…?どうしたの…?」
「…好きだなーと思って」
「え…何…急に…」
ぎゅっと腕に力を込めて抱きしめると、は笑いながらオレの背中へ手を回してくる。シャンプーの優しい香りがオレの鼻腔を掠めて、髪に口付けた。
を傷つけたらダメだ。彼女の体温を感じながら、改めて心に誓った。