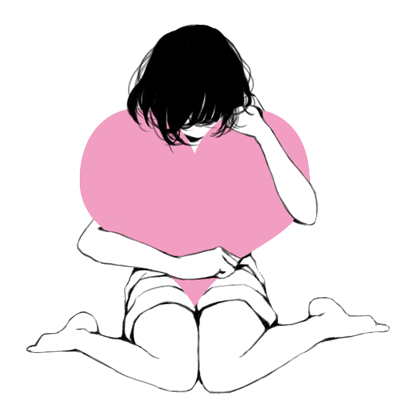
-01-あの日に帰りたい
"ありがとう。――春千夜くん"
そう言ってふわりと笑ったアイツの顏が、今もこの瞳に焼き付いたまま。
あの笑顔を守るのは、いつだってオレだと思ってた――。
【2017年・5月】
「春千夜!」
真っ白いドアを開けると、そこには純白のドレスに身を包んだ彼女がいた。陽の光を浴びて振り返る姿は今のオレには眩しすぎて、僅かに目を細めた。この世に天使なんてもんがいるなら、きっと目の前の彼女のような姿をしているに違いない。
「もー遅いよ!来てくれないかと思っちゃった…」
「…来なきゃオマエ、まーた鬼電してくんだろーが」
「えへへ…バレた?」
無邪気に笑う彼女の手にはすでにスマホが握られている。自然と目が行くのは彼女の左手薬指に光るブリリアントカットされた天然のダイヤ。光の加減によって多彩な輝きを見せるその石は、彼女の綺麗な指をさらに引き立たせている。自己主張の強いあの男が選びそうな指輪だと思った。
「ったく…いちいちオレを呼ぶな。ドレス選んで欲しいならオマエの飼い主に選んでもらえ」
「飼い主って!また犬扱いするー」
「オマエは犬だろーが。いっつも後ろくっついて来てたしな」
「……そうだっけ」
「あ?テメ、忘れたのかよ」
「そんな前のことなんて覚えてないもん」
彼女は言いながらドレスの裾をつまんで、軽く持ち上げてみせた。
「それより、このドレスどお?似合う?」
「……似合わねえ」
「もー!」
ぷいっと顔を反らせばすぐに抗議の声を上げる。凝りもせず、まだこんな態度しか出来ない自分に呆れながらも、目の前で頬を膨らませてる彼女――を見下ろした。
「じゃあ、春千夜はどんなドレスがいいの?」
「…あ?何でオレの好みなんて聞くんだよ」
「文句言うなら、どんなのがいいのかなって思っただけ」
だから春千夜が選んで、とは言った。何でオレが他の男のもんになる為のウエディングドレスを選ばなきゃなんねーんだ。そう思うのに、自然と目の前にズラリと並ぶドレスへ目が向く。その中に、柔らかそうなふんわりとしたデザインのドレスを見つけて手に取った。
「これ…」
「え、これ?春千夜、これがいいの?」
「…っせえなぁ。ちんちくりんのオマエにはこれくらいボリュームある方がいいだろーが」
「む…ちんちくりんって何よ。そりゃ春千夜には途中で身長抜かれたけど、これでもスタイルはいいねって言ってくれる人もいるんだから」
相変わらず、ガキみてえに口をとがらせてはそっぽを向いた。でもそんなの言われなくてもオレだって思ってる。まだまだガキだと思ってたら、気づけば女らしくなっていたにドキっとさせられたのはいつだったろう。
とは小学校一年の頃に出会った。コイツがオレのクラスに転校してきて、隣の席に座ったことで、そこからオレとの時間は動き出した。神様の悪戯のような彼女との出会いは、オレにとって紛れもない青春の一ページ…どころか、いつの間にかオレの全てになってた。なのにオレが意地っ張りだったせいで、コイツは来月、他の男のものになってしまう。それもオレが最も警戒してた――。
「あ、蘭ちゃん!」
――いけ好かない男。
「おーめっちゃ可愛いじゃん、」
灰谷蘭という男のものに。
「あれ、三途も来てたのかよ」
六本木でいくつもクラブを経営してるこの男は今でこそ青年実業家なんて肩書きを持ってるが、過去にはオレと同じく東卍に入った仲間だった。あの頃から何かとにちょっかいかけてたのは知ってたが、まさかが生涯のパートナーにこの男を選ぶなんて、オレは想像すらしていなかった。
「…コイツに呼ばれたんだよ」
「は?オレの可愛い婚約者をコイツ呼わばりか?いくら幼馴染つっても許さねえぞ、コラ」
「あ?文句あんのかよ」
「こんなとこでやめてよ、ケンカは!」
不穏な空気を感じたのか、が慌ててオレと灰谷の間に入る。この男と反りが合わないのは今に始まったことじゃない。もそれはよく知っているはずだ。なのに、はオレが一番イラつく相手を結婚相手に選んだ。最初にそれを聞いた時はタチの悪い冗談だと思った。オレへの嫌がらせかとも。
けど――それくらいされても仕方のないことを、オレはにしてきた。こんな捻くれた性格になったおかげで、素直な気持ちをぶつけてくるに、オレは素直に応えることさえ出来てなかったんだから。
"春千夜、大好き"
"大好きだよ、春千夜"
からはたくさんの"大好き"をもらったのに。
「あーやっぱここじゃなくて三ツ谷のとこで買おうぜ」
「いいの?蘭ちゃん、三ツ谷くんとこで買うの恥ずかしいって言ってたのに」
「まあ…でもアイツのデザインしたウエディングドレスが今まで見た中でに一番似合ってたし」
「ほんと?嬉しい!実はわたしも三ツ谷くんのドレスが一番いいなあって思ってたの」
「ま、アイツはオマエに着せる為のドレスを作ったんだろうからなー」
「え、何それ。初耳…」
「たいがいも鈍いよなァ?」
「あ、酷い、蘭ちゃん!――あ、じゃあちょっと三ツ谷くんに電話してみるね」
仲の良さそうな会話が延々とオレの後ろで交わされてるのを聞いてたら、イライラも頂点に達した。その思いのまま灰谷を睨めば、アイツは勝ち誇ったような笑みを浮かべてオレを見ている。出来ることなら今すぐ殴り倒したいくらい、憎たらしい男だ。ただ、の欲しいものを、この男は素直に与えられたんだって思うと、そこからしてすでにオレはコイツに負けてる。
「蘭ちゃん、三ツ谷くんが今からアトリエおいでって」
三ツ谷に電話してたらしいが戻って来て、ふとオレを見た。
「春千夜も行く?」
「あ?行くわきゃねーだろ」
「……でも…春千夜にも見てもらいたいな、三ツ谷くんのドレス着るとこ」
「何でオレがそんなもん見なきゃなんねーんだよ。オレは忙しいんだ。いちいち下らねーことで呼び出すな」
こんなこと言いたいわけじゃないのに、一度口から出だすと次々に冷たい言葉を吐き出してしまう。昔からオレは、に優しい言葉一つ、かけてやることが出来なかった。
"春千夜にも見てもらいたいな、三ツ谷くんのドレス着るとこ"
見れるわけねえだろ。他の男の為に着るドレスなんて。
でも――そうか。三ツ谷はの為にドレスを作ったんだな。
は昔から東卍の皆に可愛がられてた。素直で無邪気、バカがつくほど純粋だから、チームのマスコット的な存在だった。そんなが何故かオレのことを好きになってくれた。バカで口が悪くて、ケンカっぱやいオレを、見捨てずにそばにいてくれた女はだけだった。どんなに突き放しても、は諦めずにオレのことを好きでいてくれた。もし、過去に戻れるなら、また一からやり直したい。
初めてに会った――あの日から。