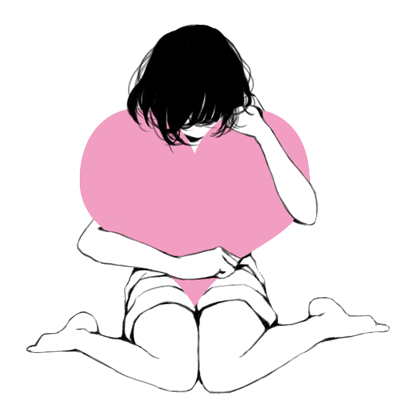
-07-空の下で何を思う
1.
朝、家に来たの目は真っ赤に充血していた。どうしたのって聞いたら、やっぱりハル兄のことで、この前話してた作戦ってやつを夕べ実行したらしい。
「…あっさりフラれちゃった。こんなことすんなって…」
いつも元気ながほんとに泣きそうな顔でそんなことを言うから、こっちまで何だか悲しくなって、こんなにもハル兄を想ってくれてるを泣かした愚兄に心底ムカついた。
「これで懲りたでしょー?もうあんなヤツやめなよ。にはもっといい男がいるって」
ジブンは慰めるつもりで言ったのに、は「そんな人いないよ」と、今までの落ち込み顔から一転、やさしい笑顔を見せた。
「わたしにとって春千夜は、たったひとりのヒーローだもん。代わりになれる人なんていないの」
その言葉を聞いて、ガラにもなく胸が熱くなった。誰かをこんな風に思えるってすごい。ジブンはジブンより弱い男子になんか興味もないし、未だに"れんあいかんじょう"ってやつはよくわからない。だけど大好きな幼馴染が、ジブンの兄貴をこんな風に言ってくれるのは素直にうれしいと思う。
(こんな見てたら応援したくなっちゃうじゃんか…)
ハル兄はガキだからの大事さをわかってないんだ。チューされてビビってるようじゃ話にならない。そのうちを他の男に掻っ攫われる羽目になるかもしれないのに。
そこでふと気づいた。もし、万が一とハル兄が結婚したら、はジブンのお姉ちゃんになるってことに。
(ハル兄にはもったいないと思ってたけど…がお姉ちゃんになるのはうれしい…)
うちにはお母さんがいない。お父さんは生きてるけど忙しくて殆ど帰って来ない。唯一親代わりの長男は遊び歩いてて、これまた殆ど夜は家にいない。だからが朝や夜、いつもジブンやハル兄のためにご飯を作りに来てくれるようになった。何でもハル兄の為に料理をママにおそわっているようだ。こんなことをしてくれる他人はいなかった。だからジブンはが大好きだし、もっとやさしい男を好きになれよって思ってた。でも、だけど。がほんとのお姉ちゃんになってくれるなら…ハル兄と結婚するのはありよりのありだ。
「…そんなにハル兄のこと、好き?」
「うん。大好き」
は会った頃から一貫して変わらない。ハル兄のことを話す時はいつもすごく幸せそうな顔をする。
「じゃあ一回フラれたくらいでめげんなよ」
「…千壽」
「どーせハル兄、女に"めんえき"ねーからひよっただけだし。でも絶対、意識はしてると思うぞ」
「…そうかなぁ。っていうか、千壽って難しい言葉知ってるね。免疫ないなんて」
「ああ、エマから教えてもらうんだ。アイツ、小学生のくせにドラケン好きとか色気づいてて最近マセてんだろ」
「……千壽も相当だと思うけど。っていうかエマと同じ歳でしょー?」
どや顔で言ったらに笑われた。でもやっと笑ってくれてホっとする。
「じゃあご飯作っちゃうね」
エプロンをつけながらキッチンに向かうは、すっかりウチに馴染んでる。食器も鍋も全部が使いやすい配置になっていて、そういう小さなことがうれしいと思う。今からウチにお嫁に来て欲しいくらいだ。
「…ハル兄、起こしてくるね」
そう声をかけると、は照れ臭そうな顔で笑って頷いた。
2.
わたしの心とは裏腹な快晴。青空から降り注ぐ朝日は、泣きはらした目にやたらと沁みる。
「あ、春千夜、おはよう。朝ご飯できたよ」
「……何で」
ファーストキスを交わした次の日の朝、わたしはいつものように学校前、春千夜の家に寄ってふたりの朝食の用意をしていた。起きて来た春千夜は明らかにギョっとした顔で僅かに頬を赤くしながらわたしを睨んでる。これは夕べのこと相当怒ってるなあと思った。
わたしが強引な手段に出たのには理由がある。もちろん春千夜との仲を進展させたいと思ったのもあるけど、もう一つ心配だったこと。それは中学になれば春千夜は確実にモテる部類に入ってしまうからだ。美人顔というのもあるけど、今や真一郎くんや万次郎の影響で不良に片足を突っ込んでいる春千夜は、ギャップ系男子に属すると思う。"ちょい悪"が流行ってるし――春千夜たちは極悪かもだけど――絶対に女子からモテるとわたしは確信している。惚れた欲目だけではなく、実際春千夜は小学校高学年から急にクラスの女子から人気が上がったのをわたしは知っている。大人しい性格だった春千夜がヤンチャになった時期だ。
わたしに関して春千夜はまだまだ小学生のノリで、今のままじゃ一生わたしのことを女扱いしてくれないだろうし、中学に入って可愛い女の子に言い寄られたら急に目覚めてしまうかもしれないと思った。思春期だし、特に男の子のソレは女の子と違う。本人ですら抗えない欲が急激に上がる時期だと雑誌で読んだ時、このままじゃ危ないと思った。春千夜が盛る前にわたしがファーストキスを奪ってしまおうと思いついてしまった。そうすればわたしを女として意識してくれるはず。そう思ったのに――。
(やっぱり春千夜の気持ちを無視してあんなことしたのは失敗だったのかな…)
目の前で怖い顔をしてる春千夜を見てそう思った。
「何でって…いっつも作ってるじゃない。早く食べて学校行こ?」
「……顔洗ってくる」
春千夜はムスっとした顔でそれだけ言うと、洗面所の方へ歩いて行った。その背中を見て溜息を吐くと、黙ってご飯を食べてた千壽が「気にすんな」と小声で言ってくれる。今回の作戦はさっき千壽にも話した。小学生の千壽にファーストキスを仕掛けた話なんて良くないかと思ったら「バカにすんな!わたしのバイブルはヤンキー漫画だけじゃないから、たかがキスくらいの話では驚かん」とドヤ顔で言われてしまった。最近の小学生はマセている。
「でも…ほんとにチューしたの?ハル兄、いつもと変わらず仏頂面だけど」
「…し、したよ。でも…怒ってると思う」
「ったく…やっぱチューだけじゃなくて押し倒すくらいしないと、ハル兄もオスとして目覚めないんじゃない?」
「オ、オスって…」
「だーって精神年齢、小学生のままじゃん。まあマイキーもだけど、マイキーの場合、時々高校生かなって思うくらいマセてるから、ハル兄よりマシ」
「…マセてるって…」
だからそれは千壽もだよと突っ込みたくなったけど、そこに春千夜が戻って来たから話は中断された。
「…いただきます」
「う、うん…」
ムスっとはしてるけど、ちゃんとそう言ってくれる春千夜に少しホっとした。春千夜のそーいうところが好きだ。どれだけ機嫌が悪くても、わたしの存在を無視したりしない。ちゃんと見てくれてる。
(でも…こうして見ると春千夜も随分と変わったなぁ…ピアスも見るたび増えてくし、髪なんかキラキラの金髪で前髪も伸びてきたからちょっとホストっぽい…カッコいいけど)
出会った時も思ったけど、春千夜はその辺の女の子より美人顔だ。成長すればするほど、それは際立ってきて完全にイケメン枠に入ってしまった。それはわたしだけじゃなく、他の女の子からも好意を寄せられる可能性が上がったということに他ならない。だから中学に上がったら今までの関係に変化が欲しいと思った。春千夜が男の煩悩に目覚める前にわたしを女の子として認識して欲しい。ただの幼馴染じゃなくて、もっと女の子として扱って欲しい。そんな欲求が強くなった。
「…何だよ。ジロジロ見んな」
わたしの焼いた玉子焼きに箸を伸ばしながら、春千夜は不機嫌そうに言った。
「春千夜、カッコいいなあと思って」
「……っバカじゃねーの」
素直に思ったことを言ったのに、春千夜はギョっとしたように顔を上げてしかめっ面をした。前はこう言っても「当然だろ」ってどや顔で言ってきたのに、今は心なしか頬が赤い。これはいい兆候なのかなと思いながら、いつものように笑って誤魔化しておく。そこに千壽が「ほーんとってバカ」と笑い出した。
「ハル兄がカッコいいとか目が腐ってる」
「あ?テメェもたいがいうるせーな、千壽!最近生意気になったんじゃねーの」
「べー!――じゃあ行ってきまーす!、ハル兄をよろしくー」
先に食べ終えた千壽が思い切り舌を出してランドセルを背負うと、そのまま家を飛び出していく。更に不機嫌になった春千夜といきなりふたりきりになってしまった。
「…チッ。オマエが変なこと言うからだぞ」
「ごめん…」
オデコがピクピクしてるのは春千夜が怒ってる証拠だ。でもやっぱり明らかに前の反応とは少し違う。
「ごちそーさま」
「あ…うん。すぐ洗っちゃうから待ってて」
何だかんだと作った朝ご飯は綺麗に食べてくれたのを見て笑顔になった。すぐにお皿をキッチンに運んで洗っていく。その間に春千夜はいつも着替えて、洗い終わる頃には学校に行く用意が――。
「あれ…春千夜?」
洗い物を終えて振り向いても、そこに春千夜はいなかった。おかしいなと思いながら部屋を覗いてみても、春千夜はいない。そこでふと気づいた。慌てて玄関に行くと、そこにあるはずの春千夜の靴がない。
「ウソ…先に行っちゃったってこと…?」
その事実に気づいたわたしはすぐにエプロンを放り投げると、鞄を持って春千夜の家を飛び出す。合鍵で鍵をかけて通学路を走って行くと、前に春千夜が歩いてるのを見つけた。
「待ってよ、春千夜!」
後ろから声をかけると、春千夜はギョっとした顔で振り向いた。
「何で先に行っちゃうの?」
「…むしろ何でと学校行かなきゃなんねーんだよ」
「え、だっていつも一緒に行ってたじゃない」
「そりゃ小学校の時の話だろーが。もうお互い中学生なんだし、一緒に学校行かなくてもいーだろ」
「何でそんなこと言うの…?やっぱり…夕べのこと怒ってる…?」
泣きそうになるのをグっと堪えて尋ねると、春千夜はプイっと顔を反らした。
「何のことだよ」
「な…何のことって…」
思わず言葉を失った。夕べの今日で忘れてるはずはないのに、春千夜は何事もなかったように言った。朝日が眩しくて、春千夜の表情はよく見えない。
「あーそれと…今夜は夕飯いらねーから」
春千夜がふと思い出したように言った。こういう時はだいたい万次郎の家でご馳走になると分かっている。
「…万次郎のとこ?」
「おー。ワカくんとベンケイくんが釣りに行くから今夜は真一郎がそれさばくんだってよ」
ワカくんとベンケイくんは真一郎くんが頭を務めた元黒龍の特攻隊長と親衛隊長さんだ。今はふたりとも引退して都内でスポーツジムを営んでるらしい。生きる伝説なんて言われてるくらいケンカが強いみたいだから、春千夜も一目置いてるようだ。
「え、釣りたて食べられるってこと?」
「かもなあ。オジサンとオバサン、今夜も遅いんだろ?も来りゃいーじゃん」
「え、いいの?」
「どーせオレが誘わなくてもマイキーが誘うんだから同じだろ」
「行く!」
嬉しくて思わず即決していた。ウチはお母さんもお父さんも共働きだから、いつも帰って来るのが遅い。だから春千夜の家だったり、万次郎の家で夕飯をとることもしょっちゅうだった。さっきはもう一緒に学校は行かないと言われて、昨日のことすらなかったことにされたからヘコんだけど、誘ってもらえて正直ホッとした。
ただ、前と態度が変わらないということは、結局わたしが一大決心をしたキスも、春千夜にとっては何の起爆剤にもならなかったということだ。結果、わたしのファーストキスは不発に終わり、苦い思い出として風化していった。
でも、春千夜の中では大きな変化があったことを、この時のわたしはまだ気づいてもいなかった。