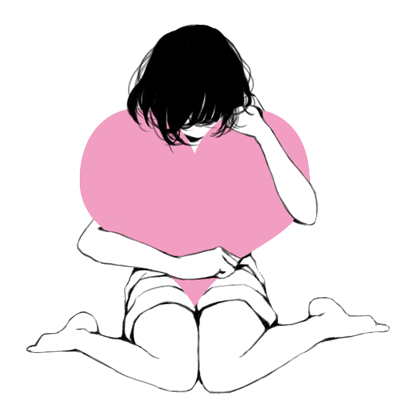
-11-叶うなら、もう一度
2017年5月。
「春千夜!こっち」
東京駅の混雑した中に明るい笑顔を見つけて軽く手を上げた。は春色のワンピースに薄手のカーディガンを羽織って女の子らしい恰好で立っていた。
「時間通りに来るなんて珍しいね」
「あ?そーか?」
「そーだよ。昔から遅刻の常習犯だったじゃん。あ、はいこれ。買っておいた」
は笑いながらオレにチケットを渡して改札を抜けていく。オレもその後に続いた。
「ん。チケット代」
「え、二人分あるよ」
「移動費、出してやるよ。結婚前で色々物入りなんだろ?」
「え、でも…」
「あーそれとも灰谷にお小遣いでももらってんの」
からかうように言えばが「子供じゃないんだから」と口を尖らせている。
「じゃあお言葉に甘えて」
「おー」
「そろそろ並んでおく?何か今日、人多いよね」
「休日だからな。人混みうぜえけど行くか」
そのまま二人で名古屋行きの新幹線が到着するのをホームで待つことにした。
今日は前に約束したマイキーのレースをと二人で見に行くことになっている。灰谷が仕事で来れないからって理由でオレが誘われた。よくあの嫉妬深い男がそれを許したもんだ。
「ああ、そーだ。マイキーが夜は皆で飯でも行こうって言ってたぞ」
「え、ほんと?やった!わたし、手羽先がいいなー!手羽先とビール!」
「オッサンかよ」
「えーでも春千夜も好きじゃない」
「まあな。でもオレひつまぶしも食いてーわ」
「あ、それも捨てがたい。じゃあそれは明日のお昼に行こうよ」
「そうだな」
今日は名古屋に一泊する予定だった。ちょっとした旅行気分なのか、があれこれと行きたいところをスマホで検索している。目的はマイキーのレースなのにの中では観光と同じみたいだ。
「今日はココくんと稀咲くんがくるんだよね」
「あーアイツら、マイキーの大スポンサー様だからなー。手羽先じゃなくても、めちゃくちゃ高い店とか連れてってくれんじゃね?」
「わたしは手羽先がいいんだもん」
「あっそ。お、来たぞ」
時間通りホームに滑り込んで来た新幹線に乗り込み、グリーン車の座席へ座る。は当然と言った感じで窓際を陣取った。
「あ、駅弁買えばよかった」
「車内販売すんだろ、どーせ」
「あ、そっか」
そんな他愛もない会話をしながら、ウキウキしてるを眺めた。小旅行用のバッグから名古屋観光の雑誌を出して「ここ行ってみたいなあ」とオレに提案してくる。オレはいつも通り「めんどくせえ」って言いながらも、結局最後は「分かったよ」という羽目になった。でもそれでいいんだ。こうして二人でどこかへ出かける機会なんて、この先絶対に訪れない。
「…オマエ、結婚前で準備忙しいのに、よく灰谷がこの旅行許したな」
「え、旅行って言っても一泊だし、蘭ちゃんも出張で北海道に行ってるから」
「そーいう問題かよ。他の男と地方に行くって、普通なら反対されんじゃねーの」
「蘭ちゃんは心が広いんだよ」
「あっそ。つーか、アイツ、何しに北海道行ってんだよ」
クラブのオーナーが出張って何するんだと疑問に思って尋ねると、どうやら"すすきの"に新しい店をオープンさせるらしい。相変わらず手広くやってんなーと苦笑が洩れる。
「でも何ですすきの?愛人でもいんじゃねーの」
「もー。春千夜、すぐそういうこと言う。蘭ちゃんは浮気なんてしません」
「どーだか。アイツ、東卍時代からころころ女変えてたじゃねーか」
オレが知る限り、灰谷は東卍に入って来た頃から女によくモテていた。会うたび違う女を連れてたのは忘れてねえし、だって知らないはずがない。未だに何でがアイツを選んだのかがサッパリ分からない。
「でもそれ言うなら春千夜もあの頃はとっかえひっかえしてたじゃない」
「…そうだっけ」
やぶ蛇だったと思いつつ、視線を窓の外へ移した。
「そーだよ。中学二年くらいから色んな女の子と付き合ってたし」
「……あれは…向こうから寄ってくんだから仕方ねーだろ」
「うわ、遠回しにモテるって言いたいんだ」
「実際モテるし」
「…ふーん」
オレの言葉には何故か俯いて不機嫌そうな瞳を流れる景色へ移す。その表情を見てドキっとした。あの頃、オレと女が一緒にいる時に会うと、はいつもこんな顔をしてたっけ。でもあの頃はオレも必死でを遠ざけようとしてたから、何も考えずに寄って来る女に手を出してた。でもそれはオレの中に芽生えたモヤモヤを吹っ切りたかっただけだ。全部無駄に終わったけど。
どんな女と付き合ったところで何一つ変わらなかった。相変わらず心の真ん中にはが居座っていて、それは絶対に消えてなくならない。あの頃はオレなりに足掻いてた気がする。変に男に目覚めて、でもそういったもんをにぶつけて傷つけたくなかったんだと思う。オレの中では特別な存在だったから。あの頃のオレにはよく分かっていなかったけど、それが――。
「初めてだね」
「あ?」
不意にがオレを見て言った。視線を戻すと、さっきまでの不機嫌さは消えていて。代わりには笑みを浮かべていた。
「春千夜とこうして遠出するの」
「ああ…そう言えば…そうだな」
「昔は行ってもバイクで湘南とかだもんね。ちょっと遠くて千葉とか」
「あー。がミッキーに会いたいとか言い出したヤツな」
「そうそう。東卍の皆で連れてってくれたよね。あの時は嬉しかったなあ」
「皆で貯めてたお年玉使い切って、しばらくビンボーだったことまで思いだしたわ」
「そうだったね。なのにわたしの分まで皆で出してくれて…」
「でも中じゃオマエがオレ達に色々と飯とか奢ってくれただろ」
「そうだっけ?でも…懐かしい」
は嬉しそうな笑顔で言いながら、また窓の外へ視線を向けた。その横顔はどこか寂しげで。もうすぐ結婚するヤツの顔じゃない。何が原因でにそんな顔をさせてるのかが分からなかった。
「戻りたいなぁ」
その時、ポツリとが呟いた。
「…あ?どこに」
「あの頃に」
オレのことを見ないまま、が言った。
「はあ?戻ってどーすんだよ」
「…また皆でバカやって騒ぎたい」
「そんなの今でも出来んだろ。結婚したって皆にはいつでも会えるし」
「うん…そうだね」
頷くくせに全然そう思ってないって顔に見えた。思わず腕を伸ばしての手を掴むと、はハッとしたようにオレを見た。
「オマエ…何か悩んでんのかよ」
「…な、悩んでなんかないよ。幸せだし――」
「全然そんな風に見えねえよ」
まさかすでに灰谷の野郎が浮気でもしてんのかと疑った。でもは「失礼だなーわたしは幸せだよ」と微笑む。
「あ、車内販売の人だ。春千夜、お弁当買おうよ」
「……ああ」
いつものに戻って無邪気に笑う。そこでオレは掴んでいた手を離した。その瞬間から後悔のようなものが襲う。昔もオレは意地を張っての手を離したことを後悔したというのに、また同じことをするつもりかと思った。後悔をするのは二度とごめんだ。
まだ間に合うなら、今度こそオレはこの手を離すべきじゃない。なんて、あの頃、何度もを傷つけたのはオレなのに、勝手な思いが過ぎる。
だけど、知らなかったんだ。あの頃オレに芽生えた気持ちが、こんなにも大きく膨れ上がって、大人になった今も心に居座るなんて。
でも今ならハッキリ言える。あの頃、に向けていた勝手な想いは、確かに恋だった。オレはに、恋をしていたんだと。
それをどこかで分かっていながら逃げてただけだ。ガキの恋愛なんていつかは終わる。だから関係を壊したくなくて、永遠にそばにいられる方を選んだつもりでいた。そんなの後悔するに決まってるのに。
――春千夜、大好き。
叶うなら、もう一度あの笑顔でそう言って欲しい。そうしたらオレも誰に遠慮することなく、が大好きだって素直になれる。とことん、らしくはねえけどな。