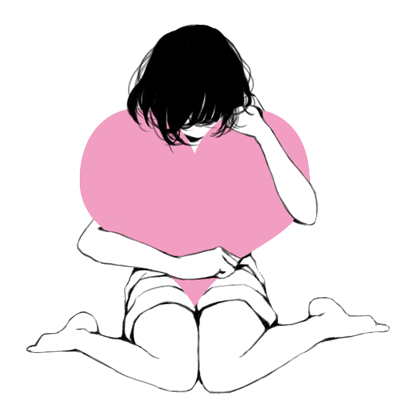
-13-いつか想いは冷める、永遠なんて信じない
1.
「春千夜に近づくんじゃねえよ」
そう、それは全くの同意見だ。何て気が合うんだろう。違う世界線なら友達にだってなれそうだ。でもこの子とはいくら気が合うと言っても絶対に友達にはなれない。春千夜の彼女という称号を与えられた、この子だけは。
「近づくも何も…わたしは春千夜の幼馴染だし、付き合いだってそっちより古いんですけど」
「幼馴染なのは知ってるけど、アンタ、春千夜にちょっかいかけてんだろーがっ。学校の子に聞いたよ?アンタ、ずーっと春千夜に片思いしてるんだって?可哀そ~」
春千夜の前じゃ甘えた声を出してるクセに、わたしの前じゃ不良も真っ青なくらい口が悪い子で、内心びっくりした。でもそんなことで怯むと思ったら大間違いだ。
「だから何ですか」
「目ざわりなの。集会の時も周りにチヤホヤされたくて来てんでしょ?なのに春千夜にまでちょっかいかけやがって」
「かけてませんけど。それにチヤホヤされたいのそっちでしょ。知ってるのよ。春千夜と付き合ってるくせに蘭さんにこっそり連絡先渡してたの」
「……っ」
「新しいメンバーの人ならバレないとでも思ったの?」
この話はこの子が蘭さんに何か渡してるのを見かけたわたしが直接蘭さんに聞いたから間違いない。わたしの一言でその子の顔色が変わった。派手なメイクをして、イラついたように綺麗に巻いた髪をしきりに手で梳いている。その指先にはキラキラ光る装飾のついた長い爪。でもその派手な見た目は抜きにしても、この子は相当遊んでる。空気とか匂いで分かる。きっと春千夜以外にも男がいるんだ。蘭さんから話を聞いた時、そんなの許せないと思った。
「春千夜を傷つけたら許さないから」
「…は?何それ」
「春千夜はああ見えて繊細だし傷つきやすいの。だから春千夜に嫌な思いはさせないで。彼女なら彼女らしく振る舞ってよっ」
「…っ知った風な口利くんじゃねえよ!」
それは一瞬のことだった。髪をいじってた手が振り上げられて、気づいた時には頬に痛みが走っていた。
「オマエは相手にされてねーんだから春千夜のことはサッサと諦めろ」
最後にそんな捨て台詞を吐いて、その子はわたしの前から走り去った。途端に神社は静寂を取り戻して、小鳥の囀りさえ聞こえて来る。東卍がいつも集会に使うこの場所に呼び出されて来てみれば、散々な結末が待っていた。
「…痛い」
叩かれてジンジンとする頬へそっと触れると、指先にまさかの血がついていた。
「え、嘘…」
ちょっと驚いて鞄からリップとか入れてるポーチを出して中から鏡を取り出した。すぐに自分の顔を映してみると、叩かれた辺りの頬に引っかかれたような一筋の赤い線が走っている。そこであの子の派手な爪を思い出した。きっと爪先に付けてた装飾が叩かれた拍子に頬をひっかく形で当たってしまったんだろう。
「最悪……」
あの子に言いたいことは言えたけど、やっぱり悪意をぶつけられるのは楽しいことじゃない。汚い言葉をぶつけられ、あげく――。
――オマエは相手にされてねーんだから!
分かってるよ、そんなこと。アンタに言われなくてもわたしが一番それを理解してる。春千夜があの目に映すのは、いつもわたし以外の誰か。
「分かってるよ…そんなこと」
無意識にそんな言葉が零れ落ちた瞬間、涙まで零れ落ちた。頬の傷口に沁みて少しだけピリピリとした痛みが走る。
「そっか…涙って塩分含まれてるんだっけ…」
こんな時なのに、そんなどうでもいいことを思い出した。真っすぐ帰る気分にもならなくて、そのまま駅まで足を伸ばした。渋谷の駅は人がゴチャゴチャしてるけど、今みたいな寂しい気分の時はこのざわめきが何故かホっとさせてくれる。週末の夕方。更に人は増えて、駅から歩いて来る人達の合間を抜けて、わたしは時々立ち寄るカフェに向かおうとした。春千夜の彼女に呼び出されて酷く緊張したからか、喉が渇いている。冷たいドリンクを飲めば、少しは気分も上がるかもしれない。そう思いながら人の流れに逆らうように歩き出した時だった。
「あれ、ちゃん?」
聞き覚えのある声に名前を呼ばれて思わず振り向くと、そこには――。
「やっぱそうだ」
灰谷兄弟のお兄さんの蘭さんが立っていた。でも彼はわたしの顔を見て少し驚いたように「そのホッペ、どうした?」と僅かに目を細めた。やっぱり傷は目立つらしい。
「い、いえ…ちょっと引っ掛けちゃって…」
と言い訳をしていると、蘭さんの隣からひょこっと顔を出したのは知らない女の人だった。
「蘭ちゃん。誰?この子」
「あー…」
まずい。女の人を連れていたのか、と少し焦った。慌てて自己紹介をしようとした時、蘭さんの方が先に口を開いた。
「この子は東卍の総長や初代メンバーの幼馴染の子でさ」
「ああ、いつも蘭ちゃんが話してる人たちだ」
その女性は親しげに蘭さんと話している。雰囲気からして、いつも蘭さんや竜胆さんが連れて来る女の子達とは少し違う印象を受けた。もしかしたら恋人なのでは、と思っていると、蘭さんがその人に「ちょっとこの子と話あんだけどいい?」と言い出した。デート中かどうかは知らないけど、女の人が一緒になのに何で?と焦ってしまう。この人だって絶対に気分を害するはずだと思った。なのに、その人は「うん、分かった」と笑顔で頷いている。
「わりいな。一時間後くらいに、またここで待ち合わせしよ」
「うん、いいよ。じゃあ、わたし、目当てのパルコで買い物でもしてくるね」
「おう。じゃあな」
と言って蘭さんも手を振っている。いったい何を考えてるんだと呆気に取られていると、蘭さんは「じゃあ行こうか」とわたしを今行こうとしていたカフェに促す。サッサと歩いて行く蘭さんにハッとして、わたしも慌てて後を追いかけた。
「あ、あの…いいんですか?彼女さんほったらかしてわたしと――」
「彼女ぉ?ああ、違う違う。今のはオレの幼馴染」
蘭さんは振り返って楽しげに笑いだした。幼馴染と聞いてちょっとだけ驚く。
「オレが最近渋谷に来ること増えて話聞かせてたら私も渋谷に行きたいって言いだしてさ。だから連れて来てやったの。――ああ、ちゃんは何飲む?」
「え?あ、えっと…じゃあ…ストロベリーフラペチーノを…」
「へえ、ちゃんもそれ好きなんだ。アイツもそれ好きなんだよなー。あんな甘いのよく飲めるな」
蘭さんは笑いながらもわたしの言った飲み物を注文をしてくれた。蘭さんは甘い飲み物は苦手のようで普通のドリップコーヒーのアイスが好きらしい。
「で…?どうしたんだよ、その傷」
「え…」
店内の空いている席に座った途端、蘭さんが溜息交じりで訊いて来た。
「引っ掛けたなんて嘘だろ?どう見ても誰かに殴られた痕だ。何気にホッペ赤くなってるしバレバレ」
「………」
「オレを誰だと思ってんの?殴られた痕は見慣れてるっつーの」
蘭さんはアイスコーヒーを飲みながら苦笑している。そうか、しょっちゅうケンカをしてる人から見れば、すぐに分かってしまうんだ。ならどんな言い訳をしても無駄かもしれない。
「で…こんな可愛いちゃんを殴った奴はどこのどいつ?何ならオレが今からソイツ、ぶん殴って来てやろうか?」
「えっダ、ダメです…相手は女の子だし――」
驚いて顔を上げると、蘭さんは意味深な笑みを口元に浮かべた。そんな意地悪そうな顔でも蘭さんは綺麗すぎるから嫌になってしまう。
「へえ。女の子なんだ」
「あ…」
まるで蘭さんの誘導尋問に引っかかった気分になって、わたしは再び俯いた。
「何があったかくらい教えろよ。別にその子を殴ったりしねえから」
「はあ。いや、でも…」
「あー…なるほどな」
「え?」
まだ何も言ってないのに、蘭さんは何かを察したように苦笑いを零した。
「あれだろ。三途の女」
「……っ?」
ほんとに何でこの人にはそんなことまで分かってしまうんだろう。そう思ってると、わたしの顔を見て蘭さんは笑いだした。
「やっぱそうか。まあ…ちゃんの表情で分かったわ」
「え…わたしの?」
「言いにくそうにしてるってことは殴った相手はオレの知ってる女。じゃあ何でちゃんはそこまで相手を言いたくないのか。それはその女の彼氏に知られたくねえから。だろ?」
「す…凄いですね、蘭さん……千里眼でも持ってるんですか…?」
「ぶははっ。そんな大層なもん持ってねえけど、ちょっと考えりゃ分かるし。その傷、あの女の爪に引っ掛けられたんか」
「…はあ。まあ…でも大丈夫です…わたしも言いたいことは言えたんで」
「ふーん。強いじゃん」
蘭さんはそう言って笑うと、腕を伸ばしてわたしの頭をクシャクシャっと撫でてくれた。意外にもその大きな手が優しくて、また泣きそうになるのをグっと堪えた。
「ちゃんはホント三途のこと好きだなー?アイツのどこがそんなにいいわけ?」
「え…ど、どこって…」
「言っちゃ悪いが、アイツは素直じゃねえし口も態度も悪いし、ついでに女を見る目ねえし?オレにはさっぱり分かんねえわ」
「む…で、でも春千夜にも良いとこいっぱいありますから。不器用なだけでホントは凄く優しいし…そりゃ確かに素直じゃないとこはあるけど――」
とムキになって言い返すわたしを、蘭さんがニヤニヤしながら見ていることに気づいてハッと息を飲む。きっと今の言葉はわざと言ったに違いない。わたしの反応を見て楽しんでる気がした。
「ほら、やっぱ好きじゃん」
「そ…そうですけど…何か?」
「いや…ちゃんの気持ち分かるなあと思って聞いてた」
「…え?分かるって…」
想像と違った応えが返って来て驚いたのと同時に、今の言葉が気になった。気持ちが分かるってことは蘭さんもわたしと同じような想いを抱えてるってことだろうか。そう思いながら蘭さんを見つめると、彼はふっと笑みを浮かべて窓の外へ視線を向けた。
「オレもしてんの」
「え…」
「幼馴染に片思いってやつー」
言いながら、蘭さんは視線をわたしへ戻すと、にっこりと微笑む。まさかの告白に、わたしも言葉を失った。
2.
――春千夜、大好き。
これまで何度もに言われた言葉が頭の中をぐるぐる回ってる。振り払いたいのに、いつもオレの中の真ん中に居座って、なかなか消えてはくれない。
「オマエとは終わりだ」
「は?」
「テメェはオレの大事なもんに傷つけたろ。二度とそのブサイクなツラ、オレの前に見せんな」
そう吐き捨てると、派手なメイクをした顔を歪ませて「自惚れんな!もともと春千夜なんて好きじゃなかったし!」と怒鳴りながら、女は怒って走り去った。でも何の感傷もない。アイツがオレのことを本気で好きじゃないのも分かってたし、オレも好きで付き合ったってわけじゃない。じゃあ何でと聞かれれば「何となく」としか言いようがねえ。でもそんなもんだろ。オレ達の歳での惚れた腫れたは一時のもんだろうし、そんな一瞬のことに心を消費して何になる。オレの中での一番は昔から変わらない。それ以上の相手は出てくるはずもなく。だったら適当な女と適当なことして遊んでりゃいい。そうすればオレの中のモヤモヤを一時でも吐き出せて、またいつものようにオレのそばで笑顔を見せるアイツと一緒にいられる。
「なかなか不器用な男だなあ、オマエも」
場地はそう言って笑うけど、器用なヤツなんてオレらの周りにそうそういねえだろが。皆、を好きなクセに、の気持ちを優先して諦めてるやつばかり。そのに想われてるオレは、アイツを女の子だと認識した日からキスされた記憶をリセットさせて必死で幼馴染という立ち位置を守ろうとしている。自分の気持ちに気づくのが怖くて、気づいたら何かが壊れてしまいそうで、つい冷たく接してしまうのが不器用ってんなら、確かにそうなんだろう。でも、だけど。オレにも失いたくないものがあるんだ。の想いを受け止めて、アイツとそう言う関係になったとしても。それが永遠に続くかどうかは分からない。今はオレのことを大好きだって言ってくれるが、もしオレを手に入れたら、そこから気持ちが少しずつ減っていくんじゃないかと怖くなる。
人間なんてそんなもんだろ。欲しくて欲しくてたまらなかったものが手に入れば、熱は冷める。それまでの情熱は消えて、必ず他のものへ目が向く。オレ達みたいなガキの恋愛に、永遠なんてものはあり得ない。
だからオレは怖かった。に「大好き」と言われれば言われるほど、この想いを受け止めてしまったら、後は冷めていくだけだと分かるから。だからこそ、今の関係を崩したくないって思ってしまうオレがいる。
オレは不器用なんかじゃない。臆病なだけなんだ。