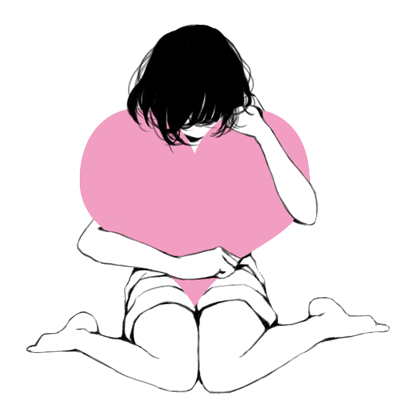
-15-あなたに届くものが声であればいい~⑴
2017年5月。
1.
「ではでは、マイキーくんの優勝を祝しまして…」
「「「「かんぱーい!!」」」
名古屋駅近くのホテルのレストランで、マイキーの優勝祝いと称した食事会が開かれた。音頭を取ったのはマイキーのスポンサーである九井、そして稀咲だ。今日のレースは呆気ないほどマイキーの圧勝で、は大興奮だった。今はマイキーの隣で今日のレースの凄さを熱く語ってる。それを昔と変わらず「はいはい」と聞きながら、マイキーも楽しそうだ。ドラケンは今後のことで九井たちと真面目な話をしてるし、オレは特に興味はないから目の前の豪華な料理に舌鼓打っていた。のリクエストだった手羽先なんかも出て来て、レストランで手羽先かよと思わないでもなかったけど、はとにかく満足そうだった。
「春千夜、飲んでるか?」
酒のボトル手に声をかけて来たのは稀咲だった。コイツとも東卍を結成した時からの付き合いだ。どこで知り合ったのか、ガキの頃マイキーが連れて来た花垣武道が、「コイツも仲間に」と言って連れて来たのがこの稀咲だった。元々がり勉タイプだったようで、稀咲はやたらと頭が切れる。九井とは何気に気が合ってたようで、若い頃から一緒に事業を展開して成功者となったのはさすがだと思う。
「このワイン美味いんだ。飲むか?」
「お、いいじゃん。それも好きなヤツ」
「だから頼んだんだよ」
稀咲は笑いながら大きなワイングラスにワインを注いだ。何となく互いにグラスを持つと「乾杯」という感じの空気になって、軽くグラスを合わせる。チンっという小気味いい音が耳に心地よく響くのはグラスまでが高級なせいだろう。実際ヨーロッパでは乾杯の時にグラスを合わせることはしないらしい。お互いにグラスを軽く持ち上げるだけで成立するようだ。でもここは日本だし昔から馴染んだ方法で乾杯する方がオレらにはあってるようだ。
「美味いな、やっぱ」
「も結構飲んでたぞ」
「げ…マジか」
「今日は名古屋に一泊すんだろ?」
「ああ。このホテルに部屋はとった」
「さすが人気ユーチューバー。やるじゃん」
「いや、散々稼いでるオマエに言われたくねえよ」
オレがツッコむと稀咲は楽しげに笑った。人気なんて言ったところでユーチューバーで長いこと稼げるのはほんの一部だけだ。地に足のついた仕事をしてる皆の方が、オレは凄いと思う。何年か前、妹の千壽に誘われて、配信なんてものを軽い気持ちで始めただけだったはずが、二人して素で会話してるだけで何故か登録者数がえらいことになってた。そこから定期的に配信をしてたらアっという間に登録者数が倍になり、そのうち広告収入がどんどん入ってきてオレ自身ちょっと驚いてる。でもそれまで働いてたバイクのエンジニアの仕事も好きだから続けてるし、将来的にはそっちの道で食っていきたいとは思っていた。
「なーんか、こうしてると昔を思い出すよな」
ふと稀咲が皆の方を見て呟いた。マイキーやドラケン、に九井。皆が楽しそうに話しながら酒を飲んでる姿は、確かにあの頃と重なるものがある。あの頃は酒なんか当然飲めなくて、それぞれコーラやジュースで乾杯して、公園とか神社で夜遅くまで騒いでた。夏には皆で花火をして、次の日には誰かしら蚊に刺されてて「かゆい!」と騒ぐまでがお約束。
「そういやが一番刺されてたよなーオレや春千夜は一か所二か所なのに、何故かは八か所とか笑ったわ」
「アイツは昔っから刺されやすいんだよ。血液型にも関係あるらしいけど、とオレは同じなのに何でかアイツの方が血は美味いらしい」
「ああ、そう言えば春千代の血はマズいらしいってが言いふらしてたことあったな」
「あ?アイツ、そんなこと言ってたのかよ。ウゼェ」
稀咲の話に思わず吹き出した。そんな些細なことでもあの頃は話のネタになって、からかったり笑ったりと大騒ぎしてたっけ。将来への不安なんか一つもなくて、根拠もない自信に溢れてた気がする。も変わらず隣にいるもんだと思っていた。これから先も幼馴染として一生、一緒に未来を歩んでいくものだと。でもいざ大人になってみれば、はもうすぐ他の男と結婚する。の隣にいるのはオレだったはずなのに、あの忌々しい灰谷がその場所を奪った。
(ま…それもこれも全部自業自得なんだけどな…)
あの頃の自分をぶん殴りたい気分だった。何でもっと素直になれなかった?何度考えてもオレがバカだったとしか言いようがない。の気持ちに胡坐をかいて、コイツは絶対にそばにいてくれると過信していた。が恋人を一度も作らなかったから安心してたってのもある。
ただ一度だけ、ハタチになる少し前、が高校時代の同級生と付き合いだしたなんて噂が広がったことがある。でもその時は単に同級生グループと大勢で映画に行って、たまたまその中の男とポップコーンを買っている姿を一虎に見られたことで変に脚色されて話が大きくなっただけだった。でもその時、初めてが他の男と付き合うかもしれないという不安に駆られたのは事実で。中学の頃から何も進展していないオレ達の関係を変えてみようかと思ったことはある。オレもだいぶ大人になってたし、他の男に奪われるくらいなら、今更照れ臭いなんて言ってられない。そう思った。
――話があんだけど。
いつものように夕飯を作りに来てくれてたにそう言って、自分の部屋に連れて行った。だけどいざ二人きりになっての顔を見ていたら、なかなか切り出せなくて。情けない自分にだんだんイライラしてきた時、が「話ってなに?」とオレの顔を覗き込んで来た。至近距離で目が合って、ドキっとしたのはオレの方だ。はいつの間にか凄く綺麗になっていて、毎日会ってたはずなのに、今更ながらに実感した瞬間だった。でもだから余計に照れ臭くなったのかもしれない。
――春千代、顏真っ赤だけど…どうしたの?具合悪い?
――は?悪くねえし!いいからもう帰れよっ
――え、でも…話って?
――それは……あ、明日の弁当…いらねえから。
――ええ…もっと早く言ってよ…おかず作っちゃったじゃない。
結局あの日はそんな会話で終わってしまって、かなり落ち込んだくらいのトラウマになった。好きだってたった一言がどうしても言えなくて、いつもキツい言い方をしてしまう。みたいに、素直に好きだと言葉に出来る気がしなかった。それからもグダグダして、何も関係は変わらないまま。がまだオレのことを好きなのかどうかさえ分からなくなってきた頃、降ってわいた灰谷との結婚話にオレは言葉を失った。
「ところでこのホテルって春千夜の名前で予約したのか?」
「ん?ああ、そうだけど…何で?」
「いや。有名人だし本名で予約したなら大丈夫かなと思って」
稀咲はそう言って笑っている。
「別にそこまで有名じゃねえって。それより…最近どんな金儲けしてんだよ」
「金儲けって…なーんか人聞きわりいな」
ワインを注ぎながら訪ねると、稀咲は苦笑しながらも「今は九井と海外の土地購入して――」と楽しく語り出した。それを聞きながら、ふとを見るともオレのことを見ていて、不意に目が合う。その感覚が懐かしいとさえ思った。あの頃も、オレがチームの誰かと話してると、気づけばがこっちを見ていて、そしてその後――必ず嬉しそうに微笑んでいた。
「春千夜と稀咲くんは何話してるのー」
テンションも高く割り込んで来たがオレの膝の上に座る。
「稀咲の金儲けの話…っつか、テメェ、どこに座ってんだよ」
「だって椅子持ってくるの面倒だし…。じゃあ稀咲くんの膝に――」
「やめろって。稀咲のスーツ、いくらすると思ってんだ。シワになるからオマエは大人しくここにいとけ」
移動しようとしたの腕を慌てて掴むと、それを見ていた稀咲がニヤニヤしている。オレの腹ん中、全部見られてる気がして思わず咳払いをした。別に今更他の男の膝に座ろうが、それを止めようが何も変わらないのに。現実を思い出して、また絶望へと一歩近づいた。
2.
「あー楽しかったぁ」
「オマエ、飲み過ぎ。フラフラしてんじゃん」
腕を掴んで支えながらホテルのチェックカウンターへ向かう。マイキーのレース後、チェックインもせずに少し観光してからレストランに直行したからだ。
「すみません。予約した明司だけど」
「はい、少々お待ちください」
受付のオッサンはパソコンで何かをチェックし、すぐに「明司様でご予約は二名様ですね」と確認してきた。
「はい」
と応えながらも、隣にでフラフラしてるに「大丈夫かよ」と声を駆けつつ、オッサンがキーを持ってくるのを待つ。すると数秒ほどでキーを差し出された。
「2015号室です」
「あーはい…」
とカードキーを受けとり、エレベーターの方へ行こうとした。だがふと足を止めて手の中のキーを見下ろす。どう見てもそれは一つしかない。
「あの…すみません」
「はい」
もう一度受付に戻ると、手にあるカードキーを見せた。
「これ一つしかないけど。予約したのシングル二つだったよな」
「え…?」
「え?」
オレの問いにオッサンが驚くからオレも驚いた。
「ええと…先ほど赤司様からお電話でお部屋のタイプを変えたいという申し出がありましたので、ダブルでお部屋をご用意させて頂いたのですが…」
「は?オレが?」
「はい。そう承っておりますが…」
オッサンの説明に思わず声を上げた。いつオレがホテルに電話して部屋を変えた?多少酔っているとはいえ、そんなことを忘れるはずがない。
「いや記憶にねえ。いいから最初の予約通りシングル二つで――」
「申し訳ございません。先ほどシングルは全て埋まってしまいまして…」
「…は?」
「申し訳ございません」
オッサンは丁寧に頭を下げて来る。空気的にこれ以上何を言っても無駄な気がした。そもそもオレ自身が部屋を変えたことになってるんだからホテル側に落ち度はない。ならいったい誰がオレの名前を語ってホテルに――と考えたところで、あの眼鏡ヅラが浮かんだ。
「アイツ…!」
だからさっきオレの名で予約したか確認したのか。でも何でこんなことを?と思いつつ、隣で「春千夜…どうしたの?」と不安げに見上げて来るを見下ろす。どう応えようか困ったものの、こんな時間に他のホテルを探すのも大変だ。しかも今夜はオレ達と同じように地方からレースを見に来ている客が大勢いる。どこのホテルも満杯だろう。
「…悪い。部屋がダブルしかねえって」
「…えっ」
二人してロビーに佇みながら、途方に暮れた瞬間だった。