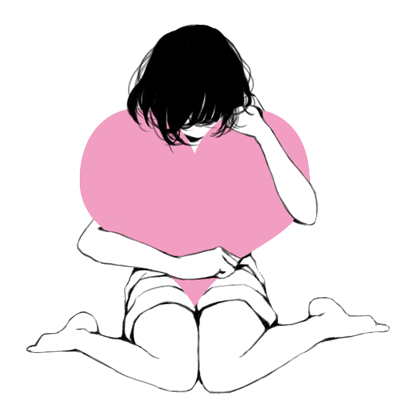
-17-いるべき場所は君の隣
1.
「春千夜~千壽~ご飯出来たよー!」
そう声をかけながらコーヒーにたっぷりミルクを入れる。明司兄弟はどちらもこれだ。自分の分と三つのコーヒーを淹れてからパンの焼け具合を見た。前はザ・日本の朝食って感じのが多かったけど、高校に入学して少しした頃から千壽が「たまにはパン食もいいなー」と言い出してから、一週間に2回はパンになっている。パンともなるとおかずのバリエーションが似たようなものになっちゃうから卵料理で工夫をしていた。今日は小松菜とベーコンのミニオムレツ。いわゆるキャッシュ風だ。他にフルーツとヨーグルトにちょっとしたサラダ。春千夜はご飯でもパンでも美味しければ何でもいいって人だから、もっぱら千壽の食べたい物に合わせていた。まあ二人の食の好みは似てるから、その辺はわたしも助かってたりする。
「おはよ~」
まずは千壽が目を擦りながら起きて来た。ふわふわの髪に寝癖がついてるから「歯を磨くついでに顔洗って髪直しておいでよ」と笑う。千壽は素直に頷いて洗面所へ歩いて行った。そのすぐ後に春千夜が欠伸をしながらリビングに一度顔を見せる。
「あ、春千夜、おはよ」
「ん…はよ」
まだ眠たいのか、春千夜の大きな瞳が今は半分になっている。夕べはまた夜更かしをしたらしい。
「今、千壽が顔洗ってるから春千夜も洗ってきて」
「…マジか。アイツ、すぐ洗面台びしょびしょにすんだよなぁ…」
ブツブツ文句を言いながら春千夜も洗面所へ向かう。春伊代は潔癖気味だからその辺は意外とうるさい方で、いい加減な千壽はいつも怒られていた。今朝もまた洗面所からキャンキャン言い争う声が聞こえて来た。
「オマエ、水出し過ぎなんだよっ!だから跳ねるんだろ?」
「もーうふはいなー。はふひよはー」
「何言ってっか分かんねえぞっ」
歯を磨きながら文句を言う千壽に春千夜がまたキレる。こんな風景も昔と殆ど変わってない。
わたし達は高校生になり、その頃には東卍も解散することになって、東京卍會というチームはなくなってしまった。日本最大のチームになったことでマイキーの夢は叶い、そこでスッパリ解散することにしたそうだ。夢が叶ったと同時に解散なんて、マイキーらしいなあと思う。今後は好きなバイクに関する仕事がしたいと話してて、他のメンバーもそれぞれ自分のやりたい道へ進む為に、今は真面目に高校へ通ってるようだった。
チームは解散したけど、仲間との交流は今でも続いている。時間があればつるんでるから、チームがなくなってもその辺は前と何も変わらない。因みに春千夜はバイクのエンジニアの仕事に興味があるようで、来年卒業したらそっちの道に進むような話をしていた。先月から近所の整備工場で週三回、バイトも始めている。そしてわたしはと言うと、皆ほどハッキリした将来の夢はなく。漠然と大学進学を考えていた。
(あーそろそろ、どこの大学にするかハッキリさせないとなぁ…。やっぱり近さで選んじゃう?)
アレコレ考えつつ、先に朝食を食べ始めると、未だに言い合いを続けながら千壽と春千代がリビングにやってきた。
「歯を磨いて顔を洗い終わったら最後に洗面台を拭けっつってんだよっ」
「忙しい朝にいちいちめんどい。気になるならハル兄がやれば?」
「はあ?何で汚してねえオレがオマエの後始末やらなきゃなんねーんだよっ」
よくもまあ飽きもせず同じネタでケンカできるもんだと感心しつつ、「ほら、二人とも座って。早く食べないと遅刻しちゃう」と声をかける。まずは春千夜が渋々といった顔でテーブルにつき、千壽もまたムスっとした顔でわたしの隣に座る。でも二人は食べ始めると機嫌が直るのはいつものことだ。睡魔と空腹で朝の機嫌が悪いのは明司家の特徴だったりする。
「んー、このオムレツ美味しい!これ、ホウレンソウ?」
「ああ、それは小松菜。意外と合うでしょ」
「へえ、いつもありがとね、工夫してくれて」
「いえいえ。わたしも結構楽しんで作ってるから」
「パンもいつもと違うね。このロールパン、ほんのり甘い」
「ああ、それ駅前に新しく出来たパン屋さんで買ってみたの。ふわふわで美味しかったから。春千夜、ふわふわパン好きでしょ?」
「あ…?」
急に話を振られて驚いたのか、黙々と食べてた春千夜が顔を上げる。
「あーまあ。美味いわ、確かに」
「良かった。また買って来るね」
「…おう」
春千夜は小さく応えつつ、コーヒーを飲み干すと徐に立ち上がった。
「ごちそーさま」
「うん」
どんなに機嫌が悪くても、春千夜はその言葉を欠かさず言ってくれる。それだけで、何となく報われた気持ちになった。
「あ、いいよ。そこに置いておいて。私洗っておくから春千夜は着替えておいでよ」
「あー…さんきゅ」
空いたお皿やカップをシンクに置いて、春千夜は自分の部屋へ戻っていく。残さず綺麗に食べてくれたお皿を見ると、自然に頬が緩むまでがわたしのデフォルトだ。
「まーたニヤけてる」
千壽も空いたお皿を下げながら、わたしのことを肘でつつく。そういう千壽も顔がニヤついていた。
「ほんとも一途というか、しつこいというか…」
「む。しつこいは余計だし」
「だってハル兄好きになって何年経ったっけ。自分としてはそろそろくっついて欲しいんだけど」
「それは…春千夜に言ってよ」
「まあ、確かになー」
千壽はケラケラ笑っている。わたしとしては笑い事じゃないんだけど。
「でもハル兄、また女と別れたぞ」
「…えっ?でもまだ一週間くらいじゃなかった?」
「最近、その辺のサイクル早くなったよなー。飽きるの早いっつーか」
千壽は呆れたように笑ってるけど、実はわたしもそれは感じてた。
春千夜が彼女なんてものを作るようになって、最初の頃は酷くショックを受けたりもしてたけど、それが回を重ねるごとに免疫がついたようで、春千夜がどこぞの女の子とくっついたり離れたりしてるのを千壽から聞きながら、わたしも「またか」くらいにしか思わなくなってた。それはきっと、春千夜に彼女が出来ても、ずっとわたしの居場所があったからかもしれない。こうして明司家にご飯を作りに来ることは、春千夜に彼女がいてもいなくても変わらなかったから。
「結局さぁ、ハル兄はあれなんだよ」
「…あれ?」
千壽は肩を竦めながらわたしに視線を向けた。
「誰と付き合っても一緒。好きにもならなければ長続きさせようとかも思ってなさそうだし、ヤレればいいーとか思ってそうだもん」
「……っヤ、ヤレればって…」
とんでもないことを言いだした千壽は、真っ赤になったわたしを見て再び笑い出した。全く千壽は年上のわたしよりそっち系の話に詳しいんだから。
「、真っ赤。純情だねー」
「バ、バカなこと言ってないで早く着替えておいでよ」
グイグイと千壽の背中を押すと「わーかったってばー」とホールドアップしながら自分の部屋へ歩いて行く。でもその際千壽が「あ、そーだ。自分今夜は遠慮してあげるから」と言い出して、何のことかと聞こうとした時、千壽とすれ違いで制服に着替えた春千夜が出て来た。
「何騒いでたんだよ?」
「な…何でもない…」
「あっそ。じゃあ行こうぜ」
「う、うん」
春千夜に促されるがまま、わたしも鞄を手に持ち玄関へ歩いて行く。その際、千壽が自分の部屋の前で立ち止まってこっちを覗くように顔を出してた。その顏は相変わらずニヤケ顔だ。思わず睨むと、千壽は慌てて顔を引っ込めた。
「何してんだ?行くぞ」
「あ、うん」
先に歩いて行く春千夜の後から、急いで靴を履いて追いかけていく。高校はもちろん春千夜と同じとこを受験したから、わたしと春千夜は今も同じ学校に通っていた。因みにその学校には元東卍メンバーも何人かいるから、中学の頃とさほど見える景色は変わらない。
どうにか追いついて春千夜の隣に並ぶと、ホっと息を吐く。わたしが一番安心するのはやっぱり春千夜の隣なんだと実感する瞬間だ。時々この場所を他の子に奪われても、気づけばまたこうして隣を歩ける幸せを噛みしめていた。
「あ、春千夜、今夜は何が食べたい?」
「朝から夕飯の話かよ」
「だから聞いておいた方が作る方は楽なんだってば」
いつものやり取り。これもわたしと春千夜の間ではお約束になっている。中学の頃は「まるで夫婦の会話だよな、オマエら」とスマイリーくん達、東卍の古参メンバーや、イヌピーくんやココくんみたいな後から組にもよくからかわれたりして。そのたび顔がニヤケちゃうのはわたしの方だった。よく彼らは自分の彼女のことを「嫁さん」なんて呼んでたけど、わたしは本当に春千夜のお嫁さんになりたい、なんて思ったりしたっけ。まあ、それは今も変わらないんだけど。
わたしの問いに春千夜は少し押し黙ると、何かを考えるように空を見上げて、すぐに俯いた。その際、指で鼻の頭を掻いてるのは何か言いたいことがある時の春千夜のクセだった。
「あー…今夜は夕飯いらねえわ」
「…え?何で?どこか出かけるの?」
春千夜がこれを言い出す時は大抵、彼女と夜出かける時が多かった。でも千壽はさっき今の彼女とはもう別れたって言ってたのに。
「もしかして…彼女とデート…?」
こんなこと聞きたくない。でもつい口から出てしまった。すると春千夜はギョっとしたような顔でわたしを見た。
「は?ちげーし!つか、アレとはもう終わった」
「…え?じゃあ…」
「今夜会いたいって言われたけど断ったらゴネたから面倒になったし」
春千夜は顔をしかめつつ、そんなことをボヤいている。でもじゃあ今夜は何があるっていうんだろう。もう東卍は解散したから、春千夜が彼女とのデートよりも優先してた集会はないはずだ。
「つーか、オマエこそ…何か食いたいもんとかねーのかよ」
「え…?わたし?」
何でわたし?とクエスチョンマークが脳内に溢れそうになった時、春千夜が呆れた顔でわたしを見下ろした。ほんと相変わらず目つきが悪い。ガンたれ大会なんてものがあったら春千夜は絶対上位に行けると思う。優勝はやっぱり圭介かな?なんて下らないこと考えていると、隣で溜息が聞こえて来た。
「オマエ、忘れてんのかよ。今日の誕生日だろ」
「…え…あっ!」
「はあ…マジで忘れてんのかよ…」
頭を鈍器で殴られたと思ったくらいの衝撃を受けたわたしを見て、春千夜が今度こそ盛大に溜息を吐いた。
「だ、だって…最近期末テストとかでバタバタしてたし…」
「だからって自分の誕生日忘れるかよ。ったく。まー夕飯何食いたいって聞いてきた時点で何となくそんな気がしてたけど」
呆れたように笑いながら、春千夜はわたしの頭を掴んでぐりぐりしてくる。視界が右へ左へ揺らされるのを感じながら、さっきの春千夜の質問を思い出した。
「え、じゃあ…今夜…」
「だから飯、奢ってやるよ」
「え…?春千夜が?」
「何だよ…嫌なら――」
「い、嫌じゃない!嬉しいっ」
あまりに驚いてるわたしを見て、春千夜が徐に顔をしかめるもんだから、わたしは慌てて春千代の腕をガシっと掴む。あの春千代がわたしにご飯をおごってくれるなんて、天変地異が来るかもしれないけど、それでもいい。明日地球が消滅しようと今夜さえ生きていられれば!なんて大げさなだと笑われそうなことを思いながら、「春千夜とご飯行きたい」と腕にしがみついた。
「わ、分かったって…いいから放せよ」
「あ、ご、ごめん」
道の往来だったことを思い出してパっと腕を放した。でも自然と顔はニヤケてしまう。あの春千夜がわたしの誕生日にご飯をご馳走してくれるなんて、今まで一度もなかった。いつもは万次郎の家に集まって皆でお祝いをしてくれていたからだ。ただ一つ気になったのは…。
「で、でも…何で急に…?いつもは万次郎んちで皆がパーティしてくれるのに」
「だからそのマイキーの都合がつかねえんだよ。何でか他の皆もアレコレ用事があるだの言ってたし。あげく今年はオマエが祝えばいいだろとか言ってきやがって」
春千夜はブツブツ言いながら前を歩いて行く。でもわたしはその話を聞いて皆が気を利かしてくれたんだと思った。そこで思い出した。さっき千壽も「今夜遠慮してあげるから」と言ってたのを思い出す。あれはこのことだったんだ。
「んで?は何が食いてーの」
「春千夜と食べるなら何でもいい」
「それ一番困るヤツじゃねーか…」
わたしの言葉に春千夜は苦笑すると、「放課後までに考えとけよ」と言った。
「給料入ったばっかだし少しくらい高くてもいーから」
「え…」
春千夜はそう言ってもう一度わたしの頭にポンと手を置くと、欠伸をしながら学校へ歩いて行く。その後ろ姿を見ながら、嬉しすぎて泣きそうになった。
2.
「あー!美味しかったぁ~!」
は本当に嬉しそうな笑顔で言いながら、う~んと両腕を伸ばした。
今日はの誕生日ということで、初めて外食に連れて行くことにした。毎年マイキーの家で集まるのが恒例だったのに、今年に限って都合が悪いと言われ、いつも集まる古参メンバーにも声をかけたら、何故か皆まで都合が悪いと言い出した。彼女とデートだとかぬかしてたけど、これまでは彼女がいようと絶対参加してたクセに。でもは毎年仲間同士で集まるのを楽しみにしてたから、結局前日までその話をすることは出来ずじまいで。どうしようか悩んでいた時、妹の千壽が言った。
――もう17歳だし皆で集まるより、今年はハル兄がどっか連れてってあげたら。
何でオレが?とは言ったものの、のガッカリする顔は見たくない。だから千壽も誘って初めての外食でもしようかと思った。でも千壽までが「自分、ガッコ―の友達と映画にいくし」と言い出し、最終的にオレとだけで出かけることになった。なのに何故かが行きたがったのはスマイリーとアングリーが始めたラーメン屋。もっといいものでもいいって言ったのに、は「二人の店がいい」と言い張って、仕方なくそこで誕生日を祝うことにした。オレとが顔を出すと、二人はギョっとしたような顔をしてたけど、美味しいラーメンや餃子を出してくれて、は「美味しい」と大喜びで餃子はおかわりまでしてた。あんま誕生日感はない夜だったのに、は今も機嫌が良さそうにオレに笑いかけている。その嬉しそうな顔を見て、オレもホっとしてた。
「春千夜、ほんとありがとう」
「いや、こんくらい…別に」
駅前通りを並んで歩きながら家路につく。大したことをしたわけじゃねえのに、があまりに幸せそうに笑うから、どこか気恥ずかしくなった。たかがラーメンと餃子でこんなに喜んでくれる女なんてくらいのもんだ。ふと今まで適当につき合って来た女達のことが頭を過ぎった。あれが欲しいだのこれをして欲しいだの、要求だけが膨らんでく女達が面倒で、だからすぐに別れてきた。別に連れ歩きたくて付き合ったわけでも、愛情があったわけでもない。お互い利害関係が一致しただけの、ただのセフレみたいなものだ。なのに女の中には時々勘違いしてオレに彼氏としての振る舞いを要求して来るような奴もいる。だから最近は面倒だと感じたら速攻で縁を切るようにしていた。
それに――もうそろそろから逃げることをやめて、現実を見た方がいいとオレ自身、分かって来たからかもしれない。
数年前はが女になっていくのを気づきたくなくて、無理やり見ないようにしてきた。でも少しずつ大人になってくるたび、そんなことは出来ないと気づいた。はオレの中でずっと、一人の女の子だったから。それを認めたら随分と気が楽になった気がするし、気持ちに余裕が出て来たことで前よりは多少優しく出来るようになった。
「あ、露店だー」
駅前通りの道路脇に、ハンドメイドのアクセサリーをずらりと並べてる男女がいて、が嬉しそうな声を上げて走っていく。昔からはああいう店を見るのが好きだった。何でもお店に売ってないからこそいいんだと話してた。ああいうハンドメイドのは殆どが一点ものだから、他の誰も持っていない特別な物だと感じるらしい。
「コケんなよ」
「大丈夫ー」
声をかけると、は笑顔で振り向いて「春千夜、早く」と手招きをしてくる。オレまでつき合わせんのかよと苦笑しながら歩いて行くと、は沢山並んだアクセサリーをキラキラした目で眺めていた。
「どれも可愛い~!お姉さんが作ったんですか?」
「そうよ。メンズのは彼だけど」
どうやらカップルでアクセサリーを作ってるようで、殆ど趣味だと話していた。作りたいと思った物を作って、数が増えて来たらこうして売りに来るらしい。はピアスやネックレス、ヘアアクセサリーなど、一つ一つ手に取りながら「どれも可愛くて欲しくなっちゃう」と笑った。その明るい笑顔に、オレまで釣られて笑みが零れた。
「好きなもん選べよ」
「…え?」
「買ってやっから」
「え、いいの…?春千夜」
「ああ」
別に誕生日だからと思ったわけじゃない。誕生日のプレゼントならこんな間に合わせのような感じじゃなく、もっとちゃんとした形でちゃんとしたものを渡したかった。でもがあまりに欲しそうにしてるから、つい口から出たって感じだ。なのには更に嬉しそうな笑顔で「じゃあ…これ」と手に取ったものをオレに見せて来た。
「…これでいいのかよ」
「うん、これがいい」
それは髪につけるバレッタと呼ばれるものだった。てっきりネックレスとかそーいうもんを欲しがるかと思っていたオレは何となく拍子抜けした。
「じゃあ、これ下さい」
「はーい、ありがとう御座います。これは…1500円ですねー」
「……(やすっ!)」
何となく誕生日プレゼントを意識してしまったからか、値段を聞いたら本当にこれでいいのか?とも思った。でもは「あ、付けてくんでこのままでいいです」と、ニコニコしながら受け取っている。
「…どう?似合う?」
早速は長い前髪を耳にかけて、顏の横の髪を止めるようにバレッタを付けた。そんなことを訊かれても答えに困るけど、その飾りはによく似合っていて、思わず頷いてしまいそうになった。
「まあ…いいんじゃねえの…」
この期に及んでも素直に「可愛い」とは言えないオレは、いつものように素っ気ない言葉しか言ってやれない。でもそのたった一言での顔がぱぁっと明るくなった。
「へへ…春千夜に褒められちゃった」
「……いや、褒めてはねえけど」
「もー。そこは可愛いなでいいんだよ、春千夜」
オレの態度にスネたように言い返すに、笑ったのは露店の女だった。
「あはは、彼氏ツンデレ?彼女、良かったね、彼氏に買ってもらって」
「え、えっと……はい」
オレのことを彼氏と呼ぶから思わず顔が熱くなった。でも反論する前にが勝手に返事をしている。どうやら完全にカップルと思われてるようだ。それがかなり照れ臭くて、オレは金を払うとサッサと歩き出した。
「あ、待ってよ、春千夜~!」
足早で歩くオレの後からが必死に走って来る。そして何故か追いついた時、腕を絡めて来た。
「何だよ…うぜえ」
「だって…嬉しいんだもん」
「……たかが安物のアクセサリーで大げさなんだよ、オマエは」
「でも…わたしにはどんな高級なアクセサリーより嬉しいよ?」
「…チッ。だから大げさ――」
「ありがとう。春千夜、大好き!」
ニコニコしながら見上げてくるに、ドキっとさせられる。聞き慣れたはずの言葉なのに、今はやけに心臓へ刺さった気がした。
「……はあ。帰るぞ」
どう返せばいいのか分からずに、いつも通り素っ気ない一言を放って歩き出す。それでも家に着くまで、の腕が外されることはなかった。