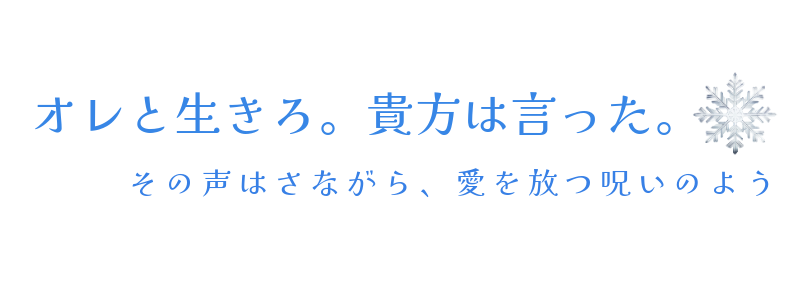とても寒い雪の夜。
大好きな人と喧嘩をした。
「神田のバカ!大嫌い!」
思わず叫んだ私に背を向け、神田は「勝手にしろ!」と言い捨てて去っていく。その冷たい背中を見ていると、私の存在は彼にとって軽いものなのかと思ってしまう。そんなはずはないって分かってるのに。
――バカは私だ。
「何よ……少しくらい否定してくれたって……」
我慢していた涙が一気に溢れて頬を伝っていく。凍えるような寒い夜だから、頬を濡らす涙も一瞬で冷たい雫となって地面に落ちた。
「――また喧嘩ですか?」
背後から声をかけられドキリとした。慌てて涙を拭い振り返ると、同じエクソシストであるアレン・ウォーカーが静かに歩いてくる。
「アレン……」
「すみません。向こうで鍛錬してたら聞こえてしまいました」
ここは教団の鍛錬場所のすぐ裏だ。誰がいてもおかしくはないけど、こんな時間にいるとは思わなかった。アレンはポケットからハンカチを出すと、それを私へ差し出した。彼の優しさはこういう時、やけに身に沁みる。
「使って下さい。あ、洗濯したばかりで綺麗ですから」
「……ありがとう」
素直に受け取り濡れた頬を拭くと、私は目の前にあるベンチへと座った。空を見上げれば白い雪が休むことなく落ちてくる。それが自分の白い息と混じり合い更に寒く感じた。
「どうしたんですか。ケガしてるのにこんな場所で……また神田に意地悪されました?」
アレンは隣に座ると、いつもの優しい笑顔を見せてくれる。彼の笑顔はこういう荒んだ精神状態の時に柔らかい安堵感をくれるから不思議だ。
「神田も……アレンみたいな笑顔を見せてくれたらいいのに」
「え?」
「なんて……神田には似合わないか」
自嘲気味に笑うと、アレンは途端に眉をへにょりと下げた。優しい人だから、きっと心配してくれてるんだと思う。
「大丈夫ですか?何なら僕がビシっと神田に――」
「いいの。私が悪いんだ……」
「……聞かせて下さい」
優しく微笑んでくれるアレンなら、私の愚かさを呆れないで聞いてくれるだろう。そう思ったら、また涙が溢れてきた。
下らない、とても下らない嫉妬をした。
神田と一緒に出向いたイノセンス回収の任務。イノセンスを宿してたのは若い女の子だった。
エクソシストになり得るかもしれない存在を、神田が私より優先するのは当たり前のことで。
彼女も今はただの一般人で、戦い方など知らないのだから仕方ない。
突然のアクマ襲来で咄嗟に彼女を抱きかかえて攻撃を回避した神田は、私をその場へ置き去りにした。アクマ数体を私ひとりで迎え撃たなくてはならなくて必死で応戦したけれど、一瞬は死を覚悟した。
戦ってはケガをして血が流れていく。痛い。怖い。
エクソシストだからと言って、神田みたいに皆が鋼の精神力を持ってるわけじゃない。人並みに恐怖を感じることは当然のように、ある。
「でも戦ってる間中、一番ツラかったのは……その場に神田がいないことだった」
「……当然ですよ。さんは女性です。女性ひとり戦場に置き去りにするなんて――」
「ううん……。違うの」
「……違う?」
首を振った私を、アレンは不思議そうな顔で見つめた。純粋で、優しいアレンならきっと、あんなやり方はしないんだろうな、とふと思った。
「私ね、神田に恋をして、それを受け入れてもらえて……少し浮かれてた。任務中でも知らないうちに甘えてたのね、きっと」
「それは当たり前ですよ。誰だって好きな相手と結ばれたら浮かれるし、傍にいてくれたら甘えてしまいます」
「うん……でも私はやっぱりエクソシストだから。いつ、どんな状況でも神田を頼るんじゃなく、ひとりでも戦える心構えが必要だった。神田はね、それを教えようとしてくれたんだと思う」
3体はどうにか倒した。けれど最後のアクマに追い詰められた私はここで死ぬんだと覚悟した。
体中から血が溢れて、全身が痛くて、泣きたくなった。
アクマが銃弾を放ったのが見えた時、私の足はとっくに動かなくなっていて。咄嗟に自身のイノセンスを構えた私の視界を遮ったのは――。
「え?じゃあ神田は戻って来たんですか」
「――当たり前だろ。バカもやし」
突然聞こえた声に驚いて私とアレンが振り向くと、そこには仏頂面をした神田がそっぽを向いて立っていた。あんなに怒って立ち去った神田が、まさか戻ってくるなんて思わなかった。顔を見た途端、堪えていた涙が零れ落ちる。
アレンは"バカもやし"と称されたことが気に入らないのか、ムっとしたように目を細めて神田を睨んでいた。
「戻って助けるなら最初から置き去りにしなきゃいいんですよ」
「アァ?!まずは一般人の非難が優先だろーが!それにオレははなからがやられるなんて思ってねえ」
「……え?」
「その場を任せても大丈夫だと思ったから置いて行った。それをコイツは鬼だ何だと文句を垂れて、あげく助けた女が綺麗だったから、そっちを優先したんだってバカなこと言いだしたから――」
「は?」
「ちょ、ちょっと神田!余計なことは言わなくていいから!」
アレンの呆れたような視線が痛くて、私は慌てて神田の口を塞いだ。分かってる。
あの時、死ぬかもしれないと思った恐怖が強すぎて、助けてくれた神田を見た瞬間バカなことを口走ってしまったことは、本当に愚かだったと思う。教団に戻ってからも引っ込みのつかなくなった私は、さっきもその話を持ち出して神田に愚痴を言ってしまったのだ。神田が怒るのは当たり前だ。
「テメェ、手ぇ放せ」
神田はやっぱり目を吊り上げて口を塞いでいた私の手を掴む。思わず首を窄めた時、不意にふわりと首元に何かがかけられ、目を開けた。
「神田……?」
私の首をぐるぐる巻きにしていたのは、肌触りのいい彼のマフラーだった。もしかしてこれを取りに行ってくれてたんだろうか。
「あちこちケガして、その上体まで冷やしたら風邪引くだろ、バカ」
「……あ、ありがとう」
照れ臭そうに顔を背けてる神田を見上げて、つい笑みがこぼれた。不器用な彼の優しさが冷えた体を芯から温めてくれる。さっきまでのどんより気分が一気に晴れていくのだから、我ながら単純だ。
「ほんと……バカでごめんね……」
「のバカは今に始まったことじゃねぇからな」
「……ひどい」
しゅんとして俯くと急に抱き寄せられた。びっくりして顔を上げると、いつもは怒ってばかりの鋭い瞳が、どこか優しさを帯びている。あまりに綺麗で見惚れていると、ゆっくりと神田が身を屈めて、あっと思った時には唇が重なった。神田の肩に小さな雪が落ちてくる光景さえハッキリ見えるのに、一瞬だけ一時停止をしたかと思うくらい脳がフリーズしてしまう。
神田の唇はちゅっと音を立てて啄んだあと、ゆっくりと離れていった。顔の熱が一気に爆上げされて真っ赤になったのが分かる。
「ちょ……神田……っ?アレンがいるのに――」
「もやしなら、呆れ顔でとっくに行っちまったけど?」
「えっ?」
神田がニヤリと笑う。すぐに後ろを振り返ると、さっきまでそこに座っていたアレンの姿がない。多分"犬も食わないやつ"だと気づいて戻ったのかもしれない。いつの間に、と驚きながら唖然としている私の頬に、神田の冷たい手が触れた。
「安心したか?」
「え……えっと……」
急にふたりきりになったことで恥ずかしさがこみ上げる。でも私の答えを聞く前に、神田は再び触れるだけのキスを、私の唇に落とした。
「次、同じような状況になってもオレはお前より一般人を優先するぞ」
「……う、うん。分かってる」
「でものことも死なせるつもりはねぇからな」
寒そうに顔をしかめながらぼそりと呟く神田の手を握れば、そっと握り返してくれる。
戦場では私を突き放すこの手も、ふたりきりの時はこんなにも優しい。
それを忘れないよう、神田の温もりを手のひらに刻んでおこう。