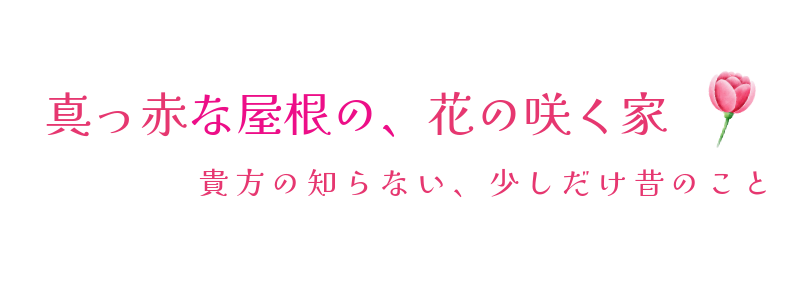月が綺麗な夜だった――。
アクマを倒し、イノセンスを回収して、任務を全て終えた安堵感から、今夜はグッスリ眠れるはずだった。なのに、宿に戻り愛しい人の腕に抱かれた後は、逆に気分が高まってしまって。彼の腕からそっと抜け出して窓の外を見上げれば、あまりに月が綺麗だから夜の散歩へと繰り出すことにした。神田は私に腕枕をしたままの状態でグッスリ眠っている。
起きる気配はない。でも今回の長旅を考えればそれも当然のことだった。
「行って来ます……」
彼の頬にキスを落として静かに部屋を出れば、あとは気の向くまま足を進める。フロントでは宿の主人が居眠りをしていた。
少し趣のある宿を出ると、そこは見知らぬ街並みが広がっている。そう言えばここは初めて来た。世界中を旅しながらイノセンスを回収していると、こうして知らない街へ来られる。それが私のささやかな楽しみでもあった。それでもハードな任務の間はこんな風に街を歩くことなど殆どない。今夜は久しぶりに心が満たされている。
石畳の道をゆっくり歩きながら、色とりどりの屋根が並ぶ景色を楽しむ。この家一つ一つに家族が住み、そこに色んなドラマがあるんだろう、と思うと、何だかドキドキしてきた。私もエクソシストになる前はこんな平凡な世界の住人だったのだ。
近所で暗くなるまで遊び、家に帰ると母の作った美味しい夕飯を食べて、寝る前は絵本を読んでもらう。 少しだけ大人になり、夕飯の手伝いなんかをするようになった頃、人並みに初恋を体験し、淡い恋心を知って母に相談したこともあった。
きっと神田に話してもヤキモチすら妬いてくれなさそうな、可愛い恋だったと思う。
その時、玄関先にチューリップが咲いている家を見つけて足を止めた。それを見ていると一人残してきた母親のことを思い出す。母もこうして家の前の花壇に沢山の花を咲かせていた。春にはカーネーション。夏には向日葵。季節ごとに花は変わる。
「家に帰ってきた時に花が咲いてると気分がいいでしょう?花は人の心を癒してくれるのよ」
母はよくそんな事を言っていた。真っ赤な屋根。玄関先には綺麗な花たち。
それを見ていると、無性に母が恋しくなった。もう、二度と会うことはない。
今の恋を、相談することさえ出来ない。
私達エクソシストは、例え死んだとしても家族のもとへ帰ることはないから。
可愛そうなアクマを作らないために、それが教団の決めた掟だった。
だからこそ私達はホームの家族を大切にしたいと思うのかもしれない。
寄り添い、時には愛し合い、絆を深めたいと思うのかもしれない。
――そろそろ帰ろう。
ふと神田に会いたくなった。今の私が一番大切にしている人に。
宿に戻って、彼の腕に包まれたい。今ならグッスリ眠れそうな気がした。
「……!」
その声に弾かれたように振り向くと、少し息を乱しながら神田が立っていた。
いつもの団服とは違い、上はシャツを羽織っただけの格好だ。
ボタンさえ留めていないその姿に思わず笑みが零れた。
裸で眠っていたはずだから、きっと慌てて羽織って飛び出してきたんだろう。
「どうしたの……?」
「どうしたじゃねーだろ……。お前、何やってんだ、こんなとこで」
「眠れなかったから夜のお散歩。月も綺麗だったし」
「……こんな夜中に散歩なんかすんじゃねぇ」
思い切り抱きついた私の頭を軽く小突いて、彼はいつものように舌打ちをした。
でも今はそんなの気にならないくらいに嬉しい。
実家の花が見られなくても、お母さんに一生会えなくても、私には心配して迎えに来てくれる人がいる。
「だいたい人様の家の前にしゃがんで何してんだ、お前は」
「あのね。この家、私の家と凄く似てるの。私の家の屋根も真っ赤で、玄関先にはこんな風に花が咲いてて」
「あぁ?」
「……この家見てたら、お母さんに会いたくなっちゃった」
「……」
最後は泣きそうになったから神田の胸に顔を押し付けた。
いつもなら「くっつくな」と文句を言う神田も、今夜は珍しく何も言わない。
いつもと違うってある意味凄く怖いかも。ああ、もしかして泣き言を言った私を呆れてるんだろうか。
「……もう。ボタンくらい留めなさいよ」
何となく照れ臭くなって抱きついたまま顔を上げると、神田は僅かに目を細めた。
でもその眼差しは、普段より数倍優しいものだ。
「んなもん面倒くせぇ」
「ふーん。ボタンを留めるのも面倒なほど、慌てて私を探しに飛び出して来たんだ」
「……チッ」
「もしかして心配してくれたの……?」
怖い顔でそっぽを向く神田を見上げたまま、わざと尋ねる。
神田は素直じゃないから、たまには私がこうして代弁してあげないと。
でも、いつもなら「ふざけんな」と素っ気ない言葉が返ってくるのに今夜だけは違った。
「……帰るぞ」
神田の手が私の頭をクシャっと撫でて、その手がそっと肩にまわされる。
私も素直に歩き出すと軽く頭を抱き寄せられた。
普段の彼ならこんなことはしない。
私を抱く時は氷が解け切ったような顔をする彼も、外では恋人同士の甘さなど絶対に見せない男だ。そんな神田が私を抱き寄せて歩いている。いつもと違うことが沢山ある夜だ。
「の家はどこなんだ?」
「前に言ったでしょ。江戸の外れの港町」
「そうか……」
神田はそれっきり、宿に戻るまで口を開かなかった。でも部屋へ戻り、ベッドに入って、冷えた体が温まってきた頃。
「……今度、お前の家でも見に行くか」
私を抱きしめながら、神田が言った。
いいよ、と涙を堪えながら呟く私を、神田は強く抱きしめて。優しいキスを唇に一つ。
他愛もない約束だった。守れるかも分からない、小さな小さな約束。
でもホームシックにかかった私には、神田の優しさが甘い夢のようだ。
「ありがと……ユウ」
普段はなるべく呼ばないようにしている彼の名を口にすれば、やっぱり舌打ちが返って来たけど。
それでも私は幸せだった。幸せな夜だった。
これで――やっと眠れる気がする。