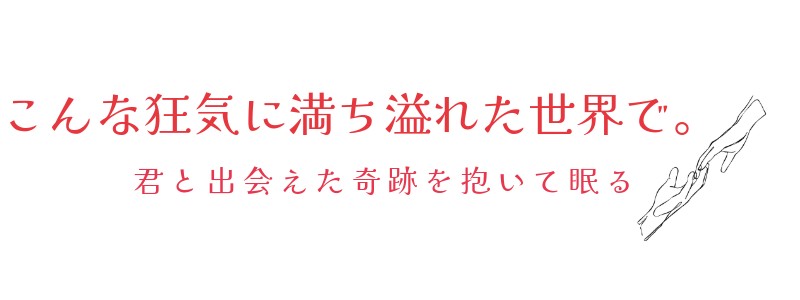「お帰り、ジャスデビ」
疲れ切った体で宿泊先に戻ったオレ達を笑顔で出迎えてくれたのは、ノアじゃないけど家族でもある、本当に普通の人間であるだった。
彼女は千年公が連れて来た女の子で、オレらをいつもサポートしてくれる。彼女だけはオレ達を化け物扱いしない、唯一の人間だ。そしてオレの大事な、女の子。
「どうしたの?ふたりとも元気ない顔してー。クロスは?」
「〜!!クロスの奴に逃げられた〜!」
「アイツ、最悪なんだよ!ヒッ!」
オレ達が泣きつくと、は苦笑いしながら抱きしめてくれた。この優しい手があればどんなに疲れていても元気になるから不思議だ。
「またいなかったんだ」
「蛻の殻だった……クソ、アノヤロー」
「っていうかは何で来たのー?まさか千年公も――」
ジャスデロが怯えた顔をすると、は笑顔で首を振った。
「大丈夫だよ。千年公は来てない。ちょっと心配になったから私だけ様子を見に来たの」
「マジ?良かったぁぁ」
「命拾いしたね、ヒッ!」
千年公が来ていないと聞いて、オレ達はとりあえずホっとした。
そんなオレ達を見ても笑うと、「疲れたでしょ。入って休んだら?」と優しい言葉をくれる。 のそういうトコがオレは――いやオレ達は大好きだった。
とりあえず部屋に入ってベッドに寝転ぶと、は「お疲れ様」とオレの頬に軽くキスをしてくれる。オレからもキスを返そうと思ったら、ジャスデロが「ちゅーしてるー」と騒ぐからやめた。
「デビッドとがちゅーした!ヒッ」
「うっさいなぁ、ジャスデロは。邪魔すんなよ」
「ラブラブだね!ヒッ」
は苦笑いしながらもそんなジャスデロの頭を撫でてあげている。オレと同じように片割れも可愛がってくれるのは凄く嬉しい。でもジャスデロにまでちゅーしなくても!
の顔を見られただけで、たったそれだけで癒されるんだから、オレもジャスデロも単純だと思う。こんなささやかな時間を幸せに感じられる自分が嘘みたいだ。
以前のオレ達はもっと刺激的なことに楽しみを見出して、それを幸せだと感じていた。
エクソシストも人間も大嫌いで、殺したって屁とも思わなかったし、むしろ殺すことが楽しかったんだ。でも今は少しだけ変わった。
は人間だけどオレ達は彼女のことを憎んだりしない。
オレ達が大切に思う人間は、唯一だけ――。
「差し入れ持って来たの。お腹空いてない?」
「チョー空いてる!」
「デロもペコペコだよ!」
ガバっと体を起こすオレ達を見て彼女はやっぱり、と微笑んだ。そして持っていたバスケットから大きなお弁当を出してくれる。は料理が上手だから、今は千年公の代わりにいつも食事を作ってくれていて、オレ達は彼女の作ってくれる物が大好きだった。
「まともな食事してないだろうなぁと思って作ってきたの。はい、ふたりの好きなオニギリ。おかずはこっちね」
「マジ?やった!玉子焼きもあるじゃん!オレ、の作った玉子焼き大好き」
「デロもだよ!の作ったご飯は美味しいよねーヒッ!」
ジャスデロは大喜びしながらオニギリと玉子焼きを頬張っている。
オレも久しぶりにの手料理が食いながら、やっと生き返った。ここ数日、まともな食事も出来てなかったし。 (これも全部あの憎きクロスのせいなんだけど)
はオレとジャスデロが弁当を食べるのを見ながら、散らかった部屋を片付けてくれている。さり気なくフォローをしてくれる彼女はホントに良く出来た女だと思う。
「皆はどーしてる?」
玉子焼きを口に頬張りながら尋ねると、はオレ達の服を畳みながら微笑んだ。
「千年公とロードは箱舟の準備をするのに江戸へ行ったよ。スキンはティエドール元帥を追ってるし、ティキも千年公に言われたリストの人物を殺して回ってる」
「皆、忙しそうだね。ヒッ」
「オレ達だけかよ、こんなとこで足止め食ってんの……」
思い切り溜息をつくと、は軽く首を傾げた。その顔も可愛い。
「そう言えば……デビッドもジャスデロも何でこんなに遅かったの?今まで探し回ってたの?」
「う……それが……」
どきっとして言葉に詰まる。まさかクロスの借金を押し付けられて毎晩バイトしてるなんてには言えない(!)
――と、その時、オレの服のポケットから、あのおぞましい"請求書"の束がボトッと落っこちた。
「何、これ……」
「わっそれは――」
が訝しげな顔でソレを手に取ったのを見て、オレは慌てて奪い返そうとした。
でも一歩遅くかった。は請求書を開くとその大きな瞳を丸くしている。
「な、何これ……酒代、宿代、女、代……?」
「や、それは……」
何か言い訳をしなくちゃと思っていると、が突然怖い顔で振り向いた。
その顔にはさっきまでの優しい微笑みはない。むちゃくちゃ怒ってる顔だ。
「デビッド……何なの、これ!宿代はともかく未成年のクセにお酒なんか飲んで、しかも女代って!クロス探す合間に浮気なんてしてたのっ?」
「えぇっ?!!や、ち、違……っ」
「違わないじゃない!お酒飲んで買った女と何してたのよ!」
はクロスの残した請求書をオレ達のものだと勘違いしたようで、涙目になりながらオレのほっぺたを思い切りビンタした。すんげぇ痛かったけど怒ってる顔もチョー可愛い。(言ってる場合か)
この恐ろしい誤解を解く為にはクロスにされたことを話さなきゃならない。でもまさか敵に借金を押し付けられた、なんて、こんな情けない失敗を彼女に話すのは躊躇われる。
と言って……このままだとオレはがいるのに、商売女とヤりまくってた浮気男として彼女に振られてしまう!
ロードやティキにまでバカにされそうだ。(うぎゃ)
オレは以外の女なんか目にも入らないのに、そんな誤解はされたくない。
でも借金のことは言いたくない!ともぜってー別れたくない!オレはどうしたらいーんだよ、ダディ!(千年公)
……と一人悩んでいたら、ジャスデロがバカ正直にあっさりバラしてしまった。
「違うよー♡それはクロスがジャスデビにつけてったヤツっす!それオレらに押し付けてクロスはサッサと逃げやがったんだよ、ヒヒッ!」
「……は?」
「うわ、バカ言うな!」
満足げにお箸を置くと、ジャスデロはにニッコリ微笑んだ。当然彼女は目を丸くして、一人青い顔をしているオレを見上げてくる。
「ホントなの……?」
「え?あ、いや……」
「デロたちはクロスのヤツの罠に引っかかって、その借金返すためにバイトしてたんだよね。ヒッ」
「バ、バイト……?」
「オイコラ、ジャスデロ!」
ベラベラと話してしまった相方を睨みつつ、オレは更に青くなる。なのに当の本人は全く気にしてないから、ニコニコ顔でオレのフォローを始めた。
「デビッドが浮気するはずないよ。一筋なんだから。ヒヒッ」
「ジャ、ジャスデロ!」
「ホントなの……?デビッド」
「……う」
「怒らないから教えて。これ、クロスの置いてった請求書なの?」
の顔にもう怒りの表情は見られない。それにはホッとしたけど、敵の罠にハマったマヌケな男と思われてないか不安だった。
「う、うん……まあ……そうなんだけど……」
ガシガシと頭をかきつつ仕方なく頷くと、は再び請求書に視線を戻し、そのまま深く息を吐き出した。
「そっかぁ……良かったぁ……」
「よ、良くねーよ!敵にこんなもん押し付けられたんだぜっ?」
「そうだけど……でもデビッドが浮気してたんじゃないって分かってホっとした」
そう言って嬉しそうに微笑むを見て、思わず言葉に詰まった。オレは浮気なんかするはずないのに。
「わりぃ。変な心配させて……」
「ううん。私こそ早とちりしちゃった上に殴ってゴメンね。痛かった?」
はそっとオレの赤くなった頬に手を添えて泣きそうな顔をした。その手の温もりに自然と笑みが漏れる。 あんなのちっとも痛くないってのに。彼女がそんな顔してるのを見る方がよっぽど辛い。
「ぜーんぜん平気!ちゃんと説明しなかったのが悪いんだし」
「そうそう。クロスに逃げられて借金押し付けられたんだからね〜ヒッ」
「笑ってる場合か、ジャスデロ!」
後ろで呑気に笑ってる相方の尻を蹴ると痛い痛いと騒いで泣き出す。は見かねてジャスデロをぎゅっと抱きしめた。(そんな甘やかさなくてもっ)
「もう……ダメでしょ蹴ったりしたら。ジャスデロだってちゃんと分かってるわよ」
「デロ、頑張ってるんだよ。ヒッ」
「あーもう、リボンがズレちゃってる」
はグスグス泣いているジャスデロの頭を撫でながらリボンを縛りなおしてあげてる。あれはがジャスデロにってあげたものだ。ジャスデロにだけズルイと文句を言ったらオレにも買ってきてくれたけど、さすがに頭につける勇気はなかったからオレは左足に巻いてるけど。
は千年公に頼まれて買い物に行った先で、オレ達に色んなものを買ってきてくれる。
オレ達が武器にしてる銃も、彼女が闇市でゲットしてくれた代物でかなり役立ってる。
彼女はオレ達双子に優しい。オレとジャスデロは蕩けてしまうくらいにその優しさに溺れてる。まるで母親に甘えるガキみたいだ。
「はい、出来た」
「ありがとー。バイトの疲れも吹き飛ぶよ。ヒヒッ」
「バイトって……いったい何させられてるの?」
ジャスデロの髪を指ですきながら、はオレの方を振り返った。にべったり甘えてるジャスデロに若干の嫉妬をしつつも「皿洗いとか……」と素直に答える。
ここまできたら隠し事はしないで何でも話した方がいい。じゃないと彼女に心配かけるだけだ。
「皿洗い?どこで?」
「クロスが通ってた飲み屋全部…あいつの罠にハマって店に出向いたら、いきなり怖い顔のババァが出てきてさ」
「クロスがオレ達の似顔絵渡して、こいつらが来たら払うって言ったらしいよ。サイテーだよ!ヒッ」
「……はあ。ホント、あの男はずる賢いんだから」
は深々と溜息をついて、眠いーと言い出したジャスデロをベッドに寝かせた。
何もそこまでしなくても、と思うけど、ジャスデロのヤツも久しぶりにと会えたから甘えたいんだろうと思れば文句も言えない。
オレ達はふたりでひとりのノアだから、きっとこの想いも同じなんだ。
大好きなヒトには、誰だって甘えたい。
ジャスデロはに頭を撫でられ、アッサリ眠ってしまったようだ。朝から晩までコキ使われたんだから、それも当然だけど。オレだってホントはすげー疲れてる。
「寝ちゃったわ」
「うん……今度はオレが甘えてい?」
こっちに戻ってきたをぎゅっと抱きしめる。は黙ってオレの頭を撫でてくれた。
を姉のように慕うジャスデロと違って、オレは彼女を女として好きだから、当然それ以上の欲求も出てくる。抱きしめる腕を緩めて、そっと屈むとは黙って目を瞑った。それを確認してから慎重に唇を重ねる。何度しても、この瞬間は胸の奥が一気に熱くなって、ガラにもなくドキドキするんだ。
「……はぁ、満たされる」
「かなり疲れてるね、デビッドも……」
「って言うか、ズタボロ?何でオレらがあいつの借金返すために皿洗いなんかしなくちゃいけねーんだよ……マジ、ムカツクあのヤロー」
「もう寝よっか。その件は明日ゆっくり考えよ?」
「……ん」
彼女の言葉に素直に頷く。でも寝るにしたってこの部屋には当然ベッドが二つしかない。
彼女も当然今夜はここに泊まるはずだ。いつもはジャスデロに遠慮して別々に寝るけど、こういう日くらいはを抱きしめて眠りたいと思った。
「、一緒に寝よっか」
「え、でも狭いでしょ?私、そこのソファでいいよ?」
「ダメダメ。をそんなとこに寝かせるなんて出来ねーし。はちっこいから邪魔になんかならねーって」
そう言ってベッドに彼女を引き込む。ぎゅっと抱きしめて、このまま彼女の体温を感じながら眠れたら、この悪夢からも覚める気がした。
……と言っても、オレだって若い男だから、それだけじゃ物足りない。
抱きしめて、同じベッドに入れば当然そういった欲求も自然と出てくる。
「ん、デビッド……?」
「もいっかいキスしてい?」
の上に覆いかぶさってそう囁くと、彼女はちょっと恥ずかしそうに頷いてくれた。
ゆっくりと唇を重ねれば、またそこから熱が生まれて。今日までの疲れが少しづつとれていく。心も満たそうと、繰り返し触れるだけのキスを仕掛けた。
「……ね、デビッド」
「ん?」
「明日もそのバイト、行くの?」
「……忘れてたのに」
キスの合間に交わす会話じゃないって、と苦笑しつつ、額をコツンとくっつける。でもは心配そうに目を細めた。
「だってあの金額、凄かったよ?大丈夫なの?」
「……全然ヨユー。つか、そのうち逃げるから大丈夫」
「でも……ん、」
言いかけた唇を再び塞ぐ。でもはすぐに「あ」と声を上げた。(せっかくのムードが)
「どしたの?」
「いいこと思いついた」
「いいこと?」
「うん。明日から私もバイト手伝う」
「……は?」
「二人より三人の方がいいでしょ?ね、私も明日一緒に行く」
「な……ダメだって!にあんなことさせられねーよ」
「どうして?お皿洗うだけなら、いつもやってるもの」
「や、でもダメ!皿洗うだけじゃねーし、酔っ払いのいる場所にが行ったら絶対、ヤローどもから狙われるに決まってる!ケツとか触れてもいーの?」
オレが必死に止めると、も「それは嫌……」と顔をしかめた。でも大げさじゃなく、あんな飲み屋に彼女を連れて行くことは出来ない。あの酒場はクロスが出入りしてただけあって、かなりタチの悪い客が来るし、その中にみたいな極上の女が来た日には、奴ら目の色を変えるに違いない。
(想像しただけで、常連の酔っ払いどもをぶっ殺したくなってきた……)
こんな風に彼女に触れていーのはオレだけだっつーの。
「ん、デビッド……?」
それ以上、何も言わせないよう少しづつキスを深めていくと、はすぐに頬を染めた。隣で眠っているジャスデロが気になるのか、視線が泳いでいる。
でもオレは素直な欲求に従って、舌を絡めながら彼女の服の中へ手を滑り込ませた。
「ひゃ、ちょ、ダメ……」
「……何で?オレ我慢できない。久々だし」
「だ、だってジャスデロが――」
「ジャスデロは一度寝たら起きないって。知ってるだろ?」
「だ、だからって……」
「もーオレの元気になっちゃって、早くの中に入りたいって暴れてんだけど」
耳元でそう囁いて、彼女の手を自分の硬くなっている部分に持っていく。は一瞬で真っ赤になって目を潤ませた。そんな可愛い顔、オレを煽るだけなのに。
「……ん、デビッド……」
オレがの身体に触れるたび、彼女の口から甘い吐息と控えめな喘ぎが零れ落ちる。それが脳に伝わって、心が満たされていくのを感じていた。
殺し合いの時に感じる高揚感とは違う。もっと優しくて、あったかくて、確かな繋がりを、は与えてくれる。
何で彼女は人間なんだろう。オレ達とは違う存在なんだろう。
それだけが悲しい。その現実が寂しい。
こうして触れることが出来るのに。心を通わせることが出来るのに。ふたりの生きる時間はどのくらいの差があるのか。その差を埋めるくらいに抱き合えればいいのに。
「……んっ」
彼女の中に入った瞬間、控えめだった声が僅かに跳ねた。隣のベッドで眠るジャスデロを気にして我慢してる彼女が可愛くて、声だしてよと耳元で囁く。
彼女は小さく首を振って、オレの与える緩やかな刺激に熱い吐息を吐き出した。少しづつ奥へと腰を進めれば、の温もりにオレの脳も蕩けそうだ。
腰を動かすたび、ギシギシと古いベッドが軋んだ音を立てる。その音を耳の片隅で聞きながら、久しぶりに触れる彼女の肌に溺れて、いつの間にか夢中になっていた。
「んん……デ、ビッド……もっと……ゆっくりして……」
「ごめ、ん、痛かった?」
小さな唇にキスを落としながら訊けば、は切なげに眉を寄せて首を振った。そんな健気な彼女も可愛くて、オレは軽く笑みを零すと再び唇を重ねる。
ゆっくりと浅く腰を動かしていると普段以上に彼女を感じる気がした。こんな行為に愛を見い出せるなんて前は思ってなかったのに、今はこんなにも感じる。
自分の中にこれほどの愛情が眠っていたなんて驚くけど、彼女を抱いているオレは確かに優しい男だった。
愛してる。愛してる。愛してる。
何度言っても足りないくらいに彼女を愛してる。こんな時間がずっと続けばいいのに。
そう思ったら何だかホントに切なくなってきて。こんな時だというのに涙が溢れた。
「デビッド……泣いて、るの……?」
オレの涙が彼女の頬に落ちて。それに気づいたはそっとオレの頬に手を伸ばした。
その手を取って指先に口づけると、何故かまた胸がぎゅっと音を立てる。
「……何だろ……すっげー切なくなっちゃった」
「……どうして?」
「が好きすぎて、オレ、死にそうなんだきっと」
何もこんな時に実感することないのに。いや、こんな時だからこそ実感するのかな。
本気で好きな女を抱いてると、もっともっとって欲が出る。
この溢れ出そうな愛情で、男ってのはどうしようもなくなるんじゃないかな。
追って追われて。戦っては殺して。オレ達は、平和な世界線で生きてはいけないから。