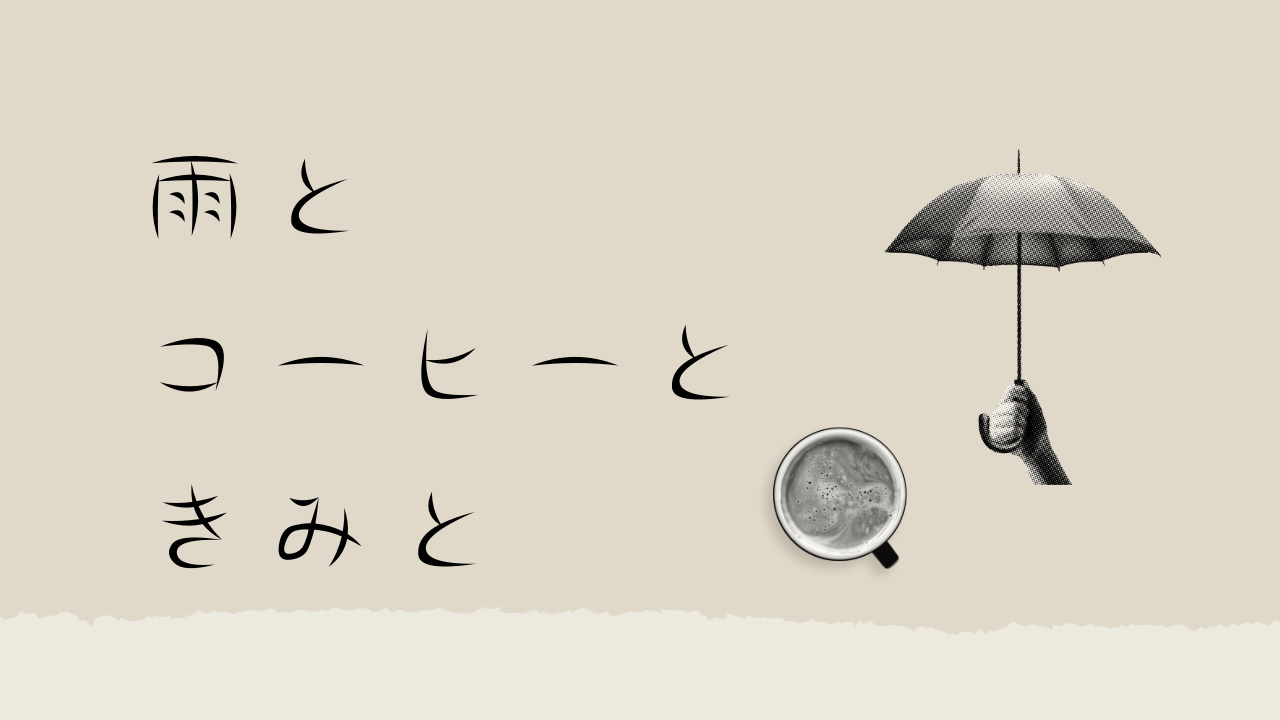ドアが開くたび、カランと鈍い音を立ててベルが鳴る。
そのたびに視線が動いて、来るはずのない人の幻を追ってしまう。
二度と戻れないあの日の青が、今も瞼の裏に焼き付いているせいだ。
小降りだった雨は次第に本降りへと変わった。
「いらっしゃい」
「マスター。いつものねー」
「はいよー」
今、店に入って来たのは近所に住む五十代くらいの女性だった。常連の顔は一通り覚えてしまうほど、何年もこの店に通っている。
それほど広くはない店内には見たことのある客が三人ほどいた。
私はいつもの窓際の席で時折その人達を眺めながら、マスターの淹れる美味しいコーヒーを飲んで過ごすこの時間が好きだった。
香ばしいコーヒー豆の香りが漂う店内には、気にならない程度の音量でオールディーズと呼ばれる曲達が絶え間なく流れている。昔から何ひとつ、マスターの好みは変わらない。
少しくたびれた感のあるソファと昭和を思わせるテーブルの上には、おみくじの引ける玩具が乗っている。これを引くのも今ではルーティンのようになっていた。
球体のおみくじ機は周りに12星座が描かれている。自分の星座が描かれてる上に硬貨の投入口があり、そこへ100円を入れて小さなレバーを引くと中のおみくじが落ちてくる仕様だ。まさにそのレバーを引こうとした時、再びカラン、と新たな客を告げるベルが鳴った。
「やっぱり、ここにいた」
「五条くん……」
高専の制服が視界に入った時、軽い眩暈を感じた。懐かしい笑顔と重なったからだ。
だけど私の前に座ったのは、あの頃の彼じゃない。
「あ、僕もコーヒー。いつもの」
「はいよ。五条くんはお砂糖とミルク増し増しね」
私と同様、マスターとすっかり馴染みになっている同級生は「よく分かってんじゃん」と明るい笑顔でマスターに親指をぐっと立てたあと、サングラスを外してその青い虹彩を私へと向けた。
「さっき電話したのに」
「え、嘘。ごめん、気づかなかった」
言いながらスマホをバッグから出すと、五条くんからの着信が五件ほど入っていた。振動の設定をしてあるものの、バッグに入れてると気づかないことがある。
「マナーモードで音だけ切ったままだった」
「ったく。任務終わったら即チェックして?」
「うん、ごめん。でもよくここだって分かったね」
「……繋がらない時はだいたい、ここにいるでしょ、オマエ」
五条くんは何か言いたそうな顔で私から僅かに視線を反らした。分かってる。五条くんの言いたいことは。
来る途中、雨に降られたせいか彼の肩が少しだけ濡れていた。術式を使えば濡れることなんてないはずなのに、それを忘れるくらい急いで来てくれたんだと分かる。嫌でも分かってしまう。
「五条くん、濡れてる」
「え?ああ……」
バッグからミニタオルを出して彼の方へ身を乗り出すと、肩を拭くのに伸ばした手を捉えられた。
「いいよ、自分で拭く」
五条くんは私の手からミニタオルだけを奪って自分で濡れたところを軽く拭くと、それを制服のポケットへ突っ込んだ。
「洗って返すから」
「え、いいよ。そこまでしなくても」
「明日休みだし洗濯しよーと思ってたからついでだよ」
「普段は殆どクリーニングのくせに」
苦笑交じりで突っ込むと、五条くんは運ばれて来たコーヒーをマスターから受け取りつつ「パンツはクリーニングしないし」と笑った。
私の物を五条くんのパンツと一緒に洗わないで、と苦情を言っても「僕のは綺麗だから」なんてふざけた言葉が返ってきて、つい笑ってしまう。
「昔も似たような会話した気がする」
「そーだっけ」
「うん……」
でもあの時はその場にもう一人、いた。
きっと五条くんも分かってる。だけど敢えて何も言わない。
「……雨、帰るまでに止むといいな」
窓を打ち付ける雨粒を眺めながら、ふと五条くんが呟いた。

11年前――。
その昔ながらの喫茶店は高専に戻る途中の住宅街にあった。
任務帰りに立ち寄るコンビニより少し手前。忘れ去られたような静かな佇まいが、どこか時代に取り残された物悲しさを漂わせていて。
レトロ好きなわたしは、いつかこの喫茶店に行ってみたいと思っていた。
「――あ、知ってる!壁に蔦がびっしりの店でしょ?私も気になってた」
娯楽室でいつもの無駄話タイム。何気なく話した店を硝子も知ってたらしい。まあコンビニへ行く時は必ず前を通るんだから当然と言えば当然だけど。
「おっされーなカフェが主流になりつつある今のご時世で、ああいう昔ながらの喫茶店って逆に新鮮だよね」
「ね。だからかなぁ。私、子供の頃からレトロな雰囲気の店とか物が好きなんだ」
「あー何か分かるかも。今は何でもかんでもデジタル化して新しいものや店も増えてるし、敢えて古い方に戻りたくなることあるかも。公衆電話をたまに使いたくなる感覚に近い」
「ケータイが普及され始めたのだって私達が小学校くらいだもんね」
「確かに」
そんな会話をして笑ってると、同級生のクズコンビが娯楽室へ顔を出した。今日も二人は一緒の任務だったらしい。
「やあ、何の話?」
「廊下までオマエらの笑い声聞こえてたぞー」
夏油くんと五条くんはそんなことを言いながら話の輪に加わった。任務帰りだというのに疲れはないようで、相変わらず元気だ。
途中のコンビニで買って来たらしいパピコを袋から出して割ると、一つを私へ差し出したのは夏油くんだった。
「これ好きだったろ」
「あ、ありがとう、夏油くん」
そんな些細なことを覚えていてくれたんだと驚きながらアイスを受けとると、五条くんは硝子に無理やり「半分よこせ」とパピコを取られてギャーギャー騒ぎ出した。まあ、いつものことだけど。
「悟もケチケチしないで半分くらいやればいいだろ」
「あ?俺は二本同時に食いたいんだよっ」
「五条のケチ!ガキ!」
「にゃにおー?早速食っといてふざんけんな、硝子!」
二人は娯楽室を走り回って残りのアイスまで取り合いしてる。余分に買ってきてくれたくせに、自分が渡すより先にとられるのは嫌みたいだ。ほんと小学生みたい、と笑ってしまう。
「全く……落ち着いて食べられないのか、あの二人は」
私の隣に座った夏油くんは苦笑交じりで、未だに騒いでる硝子と五条くんを眺めている。その眼差しは柔らかい。僅かに目を細めて微笑む夏油くんの雰囲気が、私は好きだった。
彼の隣は心地がいい。どんなに疲れていても、夏油くんの空気に包まれると心が凪いでいく気がする。
「ところで、さっきは硝子と何の話をしてたんだい?」
ふと私に視線を戻した夏油くんは、何とも言えない優しい眼差しで私を見てくるから、とくん、と胸の奥が音を立てる。
「あ、あのね。コンビニ近くに――」
夏油くんに説明しながら、静かに高鳴る鼓動に気づかないフリをした。
いつから、なんて、もう覚えてない。気づいたら目が勝手に夏油くんを追いかけていた。
短気な五条くんを煽るような皮肉めいた笑みも、よく分からない呪霊ネタで五条くんと盛り上がって爆笑してる姿も、後輩に見せる先輩としての顔も、心底呆れてる時のふざけた表情も、全部。
この目に焼き付けていたい。そう思わせる人だった。
きっとこの先も一緒にいられるんだと、信じて疑わなかった。

10年前――。
「あれ、?」
コンビニへ行こうとした夏の終わりの夕方。
急に降り出した大雨に驚いて、私は例の喫茶店の軒下へ走り込んだ。コンビニまで行けば傘は売ってるけど、そこへ行く前にびしょ濡れになるかもと思っての緊急避難的なものだった。でもすぐ名前を呼ばれて顔を上げると、そこへ夏油くんも走り込んできた。
「夏油くん、任務帰り?」
「ああ。帰る前にコンビニに寄ろうと思って。でも駅を出て少ししたらこのゲリラ豪雨で驚いたよ」
「私もコンビニ行こうと思ったらこれ。夏油くんは補助監督の車で戻ってきたんじゃないの?」
ここへ来たのは夏油くんだけで、五条くんは別任務に当たってるらしい。星漿体任務の件からは二人も別行動が増えた気がする。
「ああ、トイレに行くついでに駅で降ろしてもらったんだ。コンビニにも寄りたかったから」
「そっかー。そのコンビニがすぐそこだっていうのに、私も雨の強さに挫けちゃって避難したの」
「はは、そのまま行ってたら更に酷い状態になってたよ」
夏油くんは濡れた肩を手で払いながら笑った。それを見て「あ、待って」と声をかけてからポケットにあるミニタオルを出す。
「拭いてあげるから夏油くんしゃがんで」
「いや、いいよ。汚してしまうし――」
「いいから。髪も濡れてるし風邪引いちゃうよ」
そう言うと夏油くんは苦笑気味に「じゃあ……お言葉に甘えて」と少しだけ屈んでくれた。おかげでいつもより目線が近くなる。雨で湿ったアスファルトの匂いに混ざって、かすかに夏油くんのシャンプーの香りがした。普段からかすかに香ってくるハーブのような爽やかな香りだ。
すん、と、その爽やかな空気を吸うように鼻を動かしたのは無意識だった。
夏油くんの涼しげな黒目が至近距離で私を見るから、頬がじわ、と熱くなるのが分かった。気づかれたかも、と思うと恥ずかしくなったけど、夏油くんは普通に「ありがとう」と言っただけだった。
「あ……か、顔も濡れてるよ」
「うん。もう帰ってシャワー浴びた方が早いね、これじゃ」
そっと夏油くんの額へタオルを当てると、彼は苦笑交じりで言った。その笑みをこんな近くで見てしまえば手が自然に震えてしまう。でも体温が急に上がったせいなのか、急に鼻がムズムズしてきた。
「……っくしゅ」
慌てて夏油くんから顔を背けてクシャミをする。
「大丈夫?」
「う、うん……大丈……っくしゅっ」
「私よりの方が風邪を引きそうだな、これじゃ」
クシャミを連発する私の頭をさり気なく撫でながら、夏油くんは溜息交じりで曇天を見上げた。
「でもこの土砂降りじゃ高専に帰るまでにずぶ濡れになるだろうから余計に悪化しそうだし……」
「わたしなら大丈夫だよ」
ホントは少し肌寒かった。一度着替えに高専へ戻った時、蒸し暑いと思ってTシャツとミニスカートという薄着で出て来てしまったせいだ。
でも、まだ帰りたくないと思ったのは、偶然にも夏油くんと二人で雨宿りをしてるこの時間が嬉しかったから。
毎日顔を合わせてるけど、二人きりになれる時間は意外と少ない。だから降って湧いたような現状を、もう少しだけ、と思ってしまう。
ただ、夏油くんはやっぱり心配顔で私を見下ろした。
「でもの恰好は寒そうだ」
「へ、平気」
「震えてるだろ」
強がりを言っても夏油くんにはお見通しだったらしい。彼は自分の上着を脱ぐと、私の肩へかけてくれた。夏油くんの体温が残っているせいか、冷えた肩がほんのり温かくなる。同時に彼の思いがけない行動に、また熱が顔に集中していくようだった。
「い、いいよ……夏油くんが風邪引いちゃうってば」
「私は大丈夫。シャツの下にTシャツも着てるし、ちょっと暑かったからちょうどいい」
だから着ててくれると助かる、と夏油くんは微笑んだ。
私に気を遣わせないよう、そんな言い方をしてくれてるんだとすぐに分かる。胸のどこかがぎゅうっと苦しくなった。
肩へかけられた上着から、さっきと同じ爽やかな香りがしてくる。記憶に刻まれてしまう匂いだと思った。
「全く止む気配がないし参ったな」
「……うん」
と言いつつ、まだ止まないで、なんて不謹慎なことを願う。こんなサプライズ的な時間はそうそうないからだ。
その時、夏油くんがふと脇にある喫茶店の看板へ視線を向けた。
「ああ、そう言えばここ喫茶店だったね」
「え?あ……うん」
「が前に話してた店だっけ。ちょっと入ってみようか。結局あのあと忙しかったりして来れなかったし」
「えっ?」
いきなりの展開に驚いて思わず声を上げると、「ほら、随分と前に今度行ってみようって皆で話してたろ」と夏油くんが言った。
確かに去年、この店について話した時、夏油くんも興味を示して「なら皆で行ってみよう」という話になった。なったけど今?しかも二人で?と想定外すぎてドキドキしてしまう。
「雨が落ち着くまで温かいコーヒーでも飲んでよう」
「う、うん……そう、だね。ここに突っ立ってるよりマシかも……」
以前から気になってた喫茶店。思いがけず夏油くんと入ることになるなんて思ってもいなくて、ちょっとだけテンションが上がった。
夏油くんがドアを開けるとカラン、と鈍い音と共にベルが揺れる。中からは香ばしいコーヒーの香りと共に「いらっしゃいませ」と静かで落ち着いた声が聞こえてきた。
「ここ座ろうか。雨の様子も見られるし」
夏油くんは窓際の席を選んで座った。うん、と頷きながら向かい側の少しくたびれたソファに座ると、カウンターにいた店主らしき男の人がメニューを小脇へ挟んでお水の入ったグラスを二つ運んでくる。今時のカフェじゃ見られないサービスだ。
「決まったら声をかけて下さい」
「はい。は?何にする?」
夏油くんがメニューを受けとって私へ見せてくれる。こういう古びたメニューも時代を感じてワクワクしてしまう。
「わ、食事も出来るんだ。何か色々ある」
意外にも豊富な食事メニューで少し驚いた。ちょっとした軽食ではあるけどナポリタン、ミートソース、カルボナーラから、ハンバーグセット、ピラフ、オムライス、サンドイッチ、ピザトースト、パンケーキなどが主で、あとはチーズケーキや、パフェなどの甘味も置いてるらしい。
午後五時以降はお酒も提供してるらしく、ドリンクのところにアルコールの類がずらりと並んでいた。昼間のソフトドリンクより種類が多い。
「小腹空いた時にいいね。今度硝子や悟を誘って来ようか。お店の雰囲気もいいし」
「うん。あ、五条くんなら絶対このパフェ頼みそう」
「はは、確かに。――あ、すみません。オリジナルコーヒーをお願いします」
「私はココアを」
「オリジナルコーヒーとココアですね。少々お待ちください」
カウンターにいる渋めのマスターはにこやかな笑みと共に準備を始めた。
今のところ客は私達だけで、他の席はガランとしている。でも長いことやっているようだし、普段はそれなりに客が入るんだろう。駅から少し距離があるから常連でもついてるのかもしれない。
さほど広くない店内を見渡せば年月を感じさせる空気があちらこちらに刻み込まれてるようだ。古ぼけた昔のポスターにはレトロなビールの絵が描かれ、マスターの趣味なのか、棚に飾られている機関車や、古い型の電車のミニ型模型が可愛らしい。壁時計は振り子タイプで、それがまた古き良き時代の空間を演出してくれている。
それに店内で流れているBGMも聴いたことのあるオールディーズ。どれをとっても過去へタイムスリップした気分にさせてくれた。何だろう。やけに落ち着く。
同年代の女の子達が集まるカフェもいいけど、私的には昔ながらの喫茶店の方がゆったりと出来て好きかもしれない。子供の頃から静かな場所が好きだったこともあり、私はすっかりこの店が気に入ってしまった。
「何か落ち着くね、ここは」
夏油くんも同じことを感じたらしい。テーブルの上に置いてある丸い玩具のような入れ物を指して「これおみくじ引けるやつじゃないかな」と珍しく目を輝かせていた。
「え、これおみくじなの?」
「うん。ここにこうして100円玉を入れてこのレバーを引くと……ほら」
カシャンという音と共に本体正面にある口から手のひらサイズの筒のような形状の白い紙が落ちてきた。おみくじというだけあって、広げないと読めないらしい。
「実家の近所にこういうお店があってね。そこに同じようなのが置いてあったんだ」
「え、そうなの?面白い。内容はどんな感じ?」
「ちょっと待って」
夏油くんは小さなそのおみくじを上手く解くと、くるくると開いていく。地味に細長い。
「あ……」
「え、何だった?」
開いた瞬間、夏油くんが苦笑いを浮かべるから、内容が気になって身を乗り出す。彼は開いたおみくじをひっくり返し、私の方へ見せてくれた。そこには一言「凶」の文字。
「え、嘘。そんなのまであるの?」
「確かこの手のおみくじって凶とかはひとつしか入ってないって聞いたことがあるし、その一枚を引いてしまったかも」
「じゃあ、むしろ運が上がるかもよ」
「だといいんだけどね。も引いてみるかい?」
夏油くんはおみくじ機を私の方へ差し出した。もちろん面白そうだから引いてみる。
まずは100円を投入してレバーを引く。また同じような筒状の紙が出てきたけど、紙の色が薄っすらピンクだ。
「どう?」
「えっとね……あ、中吉!微妙!」
「ははは。"モテ期逃しがち"って面白いね」
「え、嘘。そんなこと書いてる?」
「ここにね」
とん、と夏油くんが指したところに、なるほど。そんな文言がデカデカ書かれている。モテ期なんていらないけど、逃しがちってのは何となく当たってる気がした。
「ハァ、今年も彼氏できなさそう」
なんて冗談めかして言ってみれば、夏油くんは「モテるのと彼氏が出来るのとじゃ少し違うんじゃないか?」と笑う。
私は大勢にモテるより一人の人にモテたい……なんて夏油くんに言えるはずもなく。誤魔化すように身を乗り出した。
「夏油くんのは何て書いてた?」
「凶だから良いことは書いてないよ」
苦笑交じりで言いながら、夏油くんはそのおみくじを開いて見せてくれた。そこには確かにこれから運気が下がっていく、などと最もらしいことが書かれてるけど、その後にはちゃんと新たな道を模索すれば回避できる、と前向きな言葉もあった。
だけど――最後に気になる内容が書かれていた。
「"ただし、新たな道を行けば多くを失う"……?」
何となく心がざわりとして夏油くんを見た。でも彼は特に気する様子もなく、運ばれて来たコーヒーを飲んでいる。
「多くを失うって何だろ。新たな道を切り開いたら好転するっぽいけど、何で失うの?」
「これは玩具だし、そこまで深く考え込まなくても。それっぽい言葉を書いてあるだけだと思うよ」
「あ、そ、そうだね」
真剣に考えている私を見て、夏油くんが笑うから恥ずかしくなった。
本物のおみくじでもないんだから、こんなの気にする必要なんてないのに。
そう思いながらすでに運ばれていたココアへ口をつける。上にたっぷりのクリームが乗っていて美味しそうだ――と思って油断した。
「……あっつっ」
「大丈夫かい?」
「う、うん……クリームが温いから一気に飲んだらその下にアツアツのココアが……」
「気をつけて。火傷した?」
「ん、」
不意に夏油くんの手が私の口元へ伸びて、指が唇へ触れる。頬がカッと熱くなるのが分かった。
夏油くんも気づいたんだろう。少しだけ驚いたような表情を見せたあと、手をすっと引っ込めた。
ほんの少し微妙な空気が流れて、何となく互いに黙り込む。妙にドキドキして話が続かない。
気持ちがバレてしまったのかな、と心配になってきた頃、夏油くんが不意に口を開いた。
「それ、悟に飲ませたら引っかかりそうだな。今度ここへ連れてきてココアを勧めてみよう」
「ぷ……確かに。あっちー!って大騒ぎしそうだけど」
夏油くんが真顔で言うから思わず吹いてしまった。とりあえずバレてなさそうだとホっとして、今度は十分気を付けながらココアを飲む。
「この前も唐辛子味の飴をイチゴ味だって嘘ついてあげたら、真っ赤になって大騒ぎするから大変だった。なんてもん食わせんだってデコピンされたし」
「ははは。硝子が買ってきたあの真っ赤な飴だろ?悟も少しは疑えばいいのに、変なところで素直だからな」
五条くんのことで一頻り笑ったあと、夏油くんは雨の打ち付ける窓へ視線を向けると、しばし雨音とコーヒーを楽しんでいる。その横顔をこっそり見ながら、彼の持つ独特の空気を感じていた。
目伏せる仕草だとか、カップを持つ指先だとか、視線の動きすら、好きだなぁと思う。
その全てを独り占めできたなら、どんなに幸せなんだろう。
バカみたいにそんなことを考えていたら、夏油くんがふと私を見た。
「……あまり見つめられると照れるな」
「……えっ!あ、ごめん」
どうやら私の熱い視線に気づいていたらしい。焦りと恥ずかしさで顔から一気に熱が噴き出す。そんなつもりはなかったのに、勝手に目が釘付けになってしまっただけ。でもそれを追求されたらどうしよう。気まずくなりたくないのに。
内心酷く焦る私を見ながら夏油くんは少しはにかんで、ふと目を伏せながらカップの淵を指でなぞる。それがどこか迷っているようにも見えて、いっそう心臓が早鐘を打つ。
相変わらず店内は静かで、コーヒーのいい香りが漂い、懐かしの曲が流れてる。それら全てが二人の間に流れる空気を鮮明にしていくようだ。
夏油くんは何度か視線を泳がせながら、ふと窓の外を見た。
気まずいから、もう帰りたいのかもしれないし、何かを考えてるようにも見える。
言わないで、という思いと、何か言って欲しい、という真逆な思いが交差する。
いっそのこと想いを打ち明けてみようか、と考え始めた時、夏油くんがもう一度、視線を私へ戻した。その不意打ちにどくん、と心臓が跳ねる。
「もし……私の自惚れなら――」
「……え?」
「いや、何でもない」
夏油くんはかすかに微笑むと「雨、止んだよ。そろそろ帰ろうか」と唐突に席を立つ。いつの間にか互いのカップは空になっていた。
会計をして店を出ると、確かにさっきまでの豪雨が嘘のように静かだ。雨後の冷たい空気が顔の火照りを冷まし、日中太陽に熱せられたアスファルトからの湿った匂いが鼻を突く。
夏油くんは何も話すことなく高専への道のりを歩き出した。そのあとを私もゆっくり着いて行く。目的だったはずのコンビニのことなんか、すっかり忘れていた。
さっき、夏油くんは何を言いかけたんだろう。広い背中を見つめながら、そんなことばかり頭に浮かぶ。これまで築いた関係を壊したくないと思う反面、もう壊して先へ進みたいという思いがこみ上げてくる。
もし、夏油くんも同じことを考えていてくれるなら――などと都合のいい思いが過ぎった時だった。
あと数分ほど歩けば高専が見えてくる、といった辺りで、不意に夏油くんが足を止める気配を感じた。思わず顔を上げる。
「夏油く……」
かすかに湿った風が吹き、肩にかけられたままの上着がふわりと靡いた……と思った時には、逞しい腕に抱き寄せられていた。すぐに大きな手で頬を包まれ、唇と唇が重なる。
何が起こったのかすぐには理解もできず、頭が真っ白になる。
ただ唇に柔らかいものを押し付けられて、何度も優しく啄まれた。
薄暗くなった道端でファーストキスをしている。そんな想像すらしていなかったことが現実に起こっている。夢、にしてはリアルすぎるし、夏油くんの唇から移ったかすかなコーヒーの香りが、頬に触れる彼の長い髪が、これを現実だと伝えてくる。
角度を変えながら何度か唇を重ねたあと、夏油くんはゆっくりと離れていった。だけど私の腰を抱き寄せる手の強さは残ったまま。
惚けた顔で彼を見上げると、また不意打ちのようにオデコへちゅっと口付けられた。さっきのキスと今ので耳まで赤い自覚はある。
「……どうやら私の自惚れじゃなかったみたいだ」
夏油くんが少し照れ臭そうに呟くから、私は何も言えないまま頷くことしか出来なかった。

あの時のキスを、私は始まりだと思った。だけど、夏油くんには違ったみたいだ。
半月後、その残酷な現実を私は知らされることになる。
あれから10年経った今でも、私の中であの夜は続いてるのかもしれない。
いつか、またあの日の夏油くんに会えるなら、今度こそちゃんと言葉に出来るのに。
「」
私を呼ぶ声にハッと我に返る。あの日と同じ雨上がり。同じ道。同じ――コーヒーの香りがする。
だけど目の前で私を見つめているのは、彼じゃない。
「どうした?ボーっとして」
「そんなことないよ」
心配そうに足を止めて、五条くんは何とも言えない笑みを私に向けている。
「あの店に行くと、はいつも同じ顔してるよね」
「え……?」
「待ちくたびれたーって顔だよ」
一歩、二歩。五条くんは私に近づいて、指でとん、と私の額を押す。
「まだ、待ってるんだもんな、は」
誰を、とは敢えて言わない五条くんに、微笑みだけを向ける。
愚かだと笑ってくれていい。だけど出来れば何も言わないで。
私は――まだ信じてるから。
「そういや帰りがけに引いてたおみくじ、どうだった?」
五条くんは察したように話題を変えて、私の手を引きながら歩き出す。いつから、こんな過保護になったんだろう。考えてみたけど思い出せない。それくらい昔だった気もする。
「大吉だった」
「うっそ。マジで?あのおみくじ機にそんなもん入ってた?」
「五条くんはいっつも小吉ばっかりだもんね」
「いいんだよ。僕は大きな幸せがたまに訪れるより、小さな幸せが毎日あった方がいいし」
「うわ、嘘みたいに謙虚」
「僕は昔から謙虚でしょーが」
「どの口で謙虚とかいえるかな」
「この口ー」
五条くんがおどけながら自分の唇を指して、わたしの顔を覗き込んでくる。ふと見上げると、サングラス越しに目が合った気がした。その瞬間、ふわりと風が動いて、唇同士が重なる。まるでそうなるのが必然だったかのように、自然なキスだった。
久しぶりの口づけは、やっぱりコーヒーの香りがした。
「もう僕にしとけば」
僅かに唇を放した五条くんが呟く。私は応えないまま、彼の滑らかな頬をぎゅっと抓った。
「ぃてっ」
大げさな声を上げるから思わず吹き出すと、五条くんは頬を擦りながら拗ねたように唇を尖らせた。
「いい加減、諦めろよ」
「それは出来ない」
「何で」
「大吉が出たから」
「は?」
呆れ顔の彼にさっき引いたばかりのおみくじを広げて見せると、その綺麗な青は更に半分まで細められた。少しの希望があるなら、私は信じたい。
「"待ち人来たる――"ね」
「うん」
ずっと待ってるから。待って、待って、待ちくたびれるくらい待ったから。
会えたその時には、ちゃんと失恋させて欲しい。
そうしたら私はきっと、あの日の夜から時間を進めることが出来る。五条くんと未来を歩んで行ける。
「僕も同じくらい待ってるんだけど――」
再び手を繋いで歩き出した五条くんの声が、優しく私の耳に届けられる。
それに応えるように、繋がれた手を強く、強く握り返した。