02-水に堕ちた冬
僕の手で終止符を打った親友の亡骸を、元同級生の硝子に任せるのはあまりに酷で出来なかった。だから僕らに縁も所縁もない補助監督に任せて、事後処理を済ませた後、その足で彼女の家に向かった。
分かっている。ああしなければ僕たちの間に終わりは来ない。終わらせるなら自らの手で、と決めていた。
終わった後も、後悔はしなかった。だけど胸に出来た空洞は、埋めなければならない。
親友の起こした未曾有のテロの影響か、珍しく疲れていた。肉体がじゃない。精神が擦り減っているような、どうにも不快な感覚があった。どうしようもなく心が渇く。
そんな時に思い浮かぶのはいつだって、僕の心に水を与えてくれる先輩の顏。
のことは高専に入る前から知っていた。幼い頃、ある茶会で彼女を見かけたことがあるからだ。当時は偏ったモノの見方しか出来なかった僕は、"憑きモノ筋"の彼女のことを、酷く危険視していた。御三家の人間なら特に通うこともない高専へ入学したのも、そこに彼女が通ってると聞いたからだ。
五条家と同じくらい歴史のある"憑きモノ筋"の家系は、遥か昔、忌み嫌われる存在だった。いつから"ソレ"が始まったのかは定かではないが、先祖の誰かが狗神を崇めたのが始まりとも言われている。一族繁栄の為、陰の存在を受け入れ、その力は代々女性にのみ受け継がれていくという。はまさに、その憑神を肉体に宿していた。
"本来、呪術とは人を呪う為のものである"
そう説いたのは家、初代当主だったらしい。その言葉の通り、狗神は強力な呪詛の力を持ち、憑りついた相手をその力で祟り殺すとされてきた。まさに陰の一族だ。そんな家系に生まれたは、出会った頃、あまり感情表現が上手くない部類の人だったと思う。だから余計に何をしでかすか分からない不気味さがあり、僕は相当警戒してた気がする。
でも、常に威嚇するような態度を見せる僕に対して、は普通に接してきた。今よりも更に淡々とはしてたけど、どんな最低な言動をしようと、僕のことをいつも後輩として扱う。他の人間みたく、いちいち怒ったりもしない。思えば、あの頃、唯一僕のことを許してくれる存在だった。
そこに気づいた時、を視る目が変わった。危険な憑神の人間とかじゃなく、一人の女の子として意識するようになっていた。
傑と決別したあの日、どうしようもなく心が渇いた時、傍にいて欲しいと思ったのはだった。彼女なら余計なことも言わず、ありのままの僕を受け入れてくれる気がして。
だから、新宿で傑と会ったあの日の夜。彼女に会いに行った。
いつも鍵をかけ忘れてるのは知ってた。だから勝手に部屋に上がりこんで、寝ているの隣りに潜り込んだ。彼女の体温を感じていると、不思議なくらい心が安らいで、傑がいなくなって以来、久しぶりに眠ることができた。
だから、今夜も彼女の隣で眠りたかった。たったひとりの、親友を手にかけた夜だから。
案の定、先輩は何も言わなかった。僕の言葉をそのままストンと受け止めてくれた。
(来て良かった――)
彼女の温もりで温まっていくのを感じながら、その体温は僕の冷え切った心をも暖めてくれた。あのままひとりでいたら、きっと青春時代の思い出に脳が支配されていたに違いない。
「五条くん…」
どれくらい、そうしていたのか。
不意に僕の頭を撫でていた彼女の手が止まった。
「…ん?」
「コーヒー淹れるけど…飲む?」
「…うん、飲む」
素直に頷けばはするりと僕の腕から抜け出して、ニットのカーディガンを羽織るとキッチンの方へ歩いて行った。がいなくなっただけで、少し体温が下がった気がする。
日付が変わって今日はクリスマスだ。夕べ少し降った雪のせいで、朝方のこの時間は更に冷えこんできた。
はコーヒーメーカーをセットすると、棚からカップを二つ取り出した。それは僕が男避けに、と勝手に持ち込んだものだ。律儀にちゃんと使ってくれてるのも彼女らしい。
はカップを置くと、キッチンにある蜂蜜の瓶を手にした。彼女は砂糖の代わりにいつも蜂蜜を入れる。それが絶妙に美味い。
「熱いから火傷しないように」
はコーヒーを注いだカップを僕に渡すと、ベッドの端に腰をかけた。上半身を起こして壁に凭れると、手の中で温かな湯気から漂うコーヒーの香りを楽しむ。ふぅーっと湯気を飛ばすように冷ましながら口を付けると、僕好みの甘さになっていた。
「相変わらず美味しいな。の淹れるコーヒー」
「大げさだな。この場合、私じゃなくコーヒーメーカーが優れてるんだ」
「でもこれがいいんだ」
冷え切った内臓に沁み込むような甘ったるさが、今の僕にはちょうどいい。僕に背を向けて座っているは、同じように冷ましながらコーヒーを飲んでいる。
「そう言えば…部屋を片付けてくれた?」
ふと気づいたように彼女が振り返って僕を見る。来た時はいつものように彼女の好物でもある駄菓子が所せましと置かれていたから、それらをきちんと棚に収納しておいただけだけど。
「また増えてたから、そこの棚に並べたよ」
「そう。ありがとう」
「昔と変わらず、まーだ"蒲焼さん太郎"だの"よっちゃんイカ"だの買ってるけど、飽きない?」
「飽きないな。五条くんだって昔はよく私のオヤツを盗んでた」
「まあ、だって娯楽室にあれだけ駄菓子置いてあったら普通食べていいんだと思うでしょ」
あの頃の光景を思い出して、思わず笑う。高専に入学してまず驚いたのがそれだ。寮の娯楽室が駄菓子屋みたいになってたんだから、誰だって驚く。
うまい棒から始まり、ココアシガーレット、よっちゃんイカ、ソースカツ、蒲焼さん太郎、コーララムネに、チロルチョコ。どれもきちんとカラフルな器に小分けされていて、そこを使う生徒はみんな、それを食べてた気がする。どれもこれも、当時がドン・キホーテで買い漁ってたものばかりだ。
は「私のオヤツ」なんて言ってるけど、先輩や後輩の為に置いてたとしか思えない。だって駄菓子がなくなっても彼女が怒ったところは一度も見たことがないし、後できちんと補充されてたのを、僕は知ってる。
「あんなに何かしら食べてても、先輩はちっとも太らなかったよね」
「そんなに食べてた?覚えてないな」
「いや、食べてたでしょ。駄菓子以外だと、あ、あそこ!高専の近所にあった中華屋で麻婆豆腐セットやら、レバニラやら、餃子やら。僕らより食べてたし、いっつも中華の匂いさせてたのまで思い出した」
「生まれつき、エネルギー消費がハンパじゃないからな」
はそう言って、またコーヒーに口を付ける。きっとその"生まれつき"のせいで色んなことが普通じゃなくなったんだろう。なのにその運命を受け入れて、彼女は今も"こっち側"にいてくれてる。それが僕には嬉しかった。
「先輩」
「ん?」
名前を呼んで、黙って見つめると、彼女は戸惑うように瞳を揺らして、それから視線を反らした。こういうところは変わらない。でも昔よりは感情を見せてくれるようになったと思う。だから構うことなく身を屈めて、彼女の唇に自分のを重ねる。彼女の体温が恋しくなると、こうして触れたくなるのは昔からだ。戯れでキスした日も、彼女は怒ることなく、僕のキスを甘んじて受け入れてくれた。でも更に踏み込もうとすると、彼女はいつもするりと、この腕から逃げていく。
「そろそろ…僕を選んでくれない?」
唇を放してから、これまで何度も言ってきた台詞を吐くと、彼女は黙って目を伏せてしまった。でも前よりは進歩したと思う。以前は「これで勘弁してくれ」と、チロルチョコを渡されたこともある。その都度、謎の断り方をするから面白くなって、振られたショックよりも、また告ってやろうと思わせられる。ほんと困った先輩だよ。
「選んで…どうなる?」
「んー。少なくとも先輩を"向こう側"へは行かせない。"こっち側"でうんと楽しい時間を与えてあげられる」
「こんな世界でも?」
「だからでしょ」
「…そう…そうかもな」
ふと呟いた彼女の顔には、あまり見せてくれない柔らかい笑みが浮かんでいた。
別に自惚れだと思われてもいい。昔から素直で純粋なの全ての時間の中に、僕がいたと信じたい。これからも彼女の心に在り続けたい。
そう思うのは我がままかもしれないけれど。
ただ、僕の言葉が、水に落とした小石のように、の心に波紋を広げていくよう願った。
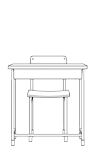
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで

