04-或る事象-2
※夏油視点(03より前の話)
2005年、春も終わり、世間ではゴールデンウィーク真っ只中のある夜。近所のコンビニへ行った帰り、背後から特殊な気配がして振り向くと、案の定、そこには先輩がいた。彼女も任務帰りなのか、愛用の赤いキャリーバッグをゴロゴロと引いて歩いて来る。どこに行くにも持ってるから、以前「邪魔じゃないんですか」と尋ねたこともあるが、とにかく荷物の多い先輩には必需品らしい。
「サムソナイトのシーライト 68L。チリレッドの4輪。360度タイヤが回るのも最高で、ずっと入荷するのを待ってたんだ」
普段は殆ど感情を見せない彼女が、あの時だけは嬉しそうに説明してくれた。見た目も独特で貝殻の表面にも似た凸凹があるそのキャリーバッグは、時に予期せぬ戦闘時、ぶん投げても傷がつきにくいのがお気に入りだそうだ。
彼女の特異な術式上、制服をダメにすることもあるそうだから、常に変えの制服を持ち歩いてる。ただ彼女の持ち物が多いのはそれだけの理由じゃなく――。
「ああ、夏油くんか」
「お疲れさまです」
高専へ続く道の途中。カーブの辺りで待っていると、先輩が私に気づいた。相変わらず表情はないものの、「お疲れさま」と返してくれる彼女の顏は、ほんの僅かに和らいで見える。ただ少し疲れているのか、足元がおぼつかないから、彼女の手からチリレッドの4輪とやらを奪うように持った。
「いいよ。夏油くんも疲れてるだろ」
「いえ、ただのコンビニ帰りですよ。それより…補助監督の方に送ってもらわなかったんですか」
ふたりで高専に向かいながら、ふと気になったことを訪ねる。そもそも何故、任務帰りの彼女が徒歩で帰宅したのかと疑問だった。この高専では呪術師を補助してくれる存在がいて、常に術師と同行するのが通例のはずだ。高専に入学して二カ月は過ぎたことで、私もだいぶここのやり方を理解してきた。
彼女は私の問いに対し、「駅までは一緒だったよ」と答えた。
「でも空腹が限界で降ろしてもらったんだ。私に付き合わせるのも何だから、補助監督には先に帰ってもらった」
「ああ、そうだったんですね。納得です」
先輩は任務をこなすたび、膨大なエネルギーを消費するらしく、限界に達すると倒れてしまうこともあるようだ。その話を彼女の担任である夜蛾先生に教えてもらった時、あの力なら、そうなってしまうだろうな、と納得もした。それに彼女の階級は異例の特級扱い。舞い込む任務も通常任務の比ではないはずだ。
――あの女の家系は"憑きモノ筋"だ。遥か昔には人を呪ってた側の血筋ってわけ。
入学当初、あの悟が先輩のことをかなり警戒してたのを思い出す。本来なら、彼女は呪詛師側にいるはずの人間だと。それは理屈ではなく、彼女の血筋に関係しているもので、本人の意思とは別だという。
こんな風に一緒にいるとそうも思えないのは、私が六眼という便利な眼をもっていないせいなのかもしれないが、彼女から感じる他の術師とは違う空気は、私にも伝わってくる。それは私の術式にも関係してるんだというのは、先輩の肉体に刻まれた憑神の存在を聞いて分かった。私の呪霊操術では到底、制御できないほどの禍々しい存在だということも。
先輩の単独任務が多いのも、きっとそれに関係してるんだろう。彼女はどこか、人を寄せ付けないようにするところがある。
「そう言えば、例の六眼の子とはその後どう?」
不意に質問され、少し驚いた。これまで先輩の方から話を振られたことはない。と言っても、こうして接するのは悟から止められてる為、それほど絡む機会もないからだが。
「ああ…まあ、何とか上手くやってますよ。おかげさまで」
あまり驚いた顔をすれば、先輩は構えてしまうだろう。なるべく自然に見えるように笑顔を繕いつつ応えると、彼女は「なら良かった」とだけ言った。人に興味はなさそうに見えるけど、少しは後輩のことを心配してくれてるらしい。
「もしかして…気にかけてくれてたんですか」
「…別にそういうわけじゃないよ。ただ、ふたりとも今の上級術師たち以上に才能も力もある。そんなふたりが同時に入ったというのに、仲違いしてるのはもったないと思っただけ」
「それ、悟に聞かせてやりたいな」
思わぬところで先輩から褒められ、らしくもないほど高揚した。御三家とはまた違った意味で、名家の娘である彼女から才能があると言われれば当然だ。けど彼女は悟の名を出すと、薄く笑みを浮かべた。
「五条くんか…。彼は…私のことが随分と気に入らないみたいだ」
「そんなことは…あの気性だから、誰かれかまわず噛みついてるだけですよ」
「…ありがとう。でもいいんだ。分かってるから」
先輩はそれだけ言うと、私の手からキャリーバッグを奪って行った。気づけば高専の敷地へ続く鳥居の前だった。
「ここまで運んでくれてありがとう」
彼女はそう言うと、そのキャリーバッグを解錠した。何をするのかと見ていると、中から何か緑色の子袋を取り出し、私の手にそれを乗せる。視線を落とすと、それは――。
「キャベツ太郎…?」
「お礼だ。さっき下のコンビニで見つけて買い占めてきたから遠慮しなくていい」
「…は、はあ。じゃあ…ありがたく頂きます」
特に好きと言った覚えもないのだが、真顔で「遠慮しなくていい」と言われてしまうと、受け取らざるを得ない。受け取ったものの、若干戸惑っていると、先輩は「じゃあ、私は寮に戻る」とひとり歩いて行ってしまった。その場には右手にコンビニ袋、左手にキャベツ太郎を持つ私だけが残される羽目になる。絵的に想像すると何故かジワジワくるものがあった。
「お、キャベツ太郎じゃん。気が利くなぁ、傑」
寮の部屋へ戻ると、ゲームをしながら待っていた悟は私の手から真っ先にそれを奪い、勝手に食べ始めた。どうしたものかと考えたものの、先輩を危険視し、監視を続ける悟に本当のことを言う気にはなれず、「コンビニに売ってたんだ」とだけ言っておく。私は悟が言うほど、彼女が悪い存在には思えなかったし、少々変わり者のところも気に入っている。出来れば悟にも監視まがいのことをやめさせたいが、五条悟という人間は他人があれこれ言ったところで自ら納得しなければ聞く耳はもたない性格だろう。付き合いはまだ短いが、だいぶ私なりに彼のことを理解できるようにはなってきたかもしれない。
ついでに頼まれていたコーラを渡すと、悟はゲームを中断して、ふと私を仰ぎ見た。
「…もしかしてアイツに会った?」
「アイツ?」
「……」
「……」
こういう時、やたらと視力のいい眼を持つ友人も困りものだ。彼女のかすかな残穢でもバレてしまうらしい。先輩のそれは独特だから余計に視えやすいのかもしれないが。
「門のところで会ったから挨拶しただけだよ」
「…フーン」
敢えてキャベツ太郎のことは伏せておく。お菓子に罪はないし、悟はすでに半分まで食べてしまっているのだから、わざわざ言う話でもない。もし言えば、この五条悟という大きな子供は、残り全てを捨ててしまう恐れもある。いや、多分絶対に捨てるだろう。私は悟のような名家でもなく、普通の非術師家庭で育ったから、あまり"憑きモノ筋"との因縁めいた関係は想像でしか考えることは出来ない。陰の一族だと言われたところで、それが先輩を警戒するのとどう関係あるのか分からないというのが正直な感想だ。彼女がそれを望んだわけでもあるまいし、過去のしがらみをぶつけられても、今更どうすることも出来ないだろうに。
「あーなくなっちまった。傑、これもうねえの?」
あっという間にキャベツ太郎を完食した悟は強請るように私を仰ぎ見た。そんな子供みたいな目で見られても「いや…ない」としか言えない。
「ああ、でも娯楽室に行けばあるだろ」
ふと思いついて提案してみたものの、悟は急に顔をテレビ画面へ戻した。
「アレは…アイツのじゃん」
「でも先輩方も勝手にもらってるだろ。彼女も特に気にしてないようだったし」
「いらねーよ。あ、それよりさー。ここの謎解きで詰んでんだけど、ちょっと助言して」
案の定というべきか、悟はあくまで拒否の姿勢を崩さない。まあ、彼の性格ならそうだろうな。五条家の秘蔵っ子だけあって、唯我独尊を地でいってるし、とにかく我がままで気性が荒い。ついでに頑固と追加しておこう。自分が認めた相手以外は、全て敵視するようなところがあるし、最初は私に対してもそうだった。
ふと初対面の時を思い出し、苦笑が漏れる。あの時は悟と数年もの間、同級生をやらなければいけないのか、とウンザリするほど嫌な男だと思った。
最初に挑発してきたのは悟の方だ。私も気が長い方じゃない。カチンときて、一触即発という空気になった。
でも、それを止めて仲裁してくれたのが、先輩だった。あれがなければ、きっと私は今も悟と険悪な関係だっただろう。
ふとあの日のことを思い出す。他人を嘲るような、不遜な態度を隠そうともしない悟は、あの瞬間、確かに私の敵だった。
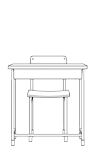
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで

