05-或る事象-3
※夏油視点
2005年、春。中学の頃にスカウトされて入学を決めた呪術高等専門学校で、一人の男と出会った。この世界を牛耳る御三家が一つ。五条家の一人息子、五条悟だ。彼は名家の出とは思えないほど、粗暴かつ態度も悪く。私の何が気に入らなかったのかは知らないが、入学初日からケンカを吹っかけてきた。
――ハァ?呪霊操術?オマエ、呪霊なんか手なづけてんの。きっもー。
幼い頃から呪いは祓うものだと刷り込まれていたらしい悟は、そんな言葉で私を煽ってきた。私からすれば別に欲しくて得た術式じゃない。手なづける、なんて可愛いものでもない。それなりにおぞましい呪霊を取り込む苦悩もある。他のことなら聞き流せたかもしれないが、あの時は私も初めて呪術界の門をくぐったばかりで多少の虚勢がどこかにあったのかもしれない。校内にも関わらず、つい術式を発動してしまった。そうなれば当然、鼻っぱしらの強い悟も大人しく引き下がるはずもなく。「やるってのかよ」と鼻で笑いながら術式を発動。まさに一触即発。怒りのまま互いに攻撃を仕掛けようとした。その時――。誰かが私と悟のちょうど間。まさに悟の収束の力と、私の放った呪霊がぶつかり合うところに、気づけば人が立っていて。それは高専の制服を着た髪の長い女子生徒のように見えた。前髪でよく見えない顔には丸く大きな眼鏡をかけている。
その彼女が眼鏡を外したと思った瞬間、ひとこと呟いた。
「飯縄…拒絶」
その瞬間、彼女へぶつかったように見えた私と悟の攻撃が、一瞬で消滅した。少なくとも私にはそう見えた。何が起きたのか理解が追いつかず、私は文字通り言葉を失い、その女子生徒が誰なのかまで考えも及ばなかったと思う。
しかし悟は違った。邪魔されたのが相当不快だったのか、「何、横からしゃしゃってんだよ、てめぇ」と、今度は彼女へ向けて詰め寄った。
「お前、の人間だろ。人のケンカに横やり入れてんじゃねえぞっ」
ただ熱くなった悟が怒鳴っても、と呼ばれた女子生徒は表情も変えずに言った。
「ここで生徒同士の戦闘は禁じられている。学長に言われなかったか?」
「あぁ?!だから?てめぇに止める権利はねえんだよ。"憑きモノ筋"の人間が!」
最後の言葉の意味がその時の私には分からなかった。だが悟は相当苛立ったんだろう。再び私に向かって「外へ出ろ。決着つけんぞ」と言ってきた。私としてはだいぶ興が削がれていたものの。まだ多少は怒りの火種が燻っていたこともあり、受けるつもりで校舎を出ようとした。あの時はまだ、有名人の悟がどの程度のものなのかを確かめたいという気持ちも少なからずあったように思う。だが、それまで黙って見ていた女子生徒が「いい加減にしろ!」と突然私たちを怒鳴りつけてきた。
それが――高専二年の先輩だった。
「お前たちの力がぶつかり合えば、多大な被害が出る。そんなことも分からないのか」
さっきみたいに怒鳴ったわけじゃない。でも静かな口調ながら、反論できないほどの圧を感じた。同時に、彼女からは独特な負のエネルギーが揺らぎ始めた。それは六眼のない私でも分かるほどに、暗く重い淀み。それほど彼女を包むそれは、おぞましい形だったと記憶している。あれは彼女の憤りが引き金になったんだと、今なら分かる。すっかり毒気を抜かれた私が矛を収めると、彼女はまた静かな声で言った。
「数少ない同級生同士、仲良くしろ。これから長く一緒に戦う仲間だ」
「はい…すみませんでした」
そう素直に謝罪したのは、彼女の言うことは最もだと思ったからだ。でもそれは私だけで、悟は引き下がらなかった。先輩の威嚇が気に入らなかったんだろう。悟は全ての怒りの矛先を遂に彼女へ向けた。
「じゃあ、お前相手ならいいのかよ。先輩」
悟はかけていたサングラスを外し、彼女を挑発するように両手を広げた。しかし逆に彼女は外した眼鏡をかけると、表情のない顔で彼を見上げ――。
「体術の授業でならいつでも相手をしよう。五条悟くん」
「……は?」
真顔で言ってた辺り、彼女は大真面目だったんだろう。それにはさすがの悟も遂に毒気を抜かれたようだ。一瞬、呆気にとられた顔をしたものの、「チッ、アホくさ」と言いつつ階段の方へ歩き出そうとした。それを目で追っていた彼女は何を思ったのか「ああ、これはお近づきの印だ」と言って、スカートのポケットから出した何かを悟の手に乗せるのが見えた。その時の悟の顏は今思い出しても笑える。手のひらに乗せられた物を、あの綺麗な顔が変形するくらい歪ませ、口をあんぐり開けながら見下ろしていたんだから。
「…何のつもりだ、これ」
「ああ、これはマルカワのオレンジがムと言って、駄菓子のガムの中でも人気ナンバーワンの――」
「んなこと聞いてんじゃねえ!」
すっとぼけた返しをした彼女に対し、悟はさっきとは別の意味でキレ始めた。手に乗せられた小さなガムの箱を放り投げ、「ふざけてんのかよ?」と再び彼女に詰め寄っている。ちなみに放り投げられたガムは私がキャッチしておいた。
「別にふざけてはないが…ああ、五条くんにはこっちの方が良かったな」
怒鳴られても全く動じてない様子の彼女は、またポケットの中から今度はチロルチョコを取り出し――ドラえもんのポケットかと思ったーー再び悟の手に乗せる。それを見た悟の顔がちょっとだけ緩んだのを、私は見逃さなかった。
(あの感じだと…チロルチョコは好きなんだな…)
だが、そこで素直に受け取るような男であれば、先輩に対してここまで舐めた態度はとらない。やはりと言うべきか、彼はチロルチョコすら後ろへと放り投げた。つかさず、それを私がキャッチする。
さすがにここまでされれば彼女も怒るのではないかとも思ったが、彼女はその一連の流れを見て僅かながら、何故か口元を緩めた。そして私と悟を交互に見ると、「いいコンビになりそうだ」とひとこと言って、その場を去って行った。残された者同士、自然と顔を見合わせてしまったのは、きっと同じ思いを彼女に抱いたからだろう。
「何だ、あの女…調子狂うわ」
「まあ…変わった先輩ではあるね」
「そんな可愛いもんでもねえけどな、アイツは」
「彼女を知ってるのかい?」
「……まあ、オレがここに入った元凶だからな。大人になってから会うのは初めてだけど」
その言葉の意味を、私は後々知ることになるが、この時はまだ何のことか分からなかった。
「で…これ、食べるかい?」
すっかり怒りも収まり、何となく悟に向かって話しかけた。手には先ほどキャッチしたガムとチョコがある。彼女が悟にあげた物だから、私が食べると言うのも違うし、どうすればいいのかと思っただけだ。悟はそれを一瞥すると「いらねー。お前が食えば」と言いながら、歩き出したので、私も何となくそれについて行く形で歩き出す。とりあえず手の中の物はズボンのポケットへと突っ込んだ。
それにしても、さっきまでは殺し合いにでも発展しそうなほど殺気を向け合っていた相手なのに、今は前から知り合いだったかのような空気になっている。とりあえず呪術界の有名人は短気、と私の脳がインプットした、その時。不意に悟が私を見ると「お前、一年の教室分かる?」と聞いてきた。雰囲気からして、悟もすっかり怒りが萎えたんだろう。さっきのような剣はなく、悟を取り巻く空気が和らいでいるように見えた。それにどこか気まずそうな顔だ。
「ああ、確か四階の教室だったと思うよ」
「あっそ。んじゃあ…そろそろ行く?」
「ああ、そうしよう」
「ん」
そんな会話の後、何となくふたりで並んで歩きだすと、悟が再び話しかけてきた。
「…お前、名前は?」
「ああ、夏油傑という。君は五条悟だろ?この世界じゃ有名人だと聞いてる」
「…まあ…そうだけど」
ガシガシと頭を掻きつつ、悟はチラリと私を見て「さっきは…言い過ぎた…わ」と言った後、何故か思い切り顔をしかめた。きっと私に対する不遜な態度への謝罪のつもりだったんだろうが、とても謝ってる人間の顔じゃない。きっと人に謝り慣れてないんだろうと感じたが、逆にそれが面白かったし、そんな人間が少しでも悪いと感じてくれてることが、むしろ真の謝罪のようにも感じて何となく嬉しかったのを覚えている。
「いや…先に攻撃を仕掛けようとしたのは私だ。すまなかった」
「…それは…まあ…そうだな。お前も悪いわ」
「………」
素直に謝罪すると、悟はそんなことを呟いて、再び私を見る。私も悟を見る。数秒、目を合わせたまま沈黙が流れた後、ふたりで同時に吹き出してしまった。後で聞けば、悟は呪霊操術という術式を持った人間と会うのは初めてで、つい弄ってしまったと言っていた。弄るなんて可愛い態度でもなかった気もするが、そこはあの五条家の一人息子。しかもうん百年ぶりに生まれた六眼だという。きっと蝶よ花よと大事に育てられ、術師としての常識は叩き込まれたんだろうが、人に対して敬意をはらうという世間一般的な常識は教わらなかったんだろう、と思うことにした。
「そう言えば、お前知ってる?俺らのタメに女が一人いるらしいって話」
「へえ、そうなんだ。ということは私と五条くんと、その子の三人だけってことかな」
「…五条くんってキモいから悟でいーし」
「なら私も傑でいいよ」
「夏油より、その方が呼びやすいな。つーか、それより、その女と傑は会ったか?」
「いや、まだだよ。どうして?」
「そりゃ術師の女って生意気なの多いから、きっとそいつも生意気なんだろーなーと」
「ちょっと偏見が入ってる気もするが…どんな人間にしろ、また暴言は吐くなよ、悟」
「……うっせえ」
斯くして――私と悟はそんな流れで、打ち解けることが出来た。それもこれも、この時はまだ名前すら知らなかった彼女のおかげだと、今も感謝している。
2.
「何、ひとりで笑ってんだよ、傑。キモい」
最悪と同時に最高の出会いを思いだしていると、ゲームに夢中だった悟がふと私へ視線を向けた。気づかないうちに、顏に出ていたらしい。だからってキモいは失礼だな。
こういう口の悪いところはあまり変わってないのも困りものだ。
「悟と初めて会った時のことを思い出してたら、ついね」
「あ?何でそんなもん思い出してんだよ。よけーキモいわ」
あの時のことは未だに気まずいのか、悟はおもむろに顔をしかめながら再びテレビ画面に視線を戻した。謎の解き方を教えたからか、今はスムーズに先を進んでいるようだ。手元のコントローラーをカチャカチャ鳴らしながらキャラクターを操作している。
「ところでさー。アイツ今日もひとりだった?」
ゲームを進行しながらも不意に悟が訊いてきた。それが先輩のことだとすぐに気づく。
「ああ。先輩は特級扱いなんだから単独任務が多いのも当然だろうね」
「まあ…それもあるけど」
「ん?そうじゃない場合もあるのか?」
何となく含みのある言い方が気になって尋ねてみると、しばしの沈黙の後「アイツの専門は主に呪詛師なんだよ」と悟は言った。呪詛師とは呪術で悪さをする連中だと聞いている。金をもらって誰かを殺したり、趣味や己の欲望の為に人を殺したり、とにかく、呪いの力で非術師に危害を加える連中だ。私たち呪術師はそういう輩を警戒し、排除するのも仕事のうちだ。ただ呪詛師は同じ人間であり知能もある。中には強者もいるので、学生にはその任務はほぼ回ってこない。あくまで呪霊が対象だと聞いている。だが先輩は違うらしい。きっと彼女の能力も考慮して、そんな任務を与えられてるんだろうと思った。だが悟は「それもあるけど、多分ちょっと違う」と言った。
「上層部は敢えてそういう任務をアイツに与えて様子を見てる気がすんだよなー」
「様子を見る?何故そんなことを?」
悟は一瞬、黙ったものの、ゲームを中断してコントローラーを床に置くと、コーラを一気に飲み干した。そして空き缶を呪力で押し潰す。いつ見ても便利な力だ。
「アイツが呪詛師と通じてないかどうか?」
「…まさか」
ちょっと驚いてしまった。彼女は呪術師であり、この高専の生徒でもある。なのに上層部の老体たちはそこまで疑ってかかるのか、と少々呆れてしまう。そんな思いが伝わったのか、悟は冷めた目で私を見た。
「言っただろ。アイツはどっちに転んでもおかしくない血筋だって」
「ああ、聞いた。でも先輩と接した限り、そんな人じゃ――」
「傑はアイツのこと買いかぶりすぎ。つーか何気に気に入ってんだろ」
「気に入る気に入らないという問題じゃなく、そこまで警戒する必要性を感じられないだけだよ。実際、彼女が呪詛師と繋がってるという証拠でも出たのか?」
「…んなもんねーよ。でも、アイツの家系はこれまで闇落ちしたヤツの方が多い。アイツだっていつ"あっち側"へいくか分かんねーだろ。そうなった時、その辺の呪詛師とは比べもんにならねーほどヤバい事態になる」
「…そんなまだ見ぬ未来の話をされてもな」
「…む。案外、傑も頑固だな」
悟はムっとしたように睨んできたが、気にすることなく自分の気持ちを口にした。私は自分の目で見たものしか信じない。先輩からは確かにおぞましい力を感じたこともあったが、彼女本人からはそれほどの悪意を感じたことはなかった。それは私が悟ほど、長い歴史を身近に感じて育ってないからだろう。彼女を色眼鏡で見る材料がないのだ。だから私は自分の感覚を信じたいと、悟に言った。まさか、この会話から悟があんな行動に出るとは思いもよらずに。
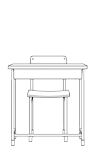
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで

