09-もっと知りたい
「意外と片付いてるんだな。五条くんはゲームが好きなのか?」
何だ、これは――。
「私はもっぱらアクションゲームしかしないんでプレイしたことはないが、面白いのか?これは」
一体全体、何でこんなことに?
「…五条くん?」
俺の部屋にがいる。その光景を直に見てると、何かあり得なさ過ぎて合成写真じゃないのか?とさえ思う。だいたい何で俺はこいつを部屋になんか――。
「五条くん。どうした?顔色が悪いけど、何か変な物でも拾い食いしたのか」
「――って、何で拾い食いしか選択肢がねぇんだよっ」
俺が少しの間、意識を飛ばしてたら、彼女は真顔で適当なことを言ってくる。ちょっとズレてる辺りが俺の調子を狂わせるのは、この間の件でだんだん分かってきた。でも何か気になる。そんな存在。この間から前とは違う意味で、彼女を見かけたら勝手に目で追っちまうし、気づけば彼女のことを考えてるのは、どういう呪いだ、これ。
「そんなに声が出るなら大丈夫だな。で…動画は」
「あ、ああ…ちょっと待って」
ふと我に返り、この前撮りまくった動画を探す。尾行動画はどこにも移さず、消しもせず、カメラの中に入れっぱなしだから、テレビに接続さえすればOKだ。何で今更こんなもんを観たがるのか分からないが、その辺を上手く聞きだせたら少しは彼女のことが分かるんじゃないか、という淡い期待もあった。俺がのことを気にしてるのは、きっと何も分からないからだ。分からないものには興味が湧く。知りたくなる。それだけのことだ。
「えっと…例のスポーツセンターの時の映像だっけ?」
「そうだ」
「あれは初日だから…最初のに入ってる」
一番古い日付を表示させると、映像は確かにあの日のものだった。それをテレビ画面に映し出せば、彼女は「ああ、綺麗に撮れてるんだな」と言いながら、何故か俺の隣に座りこむ。いや、座布団もねえのにケツ痛くねえのか?と思って横目で見てたけど、彼女は相変わらずの無表情でジっと動画に見入っている。ケツが痛いとか考えてもないって顔だ。
仕方がないから、愛用のビーズクッションを貸してやると、彼女は少し驚いた顔で俺を見て、その後に「ありがとう」と、またきちんとした礼を言ってきた。何かむず痒い。この間からずっとこんな感じだ。
彼女には俺がどんなに口撃したところで届かないし、まさに暖簾に腕押し状態だから、前のような態度をしたところで無意味だと気づいた。会うたび絡むのにもいい加減疲れてきた。なら、少しやり方を変えて、逆に懐へ入ってしまえばいいんじゃないかと考えた。
そう、俺が彼女の頼みを聞いてやってんのも、まさにそれだ。決して憑きモノ筋への警戒を解いたわけじゃない。たぶん。
それにしても、こうして近くで見れば見るほど、彼女は細身で大飯喰らいには見えないな、と思う。肌も色白すぎて血管が透けて見えるし、長い髪はさらっさらで、彼女が少し動くたびに滑らかに流れるように動く。ついでに言えば、制服の襟から覗くデコルテ部分は思春期の男にとっては目の毒かもしれない。何故なら、彼女はこんなに細身なのに、胸元は制服を押し上げてるのが分かるくらいの丁度いい大きさ。自然とそこへ目がいってしまうのは、悲しいかな、男の浅はかさだと自覚する。
――って、ただの欲求不満か、これ。
そもそも、何でこの俺がこんな女を女として意識しなくちゃならねえんだ。俺の性癖どうなってる。愛想もない大飯喰らいの憑きモノ女に、そんな劣情を持つわけがない。そりゃ、外見だけ見れば何気に俺好みだったりもするわけだけど、表情が乏し過ぎて魅力が半減してるような女だ。だから全て気のせいだ、気のせい。そう、俺の気のせい………――。
「…何…探してんだよ」
最初は何となく俺も隣に腰を下ろして一緒に動画を見ていた。時々ちらちら視線を送ってみたが、彼女は映像の隅から隅まで観てる感じだった。随分と熱心に観ている。その姿は何かを探してるようにも見えて――だから訊いてみた。
彼女はふと視線を画面から俺へ向けて、互いに眼鏡とサングラス越しに目が合う。不覚にもドキっとさせられたのは何となく屈辱的だった。
そんな俺のおかしな情緒にも気づかず、彼女はいつも通り淡々とした口調で言った。
「ある呪詛師の痕跡だ」
「…呪詛師?」
その言葉を聞いて、今度は違う意味でドキッとした。この場所はある殺人事件の現場なのは尾行の際に調べたから知ってる。ならやはり、あの事件は呪詛師絡みってことか?俺に話すってことは特にやましいことがあるわけでもなさそうだ。
だから彼女に直接そう尋ねてみると、彼女はほんの僅か逡巡したあと小さく頷いた。
「五条くん、この事件の詳細は――」
「知ってる。つっても…まあネットニュースに載ってたくらいのもんだけど。特に深くは調べてねぇよ」
「そう」
「何だよ。あの事件と今あんたが探してる呪詛師は何か関係があんの」
「あるかどうかを調べてる」
「あ?どういう意味…?」
本格的に気になってきた俺は、更に追及するように問いかけた。彼女のことは分からないことがありすぎるから、少しでも何か"こちら側"だと思える根拠があれば、俺だって無駄にこの人を警戒したくはない――。
そこまで考えてハッとした。そう思うってことは、俺の中で揺らぐことのなかった不信感が薄れつつあるってことだ。知らないうちに彼女の何かを信用してしまってるってことなんだろうか。
彼女は俺の問いかけに応えようと口を開いたが、ふと画面を見て一時停止ボタンを押した。
「あった…」
「…あった?」
何が?と思いながらテレビ画面に視線を戻すと、そこにはスポーツセンター内を映した映像だった。彼女が到着する前、隠し撮りを出来るような場所を探しながら、薄暗い廊下をカメラを構えて歩いた。念のためにと、試し撮りをしていた箇所だ。でも彼女を映したわけじゃないから、確認の際はいつも早送りしてた。
「何が…あった?」
「ここ」
一時停止をした画面、彼女が指した廊下の壁には不思議なマークが描かれていた。よく見ればそれは人の耳の形にどこか似ている。ここを通った時、俺の視界にも入ってたかもしれないが、あの場所はガキが出入りしてたというだけあって、あちこちにスプレー缶のいたずら書きがあった。だから気にも留めなかったんだろう。
「これが…何?」
「この事件…四人が惨殺体で見つかったのはニュースでも流れたが、マスコミにも開示してない情報があるんだ」
「…それって」
「遺体の一部が持ち去られてたということ」
「持ち去られてた?どこを――」
と聞こうとして、俺は自然とテレビ画面に視線を戻していた。
「まさか…耳?」
「そう。四人全員、両耳を切り取られ、持ち去られていた。ただ、遺体の一部を持ち去られてただけじゃ私が探している呪詛師の仕業とまで断定できなかった。他にもそういった事件はあるしね。でも…」
彼女もまた画面を見ると「この絵があるなら話は別だ」と言った。
「彼女は自分が殺した人間の体の一部を持ち去り、かならず現場に持ち去った部位の絵を残していく」
「……彼女って…その呪詛師は女?」
「ああ」
「…あんた…そいつのこと知ってんのかよ」
「知ってる。前に…会ったことがある。中学生の頃だけどね」
そう言って彼女は今度こそ動画の停止ボタンを押した。そのまま立ち上がるから「え、もういいのかよ」とつい声をかけていた。
「確認できたからいい。この通路は探してなかった。あそこは広いしな。助かったよ」
彼女はそれだけ言うと部屋を出て行こうとするから「待て待て」と思わず腕を掴んでいた。だいたい中途半端に話を聞かされて、こっちは色々気になってんだよ。何の説明もしないまま帰るつもりか?そう文句を言えば、彼女に「これは私個人の問題だから」と言われてしまった。個人の問題なんて言われれば、もっと気になってくるんだから始末が悪い。
「そもそも…何でその呪詛師を追ってんの。やっぱお友達とか?」
いつもの軽口を叩いてみたものの、真顔で「友達ではないな」と返された。まあ、もしお友達なら俺にあんな話はしないだろう。ますます俺に疑われるだけだし。でも彼女はその呪詛師を探していて、わざわざ自分を尾行してた俺にまで頼み事をしてきた。それも映ってるかどうかも分からないその呪詛師が事件に関わったという手がかりを得るために?やっぱ気になるだろ、そこは。
「良かったら話聞かせてくんねえ?このままじゃ気になって、またあんたのこと尾行するかもしんねえし」
「…別についてきたいなら構わないが。私のスケジュール、教えておこうか?」
「いや、そういうこと言ってんじゃねえじゃん!」
マジですっとぼけた女だな、と俺が頭を掻きむしると、彼女はまたしても真顔で「何だ。違うのか」とかすかに笑ったようだった。いったい、こいつは何なんだ。理解できなさすぎて、むしろ気になるわ。
「とにかく…その女呪詛師との関係くらいは教えろよ。何で探してんの。ってか、そもそも個人的な問題とか言ってたけどさぁ。そいつが人を殺してまわってんなら高専としても黙ってられねえだろ」
そう詰め寄らずにはいられなかった。尾行中、彼女が再びあの現場に足を運んでいたのは、あのマークを探す為ってのは見えてきたが、何となく彼女はその呪詛師に固執してる気がする。どういう関係かくらいは聞きだしたかった。
彼女はやはり黙ったまま。でも俺が話を聞くまで引き下がらないと思ったのか、ふっと小さな息を吐いてこっちを見た。
「……まあ、高専側も彼女の存在は把握してる。ただし、彼女に関してのみ、全権を任されてるのは私だ」
「は?学生のあんたに全部任せてるって…何でだよ」
本来、呪詛師案件は学生に回ってこない。でも彼女が任されてるのは聞いていた。でも全権を任すというのは異例な気もする。
そう思っていると、その答えは彼女が話してくれた。
「過去に私が彼女と接触したことがあるという理由が、まず第一。あとは…彼女は危険人物だから、だろうな。それを対処できるのは憑きモノ筋である私が適任と上が判断したんだろう」
「…危険って?どの程度?あんたに任せるってことは…特級案件か?」
その問いに彼女はまたダンマリを決め込んだ。でも逆にそれは認めたようなもんだ。
呪詛師で特級。しかも女?なかなかお目にかかれない代物だ。ますます好奇心が刺激され、出来ればその呪詛師に会ってみたいと思ってしまった。
「そいつ、俺でも無理?」
「…どうして?」
出て行かせないよう、ドアのところを手で塞いで訪ねると、彼女は怪訝そうに俺のことを見上げた。
「…俺も探すの協力してやるよ」
「え?」
「俺の眼、意外と役に立つと思うけど」
身を屈めて自分の眼を指しながら彼女の顔を覗き込むと、表情のない彼女の瞳が不思議そうに瞬きを繰り返す。その顏が普段とは違い、年相応に見えて、何故か俺の胸の奥が変な音を立てた。何だ、この甘酸っぱい感覚は。
「五条くんは…何故そこまでして協力したいのかな。私を探る為?」
「……いや、別に前ほど疑っちゃねぇよ。これは俺の好奇心ってやつ。そんなイカレた呪詛師は野放しにしておけねえじゃん」
まあ半分くらいはまだ疑ってる部分もあれど、今日話してみても彼女は嘘を言ってる感じじゃないのは分かったし、あとは言った通り、単なる好奇心ってやつだった。あとは――。
もう少し、彼女について知りたくなった。それだけのこと。
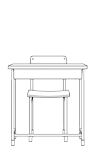
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
