10-黒の乖離
※流血、残酷描写あり
最近、随分と周りが騒がしい。後輩たちが容易く私の領域内へ踏み込んでくるせいだ。
高専へ入学した頃はこちらから距離を置いていたせいか、同級生や先輩達も必要に迫られた時以外は私に近寄らなかった。誰も好き好んで"憑きモノ筋"の人間と親しくなろうとは考えない。こちらも理解してるので当然、近寄らない。だから必然的にひとりでいることが多かった。
それを超えて近寄ってくる連中は、それなりに下心があって私に声をかけてくる。最近では先輩の男がそうだ。何だかんだと飲み会に誘って来ては、私の体を無遠慮に撫でまわす。どうせお前はそういう女だろう?と、下卑た視線で私を見てくる。親にでも聞いたんだろう。"憑きモノ筋"の女が過去にどんな扱いを受けて来たのか、彼はそれを知っていたようだ。だんだん態度が露骨になってホテルへ誘ってくるようにまでなっていた。
だけど、それがある日を境にピタリとやんだ。私にセクハラをしてる三年の先輩がいると、上層部に匿名の生徒から報告が上がったとのことだった。その件で私は担任の夜蛾先生に呼び出され、いくつかその件についての質問をされた。誤魔化す必要もないので事実だと認めると、私に触手を伸ばしていた先輩の男は、一カ月の停学処分となったらしい。
でも、それを聞いても特に何も思わなかった。私にはどうでもいいことだ。
ただ――その匿名希望の生徒には心当たりがあった。容易く私の領域へ踏み込んでくる後輩達のひとり。最近まで私の尾行をしていた五条悟だ。きっとその時にでもあの先輩の愚行を目撃したんだろう。そんな五条くんの行動は少なからず私を驚かせた。あれほど敵意を剥き出しにしていた彼が、私の助けになるようなことをするとは思えなかったから。
つくづく人間の感情とは不思議なものだと思う。ただ、その辺りから少しずつ私を取り巻く環境が変化していって、彼を含めた一年生が顏を合わせるたび、何かしら声をかけてくるようになっていた。
「先輩、これ好きですよね。食べます?」
「おい、硝子。それ俺が買って来たやつな?」
「うわ、ちっさ。細かい男ってどう思います?先輩」
「あ?細かくて何がわりーんだよ。ってか、俺のマーブルチョコ返せって!」
「おい、やめないか。二人とも。――朝から騒がしくてすみません、先輩」
こんな風に、まるで普通の学生同士が話すみたいに声をかけ、彼らは私が長年かけて作ったはずの壁をいとも簡単に破ってくる。その事実に時々、私の心が波立ち騒いで落ち着かなくなるのは、こんな風に普通の人として扱われた経験が乏しいからだろう。
――俺の眼、意外と役に立つと思うけど。
五条くんからの唐突な申し出を悩んだ末に受けてみることにしたのも、ほんの少し自分を変えたいと思ったからなのかもしれない。彼の目的は私の本性を探ることなのは分かっていたし、もし私が"あちら側"へ渡ったその時は、彼の手で終わらせてくれたらいい。そんな風にも思っていた。
それに何より、私は"カノジョ"と会いたかった。その為には彼の言うように"よく視える眼"が必要だ。
「ほら、行くんだろ?だったら早く行こうぜ」
朝、食堂で朝食を終えたあと、五条くんが声をかけてきた。夕べ、都内で再び殺人事件があり、今度は若い男女が殺されたという。ふたりの左手薬指だけが欠損してることから、私に調査の依頼が回ってきた。それを五条くんに報告すると、彼は自分の任務を共に行くことが決まっていた夏油くんのみに任せ、今日一日私に同行すると言い出したのは、先日の約束を守るということなんだろう。念のため、夜蛾先生にも相談したが、五条くんを連れて行っても問題ないと言われた。どうやら五条家が直々に手を回したらしい。彼はなかなか容易周到だ。
ただ私付きの補助監督、如月さんは少し驚いたようだった。
「え、五条くん…も一緒に、ですか?」
如月さんは何も聞かされてなかったようで、彼が同行すると言ったら、その円らな瞳を更にまん丸にして驚いていた。それも当然かもしれない。先日まで五条くんが私を敵視していたのは彼も知っている。でも簡単に私からも説明すると、如月さんは「分かりました。ではそのように」とすぐに目の前の事実を受け入れてくれた。
「では五条くんとも情報を共有しますね」
言いながら資料などを彼に見せ、端的に説明している。私もその資料に目を通しながら、被害者が若いカップルというところに着目した。"カノジョ"が好んで狙うのは、先日の若い男もそうだが、最も多いのは"幸せそうな男女"だからだ。
「薬指はふたりとも欠損してたんですか?」
「はい。そのようですね。ああ、現場写真は最後にあります。警察の方でも捜査をしてますが、こう立て続けに事件が起きると、細かいところまでは手が回らないようで、その…例の確認はまだ…」
「かまいません。こういう事件は全てこちらで調査すると言ったのは私なので自分で行きます」
きっと"カノジョ"の痕跡はまだ未確認と言いたかったんだろう。如月さんはハンカチで額の汗を拭きながら「すみません」と謝罪してきた。別に彼のせいでもないのに律儀な人だ。年齢も十歳は上なのに、こんな学生風情にまで敬語を使い、頭を下げなくてもいいのに、とさえ思う。いや、彼に直接そう言ったこともあった。でも彼は「この世界は年齢関係なく、呪術師の方が僕の上司と同等ですし、特級術師のさんに僕なんかがため口きけるわけありません」と言われてしまった。特級なんていうものは私の力でも何でもないというのに。
彼は上層部が私担当の補助監として付けた人物だ。どうにも気が弱く、また仕事も遅いことから、上は彼を使えないと判断し、適当に私へ付けたようだ。私に付きたがる補助監督はそうそういない。なので気の弱い如月さんなら、文句も言わないと思ったに違いない。でも彼と任務に当たっていると、上の判断は間違いだとすぐに気づいた。如月さんは仕事が遅いのではなく、ただひたすら丁寧なだけで、その内容はどの補助監督よりも優れている。資料一つ調べるにしても、余計な仕事はせず、要点だけを上手くまとめてくれるので、私はいつも助かっていた。
あとはもう少し強気になってくれればいいんだけれど――。
「えー真っすぐ現場行くの?ちょっとコンビニ寄ってよ。俺、喉乾いちゃったし」
「え?あ、え?は、はあ…い、いや、でも時間が――」
早速五条くんの我がままに付き合わされ、あたふたとしている如月さんを見ていると、少しだけ申し訳ない気持ちになった。これも人の感情というやつなんだろうか。私にはまだよく分からなかった。
|||
そのホテルは今時あまり見かけないような、古臭い、何と言うか哀愁の漂う建物だった。ギラギラとしたピンク色の看板には大きく"HOTEL 大江戸"という地名にちなんだような名前が載っている。昭和時代に建てられたであろう、耐震強度など皆無に等しいそのホテルは、駅から随分と離れた街道脇に建っていた。無駄に広い公道のわりに、車通りの少ない廃れた一画。そこのラブホテルの一室で、若い男女の遺体が発見されたという。
目的地に到着して、すぐ近くの駐車場へ車を止めると、如月さんが現場まで誘導してくれる。ここまでスムーズに来れたのは、彼が前もって下見をしてくれていたからだ。ホテルまでの道のりを迷うことなく歩いて行く如月さんの背中を見ながら、この人はいつ休んでるんだろうと首を傾げてしまった。
「現場はここの二階の部屋です」
如月さんが指す方向に古ぼけたホテルがあり、その入り口には警察が引いたと思われる【立入禁止 KEEP OUT】と書かれたバリケードテープ。夕べの今日なので、入口には制服警官がひとり立っていた。
「うげ…こんなラブホ、良く入るな…。何かGが出そうじゃん」
「…G?」
綺麗な顔をよくここまで変形できるなと感心するくらい、思い切りしかめっ面をした五条くんを見上げると、彼は「Gだよ、G」とその言葉を繰り返した。何のことかと眉間を寄せると「え、G分かんねえの?」と何故か驚いているので、どうやら世間一般でも使われてる言葉らしい。
「ゴキのことだよ」
「ああ…ゴキブリ…それでGか」
「いやフルネーム言いたくねえからGっつってんのに、そこ言う?」
なるほど、そういうことか、と納得しつつ、「面白い名前をつけるな、五条くんは」と感心してしまった。でも俺が付けたんじゃねえと何故か怒り出したので、名付け親は別にいるらしい。
「ったく…面白いのはどっちだよ」
「…私?いま何か面白いことを言ったか?」
「……いや、もういいですー」
「…?」
サングラスの奥に見える六眼が半分ほどになったのを見れば、何となく私が悪いのかな、とも思ったが、何がどう悪かったのかも分からない。なのでそこは気にしないでおいた。五条くんはそもそも常に機嫌が悪いイメージだ。
「それより…五条くんの眼で何か見えるか?」
ホテルに入る前に呪霊の存在を確認してもらうと、「奥に数体視える」とのことなので、如月さんがすぐに入口にいる警官を誘導してはけさせた。こういう時の為に警察の方から必要書類をもらってあるので、それを見せるだけでいい。ああいう下っ端の警官は呪術界のことを知らないので、任務中ゴネられないように、今はこういった措置が取られている。
警官がいなくなったあと、如月さんが帳をおろしたのを確認して、私はホテルの中へと足を踏み入れた。後ろで五条くんが「マジで入んの?」と顔を引きつらせているのは、さっき言ってたGのことを気にしてるのかもしれない。
「入らないと確認できない。五条くんは外で待っててもいいよ」
「………いや、行くけどさ」
どこかスネたように艶のある唇を尖らせた五条くんは、渋々といった様子で私のあとからホテル内へと入って来た。前から少し気づいていたが、彼はどこか天邪鬼みたいな一面がある。文句は言うが、こちらが引くと、途端に素直になって距離を詰めてくる、といった感じだ。どこかツンデレ感のある猫みたいで、そこがちょっと面白い後輩だとは思う。
なのでいい意味で彼に「ツンデレなペルシャ猫って感じだな」と言うと、「ハァ?猫扱いすんな…ってかG知らねえのにツンデレって言葉は知ってんのかっ」と何故か怒り出した。ほんとに情緒の激しい後輩だ、と思いつつ、今の問いに応えることなく、建物内を歩いて行くと、無視すんなと追いかけてくる。でもロビーの壁にある室内メニューの写真を見ると、途端に静かになった。何か気になるものでも映ってるのか、サングラスをズラしてジっと凝視している。
「…今時…真っ赤な丸いベッド…」
「ああ、それは回転するタイプのものだろうな」
どうやら五条くんはラブホテルの部屋に興味があったらしい。そう教えてやると、そのキラキラした瞳をギョっとしたように丸くしながら振り返った。
「…って、何でそんなこと知ってんだよ」
「何で?今時これくらいの知識はみんなあるんじゃないか?」
「は?ってか…こういう場所…来たことあんのかよ…」
その問いにふと顔を上げると、五条くんはこちらを見下ろしていた。サングラスのせいで表情は見えないものの、彼の唇がまた少し尖っている。今度は何にスネているのやら、さっぱり分からない。
「いや、ないけど。何故?」
「……別に。ってかサッサと二階行くぞ」
首を傾げた私に対し、五条くんはそっぽを向いた。でも心なしか、ほんの一瞬口元が綻んだようにも見える。よく分からないが機嫌が直ったなら、それに越したことはないので、私も彼のあとからエレベーターへ乗り込んだ。古いタイプなのでボタンも大きく、上がる瞬間、がくんと揺れるそのエレベーター内。壁にはカラフルな紙が貼られ、いかにもラブホといった雰囲気が充満していた。
"バイアグラはフロントにてお売りいたします!"だの、"大人の玩具貸し出し中!"だのと、後付けされたサービスの宣伝らしい。最近のホテルではデフォルトのようにあるらしいが、こういう古いホテルには、そんな気の利いたものなどなかったんだろうな、と思わせる内容だ。
私には全く興味がないので景色のように眺めていたら、何となく隣にいる五条くんの様子がおかしいことに気づいた。急に小さく咳払いをしたり、トントンと床を踏み鳴らしたり、どこか落ち着かない様子で天井を見上げている。その様子を見ていたら、何となく気づいてしまった。
「…五条くん。トイレなら適当な部屋で使わせてもらえばいい」
「は?な、何で…トイレ?」
サングラス越しでも視線を泳がせてるのが分かるほどに動揺している。そんなに漏れそうになるまで我慢しなくてもいいのに。
「いや、さっきからソワソワしてるから。トイレ我慢してるんじゃないのか?」
「してねえよ!何だ、トイレ我慢って!小学生か、俺はっ」
急に怒り出す彼の情緒が本当に分からない。けど五条くんの色白な頬が何故かほんのり赤かった。彼はちょうど開いた扉を自分でもこじ開けるようにして廊下へ出ると、現場となった部屋まで大股で歩いて行く。どこか慌てているその姿を見ていたら、やっぱりトイレに行きたかったのか、としか思えないが、本人が違うというなら違うんだろう。分かりにくいところもあるけど、ちょっと面白い後輩だと思う。そもそも私に対してあれだけぽんぽん怒鳴ってくる人間はいないので、そこが新鮮に感じていた。
「ひでぇな、こりゃ。血まみれじゃん」
現場の部屋へ足を踏み入れた途端、濃い血臭が鼻を突き、五条くんは顔をしかめながら血まみれのベッドへ視線を向けた。五条くんの言う通り、室内の壁や天井に血が飛び散り、元の色が分からないほど赤くなっている。すでに遺体は警察の手で回収されている為、鑑識が撮ったと思われる写真を見ながら、目の前の状態と照らし合わせた。
「ベッドの上に女性の全裸遺体。男性の方はベッドから上半身だけ落ちた状態か…」
「うわ、男もすっぽんぽんのフルチンで死んでんじゃん。悲惨~」
私の持つ資料を覗き込みながら五条くんが同情の声を上げた。だがふと私が顔を上げると、至近距離で目が合う。五条くんは「あ」と言う顔をしたあと、「こういう発言もセクハラなんのか?」とブツブツ言いだした。どうやら私に気を遣ってくれてるらしい。こういうところは優しいんだな、と、つい苦笑が漏れてしまった。
「あ…?なに笑ってんだよ」
「いや。別にフルチン発言でセクハラとは私は思わないし気にしないでいい」
「バッ…お、女がフルチンとか言ってんじゃねえよっ!だいたい、よくそんなモロ写りの写真なんかマジマジと見れるな」
「資料だから確認しないと繊細が分からないだろ。見なければ五条くんの言う通り、この被害者がフルチンで亡くなってることも――」
「あー!もうフルチンフルチン言うな!」
五条くんが急に怒鳴り出し、顏も真っ赤になっている。こういうところは純情らしい。つくづく読めない男だ。一見チャラチャラしてるように見えて、実は童貞かもしれない。
と、考えた瞬間、五条くんがジトっとした目で私を見下ろして来た。
「お前…今なんかとてつもなくシツレーなこと考えただろ」
「…いや、失礼なことは特に。童貞かなと思っただけで――」
「んなわけねえだろ!ってか、やっぱ考えてんじゃねえか。言っとくけど俺は――」
と何かを言いかけた五条くんの眼が何かを捉えたらしい。その視線を追っていくと、そこには小さな絵が描かれていた。設置されたミニ冷蔵庫の扉。そこに人の指のようなものが二つ。――"カノジョ"だ。
「おい、あれって…」
「ああ。どうやらこの件は私が探してる人物がやったらしい」
ミニ冷蔵庫の前へしゃがんで絵の写真を撮ると、その二本の指の一つにはかすかに指輪のようなものも描かれている。僅かに息を呑み、被害者のことが書かれた資料へ目を通すと、そこには"被害者は婚約していた"という文字が最後の方に記されていた。
「ん?その絵、片方の指に何か描いてねえ?」
私の背後から覗き込むようにして見ながら、五条くんが言った。そうだ。これはあの時と同じ――。
「…これは…婚約指輪だ」
「え…?」
呟いたのと同時に、私の手が無意識に首から下げているものへ触れていた。
|||
"カノジョ"とは中学二年に上がったばかりの頃、預けられていた祖父母の家の近所にある神社で出会った。
当時の私は今よりまだ、自分の運命を受け入れきれず、むしろ理不尽な運命を呪うような女の子だったと思う。
生まれた瞬間から私の呪われた人生はすでに決まっていたからだ。
そのことを嘆く心がまだ残っていた頃、実家のある都会を離れ、祖父母の住む田舎へ預けられたのは、今は亡き母の意向だった。
"憑きモノ筋"の家は、その憑神の力が女にだけ受け継がれる。それを宿した女は一生かけて家を護っていかねばならず、またの血を引いた男の子供を生まなければいけないとされている。
古くは差別の対象となっていた"憑きもの筋"の女性との結婚が忌避されていた時代もあり、また現在も家以外の男とは婚姻を結んではならないという決まりがあった。血縁同士の婚姻は許されない時代、それでも、なるべく遠縁同士を選んで契りを交わさせる。それは"憑きモノ筋"である一族の血が薄れることを恐れた先祖たちが決めた、ただの悪習に過ぎない。そんな反吐の出るような決め事を守る為、一族以外の血を入れることを拒み続けた家は、憑神を宿した女を家に縛り付けておくため、またはその呪詛の力で抵抗出来ないよう心を支配するために、初潮が始まる頃には婚約者を決められ、その身に男の味を教え込むのが通例だった。
通称"籠女"――。文字通り女を一族の男が囲んで逃げ出せないようにする下卑たやり方だ。
まだ男女の何たるかも分からない少女を、婚約する相手とはいえ男の慰みものにする悪習は、私の母が通って来た道でもある。だからこそ、母は私を護ろうと一族から距離を置いていた祖父母の家へ預けたのかもしれない。
「ごめんね…お前を生むんじゃなかった…私からに憑神が受け継がれていくのは分かっていたことなのに…」
よく、そんなことを言いながら私の頭を撫でてくれた母は、とても優しい人だった。外では術師の任務をこなし、家では良き妻で、良き母だったと思う。外道のような父に嫁がされても、一族を恨むことなく、己の運命を受け入れていた。
そんな忙しい母と、月に一度ほどは一緒に出かけたりもした。父は厳しい人で、子供の私を甘やかすようなことはしなかったが、その分、外出をした時は母が思い切り私を甘やかしてくれたように思う。
普段はオヤツすら与えられない私に、母はよく駄菓子を買ってくれた。それが凄く嬉しくて、美味しくて、どんな高級な菓子よりも、それは私にとって特別な"オヤツ"だった。きっと母がいなければ、私は孤独な幼少期を過ごしてただろう。
だからこそ、大好きな母と離れて暮らすのは何より寂しくて、怖くて、心細かった。
先のことが理由で、一時は母に護られた形となり、私は祖父母の家から近所の中学校へ通っていた。そんなある日、花冷えのする頃だった。"カノジョ"は唐突に私の前に現れた。
朝から曇天だったのに、傘も持たずに出かけた午後、降り出した雨の一粒が私の頬を濡らした。ふと空を見上げれば、不思議なことに、ちょうど私の頭上の右と左で薄黒い雨雲と晴れやかな青空が見事に分かれている。飲み込まれまいと、どちらもせめぎ合うその光景が、まるで自分の心のようだと自虐的なことを思いながら、雨宿りの出来る場所へと急いだ。薄黒い雨雲は当然のように青い空を侵食しながら空を鈍色に染め上げていった。
途中、神社の鳥居を見かけて思わずそこへ走ったのは、境内に行けば雨を凌げる場所くらいはあるだろうと思ってのこと。
神社は神様のいる神域だというのも忘れ、堂々正面から鳥居をくぐる。
今、思えば憑神を宿す女が、土足で神の家へ上がったようなものだったな、と苦笑するが、その時は雨宿りすることしか考えていなかった。
参道を走ると玉砂利を踏みしめる、しゃりしゃりという音が辺りに響く。この突然の雨のせいか、その小さな神社に参拝客はひとりもいなくて、足音も私のものだけのはずだった。だけど、手水舎の先まで進んで境内社を超えたところで、どきりとして足が止まった。誰もいなかったはずの背後から、しゃり、しゃり、と玉砂利を踏む音が聞こえたからだ。
ここまでの一本道に人はいなかった。なのに後ろからは確かに、しゃり、しゃり、と人が玉砂利を踏む音が近づいてくる。あの時の感覚は言葉に出来ない。生まれてこの方、恐怖というものを感じたことのない私が、狗神を宿してるはずの私が、ほんの刹那、背中に怖気を走らせたのだから。
その時、遂に雨が本降りへと変わり、サァァァと静かな雨音が聞こえ始めた。私は依然として振り向くことも出来ないまま、その場に立ち尽くすことしか出来ない。次第に激しくなってきた雨が、容赦なく私の髪や、服を濡らしていった。そして雨が強くなってきた頃、砂利の湿った匂いに交じって、かすかに鉄のような匂いが漂っていることに気づく。緑の多い神社の境内に不自然な匂いだ。
(これは…血の匂いだ)
憑神のおかげで鼻は利く方だ。今、漂ってくるこの匂いは、間違いなく人間の血だった。それも少量じゃなく、大量の血液が流れてる。空気に漂う血臭の濃さから、そう判断した、その時――。
しゃり、と玉砂利の踏む音が、私のすぐ後ろで止まった。
「――おまえ、何者?」
耳元で私の鼓膜を揺らしたのは、その場に似つかわしくないほどの、凛とした涼やかな声。それは女の声だった。同時に今まで何故気づかなかったのかと驚くほどの、じっとりと重く、黒い乾留液のような呪力と殺気が、私のすぐ隣で息づいていた。耳にかすかな吐息を感じるほどの、すぐ近く。ひた、と肌にまとわりつくような、呪いの粒子。
動けば殺される――。
そう肌で感じた私は、眼球だけを動かし、声のした右側を見る。すると吐息が交わるくらいの距離から、こちらを見つめる射干玉のようにまあるい黒目が、ぎらぎらと闇をたぎらせた大きな目が、じっと私を見つめていた。思わずひゅっと息を吸い込む。
その黒目と視線が交わった瞬間、それが、にたぁ、と笑うのを感じたからだ。
そのあとの行動は私もあまり覚えていない。咄嗟にそれから離れなければ。そう思ったんだと思う。気づけば境内社の脇まで跳躍していた。一秒でも遅れていたら私は何らかの攻撃を女から受けていたに違いない。そんな確信めいたものがあった。
「――"飯縄"」
名を口にした途端、私の肉体を媒体に現れた小さな狐。懐柔した憑神の一つを呼びだしたのは、目の前の人物が、女が、明確な殺意を向けてきたからだ。
「…あなた…誰」
そこにいた人物の正体を知り、気づけば尋ねていた。
歳の頃は二十歳前後、すらりとした長身。私と同じような黒髪を垂らしたその女は息を呑むほど美しかった。なのに、女の手には真っ赤に濡れた、人間の首。無造作に髪を掴んでいるせいか、それがゆらり、ゆらりと揺れるのだ。苦悶の表情を浮かべ、絶命したとみられる男の顔が、脳裏に焼き付いた瞬間だった。
「へぇ…面白いもん飼ってんね、おまえ。それに――」
女はにたり、と笑いながら、手にしていた首を、まるでゴミのように後ろへと放り投げた。放られた首は空中で弧を描いて、そのまま地面に転がった。ぐちゅ、という不快な音が響く。この時、気づいた。首が転がった先。境内社の裏手には人がふたり倒れている。それは若い男女の死体だった。一つは首がない。女の捨てた首はあの男のものだろう。ふたりの体から流れ出る大量の血は、地面に広がり大きな血だまりを作っていた。
「その目…この世界になーんの希望も抱いてない…。あは、おまえ…私と同じ種類の人間、だよねえ?」
どこか愉しげな様子の女は私を観察しているようだった。ねっとりと、舐めるような目つきで見てくる。まるで女の視線が私に絡みついてくるようだった。
「…その人たちはあなたが殺したの」
彼女の言葉に否定も肯定もせず尋ねると、彼女は抑揚のない黒目をふたりの方へ向け、「ああ、あれ?」と鼻で笑った。
「どこか雨宿りできる場所はないかとここへ来たら…境内をイチャイチャしながら歩いてるからさぁ。道に迷ったふりして声をかけた。なーんか、ここ縁結びの神様がいるんだって。もうすぐ結婚するんですーとか言いやがって、あまりに幸せそうでさぁ。目障りだったし殺っちゃった。ダメだった?」
女は平然と言いのけた。何の感傷も、抑揚もない声で。まるで無邪気な子供が目の前を飛びまわる鬱陶しいハエを叩き潰したとでもいうような、何の感情もない、顏で。
実際、女は自分が殺めたふたりのことは、すでに何の興味もないようだった。
しゃり、と砂利を踏み鳴らし、私の方へゆっくりと歩いて来る。咄嗟に身構えると、女はふふっと笑みを浮かべて「おまえ、私と同じ種類だろう?」と小首を傾げる。心の中を見透かすような、そんな笑みを浮かべながら。
「そんな目をしてるんだよ。自分の運命を、世界を、丸ごと憎んで、ぜーんぶ消してやりたいって、そんな目だ。違う?」
私と同じだから分かるんだ、と、女は愉しげに甲高い声を上げて笑った。実際、彼女からは濃い血の匂いの他に、深い憎しみの気配が漂ってくる。こんなに禍々しい呪力を感じたのは、後にも先にも彼女が初めてだった。
そして、私は彼女の問いに、違う、とも、そうだ、とも答えられなかった。
しゃり、と一歩、また女が私に近づく。
「ねえ、おまえ、名前は?」
「………」
「そう、綺麗な名前ねえ?」
女は私の髪へ手を添えて、優しくするり、と一撫でした。この時、私は女と戦うことを、自ら放棄したも同じだった。女の殺意も、気づけば綺麗に消えていた。
「ねえ、…簡単だよ」
「簡単?」
「そう。おまえが憎むもの全て消し去るのは、思ってるよりもずーっと簡単なんだよねえ」
女は言った。私の耳元へ、その綺麗な形の唇を近づけて。
邪魔な奴らは全員、殺しちゃいなよ、と。"こっち側"は楽しいよ、と――。
まるでコソコソ話をして、無邪気に笑う子供のように。
「私はオトネ。また会おうねえ、」
オトネと名乗った女は、去り際に「これ、プレゼント」と微笑み、私の手にぶにっとする何かを握らせ、去って行った。
女がいなくなってからも、私はしばらくその場から動けなかった。殺意の塊のような人間と遭遇したのは初めてで、どこか高揚してたのかもしれない。驚いたのは、彼女のことを全く怖いと感じなくなっていた自分にだ。
どれくらいそうしていたのか。雨に打たれて冷えた体にかすかな寒気を覚えて、ふと我に返った。そこで手の中にあるものを確認するのに開いてみれば、そこには人間の指があった。後ろで死んでる女のものに違いない。淡い桃色のマニキュアをしてダイヤの指輪をはめたままの薬指だった。
きっと婚約指輪だったんだろう。境内社の裏に重なるようにして倒れている死体を横目に、その指から指輪を抜き取ると、それをポケットに入れて、指はあの首と同じようにその辺へと捨てた。
オトネの言う通りだ。私は"カノジョ"と同じ種類の人間だ。現に人の死体を見ても、何の感傷もなく、興味すら湧かない。このカップルは事故にあっただけ。たまたまそこにいたら災いに遭遇してしまった。ただ、それだけのことだ。
だけど、その帰り道。ポケットに手を突っ込んで、オトネにもらった指輪を出そうとしたら、先に指先へ触れるものがあった。それは母からもらったチロルチョコ。それを見た途端、不思議と心が凪いでいくのを感じた。
――おまえ、私と同じ種類の人間、だよねえ?
違う、とどうして言えなかったんだろう。母は私を信じてくれている。決して、"あちら側"へ行くような子じゃないと、そう言ってくれた。憑神に飲み込まれるような、そんな子じゃないと。
ふと足を止めて振り返る。雨に打たれた恋人同士の遺体は、まるで抱き合ってるように見えた。
ふたりは結婚を控えていた。なのに、その幸せを一瞬で奪われた。あまりに理不尽な、取るに足らない理由で。
「…これ、持ち主にいつか返さなくちゃ」
不意にそんなことを思って、光り輝く指輪を空にかざす。血が雨で流れ、そこには愛の象徴だけが、残されていた。
あの日、もうひとりの自分ともいえる"カノジョ"に出会ってから、ずっと考えている。
私は善か、悪か――。
私もいつか"カノジョ"のように呪詛師へ落ち、人を殺めるのか。それとも呪術師として人を助けるのか。
今もそれを知りたいと願いながら、"カノジョ"を探している。
|||
「…それが…その指輪?」
"カノジョ"の話を終えたあと、五条くんが私の下げているものを指さした。それはあの日、"カノジョ"からもらった婚約指輪。
今も肌身離さず持っているのは、あの日のことを忘れない為だ。あの日の、"あちら側"へ傾きかけた――愚かな自分を。
「そうだな…」
何故、五条くんに"カノジョ"の話をする気になったのかは、自分でも分からない。答えの出ない疑問を延々ひとりで考えているのが嫌になったのか、それとも彼に今すぐ殺して欲しいのか。
少なくとも、私は"カノジョ"のことを通報もしなかったし、また誰にも話さなかった。高専側にも詳しい話はしていない。ただ、"カノジョ"の犯罪現場にたまたま遭遇したとだけ言ってある。
誰も"カノジョ"の顔を知らない。だから、唯一会ったことのある私に、白羽の矢が立った。
生徒には下りてこないオトネという呪詛師が起こした特級案件の事件を、高専も見過ごすわけにいかなくなったんだろう。
「…そいつ、何したんだよ」
「…総監部のひとり、その家族を全員、惨殺したんだよ」
「…は?マジで?」
「そう聞いている。理由は分からないが…」
高専に入学した時、私は上に呼び出された。そこで"カノジョ"との関係を初めて聞かれた。それは"カノジョ"が私に宛てたメッセージを、現場に残したからだ。
「メッセージって…どんな」
「…何とも"カノジョ"らしい、分かりやすいメッセージだ」
そう、"カノジョ"は殺した総監部の遺体の体に、私の名とメッセージを刻んだ。
――、早くこっちにおいで。
五条くんは心底呆れたような引きつった顔で「…やべえヤツじゃん」と呟いた。
「そこから、この遺体の一部を持ち去る事件が起こり始めた。きっとこれも私に対するメッセ―ジだと思う」
「呪詛師への勧誘ってか?頭のイカれてる奴のやることは理解不能だわ」
「…そう、だな」
そのバッサリと切る辺りが、何とも五条くんらしい、と思ったら、つい笑ってしまった。
「何笑ってんだよ…」
「…いや、重く考えてる自分がバカらしくなっただけだ」
「ハァ?んなの考える必要ねえだろ。頭のおかしい女をサッサととっ捕まえりゃ終わる話だ」
「…そうかもな」
今は五条くんの軽いノリが救いになっていた。そう考えられる自分にもホっとして、指輪を服の中へしまう。その時視線を感じて、ふと隣を見れば、五条くんがどこか気まずそうに視線を泳がせていた。ついでに何かを言いたそうに口を開いては、すぐにまた閉じるを繰り返している。
「…何?」
「いや…まあ……つーか…さ。あんたの…その……境遇とやらは少し…だけ分かった…」
「ああ…今の話を聞かされて五条くんからすると心配になるのは分かる。私の家系は元々が陰の一族だしな…いくら善行をしようと、私みたいな"憑神"を宿した者の中にはまだ一定数、呪詛師に堕ちる人間はいる――」
と言いかけたその口を、五条くんの手のひらに塞がれた。何事かと思った。ぱちぱちと瞬きを繰り返しながら、目の前の五条くんを見れば、彼はそっぽを向いたまま「もう、いい」とひとこと言った。
「……そうかもしれねえけど…でも、もう、あんたのこと疑うのはやめる」
「やめる?…それはどういう――」
私の問いに五条くんは一呼吸を置くと、「今まで…悪かったよ。先輩」と、これまで見たこともないくらいの真剣な顔で言った。そのらしくないほどのしおらしい謝罪に、少しばかり面食らっていると、「何だよ、その顏」と、すぐにまた普段の彼に戻る。
どちらかと言えば、五条悟にはそっちの方が合ってる気がした。
「いや、別に。何も」
「あっそ。んじゃー他の部屋もサッサと調査しに行こうぜ」
どこか照れ臭そうに顔を背けて歩いて行く五条くんを見ていると、私の空っぽのはずの心がじんわりと温かくなる。何が五条くんの態度や気持ちを軟化させたのかは分からないが、その事実は母の腕に包まれた時のような心地よさだ。私の中にもまだまだ人の心は残ってるんだな、と自嘲しながら、彼の背中に「ありがとう」と、小さく呟いた。
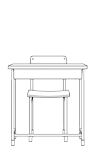
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
