11.初恋の結末
珍しく任務の入らなかった今日、私と悟は普通授業を終えたあと、娯楽室でそれぞれ寛いでいた。
高専に入学して早いもので、今はもう夏の終わり。少し涼しくなり、だいぶ過ごしやすくなった。本当なら任務のないこんな日は悟と都内に出て映画に行ったり、悟に付き合い新しいスイーツを出すような店を探索したりもするのだが、今日の天候は午後からあいにくの豪雨。秋に向かい始めるこの時期の台風は雨量も多く、とてもじゃないが出かける気にならない。
そこで無難に暇をつぶせる娯楽室に自然と足が向いた。娯楽室はその名の通り、様々な娯楽が置いてある。悟の好きなゲーム機やゲームソフトもあれば、本棚には漫画や小説、エッセイ、芸能人が出しがちな自伝書、あと何故か絵本まで並んでいる。これらは元々あった物もあれば、生徒がおのおの自分の私物を持ち込んだりして増えていったようだ。基本ここにあるものは持ち帰る以外なら好きにしていいという暗黙のルールがあるので、私は棚に並んでいる本の中から好きな作家の小説を手にすると、いつもの椅子に座り、いつものようにコーヒーを飲みながら読書を楽しむことにした。
しかし気になることが一つ。普段ならすぐにゲーム機を起動する悟が、それには目もくれず。窓際のソファに寝転がり、ただ、ひたすら窓に打ち付けてくる雨粒を眺めては深い溜息を吐いている。ここ最近、よく見かける光景だ。
その溜息の原因はよく分からないが、近頃の悟は少し様子がおかしい。先輩の任務に同行を始めた頃辺りから、気づけばあんな感じだ。
そう言えば彼女に対する態度が軟化し始めたのも、確かその頃だったな、とふと思う。
これまでガチガチだった"憑きモノ筋のは危険人物"という悟の偏った考えが、彼女のことを知るにつれて崩れつつあるんだろう。いや、すでに崩れたと言ってもいいかもしれない。
――あいつ…何か色々大変だったみたいだわ。
先々週、初めて先輩の任務に同行した日。高専に戻ってきた悟の口から、そんな言葉が飛び出したのがいい証拠だ。それまでも尾行がバレたあとくらいから少し軟化していた彼女への態度も、更に柔らかいものへ変化していったのは、きっと彼女の育って来た環境を知ったからかもしれない。私にその話を聞かせてくれた時の悟の表情は、前と比べ物にならないくらいに優しいものだった。
それにもう一つ変わったことと言えば、悟の彼女への態度が更に更におかしなものへ変化をしたということだ。
彼女との任務がない日は今みたいに元気がなく、どこか覇気のない顔をして黄昏れ始める。そして彼女と顔を合わせた時は、その綺麗な顔に喜色を浮かべながら声をかけに行くようになった。それまでの悟を見ていたからこそ、驚かされたのは何も私だけじゃない。やはり硝子も気づいてたようで「何あれ。何か嫌ってたの嘘みたいに懐いてない?」と呆気にとられたような顔でしきりに首を傾げていた。
でも、まあ何がそこまで悟を変えたのかは分からないが、彼女の過去を知ったことで良い方向へ転がったのなら、私としても一安心だ。仲間内でギスギスした関係を続けていくより、互いを理解しあえるならそれに越したことはない。
悟が彼女を尾行するキッカケを作れたことは、自分でもいいアシストだったな、と思う。あれがなければ今も悟は先輩のことを延々と敵視してたはずだ。
ただ…やはり、最近の悟の異変は少し気になるところではあるが――。
「何だ、いたのか、夏油くん」
不意にそんな声が聞こえて娯楽室に顔を見せたのは先輩だった。その手にはいつものキャリーバッグと、もう片方にはドン・キホーテの袋。大方また新しい駄菓子を仕入れて来たんだろう。
「お疲れ様です。先輩は任務帰りですか?」
ハンカチで雨に濡れたであろう肩を拭いている姿を見て尋ねると、彼女は「今日は普通に呪い討伐のね」と応えた。わざわざ、そんな言い方をしてきたのは、私が悟からある程度、自分の情報が入ってると思ったからだろう。
先輩は袋からいつものように駄菓子を取り出していく。それをオヤツ専用の棚――彼女が置いたらしい――へ並べていると、悟も彼女に気づいたのか、さっきまでの鬱々とした顔が嘘みたいな明るい表情でソファから起き上がると「、帰ってたのかよ」とこちらへ歩いてきた。
………ん?今、悟はなんて言った?
「ああ、五条くんもいたのか。静かだから気づかなかった」
「俺がいつもうるさいみたいに言うな。ってか、めっちゃ濡れてんじゃん」
「門からここまで来る間に濡れた。傘をさしてても意味ないな。強風で吹っ飛んでったし」
「ったく…風邪引くぞ」
私の思考がはてなの海に溺れそうになっている間に、悟は彼女の手からハンカチを奪うと雨に濡れた肩や髪を丁寧に拭いてあげている。その光景は再び私の脳内が機能停止をするくらい驚くものだった。
悟はいつから彼女のことを「」と呼ぶようになり、あんな気遣いをするほど優しく接するようになったんだ?私の見間違いか?と何度か目を擦ってみたが、相変わらずそこには先輩にジャレつく悟がいた。
「うわ、コーヒービートとマーブルチョコ箱買いかよ」
「どうせ、すぐなくなるからな」
「何気にこれ、みんな好きだよなー。この前は冥さんが懐かしい、とか言って一本持って帰ってたし」
「彼女は酒飲みだが甘い物も好きだからな」
「へえ、よく知ってんだ」
そんな会話を交わしているふたりは、どう見ても親しい先輩後輩だ。前のような険悪な空気は一切ない。それはさっきも思ったように良いことではあるが、悟の彼女への距離がやけに近いことが気になった。先輩の方は相変わらず淡々とした態度で分からないが、悟の方は明らかに彼女を意識してる。そう感じたのは私の男の勘というやつだ。
先輩は「任務報告書を書かないと」と言って、駄菓子の袋を悟に預けると、すぐに娯楽室を出て行った。悟はそれを置いて行かれた子犬のように見送っている。何となく「くぅん」と鼻を鳴らす音が聞こえそうな勢いだ。ついでにハァ、と溜息を吐いたのを私は聞き逃さなかった。さっきまでの明るい顔はどこへ行った?
「悟、どうした?」
「…んー?ああ、いや…何か…この辺が重いっつーか苦しいっつーか…何か変なんだよな、ここ最近」
悟は胸の辺りを擦りながら首を傾げている。どうやら体調が悪いようだ。この男でも体を壊すこともあるのか、と驚いたが、それを言うと怒り出すのは目に見えているのでやめておいた。
「そんなに具合悪いなら硝子に診てもらったらどうだ。彼女も医者志望なんだ。軽い胃痛や胸やけくらいなら治してくれるだろ」
「あー…まあ、そうだな」
悟はガシガシと頭をかきつつ、「ちょっと行ってくるわ」と持っていた袋を私に預けて娯楽室を出て行った。硝子は今日、医者になる為の授業をしている日だ。きっと彼女のいる医療学室にでも行くんだろう。
「あの悟が胸やけねえ…最近様子がおかしかったのはそのせいか?」
苦笑気味に言いながら預かった袋の中身をオヤツの置いてある棚へとしまっていく。
この時はまだ私も、悟の異変が体調によるものだと信じていた。
|||
「――え、どこも悪くなかった?」
夕飯時。食堂で食事をしていると、硝子と一緒に悟が首を傾げながらやって来た。胃痛があると言う割に、悟が選んだメニューは食堂で一番人気のカレーセット。通常のカレーに唐揚げがセットで付いて来る食べ盛り世代が好みそうな組み合わせだ。他にサラダやスープも付いてるので、なかなかにボリュームもある。そんなものを選ぶのだから、てっきり硝子に悪いところを治してもらったんだと思った。
なのに私の隣に座った悟から「どこも悪くねえんだと」と言われて少し驚いた。向かい側の少し離れた席へ座った硝子を見ると、若干呆れた様子で「健康そのものだったわ」と肩を竦めている。何でも医療学室には色んな医療器具があるので、アレコレ使って調べてみたそうだ。だが悟の体は健康そのもの。内臓や消化器系なども悪いところは一切なかったらしい。
しかも悟は「検査してる途中から胸の苦しいのは消えてた」と言う。じゃあ、さっきの具合悪そうな顔は何だったんだ、と私まで首を傾げたくなった。
「だーから何か変なもんでも食べて一時的に胸やけしてただけだって」
「あ?変なもんなんか食ってねえ。でも時々そうなるんだよ。硝子が見落としただけじゃねーの」
「バーカ。見逃すわけないでしょ。最新の機器で隅から隅まで調べたんだから。ああ、でも異常があったとしたら、五条の心臓に毛が生え散らかしてたことかもねー。それもぶっといヤツ」
「は?オマエ、ケンカ売ってんの?買うよ、いつでも」
「…おい、やめないか。こんなとこで」
私があれこれ考えてる間に、悟と硝子がいつもの言い合いを始めていた。これまたいつものように間に入って止めると、ふたりは互いに舌を出し合った後、食事をし始める。全くどこの小学生だ。
「でもまあ悪いところがないなら良かったじゃないか」
「…まあ。でもさーじゃあ何であんなぎゅーっと痛くなるわけ?何かモヤモヤして気持ち悪いんだよ、あれ」
「私に聞かれても。今は何ともないのか?そんなこってりした物食べてるけど」
「ぜーんぜん。っつか腹減ってるし美味いしかねえわ」
「……あ、そう。ならやっぱり悪いとこはないんじゃないか?」
そう言った時だった。悟の視線が私から外れ、食堂の入口へと向けられた。視線の先を自然に私も追ってみると、ちょうど先輩が入ってくる。彼女は悟と同じくカレーセット――量は大盛りだが――を注文して、それを受けとると私たちのいるテーブルの方へ歩いてきた。それを見た硝子が「先輩、こっち空いてます」と声をかけると、彼女は素直にこちらへ歩いて来て、硝子に促されるまま隣へ座らされている。彼女が遠慮がちに私たちの方へ視線を向けて来たのは、きっと自分が後輩の食事を邪魔していないか気にしてるんだろう。先輩は無意識にそういうことを気にしてるところがある。それも彼女の生い立ちが原因なんだろうが、そう考えると彼女も色んなことを今まで諦めてきたのかもしれないなと思った。悟の頑なな気持ちを変えてしまうくらいに――。
と、そこで異変に気付いた。先輩がきた瞬間から、やけに隣の親友が静かだということに。
「悟…?どうした?」
悟は急に食べるのを止め、胸の当たりを押さえて顔をしかめている。またさっきの痛みが復活したようだ。「またぎゅーっときてる」と言いながら、胸を擦りだした。こうして見てると確かに具合は悪そうで、本当に検査で何も出なかったのか?と私でも少し硝子を疑ってしまう。と言って、高専にある最新機器で調べても異変は出なかったのだから、今更普通の病院で検査を受けても結果は同じような気もする。
ということは――。悟のこの症状は体じゃなく、精神的なものなんじゃないかと推察してみた。
「悟、ちょっと聞くけど、そういう状態になるのはどんな時が多い?」
「あ?あー…」
悟は首を傾げつつ考える素振りを見せると、何故かその視線を少し離れた席で硝子と一緒に食事をしている先輩へと向けた。
「そういや…と顔を合わせた時はよくこうなるな…」
「…え」
「最初は何か見えない攻撃でもされてんのかって思ったけど、俺の目がそんなの見逃すはずねえし、だいたい攻撃してくるような人でもねえし――」
「ちょ、ちょっと待て、悟。それは…確かなのか?」
「あ?」
「彼女と顔を合わせると、その…胸の当たりがぎゅーっと…痛くなる?」
「ああ、まあ…そんな感じだな」
「…………」
「な、何だよ…その顏…」
大口を開けて徐に顔をしかめた私を見た悟は、怪訝そうに眉を潜めてから口を尖らせた。よく分からないが私に呆れられてる、というのは察したようだ。
やれやれ、と深い溜息を吐き出した私は、「だから何だよっ」と怒り出した悟へ、思い切り同情の眼差しを向けてしまった。五条家で大事に大事に育てられたこの男は、自分の心に芽生えたものの名前すら分からないらしい。
「悟…その胸の痛みの理由、教えてあげようか」
「…は?傑に分かんの?硝子でも分からなかったのに」
「そりゃいくら硝子が優秀な医者でも分からないだろうね。恋の処方箋の出し方は通常の医学では習わない」
「……は?こい?」
悟は未知の言葉を聞くかのような顔で、その綺麗な碧眼をまん丸にして私を見つめている。きっと頭の中では「鯉」だの「濃い?」だの「故意」だのという見当違いな言葉を思い浮かべてるんだろう。女の子を想う恋心を病気と勘違いするくらい、これまでの五条悟には無縁の感情だったらしい。
「そう、それは恋だよ。悟は先輩のことが好きなんだ。だから会うたび胸が苦しくなったり、ドキドキしたりする。恋をしている人間なら至って正常な反応だ」
分かりやすいように説明してやると、今度は悟の口がぱっかり開いた。かなりの衝撃を受けたらしい。きっと悟の脳内ではベートヴェンの運命が大音量で流れてることだろう。それを想像すると、ちょっとだけ笑ってしまった。
悟はその顔のまま、再び先輩を見る。そして、彼の色白の頬が見事に赤く染まっていったのを、私もまた信じられない思いで見ていた。
「…俺が……を好き?このドキドキ苦しいのが…恋…」
「ほんとに気づかなかったのか?悟もあんがい晩熟なんだな」
「………好き、なのか。俺はを…」
「………(聞いてないな)」
唖然茫然としながらブツブツ言いだした悟は、そのままふらりと立ち上がると何故か食堂を出て行ってしまった。それでも見事にカレーは平らげてたようで、空の皿を見て苦笑が漏れる。食べ終わってて良かったかもしれない。食べる前ならきっと食欲など出なかっただろうから。
「ま…嫌いと強く思うのも意識してる証拠だしね。それがひっくり返れば――恋に落ちることもある、か」
ふと独り言ちながら、意外すぎる親友の恋を思って笑みが漏れた。最強故にあまり他人を認めないところがある悟も、これで一皮むけるかもしれないなと思う。
ただ、この恋が実るのかどうかは、さすがに私にも分からない。先輩の複雑な事情もあることを考えれば、そう簡単にはいかないだろう。でも悟なら何故かそんな彼女の事情すら、吹き飛ばしてしまいそうだ。
そして、その私の勘は――何ひとつ間違っていなかったらしい。
私に「それは恋だよ」と指摘を受けた悟は、この次の日。いきなり彼女に告白をしたのだから。
|||
「………は?キスした?」
「ああ……」
「……告白する前に…?」
「…ああ」
「…………」
私が一つ質問をするたび、悟は机に突っ伏していた顔を少しずつ横へ向けて、これ以上尖らないだろう、というくらい口を尖らせ始めた。どうやら責められてると感じたらしい。いや、出来ればゲンコツをかましたい気分だった。だが無下限呪術の使い手に手を上げることほど無駄なことはないので、そこはどうにか堪えておく。
まさか悟がいきなりそんなアプローチをする男だなんて思いもしてなかった。
ただ、よくよく話を聞いてみれば、告白はちゃんとしたらしい。それもキスをしたあとで。
そもそも何でいきなり、そんな行動に出たのかと問い詰めたところ、悟は気まずそうに視線を泳がせ始めた。
私に自分が恋をしていると気づかされた悟は、今日、例の彼女の任務に同行し、いつも通りに呪詛師の調査をおこなった。その最中も胸のぎゅーはあったらしく、それが彼女と目が合うたび感じること、そしてそのぎゅーが、きゅんに近い感覚だと気づき、やっと自分の気持ちを自覚したという。
そこで任務帰り、校舎に向かう途中、突然彼女に告白しようと決めたようだ。その理由は悟なりにあったらしいが、きっと彼女の家のことも関係してるんだろう。あとは好きだと気づいたら早く自分だけのものにしたいという独占欲が一気に増したそうだ。そこで「報告書を書く」と言う彼女につき合い、誰もいない教室へ向かった悟は、彼女と二人きりになったところで、いざ告白をしようとした時。今日まで女の子に告白なんてものをしたことがない、という現実に直面したという。
しかも、ついこの間までは露骨に嫌な態度を見せてしまっていた相手。悟も自分の気持ちに気づいたばかりで、それをどう言葉にしたらいいのか分からなくなった。
そこで、何を思ったのか、言葉に出来ないなら態度で示そうと、報告書を書いていた先輩の隣に座り――。
「…で、いきなりキスをしたと…そういうことか」
「ん」
「悟……それは立派なセクハラなんじゃないか?」
「あ?別にエロい気持ちでしたわけじゃねぇよ」
がばりと顔を上げて悟は更に口を突き出した。いや、例え悟の気持ちがそうでも、いきなり彼氏でもない後輩にキスをされた彼女の方からすれば、それは性的被害といっても過言ではないだろう。そう悟に伝えたら、顔面蒼白になってしまった。ただ、その後の続きが気になるので「それで…彼女はなんて?」と訊いてみた。
すると、そこは悟も上体を起こし、身を乗り出して来た。
「それが受け入れてくれたんだよ」
「…は?いきなりキスをしたのにか?」
「ビックリはしてたっぽいけど、あの人、あんま顔に出ねえじゃん。でも嫌だったら突き飛ばすなり引っぱたくなりすんだろ」
「でもしてこなかった…と」
「ああ。だから俺もてっきりOKなのかと思って…」
悟は溜息交じりで再び机に顔を突っ伏してしまった。
|||
彼女の過去を聞いた後から俺の体調がおかしい。何というか、常に動悸がするし、意味もなく苦しくなったり、切なくなったり、どうにもコントロール出来ない状態になる。それは決まって彼女と会ったり、思い出した時に起こる現象だった。彼女と会えないと何か気になる。会ったらドキドキする。気づけば寝ても冷めても彼女のことを考えたり、顏が浮かぶ。彼女がいそうな場所を無意識に探す。気づけば一日の大半は彼女のことで頭が埋まってる。
まず顏を合わせるたび何故かドキドキするので病気かと思い、硝子に相談。でもどこも悪くないと言われた。腑に落ちない時、傑にどういう時にそうなるんだと訊かれ、正直に話したら、「悟、それは恋だよ」と指摘され、そこで初めて自分の気持ちに気づき、驚愕した。一晩寝ないで考えてみたが、納得するような現象がこれまで色んな場面に散りばめられていたことにも気づいた。
この前だってラブホに二人で入った時、やけにドキドキしてソワソワ落ち着かない気分になった。エレベーターに乗ったら乗ったで「バイアグラ」だの「大人の玩具」だのと男を煽るような張り紙まである始末。まあピチピチの俺にバイアグラなんてもんは必要すらねえけど、大人の玩具には反応してしまった。いや別にそんなもん使いたいというわけじゃなく、彼女がその張り紙を見ている、という事実に、まあちょっと…ムラっとした気分になり、酷く落ち着かなくなっただけだ。
それを彼女に「五条くんはトイレを我慢してる」と思われたのがムカついたけど、まあ変な下心を見透かされるよりはマシだったかもしれない。
その後に聞かされた彼女の家の話や過去の話は確かに驚いたけど、でも話を聞いてるうちに彼女の孤独が垣間見えてしまった。
別に彼女だって好きで憑神を宿して生まれてきたわけじゃない。
傑の言う通りだ、と今更ながらに思い知らされた。馬鹿すぎて自分を殴りたくなったのは初めてだった。
とにかく、この胸の痛みの理由を傑に教えられた俺は、彼女のことが好きだと自覚した瞬間から独占欲を発揮してしまった。
もちろん彼女の家のことも聞いたし、形だけの婚約者がいることも分かった。あとは――何となく察した。だからこそ、余計にそこから彼女を救いだしたくなったのかもしれない。
歴史のある家というなら五条家も同じで、世間から見れば俺の家だって相当おかしい決め事が在ったりする。だから彼女の家の事情なんて俺にとっては、まあ、そうだろうなという感覚でしかなく。もし俺との関係云々でゴネるようなら、それはそれで良いキッカケになるし、いざとなれば家丸ごとぶっ潰すくらいの気持ちだった。正直、家は常に危うい立ち位置にいることは間違いなく、総監部の奴らも監視目的で彼女を高専に入れたのだから、俺以上に"憑きモノ筋"の人間を危険視してるのは間違いないはずだ。なら次期五条家当主の俺が何をしたところで咎めることもないだろう。まあ、咎められたところで俺をとめられる人間なんてそうそういないんだから、脅威にもならない。
それくらいの覚悟で、俺は彼女にキスをした。女の子にこんな気持ちになったのも初めてで、だから余計にテンションも上がってたのかもしれないけど、言葉に出来ない気持ちが、キスと言う形で出てしまっただけ。
報告書を書いていた彼女の隣に座って「なあ」と声をかけたら、彼女はすぐに顔を上げて俺を見た。だからサングラスを外して、ゆっくり顔を近づけ、彼女の赤い唇に自分のそれを重ねた。彼女の漆黒の瞳が驚きで大きくなったけど、いきなりキスをした俺を突き飛ばすでもなく、怒鳴るわけでもなく。ただ何も言わずに受け入れてくれた。
だから彼女も同じ気持ちなのかと一瞬でも勘違いをしたし、その勘違いのおかげで、やっと素直に気持ちを言葉にすることが出来たのかもしれない。
「…好き。俺と付き合って」
そう伝えたら、彼女はぱちくりとした目で俺をジっと見つめた後――。
「断る」
「何で?!」
彼女はあっさり俺を振った。
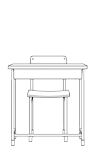
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
