12-悪い子でも許してね
※本番は在りませんが夢主とモブとの軽めな性的描写あり。苦手な方は観覧をご遠慮ください。
ゆらり、と行燈の炎が揺れ、私に重なるようにして大きな影が時折、動く。衣擦れの音をさせながら着ているものを脱がすのに夢中な男は、相変わらず私の体を雑に触ってきた。
「最初の頃よりはだいぶ…発達してきたな、ここも」
シャツの合わせ目を開いた男は、舌なめずりでもしそうな勢いで呟いた。充血し、じっとりと男の欲を孕ませた目は、私の体を舐めるように凝視する。しかし私は何も感じない。
快も不快も、何もない。この獣のような目つきを向けてくる一回りも年上の見栄えがいいだけの男が婚約者に選ばれ、私が生涯を共にする相手なのだという現実だけが、そこにある。
この醜悪な環境から一時逃してくれた母はすでに亡く、生物的に父親というだけの男に連れ戻された時から、こうなることは決められていた。
たった一人の味方を失ったあの頃の私には、すでに逃げる気力も、術もなく。ただ自分の運命に流されて今日まで生きてきた。
「表情のない奴だな、相変わらず。どこを触っても濡れもしないんだから」
私の胸に吸い付いて、好き勝手に舐め回していた男は、舌打ちしながらいつもの台詞を口にした。濡れるという感覚は経験したことがなく、体のどこを弄られようが、心が一ミリも動かなければ触感などないに等しい。一年前に家へ連れ戻され、男と引き合わされてから、この名ばかりの婚約者は幾度となく私の部屋へ忍んでは体を弄ってきたけれど、何をされようと痛みすら感じなかった。
それが理由かは分からないけど、男は私の体に触れても抱こうとはしない。まずは開発が先だとムキになっているようだ。下衆のくせに意外と辛抱強いのがおかしかった。おかげで私はまだかろうじて清いままの体を保っている。でもそれもいつまで続くか分からない。気まぐれで、もう抱くと決めたなら、この男は迷わず私を"篭女"にするべく食い物にするはずだ。
男は自分の着ていた物を脱ぎ捨て全裸になると、股の間へ自分の体を入れ、私の太腿を半ば強引に開いていく。内股に男の手形がつくほど強く。秘部に男の視線が痛いほど突き刺さるのが分かる。ごくりと喉を鳴らす音も。
この男は敢えて我慢してるのだ。そうして己の欲を昂らせている。いつか、この体をめちゃくちゃに犯してやろうという、そういった欲望の昂ぶりを男の視線から常に感じていた。
「その色気のない眼鏡は外しとけよ」
男はそれだけ言い捨てると、私の股の間へ顔を埋めた。言われた通り眼鏡を外して枕元へ置くと、男の指先が薄い下生えを軽く撫でながら鼻先をつける。思い切り息を吸い込む音がした。私の秘部の匂いをまず嗅ぐのがこの男の性癖らしい。他の男の匂いをさせていないか、または体に他の男の痕跡はないか。いつも身体中、丹念に調べる。こう見えて独占欲だけはあるのだ。自分の所有物に手垢を付けられたくないという、腐ったプライドも。
「たまんないな、処女の匂いは」
そう独り言ちながら、男は私の秘部へその分厚い舌を伸ばした。まずは割れ目に沿い、襞の隅々まで舐め回し、隠れている小さな陰核を剥き出しにして吸い付く。なのに私の体は何の快感もなく、ただ男の舌が肌を湿らせていく感覚しかない。男はどうしても濡らしたいのか、必死にその場所を舌で弄るが少しも濡れることはない。ただムキになっていく男の姿が滑稽で、声を上げて笑いたい気分だった。
「くそ…マジで不感症かよ、オマエは」
男がそう愚痴りたくなるのも理解できる。この一年、何度同じことを繰り返してきたことか。結局、今夜も男は私を感じさせることも出来ないまま、ローションなどを塗りたくって指を膣口へ押し込んできた。
「く…相変わらずキツイいな…。やっぱこれじゃナカを育てないことには話にならない」
股間をパンパンに腫らし、私の股を必死に弄る男は滑稽だった。こんな男に触れられたところで心も体も動くはずがない。無知ゆえに眼鏡を外せと言っていたが、この眼から胎内に宿る狗神がジっと息を殺して外界を見ていることすら、この男は気づかない。今にもその喉元を喰いちぎらんばかりに、殺気を垂れ流していることすら感じることもなく、ただひたすら私の体を弄ることだけに耽っている。
ああ、今なら簡単に殺せる――。
男が抑えつけている腿に少しばかり力を込めるだけでいい。男の首は簡単に折れるはずだ。
いっそ、この場で殺してやろうか――。
男への殺意を解放しようとしたその時だった。
――好き。俺と付き合って。
脳裏にあの言葉が過ぎって息を呑む。彼にキスをされた時の、暖かい感触も。
あんなに優しく触れてくれたのは、五条くんが初めてだった。
「お、感じてきたか?」
ナカを指で掻きまわしていた男が、僅かに息を呑んだ私を見て勘違いしたようだ。更に鼻息を荒くし、ナカを弄ってくる。その時、私の脳が初めてそれを"不快"だと感じたらしい。考えるより先に男の肩を蹴り飛ばしていた。たった一蹴りで男はベッドの下へと転がり落ちる。その姿はひっくり返ったカエルのようで、だらしなく勃起させたモノが恥ずかしいくらいに男の間抜けさを演出していた。
「な、何すんだ、このガキ!」
「飽きた。オマエの愛撫は下手すぎて気持ち良くもないしな」
「な、何だと…っ?小娘が偉そうに…!俺はオマエの婚約者――」
「だから何だ」
「……う」
乱された服を脱ぎ捨て、裸にバスローブを羽織ると、転がったままの男を見下ろす。そこで初めて私の眼に宿る狗神の殺意に気づいたらしい。男は顔面蒼白のまま自分の服をかき集めると、転げるようにして部屋を飛び出して行った。どうせあの男にでも泣きつくんだろう。私の、いや、憑神の父親というだけで、一族のトップに上り詰めたあの男に。一回りも下の小娘に足蹴にされたことはひた隠しにして。
情けない婚約者殿だ。
「…気持ち悪い」
今更ながら、男に触れられた感触がじわじわと不快感を連れて来て、私はすぐに風呂場へと向かった。今すぐ全ての痕跡を洗い流したかった。
(…五条くんに救われたな)
先ほど頭に浮かんだ後輩のことを思い出し、ふっと笑みが漏れる。いつもは母が私のストッパー的な存在だった。狗神に飲み込まれそうになった時も、頭に浮かぶのは母の存在や言葉だ。なのに今夜は違った。
「バカだな…。あんな告白を鵜呑みにするなんて」
ふと現実を思い出し、自嘲気味に呟く。こんな呪われた人間を本気で想ってくれるはずもない。現に彼は私を――。
――もう、あんたのこと疑うのはやめる。
あんなのは本心じゃない。そう思うのに、何故かその言葉はいつまでも私の中に木霊するよう響いて、朝まで止むことはなかった。
|||
夏の終わり、五条が先輩に振られたというニュースが高専を駆け巡り、それを耳にした私は死ぬほど――笑ってしまった。
あんなに敵意丸出しにしてたクセに、ころっと惚れるところが五条らしい。あいつは口は悪いし我がままで唯我独尊を地でいってるわりに、意外と素直でそういうところは純情なのかもしれない。
だいたい。どんな形であれ。先輩のことになると、あれだけムキになるのだから、五条の中に先輩の存在はドンと居座るくらい大きかったわけで、ちょっと刺激を加えたら方向を変えて走りだすピタゴラスイッチのように、五条の心は真逆なゴールへ辿り着いたみたいだ。
夏油はすでに知ってたらしく「その件で悟をからかうなよ。またモメるだけだから」と釘は刺されたものの。やっぱりそこはからかいたくなるのが人の心理というものだ。
その最大の理由として、普段から「俺、モテるんで」的な態度をしくさって「え、硝子、彼氏もいねえの?」と散々煽られてきたという経緯がある。
別に好きで彼氏を作らないわけじゃないのに、勝手に「硝子みたいな気の強い女はモテない」とか決めつけられてんのもムカついた。
そう。私には五条の傷口にたっぷりの塩を塗りたくり、その出来立てほやほやの傷口を化膿させる権利くらいは――あるはずだ。
将来、医者を目指す人間がやってはいけないようなことを考えるだけでワクワクして、夕べはあまり眠れなかった。
――何でこういう時に限って任務に出てるんだ、あの二人は!
なのに今朝すっきり目覚めたのは、あの五条を奈落の底へ突き落せるという、人としてどうなん?と突っ込まれそうな理由だけど、それまでの恨みがある私は人としてどうなん?と思われることを敢えてしたい気分だった。
早速、五条の息の根を止めに行くべく意気揚々と食堂へ向かう。
「おはよう、家入さん」
「おはよう御座います」
数人の先輩方と軽く朝の挨拶を交わしつつ長い廊下を歩いて行くと、お味噌汁のいい匂いが漂ってきて、お腹の虫が情けない音を立てた。
「あー今日は無性に和食が食べたい」
メニューが和洋中、各種雑多に選べるのも最高で、ここの食堂はいつ行っても食べたいものを提供してくれる便利さも気に入っていた。高専生なら誰でも同じかもしれない。
――さて、五条と夏油はどこにいる?
食堂に入ってまずテーブル席を確認する。だいたい二人は早起き組だから、私よりは先に来ていることが多い。そして今日もやはりと言うべきか。定番の窓際の席。それも一番端っこに席を陣取っているノッポの男二人が見えた。あの席は先輩のお気に入りのはずなのに、いつの間にかクズ二人の専用席みたいになってるのも腹立たしい。まあ、先輩が全く気にしてない感じだから私が文句を言うのもおかしなもので放置してるけど。
まず先にカウンターで焼き魚定食を頼むと、出てきたトレーを持ってクズ二人のいる席へと歩いて行く。
どうやって第一声で五条を奈落の底へ落としてやろうか、と考えながら、つい口元が緩む。
けど、二人の座る背後まで近づいた瞬間、ここは死人が彷徨う地獄ですか?と聞きたくなるほどの、どよんとした、重力すごくない?と首を傾げたくなるような重たい空気が、一気に私の頭上に降り注いできた。
何だ?この元気な生気を吸い取られそうなほどの、負のオーラは。
「…マジか」
その圧をかけて来てるのは他でもない。目の前で顔面をテーブルに伏せ、ぺしょんと潰れている"自称モテ男"の五条その人だった。
どうやら私が塩を塗らずとも、ぐちゃぐちゃに化膿した傷にやられて、心は再起不能らしい。隣の夏油が私に気づき、何とも言えない表情で肩を竦めたのがいい証拠だ。
「五条、生きてる…?」
「…さあ。朝からこの調子で何も食べようとしない」
「あ、そう…」
まあ、そこまでヘコんでるなら、今回だけは塩を塗るのはやめておいてやるか――。
なんて思うわけもなく。私は満面の笑みで夏油とは反対側の五条の隣に座ると、「断る、の一言で先輩に振られたんだって?」と顔を覗き込んでやった。
するとテーブルに突っ伏していた顔をギギギ、と油の指してないロボットみたいに動かして、五条はぎろりと私を睨みつけてくる。怒る元気はあるらしい。
「何よ。モテるとか言ってなかったっけ。大学生のお姉さまとか、女子高生に」
「うるせえな。をその辺の雑魚女と同等で語るんじゃねえよ」
それにまだ俺は諦めてないし、と言いながら、五条は上体を起こすと「おばちゃん!レバニラ定食!」とカウンターに歩いて行ってしまった。やっぱりお腹は空いてるらしい。
「ってか朝からレバニラって…」
「全くだ。今日一日悟と同行する私の身になって欲しいね」
夏油も苦笑交じりで溜息を吐いたけど、五条が少し復活したのはホっとしたらしい。手の付けてなかったトーストセットの目玉焼きを美味しそうに食べ始めた。
「でもマジで五条のやつ、先輩に告ったんだ」
「ああ。私も聞いた時は驚いた」
「あんなにケンカ腰だったくせに、何か勝算でもあったのかな」
「いや…そんな細かいこと考えてないだろ。自分の気持ちに気づいて、その勢いで――」
「勢いで…何?」
「いや、別に」
夏油はにっこり微笑んで熱々のコーヒーを口へ運んだ。何だ、その顏は。秒で失恋した以外に何かあるような言い方だったけど。
「ところで先輩は?」
いつもならこの時間には顔を見せるはずなのに一向に現れず、キョロキョロしていると、夏油が「ん?」とこっちを見た。
「先輩よ。直接先輩にも話聞きたかったのに」
「ああ…先輩は二日前から任務で帰ってないみたいだよ。夜蛾先生の話だと実家の方に泊まってるとかで。だから悟も朝から闇を背負ってたというわけさ」
「え…?さっきのアレ、失恋のショックでヘコんでたんじゃないの?」
「いや、それは先週の話。秒で振られたわりに悟は諦めてないみたいだから」
「えっ?諦めてないって…あいつ、そんなに本気なわけ?もしや、また告るつもりとか…」
「だったら悪いかよ」
突然上から声が振ってきて仰ぎ見れば、五条がレバニラ定食の乗ったトレーを持ったまま私を見下ろしていた。若干その艶々した口が尖っている。
五条はそのまま元いた席にどっかり座ると、今度はそのサングラスに隠れた青い瞳を夏油へ向けた。どこか不満そうだ。
「傑もペラペラ話すなよ。やっぱ俺が振られたこと誰かに話したのお前か?」
「心外だな。私も先輩から聞かされたんだよ。悟が教室で告ったところを通りがかった先輩が見かけたらしくて。まあ私は知らないフリして聞いてたけど、きっとあの先輩から広まったんだろ?」
「…あっそ。別にいいけど」
五条はそう言ったあと黙々と食事をし始めた。この様子だと夏油が言ってたように諦めたわけじゃないらしい。その辺は五条らしいけど先輩にしつこくしないか心配だ。私は五条が先輩のことを敵視してた頃から先輩が好きだし、仮に五条の気持ちが本気であっても彼女に迷惑かけるのは、やっぱり許せないと思う。まあ、あまり男女の問題に第三者の私が口を挟むのもどうかと思うから言わないけど、五条の行動が目に余るようなら私が止めなければ、と心に誓う。
その時、先輩が食堂に入ってくるのが見えて、思わず「あ」と声を出してしまった。そのせいで今まで黙々と食事を続けていた五条がふと顔をこっちに向けて、そのあと私の視線の先を追うように、入口の方へ振り返る。その瞬間、ガタンっと乱暴に椅子から立ち上がった。かと思えば「…じゃなくて先輩!」とそれまでの不機嫌そうな顔から一変、嬉しそうな笑みを浮かべて、先輩の方へ歩いて行く。その変わり身の早さに呆気にとられていると、夏油が苦笑交じりで私を見ていた。
「…分かったろ。悟が本気だって」
夏油がそう言いながら、嬉々とした顔で先輩に話かけてる五条へ視線を向ける。私もその光景を見てちょっと唖然としてしまった。何がどうなれば、あんなに熱が上がるもんなんだと首を傾げてしまう。
「意外。五条って誰かを好きになると猪突猛進型だったんだ」
「そうみたいだな。まあ悟は好意を持つ、というか認める相手が極端に少ない分、一度認めた相手には心を全開きにしてしまうんだろう」
「あー…なるほどね。そう言われてみれば確かにそうかも」
なまじ強い分、五条の中に絶対的にブレない芯みたいな部分があると私は思っていた。でもそのブレない芯は五条が自分以外の人間に愛情を向けた時でも発揮されるらしい。
「ありゃちょっとやそっとじゃ諦めないな…きっと」
「私もそう思うよ」
私以上に五条を理解しているであろう夏油も苦笑気味に頷く。たった二日会えなかっただけで死人みたいになっていた相棒に夏油も痛感させられたんだろう。
何となく。そう何となくだけど、私の中に波乱の予感が渦巻いていた。
「…あいつ、最強のストーカーになるんじゃない?」
|||
まさか硝子にストーカーを心配されてるとも知らない俺は、二日ぶりに彼女と会えて、更に自分の気持ちを実感していた。
会えない日は見る景色の一つとっても全てが色褪せてるし、好きなゲームをしててもつまらない。飯も美味くないし、お笑い番組を見てても全然笑えない。たった一人と会えないだけで、こんなにも一喜一憂する自分に驚かされるけど、意外と悪い気分じゃなかった。
「で、任務はどうだった?ってか何で実家に泊まってたんだよ」
「任務は秒で終わった。でもその後の調査やら何やらもあって、あと月に一度は実家に顔を見せろと言われててね。これでも婚約者のいる身だから」
彼女は食事をしながら相変わらず淡々と話している。まあ、その中に聞き捨てならない単語も出てきたけど、そんなの俺には何の枷にもならなかった。
先週、彼女に告って秒で振られたあと、彼女には決められた相手がいると聞かされた。でもそんなのは過去話を聞いた時から察してたことで、俺はそれでもいいと言った。どうせ彼女にしてみば、名ばかりの婚約者。彼女を"篭女"とやらにする為の、家の下衆な風習だ。そんな男なんて俺の敵じゃない。
ただ、やっぱりに惚れてる身としては、そんなクソ野郎に毎月会いに行かされてんのか、くらいは思ってしまう。
前に見た恋愛映画でヒロインの恋人の男が彼女に近づいてきた男に嫉妬をする描写があった。けど、それを見てた時の俺には嫉妬をする男の気持ちなんか少しも理解できなかったけど、今なら。そう今なら※ケビンの気持ちが痛いほど理解できる。(※ヒロインの恋人の名前)
もし今、目の前に先輩の自称婚約者が現れたら、秒で消してしまう自信がある。
まあ、これを傑に言ったら「悟。それダメなやつ」と速攻でたしなめられたけど。
でもそれくらいには俺も嫉妬をする心があったってことだ。自分でも意外だけど。
「ふーん。自称婚約者くんは元気だった?」
「まあ、元気そうだったな」
ちょっとだけ嫌味で言ったつもりだったのに、先輩には効果なし。普通に返され、へのへのもへじ顔の男がニヤケながら彼女に触れるとこまで頭に受かんだ瞬間、俺の心臓が嫌な音を立てた。硝子に検査してもらった時「毛が生えている」とかふざけたことを言われたが、あいつの眼は節穴だ。今の俺の心臓はガラスで出来ている。彼女の一言で、ピシっとヒビが入るくらいに脆い。
「…へえ、やっぱ会ったんだ」
分かりやすいくらい声のトーンが落ちた俺を、彼女はふと見上げてきた。その不意打ちも心臓に悪いんだけど。
「本意ではないけどな」
「…そう言って、また来月にも行くんじゃねえの」
と様子を伺うと、彼女は意外にも考え込んでしまった。てっきり、またシレっとした顔で「そうだな」くらいは言われると思ってたのに。
「…どうかな。向こうもしばらくは私に会いたくないだろう」
彼女はふとそんなことを呟いて、再び食事を始めた。その横顔に普段とは違う、僅かな感情が見えた気がして少しだけ気になった。相手の男と何かいつもと違うことがあったのか、それとも――。
「……それは何で」
ちょっとだけドキドキしながら訪ねてみると、彼女は食べていた手を止め、また少し考えこんだあと、俺に視線を戻した。
「殺気を込めて蹴り飛ばした」
「……は?」
「あとにも先にも、あんなことをしたのは初めてだったけど、なかなか爽快だったな」
「……マジ?」
思わずサングラスがズレて、目の前の彼女を凝視する。先輩はいつもより表情も柔らかく見えたからだ。眼鏡の奥の瞳が俺の惚けた顔を映してる。
「まあ、こんなこと言ったら五条くんにまた危険視されるかもしれないけど。でも残念ながら殺してはいない――」
彼女からその言葉を聞いた瞬間、俺は腕を伸ばしてつい彼女を抱き寄せていた。周りの先輩方がざわつく声も聞こえたが、そんなのどうでもいいと思うくらいに顏がニヤケる。
ぎゅうっと腕に力を込めても、やっぱり彼女は逃げることも突き飛ばすこともせず、黙って俺の抱擁を受けてくれていた。ただ、少しばかり力を入れすぎたらしい。腕の中で彼女がもぞもぞと動く。
「…五条くん。苦しい」
「んー。我慢してよ」
「…どうした?急に」
「別に。ただ…嬉しい」
「嬉しい?何が」
「んー?いや、その男が蹴り飛ばされた姿、俺も見たかったなーと」
俺がそう言って笑うと、彼女は「ああ…」と小さく笑った気がしてドキッとした。
「なかなか滑稽だったな。フルチンでひっくり返ってる姿は」
「…………は?フルチン?」
なかなか凄いことを言われた気がして、思わず体を放すと、彼女は普通のテンションで「カエルみたいだった」と真顔で付け足した。いや、いやいやいや、ちょっと待て。フルチンってどういう状況だよ、と突っ込みそうになったが、ギリギリそこは堪えた。彼女に家の話を聞いた時、考えないようにはしてたけど、俺にとっては嫌な話も交じってたのはあとになって気づいた。あの話を聞いた時、きっと、そういうことなんだろう、と察してたつもりだったけど、でも実際にリアルをぶつけられると、ガラスの心臓が割れるどころの話じゃなく。粉々の木端微塵になりそうだった。
でも彼女は俺の青ざめた顔を見て気づいたのか「別にセックスはしてない」とひとこと言った。その瞬間、ホっとしたけど、同時にこの人は何でこうも明け透けなんだ!と頭を項垂れる。彼女の性格なのか、それとも憑神を宿してるからなのか。彼女からは女の恥じらいというものが一切感じられないことに改めて気づかされた。
全身の力がダイソンで吸われたみたいに俺の肉体から吸いだされてる気がするくらい、脱力してしまった。
「どうした?五条くん…具合でも悪い?」
「……いや、いい。大丈夫。いや、大丈夫ではないけど…今はいいことにするわ」
「ん?」
「…とりあえず…その自称婚約者とやらに何もされてないならいいことにする」
「何もされてないことはな――」
「あー!そういう細かい話は言わないでいいから!俺の心臓がもたない」
彼女の口を塞ぐのに手で抑えると、表情のない顔にかすかながら笑みが浮かんだ気がした。だから今、ここでそれは反則だろ。
「五条くんは変な男だな」
「いや、それ先輩にだけは言われたくないやつな…?」
俺の答えに彼女はきょとん、とした顔をしてた。何かもう色々と心配だけど、彼女が普通の女の子じゃないのだけは分かるから、出来れば早く俺を受け入れて欲しくなった。
そうしたら誰の目も気にせず、反対も押しのけて、俺が彼女の腐った家ごと、潰してやるのに。
そんな騒動なことを考えていたら、遠くから「先輩に抱き着くな、五条!」という硝子の怒鳴り声が聞こえてきた。
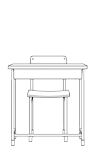
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
