13-青い春の過ごし方
「先輩、俺と付き合って」
「……これで勘弁してくれ」
今日も今日とて先輩に告っている悟は、またしても秒で振られたらしい。ずーんという効果音付きで闇を背負って私の元へ戻ってきた。先輩と一緒にコーヒーを飲んでた硝子が「失恋記録更新中ー」と追いうちのように笑ってるのが恐ろしい。そう…高専に来て、女は怖い生き物だと、私はこの歳ですでに理解してしまった。
「悟、何を持ってるんだ?」
娯楽室のテーブルにいつもの如く顔を突っ伏した悟の手に、何かが握り締められている。そう言えば先輩からさっき何か渡されてたっけ。そう思いながら訪ねると、悟は顔を突っ伏した体勢を一切変えることなく、手のひらだけ広げて見せた。そこにはチロルチョコが一粒乗っている。
「……これで勘弁してくれだって」
「え」
「俺の告白はチロルチョコと同等の価値ってこと……?」
「………それ私に聞くのか?」
やっと頭を上げてこちらを向いた悟の端正なはずの顔は…まあ何年も歳を重ねた老人みたいになっていて。ついつい「ぷ」と吹きだすとすぐに小さな舌打ちが返ってきた。こんなことが今週は五回もあったから、私も少々のことでは驚かなくなったけど、先輩は一貫してブレないというか、私の目から見ても面白い存在だなと思う。
この悟をここまでしょぼくれさせる女の子は、他にいないだろうな。
「そもそも何で硝子と一緒の時に告ろうと思ったのか分からないな。もし先輩がOKしたくても恥ずかしくてNOと言う場合だってあるだろ?」
「……仕方ねえだろ。顔見たらつい口が勝手に……そもそもは恥ずかしがるような女じゃねえし」
「それは…どうしてだい?分からないだろう」
「……どうしても何もそうなんだよ。じゃなきゃ、あんな…」
「あんな…とは?」
「…何でもねえよ。ったく硝子のヤツ…ちょっとと仲いいからってムカつく」
悟はぷいっと顔を反らして唇を尖らせた。拗ね方が子供のそれで、またじわりと笑いがこみ上げてきたが、ここはどうにか耐えておく。これ以上不機嫌になられると、こちらにも"八つ当たり"と言う名の火の粉が降りかかりかねない。硝子にもその辺を考えて欲しいところだ。
見れば硝子は悟に当てつけるように先輩に密着して楽しそうにお喋りをしていた。まあ、先輩の件をネタに悟を煽るのは彼女なりの報復なんだろうが。
それも元を辿れば悟が普段から硝子を煽り散らかしてたから…という自業自得的な理由があったりする。
「もう少しアプローチの仕方を変えてみたら?」
「……どうやって」
「だから…出会いがしらに付き合ってとかじゃなく、デートに誘って二人きりの時に告白してみるとか」
「…デート?」
興味を示したのか、悟はズレたサングラスを直しながらやっと上体を起こすと、腕組みをして「うーん…」と何やら悩みだした。
悟は見た目だけで言えば芸能人も真っ青というくらいに眉目秀麗。よって、その恵まれた容姿のおかげか――本人は人を顔だけみたいに言うんじゃねえと言うだろうが――非術師の女の子からはかなりモテる。硝子にも散々自慢してたが、私もその現場を何度も目撃しているから、悟が言ってることは殆どが事実だというのを知っていた。
だから、というわけじゃないが、自分から誘わずとも相手が寄ってくるので、悟はそれほど苦労することもなく美味しい思いをしてきた男なわけで。今みたいな状況は初めてといっても過言ではない。つまり、自ら女の子を口説くとか、デートに誘う、ということだけに関して言えば、全くの素人だ。
そこを指摘すると、むっと目を細めたものの。自覚はあるのか何も言い返してはこなかった。ただジト目で「そういう傑はデートとか誘ったことあんのかよ」とさり気なく私のことを探ってくる。
「まあ、中学の頃はこれでも彼女がいたんでね。それくらいはあるさ」
「…え、傑、彼女いたの?どんな子?どういうキッカケで付き合ったわけ」
「…食いつくね」
急にぐいぐい来られて苦笑したが、悟は大真面目に聞いてるらしい。教えろよ、とせっついてくる。まさか高専へ来て、すでに懐かしいと思えるような自分の恋バナをする羽目になるとは思っていなかった。
「まあ…その子、というか彼女は同じ中学の先輩でね。たまたま彼女が低級呪霊に憑かれてるのを見かけて祓ってあげたんだ。彼女も術式はないが視える側の人だったから、そのことでお礼を言われて、まあ…何となく付き合う流れになったというか――」
と、そこで言葉を切ったのは、悟が椅子ごと私の前に移動してきて「へー」「ほっほー」と相槌を打ちながら真剣に聞いてるからだ。いつもは私の話の半分も聞いてないくせに、こういった話題は別腹らしい。
「で?その先輩って女の子と、どういう流れで付き合うことになったんだよ。その辺をもっと詳しく教えて」
相手が先輩というところに食いついたらしい悟は、早く応えろ的な圧をかけるように、その青い瞳でジっと私を見つめてくる。内心やれやれ、と苦笑しつつ、その当時のことを思い返してみた。あれは私のちょっとした青い春だったなと懐かしく思う。
「彼女が三年、私が二年の時で、彼女に憑いてた呪霊を祓ったことで言葉を交わすようになって、一カ月後くらいだったかな。日曜日に一人でふらっと映画を見に行った新宿で彼女とばったり会ってね。彼女も一人で映画を観に来たらしくて、それがたまたま同じ映画だったから、じゃあ一緒に観ようかということになった」
「ふんふん。それで?」
「それで…二人で映画を観て、その帰りにカフェに寄って観た映画の感想などを話してる内、私と彼女の映画の趣味が同じだということが分かった」
「ほぉーで?」
「で…今度は一緒に映画を観に行こうかという話になり、その後は事前に約束をして観に行くようになったんだ。そんな感じで何度も学校以外で会ってる内に彼女との時間が楽しいと思うようになって、それで――」
「傑から告ったのか」
「いや、告白しようと思ってた矢先に彼女の方から付き合って欲しいと言ってくれてね」
「チッ。何だよ、それ。全然参考にならねえ。最後まで聞かなきゃ良かった」
「いや、悟が話せって言ったんだろ」
相変わらず理不尽な悟は「どう告って上手くいったか聞きたかったのに」とブツブツ言っている。まあ気持ちは分かるけど、非術師である私の元カノと先輩を同等に考えても仕方がないだろうに、と苦笑が洩れた。
「で、その彼女とはどうなったわけ。あ、今も付き合ってんの?」
自販機でコーラを買って来た悟は、あんなことを言ってたわりに、まだ私の恋バナに興味があったらしい。身を乗り出して訊いてきた。
「いや、彼女が先に卒業して、すぐの頃はまだ会ってたけど、私も高専に入学を決めてからは距離を置いたんだ。今以上に会えなくなるだろうと思ってね。それで半年後くらいにきっぱりと別れたよ。向こうも入学先の高校で気になる男が出来たようだったし、ちょうど良かった」
「え、マジ…傑はそれで良かったわけ」
「まあ、会えなくなって互いの環境が変わると、どうしても近くにいた時のような関係のままじゃいられないからね。あれで良かったと思ってるよ。彼女のことは好きだったけど、ある種の熱病みたいなものもあったと思うし、私も彼女のことより自分の術師としての未来の方を優先したわけだから」
「…へえ。そんなもんかよ。何かあっさりしてんな、傑は」
「言っても、まあ中二、中三の頃の話だから、その年齢で"会えなくても君をずっと想ってる"とは、なかなかいかないだろ」
「そーかぁ?俺は相手がだったら、それくらい…つーか会えない状態をどうにかするけどな。会えないとか耐えられねえし」
悟はシレっとした顔でそんなことを言い出したが、私も悟ならきっとそうするだろうな、と思った。悟は何歳だろうが、互いの状況はどうであろうが、本気で誰かを好きになることが滅多にない分、一度惚れたらとことん相手の為に動ける男だろう。そういうところは変に純粋というか、男気があるというか、それくらい悟の中で揺らがない何か信念みたいなものがあるのかもしれない。
口では弱者に対して辛辣なことを言っても、いざとなれば体を張って守るくらいの、術師としての信念があるように。
「悟はいい男だね」
「あ?何当たり前のこと言ってんだよ」
頬杖をつきながら聞いていた悟は、上体を起こすと椅子の背もたれに背中を預けながら、その長い足をわざとらしく組み直した。いつものどや顔だ。たまに褒めるとすぐこれだから困るよ、ほんと。
「…まあ、私の方がモテるけど」
「ハァ?んなの傑の外面がいいだけだろ」
「ははは。悟は何でも口に出しすぎるんだよ。少しは愛想というものを身に付けたらどうだい?」
「あ?んな外面で寄ってくるような女に興味はねえし」
「いや、女の子のことだけじゃなくて――」
「でも……そうか。映画という手もあるな」
悟は私の話も聞かず、何やらブツブツ言いながらケータイで何かを探し始めた。おおかた私の話を聞いて、先輩を映画に誘う気だろう。彼女も映画は好きだと前に聞いたことがあるし、悟もそれは知ってるはずだ。
「ま、私は応援してるよ、悟」
「あ?おーさんきゅ」
立ち上がって悟の肩をポンっと叩くと、あまり私に見せたことのない可愛い笑顔を向けられてしまった。
青春してる親友を陰ながら見守るのも、案外悪くないもんだな。
そう思いながら、私は娯楽室をあとにした。
|||
「先輩」
娯楽室を出て行った彼女を追いかけて声をかけると、はいつもの如く表情のない顔を俺に向けた。
「五条くんか。どうした?」
「いや、あのさ…先輩、次の休みっていつ?」
二人で並んで鳥居の細道を歩きながら、早速彼女のスケジュールを聞いてみた。さっき傑の話を聞きながら、確かも映画が好きだと話してたよな、と思い出したことで、頭の中がと映画に行きたいという気持ち一色になったせいだ。
は怪訝そうに俺を見上げて小首を傾げている。
「休み…?さあ…特になかったと思うが、どうして?」
「いや、休みじゃなくても少しでも時間あるなら…映画でも一緒に行かねえかなーと」
「映画…?」
「だめ?」
きっとまた秒で「断る」とか言われんだろうなーとダメ元で尋ねてみると、先輩はケータイのスケジュール機能を開きながら「明後日は一件だけで終わるから、そのあとなら行ける」と言い出した。思わず「え」と驚いたのは、まさかOKしてくれるとは思わなかったからだ。
つか、「付き合って」は秒殺するくせに映画はいいのかよ。その基準は何なんだろうと気になってしまう。
「いいのかよ」
「映画は私も好きだから」
「え、因みにどんな映画がいい?俺すぐにチケット買うから」
ケータイを出して尋ねると、はうーん、と言いながら同じくケータイで今ロードショーをしてる映画を検索し始めた。
そう言えば彼女が映画好きとは聞いてたけど、どんなジャンルが好きなんだ?その辺も知らないと、今後も映画に誘えないから、ついでに聞いとくか。
そこに気づいて「先輩はどんなジャンルが好き?一番好きな映画でもいいけど」と訊いてみた。はふと顔を上げて俺を見上げると「…テキサスチェンソーだな」と真顔で言った。俺の笑顔がビシっと固まる。それ、バリバリのスプラッターじゃね?と口元が引きつっていく。いや、別に俺もその手の映画は嫌いじゃないけども!
「え、先輩、ああいうの好きなの」
「まあ、足がスパーンと切られたり、首がポーンと飛んだりするのは面白いな」
「……(面白い?!)」
「ああ、あとシリーズ制覇したのは"クライモリ"シリーズかな。あれもなかなかに興味深かった」
「え、いや、あれ…確か人を食う頭のおかしな奴らに次々と若者が襲われて喰われていくっていうやつでは…」
「そうそう。友達が解体されてるのを隠れながら目撃する場面のスリル感がたまらない。あ、あとは食人鬼の方が機械で細切れにされるとこなんかは圧巻で――」
「ん?」
「…ん?」
が珍しく嬉々とした様子で話すから、つい聞き入ってしまったけど、内容が内容だけについ小首を傾げてしまった。彼女も俺の反応を見て小首を傾げたまま、しばし沈黙が流れる。
いや、その顏、可愛すぎだろ。つい、きゅん…としちゃったじゃん。
――って違う!そうじゃなくて。
別にが「恋愛映画が好きなの♡」と、可愛く言うとは俺だって思ってなかった。だってあのだし。でも、だけど!そんなスプラッター映画を一緒に観たって絶対に甘い空気にならなくない?という思いが駆け巡る。せめてサスペンス映画だとか、アドベンチャーもんだとか、この際アクション映画やカンフー映画だっていい。
でもデートでスプラッターはだめ!足がスパーンも、首がポーンも絶対だめだ。
「えっと…それ以外の映画は?」
脳内で怒涛のツッコミラッシュを終えると、俺はどうにか言葉を絞り出す。彼女は不思議そうな顔で俺をジっと見つめてくるから、心臓がヤバいことになるし、可愛い…で頭が埋まっていく。
「それ以外?」
「そう。スプラッター以外ってこと」
「……」
「え、ないのかよ?」
と本気で驚くと、彼女はふと口元に僅かながら笑みを浮かべた。
「そんなはずないだろ。あるよ、もちろん」
「………」
どうやら俺をからかったつもりらしい。前の俺なら「ハァ?」くらいは言ってたかもしれない。でも今の俺の脳内は、あのが意外なことをしてくるから、すげえ可愛いんだけど!だった。何だ、この複雑感情。
あまり感情を見せてくれない彼女が、俺をからかうことに意識を向けてくれたことすら嬉しいなんて、どうかしてる。
「アドベンチャー物が好きでよく観るかな」
「え?あ…アドベンチャー?」
内心じわじわと感動してたところで、は好きな映画のジャンルを応えてくれた。アドベンチャーとは、これまた意外すぎる。確か今、上映中の映画にそれ系の作品があった気がして、ケータイですぐに調べてみた。
「あ…あった。じゃあ、これは?」
「ナショナルトレジャーか。これは観たかった映画に入ってるな。ニコラス・ケイジも好きだし」
「じゃあ、これ観に行く?」
「…私はいいけど…五条くん、他に誘う相手はいないのか?」
「先輩と映画に行きたいから誘ってんでしょーが。じゃあ決まりでいい?」
「……いいよ」
「やり。じゃあ明後日の夜は俺と映画ね。約束」
「……」
俺が張りきって右手の小指を差し出すと、はこれまた怪訝そうな顔をした。
「小指、だして」
「…こうか?」
「そ。指切り、と。約束破ったら針千本だから」
の小指と自分のを絡めてそう言えば、彼女はジっとその指を見つめていた。寂しそうな、それでいて嬉しそうな。何でそんな顔をするんだろうと不思議だったけど、でも不意に柔らかい笑みを浮かべるから、予想外すぎてドキっとさせられる。こんな風に笑った顔は初めて見た。
「指きりか…懐かしいな」
「…懐かしい?」
「ああ。子供の頃、母として以来だ」
彼女はそう言いながら、ほんの少しだけ泣きそうな顔をした。彼女の母親はもう亡くなってるって話だったけど、彼女のよき理解者だったのは前に話を聞いた時に感じてた。今でも変わらず、が母親を大事に思ってるんだということも。
どう応えていいのか分からずにいると、は絡めていた指をそっと外して「じゃあ…明後日」と言いながら歩き出す。だけど俺は何となく追いかけることが出来ずに、彼女の後ろ姿を黙って見送っていた。すると彼女は少し行ったところで足を止めて振り返ると、俺を見て確かに言った。
「…楽しみにしてる」
その一言は、俺の胸に大きな孔をあけるくらいの破壊力があった。
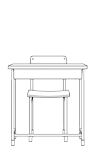
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
