14-誘惑する手
ミンミン、ジリジリ。夏も終わりに近い季節だというのに、相変わらず蝉がうるさい。不思議なもので、蝉の声を聞いているだけで暑さが増し増しになっていく気がする。
ひと昔前ならとっくに鈴虫が鳴いてるだろうに。
じっとりと肌にまとわりつく蒸し暑さに辟易しながら額の汗を拭う。
都心部にある大きな公園はこの熱波のせいで人もまばらだった。
一応、帳を下ろしたものの、これなら必要なかったかもなと思うくらい祓徐があっさり終わってしまったのは、絶好調の相棒がやたらと張りきったせいだ。
「傑ー。終わったー」
ぴょんぴょんと飛び跳ねるかのように軽い足取りで私の元へ走って来た悟は、汗の一つもかいていない。焼けつくような日差しの下で、何とも涼やかな顔をしているのは羨ましい限りだ。無限は太陽光の熱ですら近寄らせないんだろうか。
「やれやれ……」
祓徐で使用した巨大な呪霊を日よけにしていたが、もう移動しなくてはならないようだ。溜息交じりでそれを自身の中へ戻していくと、途端に高温の熱が頭上から降り注いだ。首筋から汗がつるりと滑り落ちて、シャツの衿元を濡らしていく感覚すら気持ち悪い。
「何だよ、傑ー。もうバテたのかよ」
「……この暑さでバテないのは悟くらいだろ」
肩に腕を回され、それをやんわりと外す。今は人の体温すら受け付けたくない。悟は腕を外されたことが不満だったのか僅かながら目を細めたものの、すぐに嫌味たらしい笑みを口元へ貼り付けた。
「傑って夏弱い系?」
「最近の夏はね。子供の頃は普通に好きだったさ」
「まあ、わかるけどー。俺も暑いの苦手だし」
「そんな風には見えないけどな」
シャツの胸元を摘まんでパタパタと仰ぐ悟の笑顔は、それでも涼やかだ。この午後の日差しの強さに負けないくらい、気分が高揚してるのかもしれない。
「んじゃあバテバテの傑のために涼しいとこへ避難すっか」
言いながら前を歩いて行く悟のうしろを歩きながら「約束の時間は決めてないんだっけ」と声をかけた。
浮かれた様子からも分かるように、悟は今日、先輩と念願の映画デートをする。決まった日から散々聞かされたから、こっちまで時間が気になってしまう。
悟は胸ポケットからケータイを取り出すと、「まだ連絡ないわ」と苦笑交じりで振り向いた。
「任務終わったら連絡くれることになってんの」
「そうか。なら連絡が来るまで付き合ってあげるよ」
澄ました顔で言ってやれば、悟はもともとそのつもりだったらしい。アイスコーヒーとケーキを奢ると言い出した。
ケーキって、それは自分が食べたいだけだろう。
ちゃっかり自分の好きなスイーツ店へ私を案内した悟は、メニューも見ずにサッサと注文している。店内は案の定、女性だらけ。平日の午後だというのに、六本木の小洒落たカフェの客は八割が女性で、男性陣は私と悟。あとはカップルくらいのものだった。男同士というのは私と悟だけだから視線を独り占めしている気がする。
「見事に浮いてるな」
デカい男二人が涼をとりに入るような店じゃないらしい。女性陣からの視線が地味に痛い。
「そりゃーいい男が二人も来たんだから当たり前だろ」
「……真顔で恥ずかしいことを言わないでくれ」
キリリとした顔を作る悟に思わず吹き出す。彼のこういうところは素直に羨ましい。
「そう言えば何を見るんだ?映画」
早速運ばれてきたアイスコーヒーで喉を潤しつつ尋ねると、悟は今公開中のアドベンチャー映画のタイトルを口にした。
何でも最初に聞いた先輩の映画の趣味が相当ヤバかったようで、何とか他の好きなジャンルを聞きだしたらしい。
「スプラッターって先輩らしいな」
「いや、傑笑いすぎ」
フォークに刺したケーキを上手に口へと運びながら、悟は何とも言えない顔で笑った。
デート目的で映画へ誘ったらまさかのスプラッター映画を上げられ、困った顔をする悟の顔を想像すると、どうにもおかしくなったのだ。
「まあ、がベタ甘の恋愛映画を好むとは思ってなかったけど。でもだからって生首スパーンはさすがにデート向きじゃねえし」
「ははは、確かに。で、上映は何時のにしたんだ?」
「の任務は一件だっけっつーから、夕方の時間帯を予約しておいた」
話ながらも悟の目はずっとケータイに向いてる。先輩からの連絡を今か今かと待ってる姿は、飼い主の帰りを待つ犬のようだ。案外かわいいところもあるじゃないか、とこれまた笑いがこみ上げてきた。
「あーちょっとトイレ」
悟はそう言って席を立つと、きっちりケータイを手にトイレの方へ歩いて行く。彼女からいつ連絡が来てもいいようにケータイを肌身離さず持っていくあたり、すっかり恋する乙女思考になってるようだ。
「昔の悟じゃ考えられないな」
モテる故に、好みから外れすぎていなければ来るもの拒まずの姿勢だった悟でも、女の子からの連絡は殆どがスルーだった気がする。要は自分がそういう気分じゃない時に連絡されても面倒だったんだろう。
なのに先輩が相手だと、悟は全く別の思考になるようだ。というか他の女の子なんか今は目に入らないんだろう。
現にトイレから出てきた悟に可愛らしい女の子二人組が声をかけてるけど――逆ナンというやつだな――さっくり断っている。前の悟なら適当なノリでOKしててもおかしくないが、やはり先輩のことで頭がいっぱいらしい。
五条悟という親友の変化にまた少しの驚きを覚えていると、私も女の子から声をかけられた。
「あのう……もし暇なら一緒に映画でもどうですか?」
後ろの席にいた女子大生風の女の子二人。私は当たり障りない笑みを浮かべて「ごめんね」と言っておいた。
「これから彼女とデートなんだ」
なんて……私は違うけど、と心の中で舌を出す。
もし悟が絶賛片思い中でなければ、誘いに乗ってもいいかなと思うくらいには綺麗な子達だった。でも今は悟が嫌がるだろうし、一人で行ってもつまらない。そんな気がした。
「ハァ。親友が恋愛中だと暇になるんだな……」
悟が戻って来るのを眺めながら、ふと独り言ちる。高専に入ってから何となく遠ざかっていた恋愛を、私ももう一度してみたい気分にさせられるくらい、最近の悟は輝いて見えた。
|||
『終わった。今から六本木に向かう』
待ちに待ったからのメールが届いたのは、傑と涼みに入ったカフェで二個目のケーキを頼んだ時だった。
最初はやっと来たっていう喜びに満ちていたけど、待ち合わせの時間が近づいてくるにつれ、少しずつ緊張が増してきて。駅で傑を見送った時には地味に手汗がヤバかった。
「落ち着いていつも通りにな」
なんて傑に苦笑されるくらい、顔色が悪かったに違いない。
これまで女の子とデートしてた時、どんな感じだったっけ……と過去の記憶を遡ってみたけど、そんなのは全くの無意味だと気づく。遊びの子とするデートなんて、緊張もしなければ適当だった記憶しかないからだ。
マジでクズだったな、と自嘲気味に思いながら、彼女と待ち合わせたヒルズ前へ歩いて行く。
夕方の時間ともなれば、会社帰りのサラリーマンやOLが目に付く。この辺りで働いてるならエリートと呼ばれるような連中だ。俺には全く縁のない世界だし、どいつもこいつも弱そうだなという印象しかない。当たり前だけど。
時々低級呪霊にくっつかれてる奴らもいて、それらを軽く祓いながらヒルズ前に到着した時、ちょうど見覚えのある車が歩道に横付けされた。運転席には付きの補助監督、如月さんがいる。
声をかけようと思った時、後部座席のドアが開いて、案の定先輩が下りてきた。
「五条くん、もう来てたのか」
なんて言いつつ、さすがに普段から持ち歩いてるキャリーバッグなどは如月さんへ預けたようで彼女は手ぶらだった。
「俺もちょうど来たとこ」
「そうか。じゃあ行こう」
映画の時間は伝えてあるせいか、は慣れた足取りでヒルズへ歩いて行く。まあ、過剰な反応は期待してなかったけど、顏を合わせた時の余韻など皆無で、相変わらず事務的だ。そういう態度をされると少しだけ困らせてやりたくなるんだから、俺もたいがいだなと思う。
「」
「ん?」
「手、繋いで」
「手?」
「そ。デートだろ、今日は」
彼女の隣に並びながら右手を出すと、は眼鏡の奥からジっと俺を見上げてきた。今日も可愛い……と自然に思うのは、今やお約束でもある。
は何度か瞬きをしたあと「分かった」と言って俺の差し出した手を握る。その感触だけで顔の熱が上がって、心臓がおかしな動きをするんだから、小学生かよって自分で自分に突っ込みたくなる。
今時、手を繋いだだけでドキドキするとか、俺ってそんなに純情だったっけ?いや、違う。
なのに嬉しいって思いが溢れてテンションが爆上げされてるんだから笑ってしまう。
「……って今日はデートなのか?」
「いまさら?!」
二人で映画館まで来た時、あんまりな質問をされて、つい突っ込む。いつもながらすっ呆けた女だなと苦笑しか出ない。きっと手を繋いだ瞬間からここへ来るまでの間、はあれこれ考えていたに違いない。それはそれでの脳内に俺がいたわけだから嬉しいけど、デートって自覚してもらった方がもっと嬉しい。
「フツー気づくでしょ。男が女を映画に誘ったんだから」
「そういうものか?誘われたことがないから分からないな」
「え、マジ?、映画デートしたことねえの?」
「ないな」
もしや、これって俺がの初デートの相手ってことか?と一瞬、浮かれそうになった時、彼女が「ホテルに誘って来る男ならいたけど」という最悪な返しをしてきた。
「……は?それで?」
「もちろん断ったよ」
「……(ホッ)」
――つーか。誰だ、ソイツは。ここへ連れて来い!俺がぎちょんぎちょんにしてやる!
……なんて嫉妬の炎が一瞬にして燃え上がる。多分その不届き者はにセクハラしてた例の先輩だろう。
"憑きもの筋"の家の事情を知って、なら簡単に抱けると思ったに違いない。上に報告しておいて良かったと心から思った。
ただはこんな感じだから、そういうことに関しては少し心配になる。婚約者とのやり取りから察するに、彼女はあまり性に対して深く考えていない。家でそういう扱いをされてきた、或いは母親の姿を見てきたせいか、男のそうした欲求を特別なものと感じていない気がする。
いや、まあ俺もを好きになるまで、似たようなもんだったけど。
「いい席だな。見やすそうだ」
予約した席へ座ったは、どこかワクワクしたような顔で辺りを見渡している。彼女のこういう姿は新鮮で、映画デートをしたことがないというのも本当らしい。彼女の初めての時間を共有できてることが嬉しいなんて、今までの俺ならあり得ない感情が湧いてきた。
出来ることならの色んな顔を見たい。もっと笑顔を見せて欲しいし、楽しませてあげたい。
ガチでヤバいなと苦笑が洩れたのは、とことん俺らしくない思いが次から次に溢れてくるせいだ。
は上映中、飲み食いはしないようで「何か買ってこようか」と言っても「いや、いい。映画に集中したい」と首を振った。なら、俺がすることは一つだけだ。
「それはいいけど……手は繋いでおいて」
隣に並んで座りつつ、手だけはしっかりと握り締める。「デートはこういう感じなのか」とが妙に感心したように言うのが可愛い。男女の恋愛に疎いなら俺が教えてやりたいとさえ思う。まあ、俺だって最近まで知らなかったけど。
彼女の小さな手を握る力を僅かに弱めて、細い指へ自分のを通していく。いわゆる恋人繋ぎだ。
彼女の性格上、嫌なら振り払うだろうし、嫌じゃないなら受け容れてくれるはず。そう思いながら反応を伺うと、は不思議そうに繋がれた手を見つめていた。
「こうするの嫌?」
「……いや、ではないな。むしろ心地がいい」
「え、それってどういう――」
心地がいい、というのはどういう意味だろうと身を乗り出す。気持ちがいいより、心地がいいの方が上の気がする、何となく。
彼女は少し小首を傾げつつ、でもふと俺を見上げると「五条くんに触れられるのは嫌じゃないという意味だ」と言ってくれた。触れられるのが嫌じゃないというのは、恋愛において絶対条件のうちの一つだろうと思う。俺の心臓が分かりやすいくらいに反応してしまった。
でも次の瞬間、が俺の手をきゅっと握り返して――。
「良かったら――映画のあと、ホテルに行ってみないか?」
「……は?」
が真顔で俺を誘ってきた。
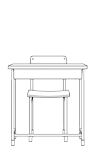
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
