15-子供の劣情
映画の内容なんて全く入ってこなかった。
――ホテルに行ってみないか。
彼女のその一言は核弾頭並みに俺の脳髄をぶち抜いて、秒にも満たない速度で思考を麻痺させた。
ホテル?ホテルって……あのホテル?
いやいやいや。まさかそれはあり得ないだろ。きっとシティホテルとか、ビジネスホテルとか、そういった類の――。
って、待て待て待て、五条悟。彼女がそんなとこに俺を誘うことじたいおかしいだろ!
なんて……ゴチャゴチャしたツッコミばかりが浮かぶ。ハッキリ言って映画が終わるまで混乱していて殆ど記憶がない。
気づけばセックスをするためだけの部屋でを抱きしめていた。俺の理性、どうなってんだ?
二人だけの密やかな空間を確保した途端、煩悩に支配されて彼女を抱きしめてしまった。
これは夢か?とも思ったけど、腕から伝わってくるの体温が現実だと突きつけてくるから、流れのままキスをしたのは早急すぎたかもしれない。好きな子とこんなことしたら当然のように体が反応するし、つい本能で硬くなった部分を彼女へ押し付けてしまった。ダメだ。動物並みに発情してるかも。
なのに小粒ほどの理性は残っていたらしい。彼女の唇を何度も啄みながら、この先に進んでいいのか迷いが生じる。なのにそんな迷いとは裏腹に、彼女の背中へ回していた手は勝手に制服の上着の中へ。シャツ越しでも分かるホックの部分が指先に触れただけで、鼓動が馬車馬のように動き出す。
本音を言えば、このまま服を脱がして彼女の全てをこの目に焼き付けたい、と思う。滑らかな肌に口付けて、押し倒して、のもっと深いところまで暴きたい。
こうして触れてしまえば、男の頭の中なんてそんな劣情であっという間に埋め尽くされてしまう。
でもシャツ越しにホックを外したところで、が僅かに俺から離れた。今の今まで重なっていた唇から温もりが消える。
「……シャワー浴びさせて」
彼女は俺を見上げながら、かすかに口元を緩めた。しっとりと濡れた唇は、まだ俺を誘ってるかのように艶やかだ。
それを見ていたら腰の辺りが疼いてたまらない気持ちになった。
「……ああ、うん」
いったん気持ちを落ち着かせたくて彼女がバスルームへ歩いて行くのを見送った。それに俺だって一日の汗を纏っているような体で好きな女を抱くわけにはいかない。今更だけど僅かに残る理性が俺を少しだけ冷静にしてくれた。
「ああ、五条くんも一緒に入るか?」
バスルームの扉を開けたがふと振り返って訊いてきた。思わず首を振ったのは、やっぱり俺の中に大きな疑問があったからだ。
「いや……俺は後でいい」
「そうか。じゃあお先に」
はそれだけ言うと躊躇うことなくバスルームへと消えた。一人になった途端、ほっと無意識的な息が洩れる。そこでらしくないほど自分が緊張してたことに気づいた。ついでに茹った頭と体がすうっと冷えていく。
こういうのが惚れた弱みとでもいうんだろうか。おかしいと思いながらもからの誘いをハッキリ拒否れないまま、促されるまま、小洒落たラブホまで来てしまった。
「ハァ……俺のアホ」
グシャグシャと髪を掻きむしり、冷蔵庫から目についたコーラの缶を取り出す。地味に喉がカラカラだった。だせぇの極致だ。惚れた女から誘われるままに抱こうとするなんて。
そもそもは俺からの告白を断ったはずだ。なのに何でホテルに誘ってきたのかサッパリ分からない。
部屋に入った途端、キスをした俺を拒否しなかったのはもそういうつもりでホテルへ誘ったんだと思うけど、その真意が謎だった。
付き合えないくせに体は許すのか――?
やっぱりその辺のことを彼女の口から聞かなければ、と思った。なし崩しに関係を持つなんて嫌だとも。
前の俺なら据え膳くわぬはっていう男の浅はかな煩悩のまま手を出したかもしれないが、少なくとも今の俺はそんな軽い気持ちで彼女を抱きたくないと思ってる。マジでらしくねえけど。
「どういうつもりだよ……」
バスルームからはシャワーの音だけが漏れ聞こえていた。
|||
「ごめん……誘われたからって俺も急ぎ過ぎた」
バスルームから出てきた途端、五条くんの口からそんな台詞が飛び出した。私がシャワーを浴びている間に頭を冷やしてしまったらしい。どうやら彼は普段見せる姿とは違う一面も持っていたようだ。
「俺、やっぱり――」
「まだ勃ってるのに?」
「……な、女がそういうこと言うなよ!」
こんな一言で真っ赤になるような性格には思えないのに、五条くんは至極真面目な顔で私を叱咤する。思春期の男子らしく体は反応しているくせに、バスローブ姿の私を見ないよう視線を反らす姿は、やっぱり私だから抱きたくない、ということなのかもしれない。
あんなにも情熱的に、何も感じないはずの私に火をつけるようなキスをしておいて。
「そうか、分かった」
「おい――」
「悪かったな。こんな場所に連れ込んで」
「いや、それ男の台詞だろ」
事実を口にしただけなのに、五条くんは小さな事柄にこだわっているのが少しだけ面白かった。だけど、それ以上に残念な想いも滲む。
五条くんなら私の中の怪物を鎮めて、心の空洞を埋めてくれる気がしたのに。
彼はバスローブを脱ぎ捨て、制服に着替え始めた私を見て慌てたように背を向けた。
「いきなり脱ぐなってっ」
「手を出さないなら別に私が裸になろうと気にしないんじゃないのか」
「いや、そういう問題じゃねえだろ。そもそも何でこんなことすんだよ」
「何で?」
着替える手を止めて五条くんの背中に視線を向ける。彼の後ろ姿からは戸惑いの匂いが漂ってきた。
「理由も分からないまま抱けるわけねえじゃん。まして付き合えないって言ったのはそっちだろ」
「理由、か。私が"憑きモノ筋"だから抱く気にならないとかじゃ――」
そう言いかけた瞬間、五条くんが徐に振り向くのが分かった。私の腕を掴み、近くのソファへ押し倒す一連の動作は、私でも抗うことが出来ないほどに速かった。気づけば私を見下ろす五条くんが視界に映っている。その顏は怒りと戸惑い、そしてどこか悲しげな表情を浮かべていた。
「……何をそんなに怒ってる」
「バカにすんな」
「してない」
「してんだろ!俺はに何が憑いてたってかまわない。抱けないのは……が俺のこと好きでもないくせに抱かれようとするからだ」
真剣な眼差しを見る限り、嘘を言っているようには見えない。透き通るほどの青さが私の裸眼を射抜くと、中の獣がざわつくのを感じた。
つまり、五条くんが私のことを好きだという気持ちは本物だということらしい。ただ、彼が勘違いをしているとするなら――。
「好きじゃないと言った覚えはないけどな」
「……え」
五条くんの六眼から見る見るうちに怒りの熱が消えていく。気づけばぱ何とも素朴でぱちくりとした目を向けられていた。
「今……なんて?」
「好きじゃないと言った覚えはないと言った」
「……」
もう一度同じ言葉を繰り返すと、しばし押し倒された状態で見つめ合う。その間も秒ごとに彼は表情を変えた。何度も瞬きをしたり、眉間に皺が出来るほど眉根を寄せたり、視線を明後日の方へ向けたりと忙しない。
そのうち色白な彼の頬が薄っすらと赤みを帯びてきた。
「え、それって……俺を好きってこと?」
やっと絞り出された言葉は、まるで幼い少年のような拙さと僅かな期待の響きを含んでいた。私は五条くんのこういう素直な内面が好きだ。私に敵意を剥き出しにしてた頃もそうだった。怯えを隠し、無理な笑顔を向けられるよりもよっぽど嬉しかった。
そういう意味で言えば私は彼のことを――。
「好きだよ」
「……マジで?」
「いくら私でも好意のない相手をホテルには誘わない。そもそも経験がないんだから」
「あ……え?ってことは……処女を俺にくれようとするくらい好きってことかよ」
「……そう、なるのか」
「え、違うのかよ」
小首を傾げた私を見て、五条くんは困惑気味に見つめてくる。本音を言えば、この好きという感情がどういった種類のものかは私にも分からない。だけど以前、五条くんに触れられた際、温もりみたいなものを心に感じた衝撃が今も残っている。あの時の感情を、私はもう一度確かめたいのかもしれない。
「好きの意味がそんなに重要か?」
五条くんの頬へ手を伸ばすと、彼の肩が僅かに跳ねた。
「そりゃ……」
「正直、私は五条くんのいう好きの形は分からない。でも触れて欲しいと思うし、触れたいと思う。それじゃダメなのかな」
「な……んだよ、それ」
「付き合ってないと抱き合ったらダメなのかと聞いてる」
「……んなの……ただの遊びじゃねえか」
「遊び……君は何でもそういう形に当てはめたがるんだな」
呆れたように呟けば、五条くんはむっとした様子で目を細めて、彼の頬へ触れた私の手を振り払った。何か地雷を踏んでしまったらしい。
「じゃあ聞くけど。俺に抱かれていいとか思うくせに付き合えない理由って何だよ」
「……五条家の次期当主を私の家の事情に巻き込みたくない」
「即答かよ!ってか家の事情って何。今更だっての」
「今更でも何でも、私と五条くんが個人的な繋がりを持てば後々面倒なことになる」
呪詛を体内に宿している私は、そもそも五条家を筆頭に呪術界から敵とみなされる一族だった。どれほど心を入れ替え善行をしようとも、憑神は消えてくれない。私を暗闇へ引きずり込もうと虎視眈々と狙っている。
そんな女が、この先の呪術界を率いていく彼と恋愛関係になるなど、誰も許すはずがない。
「関係ねえよ。そんなもん……俺は……がどんな化け物を飼ってようと好きなもんは好きなんだよ」
「……まるで子供だな、君は」
「あ?一つしか違わねえくせに年上ぶんな――って、おい、どこに行くんだよっ」
五条くんを押しのけ、ソファから立ち上げると、伸びてきた手が私の腕を掴む。それをやんわりと外した。
「抱く気がないなら帰るよ」
「は?」
「五条くんなら私の女の部分を引き出してくれるかと思って誘ったけど、自分勝手だった。すまない」
中途半端だった着替えを終わらせようとシャツのボタンを留めていく。でも不意に肩を掴まれ、反転させられた。見上げると五条くんのスネたような顔がある。
「付き合う気もないを抱くのは遊びみたいで嫌だよ。でもまだ一緒にはいたい……んだけど」
「どうして?ここはセックスする場所だろ」
「いや、別にしなくたっていいんだよ。好きな相手と過ごす時間を買う場所でもあるんだから」
「……そう、なのか?」
五条くんの真っ当な言葉に驚かされる。ちょっとだけ目から鱗の気分だった。きっと私が人よりズレてるのはこういうところなんだろうなと思う。
「……何でも形に当てはめてたのは私の方だったのかもしれないな」
「あ?」
「何でもない」
怪訝そうな顔をする彼に首を振って見せながら、ベッドに設置されている時計を確認する。ここへは休憩で入ったはずだから、あと一時間ほど残っていた。
「分かった。せっかく二時間で申し込んだんだから一時間はいないと損だしな」
「いや、そういう意味じゃねえし、何か違う!」
「五条くん、何か飲むか?今時のラブホは冷蔵庫なんて設置されてて便利だな」
「いや、聞けよ!つーか、今時じゃなくてもラブホだってホテルなんだし冷蔵庫くらいあんだろ。ほんと何も知らねえのな」
冷蔵庫を漁っていると、五条くんは一人熱くなって反論してくる。こういうところは可愛いと思うのだから、前よりは確実に感情が豊かになっている気がした。いや、昔の自分に少しずつ戻っているような感覚の方が近いかもしれない。
五条くんといると、私の空っぽになった心が動かされる。
「コーラ飲む?」
「いや、それよりボタンくらい留めろよ。目の毒すぎ」
歩いてきた五条くんに缶コーラを差し出すと、彼は受け取る前に私の胸元へ手を伸ばした。途中で止まっていたボタンを一つ一つ丁寧に留めてくれている。視線だけ上げてみれば、色白の頬はやっぱり赤くなっていた。
彼のその表情を見た瞬間、鼓動がどくんと音を立てる。そのあとのことは本能としか言いようがない。
五条くんの熱を帯びた頬へ手を伸ばして引き寄せると、僅かに背伸びをして彼の唇を塞いだ。こんな感情が芽生えたのも、自ら異性に口付けたのも、何もかもが初めてだった。
「ん、」
唇を合わせることがこんなにも心地いいなんて知らなかった。やっぱり五条くんには私の心を動かす何かがある。彼の唇は柔らかくて暖かくて、触れあうのが気持ち良かった。
五条くんの体が強張るのを感じながらも深く唇を交わせて軽く吸えば、行き場をなくした彼の手が動いて私の背中へ回された気配がする。
だけど次の瞬間――両肩を掴まれて引きはがされていた。
「ぷはってか何してんだよ……っ」
「……キス」
「普通に応えんな!ってか死ぬ思いで我慢してんだから誘惑しないで」
今では耳まで赤くした五条くんが、ぷいっとそっぽを向く。我慢するほど反応してるなら我慢しなくていいのに。
そう言ったら、今度は目を吊り上がらせた。ここまでして手を出してこない男は珍しい。
「俺だってにキスして、それ以上のこともしたい。でも今ここで手を出すのは何か違う気がすんだよ……」
「ここはしっかり勃ってるが」
「ばっ触んなっ」
一気に距離をとって股間を隠す五条くんは、やっぱりどこか子供のようで笑ってしまった。
でも理性を必死に保とうとする姿は、きっと大人の対応というより想いの質量が私とは違うと思ってるからだろう。
そういう純粋さを見せられたら、ますます確かめたくなった。
もし私の中の何かを変えられるのだとしたら、その相手はきっと五条くんなんだろうと思う。
母以外で私に"本気"をぶつけてくれたのは彼が初めてだったから。それに――。
「我慢することないのに」
「ちょ、脱ごうとするなって!もっとはじらいってものを持って?」
からかい甲斐があって面白いなんて――こんな感情が生まれたのも初めてだった。
「俺に抱かれたいなら付き合って」
無理だと応えながら一瞬だけ、それもいいかと思ってしまった。例えば何のしがらみもないただの男と女だったなら、青臭い春を一緒に過ごせた気もするのに。
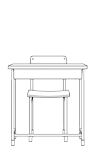
BACK
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
