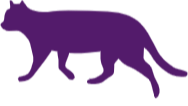
猫、現る-01
夏から秋へと季節の変わり目よろしく、朝から秋雨がシトシトと降り続く一日だった。この日、都内の大学の事務で働くは、職場の同僚たちと行きつけの店で飲み会を終え、帰宅する途中だった。同じ方角の同僚はいない為、彼女はいつも大通りからタクシーを拾いひとりで帰る。今日も例外ではなく、同僚五人の乗ったタクシーを見送った後、次のタクシーが来るまでは大通りに立っていた。しかし今日はこの天候のせいか人通りも少なく、タクシーもなかなか来ない。降り続く雨のせいですっかりアルコールも冷めて来たは小さく溜息をついた。
(…どうしよう。ここで待ってても来なさそう)
考えてるうちに人通りはどんどん少なくなっていく。仕方ない、とばかりには気を取り直して歩きだした。明日は休みなので遅くなるのは構わないが、この雨では体が冷えてしまう。足早に薄暗い大通りを自宅マンション方面へと歩きながら、時々タクシーが来ないか確認しつつ帰ることにした。幸い皆ほど家が遠いわけじゃない。車で10分。徒歩だと30分かかるかどうかというところ。ただ時間も時間で女ひとりで歩くには少し心細いといった程度だった。
(こんな時、彼氏がいれば迎えに来てもらうんだけどな…)
独り身の寂しさはこういう時に感じてしまうものだ。その時、先月まで付き合っていた男の顔が浮かんだ。高身長でその辺の芸能人よりも整った顔立ち。艶のある声。そして誰よりに愛情を注いでくれた人だった。そんな恋人にから別れを告げたのは一か月前のまだ蒸し暑い夏の夜だった。
忙しい彼から突然デートに誘われ、喜んで出かけて行った。そこで遂に念願のプロポーズ。出会って一年、彼と付き合いだして約半年。ちょうども彼との結婚を意識しだした頃だった。なのにプロポーズと共に告げられたのは、彼の本当の正体――。
男はに一年間も嘘をつき続け、職業を偽っていたことが分かったのだ。プロポーズをされ、幸せを感じていた気持ちが一気に冷めていったのは仕方のないことだった。知り合ってから一年という長い時間、嘘をつかれていたショックと、その理解できない職業のせいで、は男に別れを切り出した。好きだったのに別れを言わなければならないほど、ショックは大きかった。彼は何度も考え直して欲しい、最初からやり直したいと頼んで来たものの、はまた嘘をつかれるんじゃないか、と不安になり、それを受け入れることは出来なかった。
「はあ…ダメだ…」
彼のことを思い出すだけで胸が痛い。世界一幸せなプロポーズをされた後に、あんな話をされた衝撃は未だの心に暗い影を落としていた。その時、車の音がしてハッと我に返る。タクシーか確認する為、は無意識に振り向いたが、やって来たのは黒いワゴン車でタクシーではない。ただ考え事をしながら歩いて来たせいか、気づけば自宅マンションまであと数分の距離だった。
(何だ…もうすぐじゃない)
ホっとしつつ、このまま歩いて帰ろうと自宅マンションを遠目に見ながら、ふと愛猫の存在を思い出した。帰宅を待っててくれる恋人は失ったが、愛猫の存在に救われていた。
「ヤバいなァ…猫に依存した女は行き遅れるって、ほんとその通りかも」
苦笑気味に独り言ちたその時だった。マンション前の通りに止まっていた一台のワゴン車から誰かが降りて来るのが見えた。さっき追い越して行った車だと気づく。こんな深夜に誰だろうと思ったものの、は気にせず通り過ぎてマンションへ入ろうと歩いて行く。しかし突如背後に人の気配を感じ、振り返った瞬間、何か布のようなものを口に当てられた。驚いた拍子に手が離れ、傘が落ちる。同時に体を拘束されて全身が総毛だった。
「…んーっ!」
恐怖を感じて大声を出そうとしたが口を塞がれ、体を拘束された状態ではあまり効果はない。雨音にかき消され、誰かに気づいてもらえるような声にはならなかった。不意に意識が遠くなっていく。
(…だ…れ…?)
外灯もない場所。暗くてハッキリと顔は見えない。崩れ落ちる体を抱きかかえるようにしている人物をぼやけた視界に映しながら、の意識はそこで途切れた。
なんの代わり映えもしない日常に、時として思いがけないことが起こる日もある。この日の五条悟も、まさにそういう日だった。
呪術高等専門学校に呪われた少年、乙骨憂太が入学してから半年が過ぎようとしていた夏の終わり。高専一年生の禪院真希は自分の担任である五条の異変に気づいていた。この一ヶ月半あまり、五条はらしくないほど元気がない。最初は特級扱いの乙骨を救うため、アレコレ上とモメていたことで疲れが出たのかと思っていたが、そもそも五条は疲れるという言葉を知らない男だ。たかが面倒な生徒を一人庇うのにそこまで疲弊するはずもない。なので体調が悪いということもないだろう。なら何故あの無駄な元気さと強さだけが取り柄の五条は元気がないのか。真希は悶々としつつ、遂にその疑問を同級生であるパンダと棘に話した。
「なあ…悟のヤツ、何かあったのか?ここんとこ、ずーっとあんな感じだけど」
「ん?ああ…」
「…しゃけ」
体術訓練をしていたパンダと棘、乙骨までが、ふと五条の方へ視線を向けて苦笑した。真希の言う"あんな感じ"とは、五条が石段に座り、ボーっと空を眺めながら、時折溜息をついていることだ。その様子に気づいていたパンダたちは訝しがる真希を見て、互いに顔を見合わせた。どうやら三人は五条に何があったのかを知っている素振りだ。当然真希もその空気に気づいた。
「何だよ…オマエら何か知ってんのか?」
「いや…まあ…なあ?憂太…」
「え、ぼ、僕に振られても…」
「……しゃけ」
「何だよ。知ってんなら教えろよ」
気まずそうにしている三人を見て、ますます気になりだした真希は呪具を持って詰め寄った。朝から体を動かしヘトヘトだったパンダと棘、乙骨は、これ以上真希の相手をする元気もなく。仕方ないと言わんばかりに、全員その場へしゃがみ込んだ。そしてパンダが真希の方へちょいちょいっと指を動かす。その態度にイラっとはしたものの、好奇心の方が勝ってしまった真希は素直にしゃがんでパンダの方へ顔を寄せた。
「実はさ…悟には半年くらい付き合ってる恋人がいたんだ」
「…こっ?」
「しっ!静かにしろよ…これは男同士ってことで悟から聞きだしたネタなんだから」
「わ、わりぃ…」
人の恋路を"ネタ"扱いもどうかと思いつつ、真希はどうにか驚きを沈め、もう一度「それで?」と話を促した。パンダはチラっと五条の方へ振り向いたものの、未だ同じように空を見上げたまま、四人の様子には気づいていない。この時点でいつもとだいぶ違うことが伺える。いつもの五条なら「何サボってんの!」くらいは言って来るはずだ。
「知り合ったのは一年くらい前らしいんだけど…半年後に正式につき合いだした。んで悟としてはかなり本気だったみたいなんだよな、その恋人のこと」
「…マジ?でも悟って恋愛とかそっち系は興味ないって言ってなかった?むしろバカにしてたろ。あんなハッキリしないものに悩んだりするなんてありえないって」
「あー…確かオレらが入学したての頃、補助監督の女の子が彼氏に振られて悩んでた時なー。確かに言ってた」
「その悟がいつの間に本気になるような恋人作ってたんだよ?」
真希の驚きは最もだった。しかし五条と恋人の出逢いまで話していたら夜が明けてしまう。パンダは「そこは長くなるから後で説明する」とし、話の続きを話し始めた。
「で…何と悟はその恋人と結婚したいと思ったらしい」
「けっ?!」
「「しー!!」」
「おかか…」
パンダと乙骨ばかりか、棘にまで咎められ、真希は今度こそ口を閉じた。しかし脳内では"あの悟が結婚…あの悟が結婚?!"という文字がぐるぐる回っている。
「ったく…今から話すことはデリケートな問題だからな…静かにしろよ」
「わ、分かってるけど…っ内容がいちいちホラーなんだよ、私にはっ」
「「「…だな」しゃけ…」」」
そこは全員が納得する。教え子にとって五条悟の恋愛事情など、まさにホラーとしか思えない。そもそも本人が言っていたのだ。"愛ほど歪んだ呪いはない"――と。
「で…どこまで話したっけ」
「…けっ…結婚のとこだよ」
「あーそうそう」
頬を引きつらせながら真希が応えると、パンダは手をポンと叩いて頷いた。このメンツで話していると話が脱線していくのはいつものことだ。パンダはコホンと咳払いをして、再び真希の方へ顔を寄せた。真希の視界からはみ出るくらいには顔がデカい。
「何でも初めて本気になって結婚を意識した女だってことで、悟も気合い入れてめちゃくちゃ高い指輪とプロポーズをする為の舞台に高級ホテルを用意したらしい」
「げ…悟が…?アイツ、恋愛映画みすぎじゃねえのか」
「まあオレもそう思ったけど、そういうの人間の女は喜ぶんだろ?」
「知らねーよ。で?」
真希に女心など分かるはずもないか、と内心思ったパンダだが、自分の身を案じ、そこは口に出すのをやめておく。ヘタなことを言えば自分の体から綿が零れ落ちるくらい穴ぼこにされそうだ。
「それでサプライズ的にプロポーズをして、その恋人も凄く喜んでたらしいんだ」
「は?じゃあ悟、OKしてもらえたってことかよ」
「まあ最初はな」
「最初は…?」
そこでパンダ、棘、乙骨が微妙な表情のまま顔を見合わせている。
「実は悟のヤツ…自分が呪術師だってこと隠してその恋人と付き合ってたらしいんだ」
「…はぁ?」
「でも結婚するなら本当のことを言わないとダメだろ?で…正直に全部話したら……」
「は…話した…ら?」
「…その恋人が大激怒であっさりフラれたらしい」
「…マジ……?」
「大マジ」
「しゃけ……」
棘も同情するように首を振って溜息をついている。乙骨に至っては「やっぱり嘘をついたのが良くないんだよ…」と言い出す始末。真希もそこは納得したものの、疑問は大いにあった。
「そもそも悟のヤツ、何で呪術師だってこと隠してたんだよ…。恋人になる前から長く付き合ってて一年後に実は僕、呪術師でしたーなんて言われたら、そりゃ誰だって怒るだろ」
「まあ…そうだよなあ…。でも実は悟も付き合うことになった時、その子のことが本気で好きになってたからちゃんと話そうとしたらしいんだけど…その子が極度の怖がりだと知ってたから言い出しにくくなったらしいぞ」
「怖がり…って…」
「彼女が心霊ものとか大の苦手なんだって」
「……なるほどね」
真希も納得したように頷く。呪霊と幽霊では全く違うものの、一般人からすればこの世のモノではないという意味でどっちも似たようなものだろう。
「で…あの落ち込みようってわけか」
「まだ忘れられないって言ってたし、失恋したのも初めてだったらしいからショックデカいんだろ」
「しゃけ…」
五条は未だに溜息をつきながらひとり黄昏ている。真希はそれを横目で見ながら「けっ」と吐き捨てた。
「そもそも職業隠して付き合うから悪ぃーんだろ?最初から騙す気だったってことじゃねーか」
「まあ…呪術師なんて裏稼業みたいなもんだし一般人に話せないことも多いから、それは何とも言えねえなぁ…」
「でもダメだよ、嘘は」
そこで乙骨が真剣な顔で呟いた。
「きっとその彼女は五条先生が呪術師だからってことより、嘘をつかれたことがショックだったんだと思う。きっとその人も傷ついてるよ」
「…憂太はフェミニストだな…」
「しゃけ」
会ったこともない五条の恋人の気持ちまで考えている乙骨を見て、パンダと棘が苦笑いを零す。
「ってことでしばらくの間は悟もポンコツだと思うから、オレ達でフォローするしか――」
「だーれがポンコツだって?」
「「「―――ッ!!」」」
突然、背後から冷んやりとした低音が聞こえて、四人は恐る恐る振り向いた。
「げっさ、悟っ」
そこには五条がおどろおどろしい殺気を纏って仁王立ちしていた。目隠しで分かりづらいが、宝石の如き青い瞳は怒りで吊り上がっているだろう。
「パンダァ~オマエ、男同士の約束を破ったな?」
「なっ何のこと――」
「とぼけんな!動物園に売り飛ばしてやろーかっ?」
「いでででっ」
可愛らしいモコモコの耳を力いっぱい引っ張られ、パンダの悲鳴が校庭に響き渡る。
その時――。
「ミャーウ」
これまた可愛らしい声がどこからともなく聞こえて、その場にいた五人は声のした方へ一斉に振り向いた。するとそこには少々ぽっちゃりとした三毛猫が座っている。
「え、猫…?」
「猫だ…」
「猫、だよ」
「しゃけ」
と生徒達が突然現れた猫に驚いている最中、五条だけは「ミャウ太郎…?」とおかしな名前を口にした。
「は?みゃうたろー?」
「先生、この猫のこと知ってるの?」
乙骨が尋ねたが、五条には聞こえていないらしい。驚愕したような顔で辺りをキョロキョロ見渡している。その姿は誰かを探しているように見えた。
「五条先生…?」
「悟、どーしたんだよ。この猫と知り合いかー?」
乙骨は訝しげに五条を見ていたが、真希はからかうように笑っている。しかし五条は少し慌てた様子でその猫を抱き上げた。
「え、抱けるくらい懐いてんの?」
「…やっぱり…コイツはの猫だ」
「は?って…」
と真希が首を傾げると、パンダがつかさず「さっき話した悟の元カノだよ」と教えてくれた。
「えぇ?な、何でその元カノの猫が高専にいんだよ?」
「い、いや、オレにだって分かんねーよっ」
真希に胸毛を掴まれ、ゆっさゆっさと揺さぶられたパンダは頭がクラクラしながらも猫を抱いたままの五条を見た。きっと彼女の愛猫の姿を見て、彼女もここにいるのかと思ったんだろう。未だに辺りを気にしている。
「っていうか似た猫ってだけじゃねーの?」
「しゃけ」
「だよなあ?」
真希、棘、パンダはそれぞれ思ったことを口にしながら笑っている。しかし五条だけは真剣な顔で三毛猫を見つめながら首を振った。
「いや…コイツはミャウ太郎だ…。この太々しい顔…でっぷりとした体…僕を睨んで来るこの目…」
「あはは!何だよ、ぜんっぜん懐かれてねーじゃん」
「まあ悟って動物に好かれなさそーだもんなー」
パンダと真希が猫と睨み合っている五条を見て大笑いしている。だが五条だけは真剣な顔で「おかしい」と呟いた。
「おかしい?」
「コイツが僕に大人しく抱かれてることが、そもそもあり得ない」
「めっちゃ嫌われてたんだな…可哀そうに」
「まあ大好きなご主人さまを奪うライバルだもんな、猫からしたら。仕方ねえよ」
「しゃけ」
「うるさいぞ、オマエら!特にパンダと真希。明日から任務の数、倍な?」
「「げっ」」
合間にサラリとパワハラをしてくる五条に、その場にいた全員が顔をしかめている。その間もミャウ太郎と呼ばれた猫は五条に向かって必死にミャウミャウと何かを訴えるように鳴いていた。
「ねえ、その猫…何か悟に伝えようとしてない?」
「オレもそう思った」
「僕も…」
「しゃけしゃけ」
生徒達が一斉に疑問を口にしたが、言われる前から五条は気づいていた。
「まさか…に何か…」
「え、でもだからって猫一匹で高専まで来れる?彼女の家ってどこだよ」
「…都内」
「じゃあ無理じゃん。やっぱ他猫の空似ってことじゃないの?」
真希は苦笑交じりで肩を竦めた。その時、五条の抱いていた猫が突然鳴きやみ、フッと意識を失ったようにグッタリとした。
「は?おい!ミャウ太郎!どーした?」
頭がクタっとしてる姿を見て、さすがの五条も焦っている。しかし揺さぶってもミャウ太郎が目を開けることはなく、まるで死んでいるように見えた。その時だった。五条の探知機能が微弱の呪力を感じ取り、ふと顔を上げた。
「え…」
五条の目の前、空中に浮遊していたのは、未だ忘れられない、元恋人のだった。