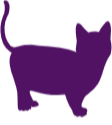
出逢い-04
一年前――。
この日は朝からどんよりとした梅雨空だった。ジメジメと湿った空気が肌にまとわりつくようなこんな日は何となく気分も滅入る。でも今夜は同僚たちと毎月恒例の飲み会があり、も渋々参加をしていた。大学との自宅のちょうど中間地点にある駅前のバルが定番の会場で、この日も適度に食べたり飲んだりして、もいい加減ほろ酔い気分になっていた。
「はあ、彼氏欲しいなぁー」
隣に座っていた同僚の山田がいつもの口癖をボヤきだした。これを言い出した時は結構酔っている証拠なので、は退席する時の目安にしている。時間もすでに10時をとうに過ぎていて、明日の為にもそろそろ帰りたくなってきた。
「じゃあ、わたしはこれで――」
そう言っていつものように先に帰ろうと席を立つ。しかしこの日の山田は少し悪酔いしたのか、の腕をグイっと引っ張り、再び席へと座らせた。若干目が座っている。
「まーたさんってば先に帰ろうとしてー」
「山田さん、飲みすぎ。明日は休みじゃないんですからねー」
「分~かってるけどー!どうせ待ってる男なんていないし帰りたくないのよねー」
頬を膨らませてボヤいている山田はと同じ24歳。ボブカットで少しボーイッシュなイメージの彼女は今年の初めに彼氏と別れたらしく、最近では飲むたび彼氏が欲しいとボヤくようになった。
「あ、もしかしてさん、彼氏が部屋で待ってるとか?」
「まさか。わたしだって彼氏なんかいないですよ。待ってるのはミャウ太郎だけです」
「あー猫飼ってるんだっけ。でもホントかなぁ?だってさん、そんなに可愛いのに彼氏いないっておかしくない?もしかして不倫とかしてるんじゃないでしょーね。ダメよ?不倫は」
勝手なことを言って勝手に説教をしている。そもそも不倫をしてたのは自分じゃないかと言いたくなるのをグっと堪えた。
「不倫もしてません!だいたい時間もないしどこにそんな出会いあるんですか」
「確かにー。大学にも出逢いないし、事務の仕事は無駄に量が多いから疲れるし、休みも家でゴロゴロして終わっちゃうしなー」
山田は溜息交じりで焼酎を煽っている。話が長引きそうだと溜息をつき、は椅子に座り直した。腕時計を確認し、あと10分経ったら席を立とうと心に決める。
が大学卒業を間近に控えていた頃、両親を事故で失い、天涯孤独になったことで安定した仕事を探していた時、たまたま自分の通っていた大学での募集を見つけて面接を受けた。運よく採用されその勢いのまま就職したものの。これが地味に細かな仕事が大い仕事だった。
大学内の学科事務室サポート業務、学生、教員のお問い合わせ対応、書類作成、ファイリング、伝票処理、郵便仕分け業務、その他庶務業務まで色んな仕事を任される。メールや郵便物チェック、仕分け等から始まり、教員、学生対応等をしながら書類作成をしてファイリング、伝票処理等、勤務時間びっしりと何かしら作業をして夕方5時に終わる。それから帰宅時に夕飯の買い物をして家に着く頃には午後6時はとうに過ぎていて、そこから食事を作ってお風呂に入って、さあノンビリしようという頃には午後10時は過ぎている。毎朝6時に起きているので0時までには寝ておきたいの一日の自由時間は二時間あるかないかだ。今日は飲み会があるので帰ったら速攻で寝るしかない。その分、休日はゴロゴロしたくなるので、ハッキリ言って異性との出会いなど皆無に等しい。きっと大半の社会人は同じようなものだろう。
「ウチの大学、若い男って学生しかいないもんねー。同僚はあんなんばっかだし」
と山田は他のテーブルにいる同僚の独身男たちを眺め、目を細めている。歳が近い男もいることにはいるが、皆が地味なわりにそれぞれキャラが濃い。あげく趣味を聞けば、地下アイドルの追っかけや、何かのアニメのフィギア集めといった、には理解しがたい答えが返って来る。こんな環境では恋が生まれるはずもなく、ただ仕事に追われる毎日を過ごしていた。
「あ、でも文学部の西島さんは素敵かな~」
「え?ああ…確かに彼は生徒からも人気があるみたいだよね」
文学部で助手をしている西島は若く、スラリとしたイケメンで、そこはも納得した。
「頭もいいし彼ならすぐ准教授になれそう。まあ、でも文学部だからな~地味よね、少し」
「別に仕事が派手じゃなくても本人が素敵ならいいんじゃないの?」
山田の言い分に苦笑しつつ突っ込むと、「そうだけど、あんなにカッコいいなら恋人いるだろうし」とボヤきながら酒を煽っている。
「あーこんなんじゃ行き遅れちゃう。転職しようかなぁ」
「…まあ、それも一つの選択肢だよね、ほんと」
相槌を打ちながら、はチラリと腕時計を見た。このまま山田の話に付き合っていれば、更に時間が遅くなってしまう。今日は遅くなると分かっていたのでミャウ太郎のご飯は大目にあげてきたのだが、そろそろ心配になってきた。
(帰ったらまずトイレも掃除してあげないと…)
頭の隅でそんなことを考えつつ、山田が隣の人に話しかけているのを見て、そっと席を立った。皆もいい加減酔っているし、こっそり帰っても分からないだろう。はそのまま出口に向かおうと歩き出した。その時、不意に手首を掴まれ、山田に見つかったのかとがギョっとして振り返る。しかし腕を掴んでいたのは山田ではなく、他の同僚の石崎だった。先ほど話に出ていた"地味な同僚"の一人だ。石崎はや山田の座っているテーブルの後ろの席に座っていたようで、さっきの会話を聞かれていたんじゃないかと思い、ヒヤリとした。しかし石崎は特に不機嫌そうでもなく、笑みさえ浮かべている。
「さん、帰るなら僕、送るよ」
石崎はそれほど酔ってもいない様子で、ジっとを見上げている。その視線に嫌なものを感じて、は引きつりながらも笑顔を見せた。
「…え、あ…あの…トイレなんで」
「そう?じゃあ帰る時は声かけて」
咄嗟に嘘をついたものの、石崎は気分を害した様子もなく、そんなことを言って来た。これまで彼とそれほど親しくした覚えもないは、そそくさとトイレの方へ歩いて行く。
――このままトイレに行ったふりをしてコッソリ帰ろう。明日聞かれたら具合が悪くなって、とでも言えばいい。
とりあえずトイレの方向へ歩いて、続く細い通路を曲がった。達が座っているテーブルは店内の奥にある。ここは出口に近いので少し待ってからそっと帰れば同僚たちも気づくことはない。そう思った時、トイレの前に具合の悪そうにしている男性が目に入った。ちょうど男子トイレと女子トイレの間に立っているその男は夜なのにサングラスをしていて、どこかグッタリとした様子で壁に凭れていた。
(酔っ払い…?人がいるならここに突っ立ってるのも変に思われるか…)
は仕方ないと形ばかりのフリをする為、女子トイレの方へ歩いて行く。そしてドアを開けようとした時、壁に凭れて立っていた男がずるずるとその場にしゃがみ込むのが見えた。
「え、ちょっと…大丈夫ですかっ?」
あまりにツラそうで思わず声をかけていた。男は顔を上げることもせず俯いたままだが、僅かながらの声に反応したようだ。軽く首を振った。
「いや…大丈夫…じゃない…」
男は気持ち悪くなったのか、俯いたまま「う…」と声を漏らした。ここで吐いてしまっては大変だとばかりに、はキョロキョロと辺りを見渡す。すると掃除用の洗面台のところにバケツが置いてあるのを見つけた。咄嗟にアレだと思い立ち、はバケツを取りに行くと男の前にそれを置く。そして背中をさすってあげた。
「気持ち悪いなら吐いちゃった方がいいですよ」
「い、いや、そこまでは…」
男はそこで初めて驚いたように顔を上げ、を見た。その瞬間、男と目が合う。夜なのにサングラスをかけている辺り怪しいのだが、そんなことよりも合間から見える澄んだ空色の瞳があまりに綺麗で、は思わず見惚れてしまった。
「が…外国の方、ですか?」
髪も色素の薄い白髪で、てっきり染めているのかと思っていたが、瞳の色を見ればそうとしか思えなかった。しかし男はの問いに「は?」と驚いたような顔をした。
「いや…僕は日本人だけど…」
「えっ?あ、ご、ごめんなさい…」
思い切り勘違いをして恥ずかしくなる。瞳の色はコンタクトなのかもしれない。それでも日本人離れした顔立ちと、高身長。モデルでもやってるんじゃなかろうかとは思った。
「えっと…大丈夫ですか?」
「あーまだ…グルグル頭が回ってる…」
男は小さく息を吐き出し、軽く頭を振っている。そして「あの…申し訳ついでに外まで肩貸してもらっても?」と訊いて来た。
「え、外って…」
「このままタクシーで帰りたいんだけどフラフラするし一人じゃ歩けそうにないんだ…。ツレがいるんだけど、こういうこと頼めないから…」
「…え、ツレってお友達…ですか?」
「いや…同僚」
この男も同僚と飲んでいたらしい。は何だモデルじゃないのかと内心苦笑した。そう言う仕事なら同僚とは言わないだろう。
「同僚の方なら送ってもらえないんですか?」
「…こういう姿は見せたくないんだよね。散々からかってくるだろうし…」
「はあ…。じゃあ…わたしで良ければ外までお送りします」
店の外に行くまでの短い距離を付き添うだけなら、とは快く承諾した。知らない男の介抱をするなんてことは初めてだが、放っておけないほど体調が悪そうなのだ。
「…いいの?悪いね」
ふぅ、と息を吐きつつ、男はふらふらと立ち上がった。思った通りものすごく身長が高い。肩は貸せなさそう、と思わず見上げたものの、相当具合が悪そうな様子を見て、は男の腕を支えるようにした。そこでふと思いつく。
「あ、あの…」
「…え?」
「実はわたしも同僚と飲んでたんですけど…送ると言われて困ってたんです。で…あなたに友達のふりを頼めないかなぁと…」
男は一瞬キョトンとした顔をしたが、の言いたいことが分かったのか、僅かに口端を上げた。
「ああ…ソイツ、男?」
「え、ええ。まあ」
「そう。なら…いいよ。僕を口実に断ってきて」
「ありがとう御座います」
すんなり了承してもらえたことではホっとした。具合の悪い友達とバッタリ会ったので送っていく。石崎に何か言われたらそう言えばいい。
「あの…わたし、と言います」
「僕は五条。五条悟」
「五条、さん」
「悟でいいよ」
「え?」
「友達、なんだろ?」
そう言って僅かに微笑む。それはの胸が素直にときめいてしまうほど、魅力的な笑顔だった。
これがキッカケでふたりは連絡先を交換し、時間が合う時には食事へ行ったり、映画に行ったりするようになった。そしてその関係が半年ほど続いた頃、彼女の優しさと素直さに惹かれた五条の方から「付き合って欲しい」と告白をし、五条に好意を抱いていたはそれを喜んで受け入れた。
「…と、まあ、こんな出逢いだったみたいだぜ」
パンダ、真希、棘と乙骨はすでに寮へと戻って食堂で夕飯を食べていた。そこで五条とのなれそめを知っていたパンダが勝手に皆へ説明をしていたところだ。
「へえ…え、でも悟って酒飲めなくない?」
「しゃけ」
真希がふと思い出したように言い、棘も同意する。パンダも「ああ、そうみたいだな」と言いつつも、
「その日は同僚の家入硝子、センパイの冥冥、コーハイの七海術師、補助監督の伊地知って顔ぶれで飲み会開いてたらしいんだけど、悟は下戸だからソフトドリンクで参加してた。でも途中、飲み物を追加した時に間違えて七海さんが頼んだウイスキーを一気に飲んじゃったんだと。色が自分の頼んだ口直し用のウーロン茶に似てたからって」
「ぶははっ。ドジだねぇ~。で、悪酔いして彼女に介抱してもらったんか」
「何でも優しくされて感動したとか言ってたな。知らない男に親切に声をかけてくれたばかりか、背中さすってくれたりタクシー乗せてくれたりして。だから別れ際、お礼するって言って無理やり連絡先を聞きだしたとか」
「…それ結果的にナンパじゃん」
「言われてみればそうだな」
真希の指摘にパンダも笑いながら頷く。
「で?半年後に告白して、彼女もOKしたと、そういう流れ?」
「ああ。彼女も悟のこと好きだったらしいし。まー悟は顏と実力だけは特級だもんなー。性格はアレだけど」
パンダはケラケラ笑いながら腹を抱えている。五条に聞かれたら「剥製にすんぞ」と言われるに違いない。話を聞き終えた真希も、パンダと同じく笑いながら身を乗り出す。
「でも彼女もよくあの性格につき合ってられたよなぁ?」
「あの性格って?」
「だから、軽薄で意地悪で自己中だし、生徒にしょっちゅうパワハラ――」
「「ま、真希!」さんっ」
「おかかおかか」
「あ?何だよ」
五条の悪口を並べ立てていた真希は、向かい側で青ざめる乙骨と、肩をバシバシ叩いて来るパンダと棘をジロリと睨みつけた。しかし三人の視線は真希ではなく、真希の背後に向いている。その視線に釣られ、真希もふと後ろを振り返ると、
「げッッ悟…!」
そこにはサングラスの合間から恐ろしい形相を覗かせた五条が、またしても仁王立ちの如く真希を見下ろしていた。その口元は若干引きつっている。
「ほぉ~オマエは僕のことをそんな風に思ってたのか…」
「い、いや、違う!あ、違わないけど――」
「真希ぃ~明日、任務前にグラウンド200週な?」
「はぁ?!おい、それ職権乱用ってやつじゃねーかっ」
「あーおばちゃん!さっき頼んだ食事、出来てるー?」
「聞けよ!」
罰を言い終えた五条は真希の言葉も聞かず、サッサと料理を受けとりに行っている。真希は拳をグっと握りしめながら肩を震わせた。任務前の200週は何気にキツイのだ。
「悟のヤロー…覚えてろよ…」
「まあまあ。僕もつき合うよ、真希さん」
元々が平和主義の乙骨が宥めるように間へ入る。これ以上、真希が暴走すれば、またどんな罰をくらうか分からない。そこへ料理をトレーに乗せて五条が戻って来た。
「悟、それ彼女の飯か?」
とパンダが声をかける。トレーの上には小さなお皿が乗っており、中身は鶏肉粥のようだった。
「そーだよ。今の彼女は空腹にならないけど彼女の猫は餓死寸前だったからね。少しずつ消化の良いものを食べさせないといけないんだけど、中にがいるのにキャットフードは食べさせられないでしょ」
「そうなのか?さっきせっかくキャットフード買って来たのに」
「あれは本物のミャウ太郎が意識を取り戻したらあげるよ」
「ふーん…悟はアレだな」
「アレ?」
テーブルに突っ伏し、ぶーたれた顔の真希が呆れたように口を挟んだ。
「彼女には随分と優しいんだな。そんなものまで用意してやるとか」
「そりゃーオマエらより何千倍も可愛いからね、は♡」
「「「「………(ぬけぬけと惚気やがった)」」」」
嫌味で言ったのに全く通じないばかりか、サラリと惚気られ、一斉に皆の目が細められる。そんな空気に五条は全く気づかず、嬉しそうに寮へ戻っていった。その幸せそうな後ろ姿を見ていると、イラっとした様子の真希は「チッ」と舌打ちしている。
「悟のヤツ、すっかり復活してるし。昼間はお通夜みてーにどんよりしてたクセに」
「まあ…今回の件が上手く片付いて彼女の体を見つけたら、ヨリを戻してもらおーとでも思ってんじゃねーの。未練タラタラで彼女に何度も考え直してくれって会いに行ってたみたいだし」
「しゃけ」
なかなかに鋭いパンダだった。それには真希も「なるほど」と納得している。
「邪魔してやろーか、ムカつくから。彼女、悟の本性知らねえだろ、多分」
「ダ、ダメだよ、真希さん…。それにまた振られたら五条先生、もっと機嫌悪くなって、それこそ僕らに八つ当たりが…」
「「「あ~…」しゃけ…」」」
乙骨の言葉に3人も大きく頷く。五条の性格を考えれば、二度もフラれた場合、今以上に理不尽な任務を押し付けられるかもしれない。それはさすがの真希もごめん被りたかった。
「じゃあやっぱムカつくけど、あの彼女と上手くヨリを戻させた方が私らにはいいってことか…」
「かもなぁ」
「しゃけ、しゃけ」
うーん、と考えていた真希だったが、仕方ないとばかりに立ち上がり「じゃあ協力して彼女の体でも探すか?」と皆の顔を見渡す。
「面白そうだな」
とはパンダ。
「しゃけっ」
笑顔で手を上げる棘。そして乙骨も笑顔で立ち上がると、
「五条先生の為に頑張ろう!」
「「「いや、それはねぇよ…」 おかか…」」」
「えっ!!」
全否定された乙骨は、皆の五条に対する扱いが塩対応すぎることに、ガックリと項垂れた。