07-それ、煽ってんの?
※性的描写あります。苦手な方は観覧をご遠慮下さい。
サァァっと静かな葉音がして、はふと目の前の大木を仰ぎ見た。緑色の葉が風に吹かれ、隙間からは太陽光が差し込んでくる。眩しさを感じて光を手で遮りながら、目を細めて見上げた空は、どこまでも青く澄んでいて自然と笑みが零れた。まるで五条先輩の瞳みたい、と思ったからだ。
同時に五条の顔も浮かび、ハッと我に返ったは慌てて首を振った。油断した途端、じわじわと頬に熱が生まれてしまう。
「さん、こっちは終わりました!」
そこへ同行している同級生の伊地知の声が聞こえてきた。今日は任務で高尾山まで伊地知と見回り兼祓徐の任務に来ていた。
高尾山は2007年にミシュランから3つ星として認定されたこと、パワースポットとしてのメディア露出が増えたこと。それらの影響で今では年間250万人ほどの登山者が高尾山へ来ている。富士山が年間、約500万人。それの半分が高尾山へ来ている計算だ。
その分、遭難者が増えたり、死亡事故が増えたりということもあり、年々呪いの数も増加傾向にあるらしい。
そこで政府から見回りもかねた祓徐を依頼されるようになった。
今回の担当はと伊地知の三年組。朝からざっと事故の多い付近を調べて回っていた。
今の時期は登山客より観光客が多い。特に大きな事故もなかったことで前回の見回りの時からそれほど呪いは増えてなかったこともあり、低級呪霊を見かけては祓うといった簡単な祓徐で終わることが出来た。
「はぁ、今回は少なくて良かった」
「そうですね。私でも祓える程度の呪霊でホっとしました」
伊地知は自虐的なことを言いながら笑っている。以前、五条から「オマエは呪術師に向いてない」とハッキリ言われたのはも伊地知から聞いている。しかし一時は落ち込んでいた伊地知も気持ちを切り替え、将来は補助監督として高専で働く、という方向に進路をシフトしたようだ。五条に言われたとおり車の免許をとる為、今は勉強中ということだった。
「日差しは強いけどさすがにこの辺りは涼しいですね」
「ほんと。空気が綺麗で気持ちいい」
任務が無事に終わり、緊張も解けた二人は、他愛もない会話をしながら引率の補助監督が待っている駐車場へ向かう。観光客用の道から少し外れた山の斜面は、なかなかに歩きにくい。念のため、靴は登山用のしっかりした靴を履いて来たものの、歩き慣れない山道は息が上がるくらいきつかった。体力のない伊地知はすでにへばっている。
「もう少しだよ。伊地知くん」
「は、はあ。私はこういうアウトドア系の場所は苦手で…」
ハンカチを出して額の汗を拭きながら、伊地知は一歩進むたびにヒィヒィ言っている。確かに伊地知はどちらかと言えばインドア派だろうな、とは苦笑した。休日も出かけることは少なく、娯楽室や部屋で常に本を読んでいる印象が強い。それも何が面白いのか分からないような政治哲学書といった分厚い本ばかりで、も一度借りて読もうと試みたものの、一ページ目の二行目辺りで断念したことがある。
「ところで…その…さん、体調の方はどうですか?今日は顔色も良くて安心しましたが…」
転ばないよう足元を注意しつつも、ふと伊地知が彼女の方へ振り返った。
「え、あ…うん。硝子先輩に治療してもらったから…前よりだいぶ楽なの。だから今日の任務も簡単な見回りなら行っても大丈夫だって言ってもらえて」
「そうですか。それなら良かった」
伊地知ホっとしたように笑顔を見せた。の知らないところで伊地知が心配してくれてたことは家入から聞かされている。しかし内容が内容だけに事情を話せないので、そこは申し訳ない気持ちになった。
ただ、例え恥ずかしさを我慢して話せたとしても、あんな事情では伊地知も困るだけだろうことも分かっているので仕方がない。なので伊地知にはちょっとした貧血と言うことにしておいた。
「す、少し休みませんか…」
「うん、そうだね」
やっとの思いで獣道から抜け出した二人は、観光客の集まる茶店付近で立ち止まった。今日は早くに出発した為、現在はまだ午前中。普段は込み合っている店なども人がまばらにいる程度だった。並ぶこともないので冷たい飲み物を一杯くらい飲むだけなら、それほど時間もとられない。
補助監督のいる駐車場まではケーブルカーで下りていかなければならないので、その前に少しの休憩を挟もうということになった。
茶屋の看板がある店先の冷蔵庫には缶ジュースの類がたくさん売られている。それを買って二人で外のベンチに腰をかけた。歩いたことで汗ばんだ肌に、冷たい山風が気持ち良く触れていく。
「ハァ…生き返る」
「ほんとだねー。任務じゃなきゃ、ちょっと散歩したいくらい」
「私はもう勘弁です…」
伊地知はそうとう疲れたのか、ははは、とから笑いしながら冷えた缶コーラをぐいっと煽っている。も疲れてはいるのだが、夕べは久しぶりにぐっすり眠れたので、今日は何となく体も軽い。
呪印が消えてないと分かった時はガッカリもしたのだが、五条のおかげで楽になったのは確かだ。今夜また家入の私室で治療と言う名のあの行為をすることになってるので、今度こそ消えて欲しいと願っていた。
帰ったらきちんと汗を流しておかなきゃ、なんてことまで考えながらも、また五条に触れられることを思うと心臓が勝手に早鐘を打ち出す。あんなにも恥ずかしかったはずなのに…いや、今も恥ずかしいのは変わらないが、このドキドキはそういった類のものじゃない気がして、小さく深呼吸をした。
五条は呪術界でも三人しかいない特級呪術師であり、しかもビジュアルすら特級レベルのカッコ良さ。そんな最強の先輩に、は入学当時から憧れにも似た感情を抱いてた。
時には厳しい口調かつ、辛辣な言葉をぶつけられる後輩達もいるし、もたまに体術が上手く出来ない時は注意されたりもするが、それを怖いとは思わなかった。
むしろ最強の先輩に教えられるのは光栄なことで、五条に指導してもらえる時間はにとっても貴重なものとして受け止めている。
その五条と、治療とはいえ親密な時間を過ごしたのは、の中でかなり刺激的なものだった。普段なら絶対に見せない甘い表情や、聞いたことのない声色で卑猥なことを言われるたび、の中で五条をただの先輩としてではなく、一人の男として強烈に意識してしまった気がする。
当たり前だ。女として秘めた部分を曝け出し、五条にもまた引き出されてしまったのだから、意識するなと言われてもそれは無理というものだ。
(でも…五条先輩はただ治療として仕方なくしてくれたことだから…あんなの迷惑だったよね、きっと)
彼女でもない、ただの後輩に性的な行為をするなんて、きっと五条も嫌だったはず。
いくら呪霊に穢されようと、恋愛経験のない彼女にはそんな風にしか思えなかった。
治療を受けてくれたのが五条で良かったと思ってはいるが、五条の方はしたくもなかっただろう。現に行為中、キスだけはしてこなかったのだから。
何度かキスをしたそうに唇を寄せてはきたのだが、必ずといっていいほど顔を反らされた気がするのだ。
あんな普通の状態じゃいられない場面で、も本能的にキスして欲しい、と思ったことまで思い出し、顏がじわりと熱くなった。
(やだ…私ってば呪霊に襲われてから…思考がエッチになってる気がする…)
無理やり女としての官能を引きずり出されたことで、未経験ながら体は快感を知ってしまっている。それが恥ずかしいのに、五条に触れられた時は羞恥心など感じてる暇もないくらいに酔わされてしまった。
(幻滅…されたかも…)
乱れた自分を思い出すと、顏が更に熱くなってしまった。
「あ、あの…私、ちょっとお手洗いに行って来るね」
五条とのことを考えてしまうと妙に落ち着かなくなり、は伊地知に声をかけて立ち上がった。こんな火照った顔のままでは変に思われる。
「ああ、そうですね。山を下りる前に行っておきましょう。私も行ってきます」
伊地知も行くと言い出し、二人は店の中にあるトイレを借りてから山を下りることにした。
「ハァ…良かった…伊地知くん、こういうことに鈍感で…」
トイレの鏡で自分の顔を見たら真っ赤になっていたので、つい苦笑が洩れた。どことなく目も潤んでいるせいか、尚更こんな顔を伊地知に見せるのは恥ずかしい。
蛇口をひねって水を出し、その火照った顔を簡単に洗うと、多少はスッキリしてくる。
「あまり今夜のことは考えないようにしなきゃ…」
持ってきたミニタオルで顔を拭くと、最後に用を足していこうと奥の個室へ入る。しかしその瞬間、またあの突き刺さるような視線を感じてぞくり、と怖気が走った。
「こ、この感じ…アレがいる…?」
間違いなく、例の呪霊の気配がする。ここ数日は任務も休んで高専内にいたから忘れていたが、またアレに見られてる気がした。
ここから出なくちゃ――!
すぐ近くに伊地知がいる。もし何かあっても――大丈夫。
自分を奮い立たせるように大丈夫、と唱えながら、急いでドアを開けようとした。だが一歩遅かったらしい。ドアノブを掴んだその手は、すでに黒い触手のような紐に拘束されていた。あいつだ、と脳が理解したは、すぐに助けを呼ぼうとした。
「ひ…い、いや…伊地…ンぐ――!」
恐怖のあまり伊地知を呼ぼうとした口を触手に塞がれ声が出せない。
ずずず…と背後からは真っ黒く大きな影がその姿を現し、を包むように広がり始めていた。
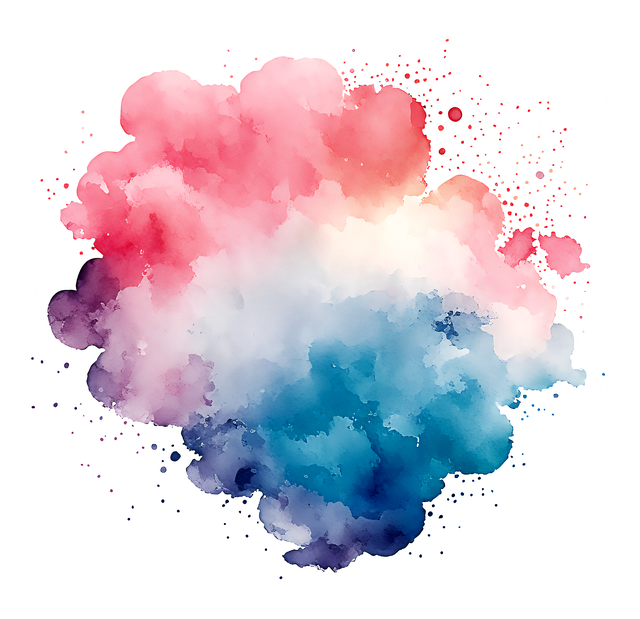
「硝子!がまた襲われたって――!」
バンっと派手な音を立てて五条が研究室のドアを開けた時。ちょうど処置室から出て来たばかりの家入は、びくりと肩を跳ねさせた。
「静かに開けてよっ!びっくりするでしょ!」
不意打ちすぎて心臓がばくばくした家入が思わず怒鳴る。しかし聞いてもいない様子で真っすぐ歩いて来た五条は「はどこだよ?」と開口一番、尋ねてきた。その焦りようは五条らしくないもので、明らかに動揺している。
こんな五条は付き合いの長い家入でも殆ど見たことがない。しいて言うなら――もう一人の同級生、夏油が離反して以来だった。
「事情は電話で簡単に説明したでしょーが。なのにアンタ、勝手に切っちゃうから」
「いいから教えろ。は無事なのかよ――?」
と家入に詰め寄った時、背後で「…ッ五条…先輩?」という声が聞こえて、五条は慌てて振り向いた。そこには腕に包帯を巻いたと、頭に包帯を巻いた伊地知が立っている。二人は研究室の隣にある処置室で家入から怪我の治療を受けてたようだ。
「おま…大丈夫だったのかよ」
「あ…はい。伊地知くんが助けてくれて…」
「は?伊地知?」
その名を聞き、の後ろでびくびくしながら立っている、もう一人の後輩へ視線を向ける。その目つきはこのヘタレが彼女を助けた?とでも言いたげだ。若干、殺気立ってる五条を見た伊地知の額から、気の毒なほど冷や汗がだらだらと垂れ流されて行く。
そんな空気に気づかないは、自分の身に起きたことをきちんと五条に説明した。
「…それで…急に拘束されて襲われかけたんですけど…不審な物音を聞いた伊地知くんが駆けつけてくれたんです。女子トイレと男子トイレは薄い壁を一枚挟んで隣同士だったらしくて…」
「それが幸いしました。隣の女子トイレからガタンガタンって不審な音がしたんで、私はてっきり痴漢かと思って…ちょうどトイレ前の壁に"痴漢注意"の張り紙があったので…」
「…マジ?でもどうやって…その呪い一級相当だったろ」
呪印の気配に触れた時、聞いた話も合わせて、五条はそれくらいだろう、と見積もっていた。それほど強い呪力と執着を、あの呪印から感じるからだ。それは万年三級の伊地知が追い払えるものじゃない。
五条の言った意味に気づいたのか、伊地知は「私もそう感じたのですが…」と前置きしたあと、ポケットからある物を取り出した。
「ちょうどこれを持ってたんです」
「…これは…祓徐後に貼る護符…?」
それは呪いの発生を抑制する為、祓徐をした場所に貼っておく、いわば虫よけみたいなものだ。低級やあまり強くない呪いなら、これを貼るだけで十分に効果はある。
「最初は痴漢かと思って女子トイレに飛び込んだんですが…黒い大きな物体がさんにまとわりついていて驚きました…。初めはその焦りで直接そいつを私の術式で攻撃したんですが、逆に触手で振り払われて吹っ飛ばされたんです。その際、私のポケットから今日使用した残りの護符が零れ落ちて…咄嗟にこれなら怯ませるくらいは出来るかと、護符をその呪いに貼ってみたら――」
と言葉を切った伊地知は、その話の先を促すよう隣にいるを見た。
「伊地知くんが護符をアレに貼った瞬間…わたしを拘束していた触手が緩んだので、つかさず私も攻撃しました。すると萎んだようにアイツが消えて…」
「…なるほどね。まあ…その呪霊からすれば、ちょっと痺れた程度の攻撃だったんだろうが、以外に攻撃されて怯んだのかもね。ってことで――よくやった、伊地知!」
「えっ?!」
それまで殺気立っていた五条が一変。満面の笑みを見せると、本能的に逃げ腰になっていた伊地知を捕まえ、思い切り抱きしめる。ぎゅうぅううっと物凄い力でハグをされ、あまりの苦しさに伊地知は目を白黒させた。
ミシミシ、と背骨の軋む不穏な音などお構いもせず、五条は「さすが僕が将来のミスター補助監に任命しただけはある!」と、伊地知を褒めている。そんな任命などされた記憶すらない伊地知は「し…死ぬっ!背骨折れて死ぬぅ!」と必死にもがいたのだが無駄な努力だった。現代最強の腕力には到底かなわない。
「オマエのことは僕が一生可愛がってやるから安心して補助監になって!」
「…はぅぅ…ぅ」(※痛くて返事すら出来ない伊地知)
この呪いのような言葉が、伊地知の未来を予見していたとは、この時はまだ誰も気づいていなかった。
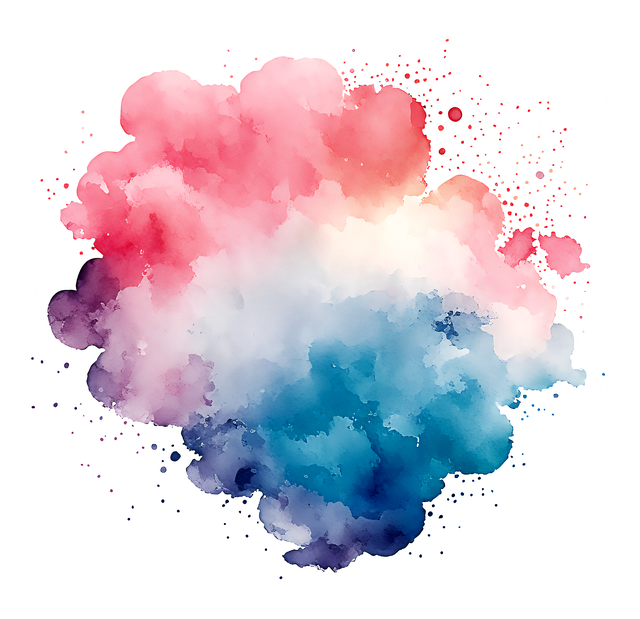
「ハァ…またここかよ…」
事情の知らない伊地知だけ先に帰したあと、五条とは再び家入の私室へと閉じ込められた。今日は体内の呪印を直接攻撃して祓うことになっているのだが、任務に出た先でも襲われたことで、も多少動揺しているようだ。
いつもは出張先のホテルでしか現れなかった呪霊が、あんな場所でも襲ってくるとは思わない。
「まあ…昨日の行為で呪いの方も自分の力が弱まったことに気づいたのかもな。それイコール、自分以外の男が触れたと思っても不思議はないし」
「そんな…」
「まあ…呪印でマーキングされたってことは、その呪いとリンクしてんのも同然だから」
そう説明しながら、五条は昨日の体に触れた時、呪いの力をその身に感じたことを思い出した。まるで威嚇するような圧だったことも。
「じゃあ…もし祓えたとしても、またわたしを襲ってくるかもしれないってことですか…?」
「多分ね。でもその心配はまず呪印を消してから考えればいい。呪霊は高専内にいる限り、には手を出せないんだから」
「それは…そうですけど…ずっと閉じこもってるわけには…」
はしゅんとしたように項垂れた。自分が任務に出られないとなると、その分同級生には迷惑をかけてしまう。それに事情を話せないのだから嘘をつくことにもなる。
「だから犯人を見つけるか、その呪いを直接祓う方法も考えるよ」
「…すみません。わたしの為に五条先輩にまで面倒かけてますよね…」
「別に…が悪いわけじゃないでしょ。オマエは被害者なんだから。いちいち気にすんな」
五条は言いながら缶コーヒーのタブを開けると、一口飲みながらソファに腰を下ろした。どこか落ち着かない様子に見える。
それに先ほどから五条はを見ようとしない。それが少し気になっていた。
「あ、あの…五条せんぱ――」
「じゃあ…始める?も早く中のもん消したいでしょ」
「え…と…は、はい…」
自分を見ないまま、素っ気なく言われたことで少なからず悲しくなった。こんな行為、五条にとっては迷惑でしかないんだろうと思うと泣きそうになる。でも泣いてる場合じゃない。五条の言うように呪印を消してしまえば、とりあえず自分が死に向かうことはなくなるのだ。
「」
「は、はい」
頭であれこれ考えていると、五条がふとサングラスをズラして、立ったままのを見上げた。
「まずは…さ。その…自分でして濡らしてみて」
「……え?」
唐突に自分でしてみろと言われ、一瞬何を、と思ったが、すぐに自慰のことだと気づき、頬が熱くなる。昨日はそれが出来ずに五条にしてもらうことになったのだ。てっきり今日も五条が助けてくれるんだろうと思っていただけに、は困惑した。
「昨日も言ったけど…自分で出来るならその方がいいでしょ、も」
「え…と…で、でも――」
「昨日教えたよね、やり方。どこが感じるとかも」
「……は、はい」
と答えたものの、思い返すと殆ど覚えていないことに気づく。あんな行為の最中、恥ずかしさと快感で頭など回っていないに等しい。でもそれを言うのは躊躇われたので、つい「はい」と言ってしまっただけだ。
「心配しないでもちゃんと濡れたあとは僕が…」
「??」
急に黙り込んだ五条に気づき、は俯いてた顔を上げた。すると五条はやはりから顔を背けたまま、軽く咳払いをしている。
「まあ…中のもんに呪力を流してみるから」
「…は、はい…」
とは言ったが、は正直それをどうやって行うのかは、よく分かっていない。五条に任せておけば大丈夫、と思っているので、その過程に至る前に自分で準備をしろということなんだろう、と理解した。ただ、その準備を自分でするということに関しては自信がない。
色々不安に思っていると、五条は昨日のように「じゃあ僕は廊下にいるから――」と、また部屋を出て行こうとしていた。その背中を見ていたら一気に不安が強くなり、気づけば五条の腕を掴んでいた。
「っ…?」
「あ…ご、ごめんなさ…」
五条がぎょっとした様子で振り向く。何で引き留めてしまったのか自分でも分からない。ただ、やはり自分でするのは自信がなく。五条にして欲しいという思いで、は腕を掴んだ手にぎゅっと力を込めた。
「あ、あの…すみません…。やっぱりわたし…自分でするのは無理なので……その…お…お願い…してもいい…ですか…?」
「………」
言った傍から顔に熱が集中していく。まるで火を噴いたのかと思うほどに熱い。五条は黙ったままを見下ろしていて、余計に緊張で声が上ずってしまった。
「ご、五条先輩にこれ以上、迷惑かけたくない…し……先輩も…わたしに触れたくないかも…ですけど…あの…やっぱり、わたし――」
「……服脱いで」
不意に今まで黙って聞いていた五条が口を開き、はドキッとして顔を上げた。
「え…」
「だから、服脱げって言ったの。僕にして欲しいんでしょ」
「は…はぃ…」
声があまりに素っ気なく、怒らせてしまったのかと思うと喉の奥がきゅっと痛くなる。しかし自分で頼んだ以上、言われた通りにしなくては、という思いが過ぎる。
制服の上着を脱ぎ、スカートを下ろす。その様子を五条は黙って見ていた。
「こ…これでいいですか…?」
さすがに全裸になるのは恥ずかしく、下着は付けたままだが昨日と同様、シャツだけ羽織った姿で尋ねてみた。五条は飲みかけの缶コーヒーをテーブルに置くと、「後ろ向いてソファに手をついて」と言いながら、自分の制服の上着を脱ぎ捨てた。それを見た瞬間、昨日の記憶が蘇る。どきりと心臓が跳ね、慌てて後ろを向いた。
「こ、こう、ですか…?」
「もっと腰をこっちへ突き出して」
「は、はぃ…」
ソファの背もたれに掴まりながら、言われた通りに腰を後ろへ突き出す。その瞬間、五条の手がショーツにかかり、するりと脱がされた。思わず「ひゃ」と小さな声が洩れる。
「…ったく。人の気も知らないで」
「え?」
ぼそりと呟く声がして、つい後ろを振り返ろうとした時、五条の指が晒された陰部にすり、と触れる。その感触にびくりと腰が跳ねてしまった。
「…ン」
「こっち見なくていいからは前だけ見て集中してろ」
「は…い」
素っ気ない声にやっぱり怒ってるんだろうか、と悲しくなった時、割れ目をなぞるように指が動いて「ひぅ」と息を吸い込む。
「昨日でどこが気持ちいいのか分かったろ。どこがいい?」
「ンン…そ、んな…の…わかんな…あっ…」
後ろから伸びた手にシャツのボタンを一つ一つ外され、その開いた場所から筋張った五条の手が忍び込み、ブラジャーのカップを下げられる。そのまま指の腹で乳首をすりすり擦られただけで、恥ずかしい声が勝手に出て来てしまう。
「ここ、弄られんの好き?」
「んっ…」
「もう少し強い方がいい?」
「あぅ…んっ」
軽くきゅっと乳首を摘ままれ、背中が僅かに反りかえる。甘い刺激が一気に広がり、五条の指が往復してる場所からじわりと何かが溢れてきた。
「もう濡れてきた。、ほんと感度いいね」
「ひゃぁ…ぅ」
その場所をぐにゅっと手のひら全体で撫でられ、びくびくと身体が跳ねてしまう。そのまま割れ目に沿って手のひらで揉まれるたび、更に蜜が溢れてくるのが自分でも分かった。
すると突然突き出している腰を片腕で抱えられ、ひゃっと声が跳ねた。五条はそのままを抱えてソファに座ると「やっぱもどこが感じるか自分で覚えて」と彼女の手を取り、濡れた場所へと誘導していく。
「ここをこうやって撫でて」
「…ん…」
五条の手に誘導され、自分の陰部へ触れると、そこは本当にぬるぬるとしていた。初めて触れる感触に再び顔に熱が集中していく。こんなに濡れてるという自覚はなく、五条の愛撫によって、それが自分の体から溢れてくるという事実が、ただただ恥ずかしい。
「ここも指でこすって」
「んん…あっ」
割れ目の上部分、ぷくりとした芽に触れる。同時に五条から首筋をぺろりと舐められ、小さく声が跳ねた。五条の手に誘導されるまま、一番敏感な部分を自分の指で撫でさせられるのは、思ってた以上に恥ずかしい。昨日自分でも触れてみた部分なのに、その時とは全然感覚が違う。
「シャツ、開いて」
「…へ?」
横向きにされたかと思うと、今度はソファに寝かせられ、上から五条に見下ろされる。心臓がきゅっと音を立てたのは、いつの間にか五条がサングラスを外していて、美しい六眼と目が合ったせいだ。
「胸、出してって言ってんの」
「…えっ」
「早く」
薄闇で光る青い目に見下ろされ、心臓が一気に早鐘を打つ。恥ずかしいのを堪え、シャツの合わせ目を自ら開くと、「そこ開いたままにしておいて」と言われてしまった。ブラジャーのカップは下ろされ、露わになった胸を自ら曝け出してる恰好はかなり恥ずかしい。顔が真っ赤になったのが自分でも分かる。
「こ、これ…恥ずかしい…」
「言ってる場合じゃないでしょ」
五条は軽く苦笑すると、空気に触れてツンと上を向いた乳首をぱくりと口へ含んだ。
「…あっ」
口へ含まれた瞬間、舌先でぬるり、と舐められる。その刺激で更に硬さを増した乳首をちゅうっと軽く吸われれば、肩がびくびくと跳ねてしまった。
「一緒に触ってやるからちゃんと自分で触って覚えて。オマエの気持ちいいとこ」
「…は…はぃ…ふぁ…っ」
乳首を指できゅうっと摘ままれ、だんだん息が乱れてくる。自分でも触っているものの、五条に触れられた時の方が快感は強く感じた。
「、ちゃんと感じてる?」
「……ん、…」
乳首を吸いながら、同時に襞の中へ指を入れて上下にゆっくり撫でられる。そのたび声も息も乱れて、頭が朦朧としてきた。気持ちいい感覚が常に襲ってくるせいか、何故こんなことをしてるのかさえ、目的すら忘れてしまいそうになる。
「どんな感じ?」
「…ど、どうって…」
「ちゃんと気持ちいい?」
「あぅ…せ、先輩に…触られた方が…き、気持ちい…んっ」
「……オマエ…それ煽ってんの…?」
「…ふぁ…っ?」
ぬるぬると往復してた指の先が、ある場所へと埋められて、動かされるたびぬちゅぬちゅとした音を立てる。じん、とお腹の奥が熱くなった気がして、腰が勝手に動いてしまった。
「いい音してきた」
「…やぁ…あっん」
指を少しずつ埋めていきながら、五条はの乳首を口内に含み、舌でちゅくちゅくと捏ねていく。同時に愛撫されてる体が快感を拾い、指の埋められた場所から、とろとろと愛液を溢れさせた。それを掻きだすように少しずつ指の動きが速くなっていく。
「あ…あ…っぁ」
ぱちゅぱちゅと音が鳴るほど指を出し入れさせながら、五条はの耳元に唇を押し付けた。
「エロい音、聞こえてる?」
「…ん…やぁ…」
直に鼓膜を震わせる五条の声だけで、更にナカから溢れてくるのが恥ずかしい。なのにその場所で轟く指の動きは止めてくれず、もう一本増えた感覚があった。
「…痛い?」
五条の問いにどうにか首を振る。異物感はまだあれど、たっぷり濡れてきたおかげで酷い痛みはない。ただ初めて触れられてる場所だからか、ナカが少し焼けるようなヒリつく感覚がある。
「かなりキツいけど、もっと広げて奥に挿れるよ。じゃないと呪印に届かないから」
「…んんっ」
指を増やされ、更に奥へと埋められていくと、ヒリつく感覚が強くなった。でも不快な痛みではない。気持ちいいかと聞かれれば、ナカはまだそこまでの快感はなく。ひたすら異物感があるだけだ。ただ五条に卑猥な行為をされてるという事実で、体は勝手に疼いていく気がした。そんな自分が恥ずかしくなるのだが、その羞恥心すら快楽に押し流されてしまう。
「んー…この辺り、かな」
「…んぁっ」
ぐい、と指がある部分を突き、びくん、と腰が跳ねる。五条曰く、そこはポルチオと呼ばれる場所らしく、女性の体の中で最も感じる部分だという。そこを開発していけば奥でイけるようになるらしいが、今のではその感覚すら分からず、そこを刺激されると少しの痛みを感じた。そして最悪なことに下りてきた呪印はその付近にあるようだ。
「…今から僕が呪印に呪力を流す。その時かなり痛みを感じるかもしれないけど…」
「へ…平気…です」
気持ち良すぎて一瞬、目的を忘れかけてただったが、五条の言葉を聞いてふと現実に引き戻された。
「説明した通り…女の子の一番感じる場所だから、それなりに激痛だと思う」
「…う…は、はい…」
激痛、と口に出されるとやはり怯んでしまうものの、ここまでしたのだから今更やめてくださいとも言えない。それに呪印が消えれば、こんな恥ずかしい行為を二度としなくて済む。
「じゃあ…流すよ」
僅かに目を細めながら五条が呟く。は覚悟を決めて深呼吸を繰り返すと、最後に大きく息を吸った。
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
