09-上書きして欲しかった
意識を取り戻した時、は病室のベッドに寝かされていた。
「あ、気が付いた?」
「硝子先輩……」
ゆっくりと上体を起こした彼女に気づいた家入が、眺めていたパソコンからふと顔を上げて振り向く。一瞬、わたしは何故ここにいるんだろうと考えたものの、いつの間にか着せられていた検査用の服を見て何があったのかをすぐに思い出す。
――あーかわい……僕もイキそう…。
――…は、ぅん、…あ…ぁっあ…ま、たイっちゃ…。
――うん…イって…。
脳裏に五条との行為がフラッシュバックした瞬間、顔全体から熱が噴き出した。同時に自分が大胆にも五条を誘ったことまで思い出した時、くらりと視界が揺れる。あまりの恥ずかしさに眩暈を起こしたのだ。
一気に逆上せたような顔になった彼女を見た家入は「ど、どうした?具合悪い?」と慌てて駆け寄った。しかしは両手で顔を覆い、首を左右に振るだけで何も応えようとしない。その様子を見て何かを察したらしい。
家入は「もしかして…」と、の前にしゃがみ、彼女の顔を覗き込んだ。
「…五条のヌいてやった…とかある?」
「―――ッ」
「あー!ごめん!倒れないで!」
家入のデリカシーのない発言で、今度は首まで真っ赤に染まったがベッドへ倒れ込む。ぷしゅーと音が聞こえそうなほど茹っている姿は、今の質問を肯定したのも同じだった。
しかし、例えそうでも普通じゃない状況。追い詰められての行動だろうというのは想像に難くない。
「つい考えず口に出しちゃうのが私の悪いクセだった…ごめんね、」
今ではタオルケットを顔まで被ってしまったを見ながら、家入もさすがにハッキリ言いすぎたな、と反省する。
ただ、何故そう思ったのかというと、全てを終えた五条がこれまでと違い、やけにスッキリした顔で出て来たのを思い出したからだ。
電話ではあれほど「キツイ」だの「股間が痛ぇ」だのと愚痴ってただけに、もっとゲッソリして出てくるかと思っていただけに、そこが少し引っかかった。
思わず五条に「やっぱ最後までしちゃった?」と聞いたくらいだ。
五条は「んなわけねえだろ」とハッキリ否定したので安心はしたのだが――。
「んなことより呪印は消したから、もう一度調べろ」
と言われたので、家入も慌てて準備に入ったのだ。
しかし意識のないに検査服を着せたり研究室へ運んだりしている間に、五条の姿は消えていたので気になっていたことを聞きそびれたという思いがあり、その好奇心がに対して出てしまったというわけだ。
(まあ、でも今は私の好奇心よりも…大事なことを伝えなくちゃね)
一向に顔を出してくれないを見下ろしながら苦笑を零す。
彼女が意識のない間に写したレントゲンと、最後に五条がちゃっかり採取していた体液を調べた結果を見せるべく、家入はが被っているタオルケットを徐に剥ぎ取った。
「恥ずかしがるのはあと。まずは検査結果を見て」
「え…」
「あいつ、呪印を綺麗に消してくれたから」
そう言って手にしていた物を渡すと、の瞳にやっと本来の生気が戻ってくる。
「…消えてる」
「うん。多分、が意識ないうちに祓ったんだと思う。どうやったのかまでは聞いてないけど――」
と言ったところで言葉を切った。の瞳からぽろぽろと涙が零れ落ちたからだ。
気丈に振る舞ってはいたけれど、彼女はまだ十八歳。訳の分からない呪霊に襲われ、体を蹂躙された恐怖と屈辱は耐えがたいものだっただろう。しかも胎内に呪印まで残され、命を少しずつ削られていく。
想像以上に怖かったはずだ。
「よく、頑張ったね、」
そう声をかけながら、家入は静かに泣いている後輩の肩を抱いた。前例のない現象ということもあり、家入にしても自分の考えた方法で助けられるのか分からなかっただけに、心の底から安堵の息を漏らす。
「はい…ほ、本当に…ありがとう御座いました…」
ぐす、と鼻を啜りながら頭を下げるを見て、家入はその頭をくしゃりと撫でてやった。
「私は特に何もしてないよ。頭使っただけだし。ま…体張ってあんたを助けた五条にそれ言ってやってよ」
「…はい。あ、あの…それで五条先輩は…」
「あー。何か気づけばいなくなってた。多分、また疲れたから寮に戻って寝てんのかも」
「そ、そう、ですか…」
「まあ、明日にでも元気な顔を見せてやればいい。も疲れたろ。戻る前にここのシャワーブース使っていいから、シャワー浴びたら今夜は早く休みな」
「え…?」
ここには解剖をした後に使用できる簡易的なシャワーブースが設置されている。きっと寮の風呂には入りにくいだろう、と思って家入は敢えてそう言ったのだ。
は不思議そうな顔で見上げてきたが、家入が自分の胸元を指でとんとんと叩く仕草を見て、更に怪訝そうな顔をした。
あーこりゃ分かってないパターンか、と苦笑した家入は、近くにあった手鏡を彼女へ向ける。するとは自分の胸元を見て、白さを取り戻していた頬を再び赤く染めた。
ちょうど鎖骨の下付近に、小さな赤い痣のようなものがいくつかあることに気づいたせいだろう。
「こ、これ…」
「まあ…無意識だろうけど、人って興奮状態の時、特に男はそーいうの付けたがる生き物だからさ…」
「え…そ、そうなんですか…?」
「深い意味は多分ないと思うから気にすんな。二~三日で消えると思うから、それまでは胸元の開いた服は控えりゃいいし…」
と笑顔で言いながらも、家入の頭の中では「何してんだ、五条の奴!」という怒りで埋まっていく。
させた行為が行為だけに五条ばかりを責められないが、キスマークを付ける男の心理はといえば、ほぼ独占欲といっても過言ではない。
そんなものを後輩につけてどーすんだ、というのが家入の本音だった。
(まさか五条の奴…のこと…?いや、まさかな…)
これまで女関係では色々とお盛んだったのは知っている。
その五条がちょっとエロいことをしたくらいで、後輩に恋慕を抱くはずもない。と、家入は苦笑した。
「それより…呪印を消したはいいけど、根本的なことは終わってない…」
シャワーへ向かうを見送りながら、家入は呪いを生み出したストーカーを探しださなければ、と考えていた。
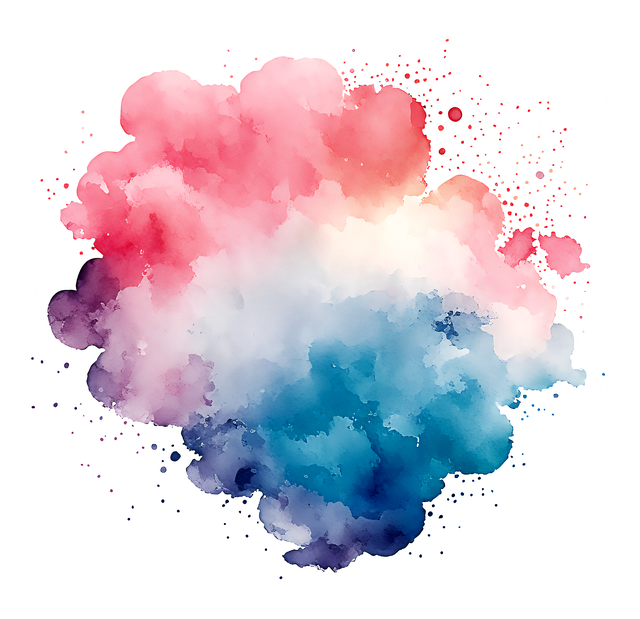
次の日、五条は都内での任務が数件ほどあり、高専に戻ってきたのは夜の十時を過ぎた頃だった。
気分的に少し疲れた五条は報告書を補助監督に任せて、一人寮への道のりを歩く。
だいぶ慣れてきたとはいえ、ふと一人の時間が訪れると、どうしても隣にいた存在を思い出すのは、この場所に思い出がありすぎるせいだろうか。
それとも夏の終わりが近づいてきてるからなのか。
「あいつ…今頃どこで何してんだか…」
夜空に浮かぶ小さな星を見上げつつ、独り言ちる。
一人で任務へ赴くことにも慣れたはずなのに、こんな夜は何となく空しくなるのだ。
そろそろ繁忙期が終わる時期とはいえ、それでもゼロになることはない。
呪術師は万年人不足に加え、五条や夏油以降、育った後輩と言えば七海一人という状況。
肩を並べていた夏油は離反し、代わりを担って欲しいと思っている後輩の七海も、今はあまりやる気を見せてはいないだけに、五条はこの先の呪術界の未来を不安に思っていた。
自分だけが強くてもダメだと気づいてからは、積極的に後輩の指導をしているが、今の一、二年も期待できるほどの術師は出てきていない。
そこそこ強いというだけじゃ生きにくい世界だけに、どうしても更に上を望んでしまう。
「ま…術師は持って生まれた才能が八割だし、厳しいか…」
それに三年も伊地知は脱落組だし――と考えたところで、それが記憶の引き金になったらしい。ふとの顏が浮かぶ。
それも――。
――先輩…あの…そこじゃなくて…ちゃんと…ナカで…。
夕べの行為中の映像が脳内でカラフルに上映しかかり、ぶわっと熱が吹き出す勢いで顔が熱くなる。
それが不意打ちの如く、何気ない時に流されるので、今日一日色々と情緒がヤバいことになった。
せっかく忘れようと別のことを考えているはずなのだが、ちょっとでも時間が空くと、すぐにのことを考えている気がする。そして脳内アダルト上映が始まるのだからたまらなかった。
「ハァ…またかよ。何でにだけ過剰反応してんだっつーの…」
手で顔を覆い、深い息を吐いた五条は、途中にある自販機へ立ち寄り、いつもの缶コーラを買った。蒸し暑い今時期に冷えたコーラは火照った顔を少しだけ冷ましてくれる。
――五条、どうやったの?綺麗に呪印が消えてたよ!体内も傷ひとつなかったし。
家入からそんな電話が入ったのは今朝のことだった。
まあ完全に消えるよう呪力を流したのだから当然なのだが、家入からお墨付きをもらったことで、五条も多少はホっとした。
夕べ、行為の最中、連続してイカせたのも半分は五条の狙いでもある。絶頂感を与えることで膣内を愛液で溢れさせ、更に呪印を下ろさせる目的だった。そして予想外だったのは、五条が考えていたよりも呪印が膣口付近へ下がってきたこと。
それを見逃す五条ではなく。が失神したのと同時に、一気に呪力を流し込んだ。
直に触れることが出来れば、どれだけ強力な呪いだろうが一瞬だった。おそらくは痛みすら感じなかったに違いない。
家入にそう説明すれば納得したのと同時に、根掘り葉掘り聞かれたものの、そこはさくっとスルーしておいた。
自分が何をしたかは話せても、が何をされたのかなんて、わざわざ話す必要もない。
呪印の影響下で起きた色々な反応に意味はなく、には早く忘れて欲しいと思っていた。
「ま、僕も忘れなきゃな…」
と言いつつ、さっきのように無意識の中で映像が流れるのだから、忘れようにも忘れられないのが目下の悩みでもある。
可愛すぎるのがいけない、とも思う。
これまで相手にしてきたどの女の子でも、に触れた時ほど男の本能を揺さぶられたことはなく。この違いは何なんだろうな、と苦笑が洩れた。
「五条先輩…?」
「――ッ」
不意に名を呼ばれ、どきりとして顔を上げた。
「やっぱり…五条先輩だ」
「…?」
寮のある方から歩いて来ていたが、五条を見つけると笑顔で駆けて来た。五条は背を預けていた自販機から離れると「どうしたの。こんな時間に」となるべく普通のテンションで尋ねたものの、内心は心臓がばくばくしている。
今、まさに考えていた相手が目の前に現れたのだから、多少動揺するのは当たり前だ。
「喉乾いたからジュースを買いに。先輩は任務帰りですよね。お疲れ様でした」
「あー…うん…」
マズい。どんな顔をすればいいのか、どんな返しをすればいいのか、サッパリ分からない。小さな動揺が次第に焦りに変わり、ますます表情が硬くなっていく。
「あ、あの…それで…」
こうして顔を合わせるのは夕べ以来。もやはり恥ずかしそうに視線を泳がせている。その表情がヤバい。五条の色んなところをガツガツ攻撃してくる。
「硝子先輩から聞いたと思うんですけど…呪印が綺麗に消えてたって…」
「…うん、まあ…今朝聞いた。良かったじゃん」
と、何故か他人事のような返しをしてしまったのだが、は気にした様子もなく、真っすぐ五条を見上げてきた。おかげで五条の心臓がまたしても馬車馬のように動きだす。一瞬、不整脈かと心配になった。
「五条先輩のおかげです。あの…本当にありがとう御座いました」
「別に…お礼を言われることじゃないし、気にすんな」
「でも…と、とんでもないことお願いしちゃったりしたので…」
色白の頬を赤らめて目を伏せる彼女は、どうにも儚げでいて、ちょっとだけ扇情的にも見えてしまう。
一言で言うならば、可愛いすぎだろ!これに尽きた。
もし彼女が後輩じゃなく、ここが高専内の敷地でなければ、五条はきっとを抱きしめていたに違いない。でもそこまで勘違いもしていないし、色ボケもしていない、つもりだ。どうにか耐えて、先輩の威厳を保つことには成功した。
「…別にいいって。呪印の影響でおかしくなってたのはお互いさまだから、も忘れて。僕も忘れる」
「え…は、はい…」
「それより…呪いは解けたわけだけど、まだ根本的な問題は何も解決してない。呪いの本体、もしくはソレを生み出した人間を探し出さないことには、また同じように襲われないとも限らないし――」
と、そこまで言って五条は言葉を切った。が見るからに怯えた顔をしたからだ。
「あ…悪い。怖がらせたよな」
「い、いえ…五条先輩の言う通りだし…犯人を見つけないと出張に行くのは怖い、です」
消え入りそうな声で言いながらが俯く。その頼りなげな姿を見ていたら、やはり自分がどうにかしてあげたいという思いが強くなった。
今現在、高専の方には家入から「は極度の貧血の為、任務に行かせるのは厳しい」と報告してもらっている。その為、明日からはだけが高専に残り、座学を受けることになっていた。
「その…心当たりはないんだよな?オマエにそういう想いを向けてるような奴に」
「はい…硝子先輩にも色々聞かれたんですけど思い当たる人はいなくて。別に誰から告白されたとかもないし…」
「ってことは…あまり積極的なヤツではないってことか…」
しかし五条もそれくらいは何となく想像できる。そもそもに好意を持った男がいたとして、積極的な男だったならまずはデートに誘うくらいはするだろう。それが出来なくても、多少は気がある素振りをするものだ。
でもはそういったことが一切なかったと家入に話したらしい。
(まあ…元々ちょっと鈍感なとこあるからな、は…)
そのせいで散々煽られたことを思い出し、つい苦笑が洩れる。男の心情など、今のに分かるとも思えない。
まあ、そういうところも可愛いんだけど――と顔がニヤケそうになるのを、どうにか堪えていた。
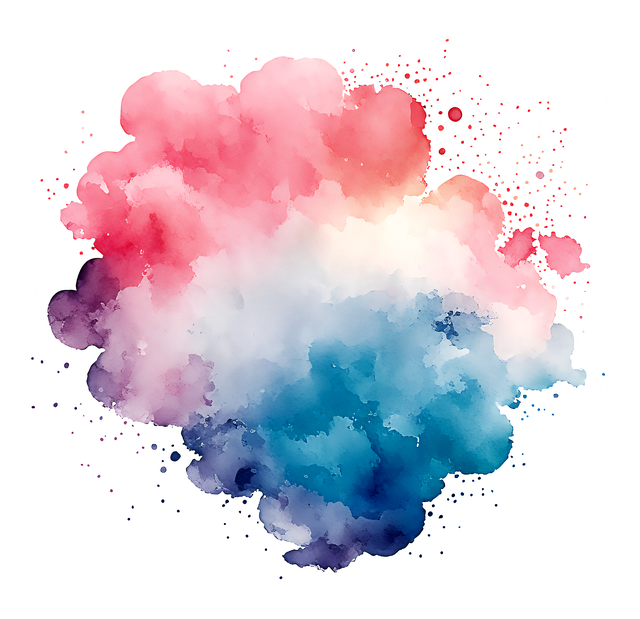
「とりあえず…明日の任務が終われば、僕も少し体が空くから、次はストーカー探しだな」
ふと五条が思い出したように言った。
「は…はい。すみません。五条先輩は凄く忙しいのに…」
特級呪術師と呼ばれる五条が多忙なのは、もよく分かっている。なのに自分の為に時間を割いてくれるというのは心苦しくもあり、また嬉しくもあった。
「水臭いこと言うなよ。は僕の大事な後輩だしね」
いつものようにポンと大きな手を頭に乗せられ、自然と笑みが零れる。しかし目が合った気もしたのに、五条はすぐに明後日の方を向いてしまった。外灯の明かりはあれど、サングラスをかけているのもあり、五条の表情はよく見えない。
「あー…じゃあ…僕は帰るから。も早く寝て体を休めろよ」
「え、あ…はい」
あまりに唐突な口調で言いながら、五条が寮の方へ歩いて行く。それを見送っていたは小さく息を吐いた。明らかに避けられた気もする。
いや、それまでは普通に話してたようにも見えるのだが、それでも合間に目が合うと五条はそっぽを向いてしまうのだ。
前とは少し接し方が変わった気もして、ちょっとだけ落ち込んでしまった。
「…幻滅されちゃったかな」
呪印のせいだと言ってはくれたものの、あれだけ乱れた姿を晒したのだから、引かれても仕方がないとは思う。
今でも自分があんなに乱れてしまった現実が信じられなかったし、思い出すだけで恥ずかしくて死にたくなる。でも高専にいる限り、五条と顔を合わせることになるのだから、なるべく普通にしなきゃと思って恥ずかしいのを耐えていた。
「やっぱり…呪いに襲われたせいだよね…」
家入も五条も穢されたわけじゃないと言ってくれたのは嬉しい。でも以前の自分には戻れない気がして、じわりと涙が浮かぶ。
――わたしの体…使って下さい。
本当は、五条にそれを上書きして欲しかった。
昨日、あんな大胆なことを言えたのは、自分の中にそんな思いが少なからずあったのだと、今更ながらに気づいたは唇を噛みしめた。
五条に幻滅されても仕方がない――。
自分を脅かす呪印は消えても、五条に嫌われたかもしれないと思うたび、心は少しずつ落ちていく気がした。
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
