10-無防備すぎでしょ
スキルはともかくとして、伊地知は呪術師としての任務が嫌いではなかった。例え祓えるのが下級呪霊ばかりでも、それに被害を受けている人達は大勢いる。そんな人達の役に立っている、と思えば、キツい任務も手を抜かずに頑張れる。
しかし都内での任務とはいえ、今日ほど祓徐の依頼が多い日はあっただろうか?と首を捻りたくなるほど、沢山の現場を回った気がする。
午前中だけでも渋谷、原宿、代々木……というか山手線の駅を全て回ったのでは、と思うほどの数だった。
それでも普段からコンビを組んでいるがいてくれれば、まだ楽だったのだが、彼女は体調不良ということで、しばらくは高専にて座学という報告を受けている。
なので伊地知としては「こういう時こそ私が頑張らねば!」と気合いを入れて高専を出発したのだが、最後の現場の祓徐を終えた時点ではヘトヘト。
補助監督の手を借りてやっとの思いで車へ乗り込む始末だった。
「大丈夫?伊地知くん。そこの袋にスポーツドリンク買ってあるから飲んでね」
「あ……ありがとう御座います。渡久山さん……」
後部座席で倒れ込んでいた伊地知は、片隅に置いてあったコンビニ袋を開けてお礼を言った。
中にはアクエリアスからOS1など、今時期の熱中症対策として最適なドリンクが数本入っている。なんて気が利くんだ!と感動しつつ、やはり私も彼のような補助監督を目指そう……と心に誓う。
渡久山は主に三年の引率を任されている補助監督で、年齢は二十九歳。ヘタレな伊地知は日ごろから世話になっていた。
同じ眼鏡仲間であり、穏やかな性格の渡久山も若い頃は高専の生徒だったらしい。自分には術師としての才能がないと気づき、サポートに徹することを誓ったという。その話を聞いた時、伊地知は自分とよく似た境遇の渡久山に共感し、お手本にしたい思うようになった。
運転も丁寧、かつ迅速で、二人はほどなくして高専へ到着。渡久山と伊地知は任務報告の為、校舎へやってきた。
「では報告書をまとめてきます」
「宜しくね。僕は事後処理で今夜も残業だよ」
「はぁ。補助監督の仕事は大変ですよね。一日私に付き合って、その後も仕事だなんて」
「そうだねぇ。でも皆のサポートを出来るのは嬉しいし、やりがいのある仕事でもあるよ」
渡久山は笑顔で言いながら「じゃあ報告書、頑張って」と伊地知を激励して歩いて行った。その背中を見送って、伊地知も三年の教室へと向かう。
五条に呪術師は向いてないと言われ、悩んだ結果。さくっと進路を変更した伊地知は、それ以降、意識して補助監督の仕事を観察するようになった。
渡久山にもその辺の話をしたところ、今では色々なアドバイスをくれるようになった。彼の丁寧な仕事を見ていると不思議と補助監督も悪くないと思えるのだ。
いいお手本が身近にいてくれるのはありがたい。
「あ、伊地知くん、お帰り!」
「あれ、さん。まだ残ってたんですか?」
教室に足を踏み入れると、とっくに寮へ戻っているだろうと思っていた同級生。しかし教室にいたのは彼女一人、ではなかった。
机に座っているを囲むように、四年生の術師たちがいたのだ。彼らは伊地知も良く知っている。
以前、何度か四年の任務を手伝ったことがあり、それ以来を気に入って何かと絡んでくる先輩達だった。
しかし本人は気づいていないのか、単に可愛がってくれる先輩と思っているようで、今も「先輩達から差し入れもらったの」と言って素直に喜んでいる。
「ちゃん、体調不良で任務休んで座学してるって聞いてさあ。一人で居残りは暇だと思って来たんだ」
「そうですか」
そう返しながらも、伊地知は先輩の一人が馴れ馴れしくの肩を抱いて「貧血大丈夫?」などと話しかけてる姿をジト目で見ていた。
男女のことは疎い伊地知でも分かる程度に下心が見え見えなのだ。出来れば注意したいところだが、当事者のが気づいていないので変に波風を立てるのはどうかと思い、いつも見て見ぬふりをしてしまう。
仕方ないと思いつつ、報告書をまとめてしまおうと自分の席へ座ると、それを見たが伊地知の方へ声をかけた。
「今日、数多かったでしょ……ごめんね、伊地知くん」
「いえ。気にしないで下さい。これくらい私だけでも大丈夫でしたから」
任務を休むことにが罪悪感を持たないよう、伊地知も笑顔で力こぶを作ってみせる。
前回、と一緒に行った任務先で彼女がおかしな呪霊に襲撃された件も踏まえ。その後の五条の様子といい、さすがに伊地知も薄々はおかしいなと思っているのだが、何か事情を話せない訳でもあるんだろう、と気づかないふりをしていた。
自分が家入にのことを頼んだ以上、そこは見守るしかないし、話せる内容ならば、とっくにの方から話してくれているはずだという確信もある。
は数少ない伊地知の理解者であり、大切な仲間だ。もし彼女の身に何かが起こっていたとして、それを自分に話すことがの負担になるなら、自分は蚊帳の外でもいいと思っていた。
だが、しかし――。
「ちゃん、手ちっさいねー」
「え、そうですか?」
「口もちっちゃいし可愛いー。あ、ここ、プリンついてる」
「え?ど、どこですか?」
「俺が拭いてやろうか?」
――このセクハラまがいな先輩達の行為はやはり許せない。
「あ、あの……!」
彼氏でもないくせにベタベタしすぎだ。そう思った伊地知は咄嗟に声をかけてしまった。
「え?あ、伊地知くんもこれ食べる?」
先輩の一人がに差し入れたらしいプリンを伊地知へ差し出す。そんなものは突っ返してやろうと思った――。
「あ、いいんですか?すみません」
――のだが、結局は長いものに巻かれる伊地知。
だが、その時。プリンを差し出す男の手を、横からヌっと伸びて来た手が掴んだ。
「これは僕がもらっておくよ」
「ごっ五条さん……?」
四年の男は自分の手を掴んでいる存在を見て目玉が飛び出そうなほどに驚いている。彼らにとって特級呪術師である五条悟は雲の上の存在だからだ。
五条はプリンを横から搔っ攫い、かつサングラスをズラすと、今度はにベタベタしていた男の方へ、その輝く碧眼を向けた。そして何を思ったのか、ぽかんと自分を見上げているの腕を引き寄せると、四年の男に「この子、男慣れしてないからベタベタ触るの禁止ね」とニッコリ微笑む。ただし目は笑っていない。
「次、同じ光景を見かけたら……分かるよな?オマエ達」
「す……すみませんっしたー!」
「失礼しやっす!」
五条の垂れ流す殺気交じりの圧を肌で感じたらしい男達はパっとから離れると、机にぶつかりガタガタ音をさせながら三年の教室を飛び出していく。しかもその途中、伊地知を睨みつけると「彼女が五条さんのお気に入りってこと先に教えとけよっ」と小声でしっかり捨て台詞を残して行った。
何のことか分からず唖然としたまま見送っていた伊地知は、ふと視線を二人へ戻す。
逃げ出した後輩への興味は失せたのか、五条はの頭へ手を乗せながら、何故か説教を始めていた。
「オマエもヘラヘラしてないで、ちゃんと距離を保って接しろよ。ああいう男どもの中に例の奴がいるかもしれないんだし、いくら高専の先輩だからって油断しちゃダメでしょ」
「あ……そ、そうですよね!ごめんなさい、五条先輩……」
「う、い、いや……別に怒ったわけじゃないし……」
しゅん、と俯いたを見て、五条も若干の動揺を見せた。
二人の会話の内容はよく分からないにしろ、その光景をジっと眺めていた伊地知の顏が、ムンクの叫びの如く変形していく。
普段は辛辣で、どちらかと言えば怖い印象のある五条だが、今は焦った様子で落ち込むを宥めていたからだ。
(こ……こんな五条さん、初めて見た――!)
まさに伊地知の心境はそれ一択。
その時だった。不意に存在を思い出したらしい。五条の視線が伊地知へと向いた時、恐怖でちょっとだけ鼻水が垂れた。
「伊地知~。オマエも気が付いてたなら早く止めろよ」
「は……はいぃっすみませんんっ!」
何故か分からないが自分まで説教されている。
理由はよく分からないものの、そこは素直に謝罪しておいた。だって怖いから。
五条の辛辣な言葉の数々は、時に伊地知のお豆腐メンタルをぐちゃぐちゃに潰して掻き混ぜて麻婆豆腐のように炒めてしまうほどの威力があるのだ。それもマイルドな北京風ではなく、ガチガチに辛い四川風に仕上がるのだから、ヘタレな伊地知にはたまらない。
触らぬ五条に祟りなし――。
伊地知の密かな座右の銘になりつつある。
なのに――。
「ああ、それと……伊地知に聞きたいことがあるんだけど、ちょっといい?」
「……へ?」
このあと、触りたくもない五条に連行された伊地知であった。
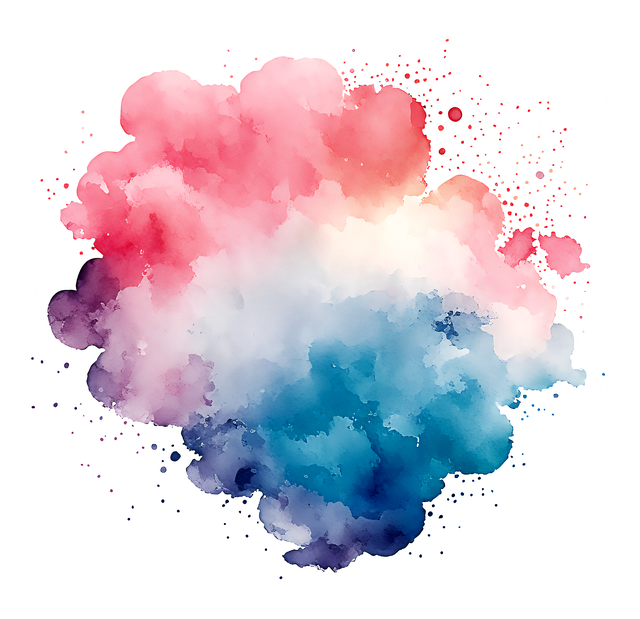
「そっかぁ。常に一緒に行動してた伊地知も分かんなかったか」
五条からの報告を受けた家入は、これまで炙り出した怪しい人物リストを眺めながら、五条に差し入れで貰ったマカロンを口へ放り込んだ。徹夜明けは甘い物がやけに美味しい。
「でもいいの?伊地知にストーカーの件、話しちゃって」
高専内にある食堂。向かい側に座る五条とを交互に眺めつつ、家入は訊ねた。
「仕方ないだろ。それにアイツも薄々何かあるとは感じてたみたいだし。それに話したのはストーカーがいるかもしれないって話だけだから。にも承諾を得てる」
「そーなの?」
家入がへ尋ねると、彼女も小さく頷いた。
「はい……。伊地知くんには呪霊に襲われてるとこ見られてるし、突発的な事故と思ってたとしても任務を休んでる以上、長くは誤魔化せないと思って……それにわたしが気づかなかったことでも伊地知くんは気づいてることもあるんじゃないかと」
「でも空振りだったわけだ」
「はい。伊地知くんも任務先で知り合った人の中でおかしな行動をしてた人には心当たりがないって」
「じゃあ、このリストの中にはいないってことかー」
再びリストを眺めながら、家入が溜息を吐く。
手がかりがない以上、これまでが関わった任務を片っ端から調べ、関わった人物を洗い出したのだが、一人ひとり当たるには人数も多すぎる。
そこで五条はと一緒の任務に出ていた伊地知へ目を付けたのだ。
「まあ、一緒に行動をしてた伊地知なら……って思ったけど、そんな分かりやすいことはしないか」
家入の手からリストを奪った五条も、溜息交じりで書かれた名前を眺める。
「たださあ。コイツらはと関わったって言っても一日やそこらだろ。何か僕的にはしっくりこないんだよねー」
あれほど執拗なマーキングをする呪いが育つほど、に対して執着する人物なら、それなりに長く関わっているんじゃないかと五条は思い始めていた。
ただ、それがどういった人物なのかまでは思い当たらない。
「さっきにちょっかいかけてた四年の奴らからは、それほどの執着は感じなかったし……」
言いながらちらっとへ視線を向けると、彼女は気まずそうに目を伏せた。彼女としては彼らを親切な先輩としか思ってなかったようで、そこは五条の心配が的中した形だ。
もしかしたら五条が知らないだけで、ああいう類が高専内にまだいるのかも、と思ってしまう。
そうなると五条も例のモヤモヤが復活してきた。
「さっきも言ったけどさ。も少しは男という生き物を警戒して」
「え……」
「オマエは無防備すぎなの。それに隙もありすぎ」
「う……は、はい……」
指で額をとん、と押され、はドキっとしつつ再び項垂れた。
言われてみれば、ちょっと親切にされたりすると、すぐにいい人判定をしてしまい、懐いてしまう自覚はある。
「ごめんなさい……五条先輩」
「別に……そこまで落ちることはない……ってかマカロン食っとけ、オマエは」
「まあまあ……素直で優しいのはのいいとこでもあるんだから。まあ、そういう子に男は弱いし、モテるのは悪いことじゃないでしょーが」
「……そんなの硝子に言われなくても分かってるよ。でもそれが原因で変態に狙われたのかもしれないんだし、男に隙を見せないに越したことないだろ」
五条は不機嫌そうにそっぽを向く。その反応を見ていた家入は、おやあ?と首を傾げた。
何となく「これ以上、他の男に隙を見せて欲しくない」オーラが駄々洩れてるように感じたからだ。
「ふーん」
「あ?何だよ、そのキモい顔は」
何となく落ち込んでしまったにマカロンを食べさせていた五条は、にんまりと笑みを浮かべた家入に気づき、口元を引きつらせる。だけがその空気を読めず、美味しそうにマカロンを頬張っていた。
「別にー。何か距離が近くなったなぁと思っただけ」
「は?」
「マカロンあーんしてあげたり、二人とも何かいい雰囲気だし?」
「……」
「……」
交互に二人を指さし、家入がニッコリ微笑むと、五条との頬がかすかに赤くなる。
「何、下らないこと言ってんだよ。硝子の冗談に付き合ってる暇ないから――」
と言いかけた時、五条のスマホが鳴った。
軽く舌打ちしながら電話に出た五条は「今から?」と徐に顔をしかめている。どうやら緊急任務が入ったらしい。
「はいはい。分かった。じゃあ車まわしといて」
言いながら唐突に立ち上がった五条は「八王子で任務入ったし、行くわ」と、最後に自分もマカロンを口へ咥える。
ついでにの頭を軽く撫でると「さっき言ったこと忘れるなよ」と言い残し、食堂を出て行った。
「何あれ。彼氏かよ」
と家入は笑ったのだが、五条の背中を見送っていたの表情がやけに嬉しそうで、家入のアンテナがまたしてもピコンと反応する。
「な、何ですか……硝子先輩……」
頬杖をつき、ニヤける家入の視線にが気づく。その頬は薄っすらと赤い。本人に自覚があるのか、それとも無意識なのかは分からないが、家入は何となくこう思った。
「意識するのは分かるけど……なるべくなら五条はやめといた方がいいと思うよ」
良くも悪くも、の情緒を破壊しかねない。
そう思った先輩からの、的確なアドバイスだった。
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
