11-あんなことくらいで
少しだけ開いた窓から心地良い涼風が頬を撫でていき、はふと資料を捲る手を止めた。
山に囲まれている高専では時折爽やかな山風が吹く。この長く続く残暑の終わりが近いことを示しているようだった。
窓の方へ視線を向ければ木々のざわめく音に交じり、蜩のカナカナカナ……という鳴き声が聞こえてくる。夏と秋の狭間である今時期に聞かれるその声は、どことなく物悲しい。
――意識するのは分かるけど……なるべくなら五条はやめといた方がいいと思うよ。
家入に言われた言葉が何度となく頭に浮かび、は資料を閉じて溜息を吐いた。先ほどから全く集中できていない。
ストーカーの件もあり、今は毎日のように教室で座学に励んでいるのだが、三年の彼女からしてみれば今更新しく覚えるようなものはそれほど多くないのも集中できない理由の一つだろう。
そしてそれ以外の理由としては――先の家入の言葉のせいかもしれない。
何度なく考えてしまうのは五条のことだった。
意識をしている自覚はあった。憧れの先輩とあんなことがあったのだから、そこは仕方ないと思う。だからこそ余計に今まで通りに接しなくては、と頑張って五条の前では平静を保っている。でもそう思えば思うほど、おかしなドキドキが生まれてきてしまうのだから嫌になる。顔を見ただけで、頭を撫でられるだけで、あの時の触れられた感触まで蘇ってくるせいだ。
なのに五条の方は意外なほど普通に――いや、前より素っ気ない態度の方が多くなった気もする。視線もあまり合わせてくれないことが増えて、そのことがやけに悲しかった。
まだ生徒とはいえ、呪術師という立場にありながら呪われたあげく、呪霊に襲われマーキングまでされた後輩に、あの厳しい五条が見切りをつけてもおかしくはない。
伊地知に「呪術師は向いてない」と言ったように、そのうち自分も言われてしまうんじゃないか、という不安がつきまとう。
しかし一番の不安は別のところにあるのもは分かっていた。
呪術師とか後輩として、というより、女として幻滅されてしまったんじゃないか。
少なくとも今、自分が気にしてるのはそこなのだという自覚があった。
「……はっ。何考えてるの、わたしってば」
思わず独り言ちてぶんぶんと頭を振る。
五条に女として幻滅されたから何だと言うんだろう。憧れてはいたけど、それは恋愛感情と違うはず。だいたい今はそんなことを考えてる場合じゃないのに――。
――オマエのせいでこうなってんの。僕も一応、男なんで。
頭にあの時の五条の言葉が蘇り、カッと頬が熱くなった。硬いものが体に触れた感触まで思い出すともうダメだった。考えるな、と思えば思うほど五条の顏や声が頭に浮かんでくる。
邪念を振り払うべく、は自身の頬を両手でぱちんっと叩き、椅子から立ち上がった。
「ダメだ……集中力ゼロ。ちょっと外の空気でも吸ってこよ」
ただ座って教科書や過去の資料を読み漁るだけの時間すら苦痛になってきたのもあり、気分転換に少しその辺を散歩でもしようと教室を出た。
午前11時になるこの時間帯は彼女の学年も含め、殆どの高専生は任務で出払っている。校内に残っているのは事務関係者と色々な手続きや申請作業をしている補助監督くらいだ。
校舎を出て広い敷地を歩いていると、時々顔見知りの補助監督と会うので、は軽く立ち話をしたり、挨拶をしたりしながら自販機のある場所までやってきた。
「あ、新しくなってる」
自販機にずらりと並ぶドリンクをみていたら、ふと気づいた。
先日までのメニューとは明らかに違う商品がある。
高専内に設置されている自販機は特定の業者のもので、依頼、管理などは補助監督が賄ってくれていた。
使用する関係者たちが飽きないよう、リクエストがあれば定期的にドリンクの種類を変更したり増やしたりするのも補助監督の仕事なんだ、と前に伊地知が話していたことを思い出す。
五条に言われて補助監督を目指すと決めたせいか、伊地知は今のうちから業務内容を把握しているらしい。
それらを伊地知に教えてるのが三年の補助を担当をしている渡久山だというのも知っていた。
「え、アイスティーもあるんだ」
紅茶好きのは見慣れない缶を見つけて思わず顔を綻ばせた。
普通の自販機だとミルクティーはあれど、ノーマルの紅茶は置いてないものが多い。
「しかも110円って他のより安い」
同じサイズの缶なのに何でだろ、と少し味的に不安を覚えたのだが、さっぱりアイスティーという名前に惹かれた。定番の甘い紅茶より、どちらかと言えばすっきりした味の方が好みの彼女からすれば、地味に購買意欲をそそられる。
だが、早速買ってみようと小銭入れをスカートのポケットから出そうとした時だった。誰かの視線を背中に感じてぎくりとした。手から小銭入れが落ちる。じっとりと観察するようなその視線は、以前にも感じたことのあるものだった。
(嘘……何でまた……)
例の呪霊が出現する前、この視線を常に感じていたことを思い出し、自然と体が震えてくる。
その時――不意に肩をぽんと叩かれたことで、「ひゃぁ!」という声が漏れてしまった。
「えっと……さん、私です」
「……あ、な、七海先輩」
その声に驚いて振り返ると、そこには一つ上の先輩、七海建人が苦笑交じりで立っている。その知った顔にホっとした瞬間、足の力が抜けてしまった。
「ちょ、そんな驚かなくても」
しゃがみこんでしまったに驚き、七海も慌ててしゃがむ。ついでに落ちていた小銭入れを拾い、彼女へ渡した。
「すみません。そこまで驚くとは思わなくて」
七海としては自販機の前にボーっと立っていた後輩を見かけ、普通に声をかけようとしただけ。
だが肩に手を置いた瞬間、叫ばれて驚いたのは七海も同じだった。
「い、いえ……わたしの方こそ、すみませんでした」
「何かあったんですか?顔色が悪い」
「……べ、別に何も。暑さでボーっとしちゃって」
「大丈夫ですか?保健室へ――」
と七海が彼女を支えるため背中へ手を回そうとした時だった。後ろから伸びて来た腕が七海の首へ回り、ガシっと捕えられる。その強さに思わず「ぐえ」と変な声が漏れた。背後に迫っている気配は感じていたものの、まさか首を絞められるとは思わない。
「なーなーみー。オマエ、と何してんだよ」
「……はぁ。やっぱり五条さんでしたか」
「ご……五条先輩っ」
が顔を上げると、そこには背後から七海の首をホールドしている五条がいた。
「別に何も――放して下さい」
五条も本気じゃなかったらしい。七海がその腕を払うと拘束はあっさりと解かれた。
「いきなり何をしてくれてるんですか、五条さん」
「悲鳴が聞こえたからオマエがコイツに何かしたのかなーと思っただけ」
「ハァ?何かって何です?」
「ち、違うんです。わたしが大げさに驚いただけで――」
何か誤解をさせたらしいと気づいたが慌てて説明すると、五条は「何だ、そういうことね」と苦笑いを浮かべた。
「ま、七海に限っては……ないか」
「……だから何がです?」
事情の分からない七海だけが不満げに目を細めたが、は五条が何を疑っているのか何となく分かった。
それにこんな時間に五条がいるのもおかしい。
特級呪術師の五条は常に多忙を極めていて、昼間から高専にいることじたい殆どないからだ。
「いや、ってか七海は何でいるワケ。任務は?」
「今日は一件だけでしたので、朝一で終わらせて今さっき戻ったとこです。そしたら彼女を見かけて」
「あっそ」
「五条さんこそ。珍しいですね。こんな時間にいるなんて」
七海もと同じことを思ったらしい。絞められた首を擦りながらジト目を向けた。
五条はサングラスをズラすと「僕も七海と似たようなもん」とだけ説明してから、ふとへ視線を移す。彼女の様子がおかしいのは一目で分かった。
七海も今の五条の説明で納得したわけではないものの、自分は部外者らしいと空気を読んで立ち上がる。
「では私は報告書を書かないといけないので」
「おー。悪かったな、七海」
五条も言いながら立ち上がる。七海は意外そうな顔をしたものの、何を言うでもなく静かに校舎の中へと歩いて行った。
それを見送りつつ、五条はへ「立てる?」と手を差し出す。未だしゃがんだ状態のはどうにか笑顔で頷くと、五条の手をおずおずと掴んだ。その瞬間、勢いよく引っ張られる。
風が動いてかすかに五条からお香のような甘い香りがした。思えば治療の間ずっと嗅いでた香りで、自然と頬が熱くなる。
「ん、少し顔色戻ったようだね」
「え……?」
何のことかと顔を上げれば、五条はの頬を手ですり、と撫でていく。その感触に心臓がいち早く反応してしまったのは、前にも触れられた記憶が過ぎったせいだ。
五条は何かを察したようにズラしたサングラスを元へ戻し、の頬から手を放した。
「さっき顔色悪かったから。何かあった?七海にまで驚いてたようだけど」
「あ……あれはボーっとしてたわたしが悪くて……突然肩を叩かれて驚いただけです」
「ああ、そういうことか。――で、何でボーっとしてたの」
納得したように頷いた五条に問われ、は言おうかどうか迷ったものの、さっき感じた視線のことを打ち明けることにした。
「え、えっと……さっき突然誰かの視線を感じた気がして――」
「視線?」
「前にもあったんです。呪霊がわたしの前に現れる少し前に、誰かから見られてるような気配と言うか……」
最初は気のせいかと思っていた。でもそのうち明らかに見られてる感覚が強くなり、そうこうしている間に例の呪霊が現れたのだ。
五条にはそこまで詳しく話していなかったのを思い出し、今回はきちんと説明しておく。でなければ不安でどうにかなりそうだった。あの呪霊がまた現れるのでは、と思うだけで指先が冷えていく。
「なるほどね……前触れはあったわけか」
「はい。でも……ここは高専の敷地内なのに何で……」
以前は任務中などによく視線を感じていたのだが、高専でそれを感じたのは初めてだった。だから余計に怖くなったのかもしれない。安心していたところへ、音もなく誰かが忍び寄って来るような不気味さを感じる。
その時、五条がふと「やっぱりな……」と呟いた。
「僕の予想は当たってるのかも」
「え……?」
何のことかとは目を瞬かせたのを見て、五条は溜息を一つ吐いた。
「もしかしたら……のストーカーは高専関係者かもしれない」
まさか、と思うような言葉を聞いて、の思考が一時固まってしまった。
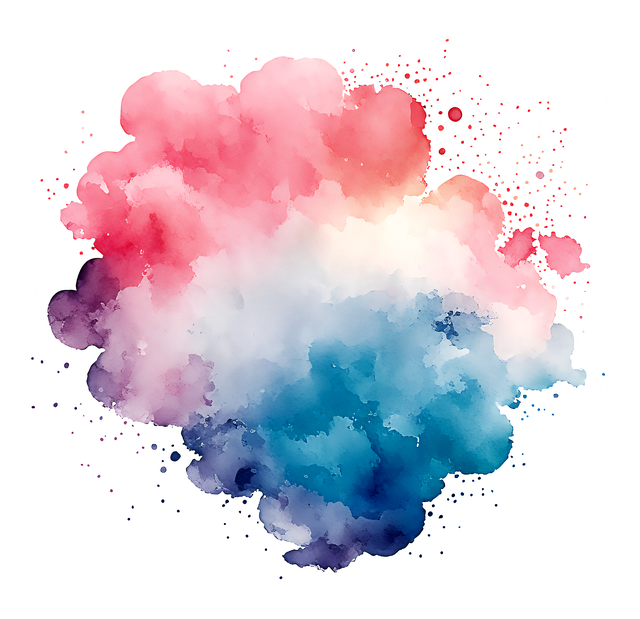
この日、五条はにも内緒で彼女を見張っていた。もちろん気配を悟られないよう、なるべく離れた場所――最上階にある資料室で。
ここ最近の任務は前倒しで終わらせ、高専側にはよほどの案件じゃない限り、任務は他の術師へ頼むよう促すのも忘れなかった。
五条が行けば秒で終わる任務も多く、そういう二級相手の任務であれば、他の術師に経験を積ませる為に回した方がいいと嘯いて。
おかげで昨日から五条は実質夏休み状態だ。
といっても遊んでるわけではなく、きちんとの周りをさりげなくではあるが探っていた。
彼女に話しかける男がいればよく観察をして、先日のようにセクハラまがいなことをする男がいないかどうかをチェックする。
例の四年の男達は五条の威嚇に心底ビビったらしい。その後はと顔を合わせてもそそくさと逃げていくようだった。
安心したところで、本命のストーカーではないと四年の男達は除外しておく。
「しっかしの奴……こう見るとかなり男どもに人気があるな」
ストーカーを絞る為、ノートに怪しい人物の名を書きこんでいた五条だったが、の周りをうろつくのが男ばかりという点にイラっとしていた。
もともと高専に女子生徒は少ない。それが理由もあるだろうが、は器量よしばかりでなく、術師にしては素直で可愛らしい性格も相まって、密かにファンも多いらしい。
この前、伊地知にストーカーの件を話した際、そう教えられた五条は何となく面白くなかった。
つい伊地知に「まさかオマエもが好きなわけ」と突っ込んでしまうくらいには。
「い、いえ!私はさんのこと大事な仲間と思ってます。でも恋愛感情では……私はどちらかといえば年上で色っぽい人が好みです」
キリ、とした顔で言い放つ伊地知に「別にオマエの好みはどうでもいい」と返しつつ、内心ホっとした自分がいることに五条は驚いた。
出来れば自分以外の男を視界に入れて欲しくない、なんて独占欲丸出しで、自分に苦笑が洩れる。
あの治療と称した行為以降、と顏を合わせるたび意識してしまう自分が嫌で、つい素っ気なく接してしまっていた。
「あんなことくらいで……」
と自嘲しつつ、あんなことくらいで済まない感情が芽生えていることを自覚する。
だからこそ、任務を投げ出してでも早く彼女の脅威を取り除いてやりたいのだと。
(任務先で知り合った人間も不発。に近しい人物も怪しいところは見つからなかった。これだけ調べても容疑者が浮上してこないというなら、もうこれは……)
下の教室で座学をしているの気配を探りつつ、五条はノートを見下ろした。そこに書かれていないのは高専関係者だけという結論に至る。
「ハァ……。一番あって欲しくなかったパターンだな、こりゃ」
ガシガシと頭を掻きつつ、独り言ちる。
よりによって高専関係者がストーカーなどあってはならない。しかも呪霊を生み出してしまうほどの劣情を抱いている、ということは当然、術師ではないという答えに行きついてしまう。
「……事務関係者か、補助監督。あとは……"窓"か」
呪力をコントロール出来る呪術師から呪霊は生まれない。
となると、そこまでに満たない未熟な人物が犯人かもしれないと五条は考えていた。
その時――五条の張り巡らせていた網に何かがかかった。
「……?」
意識を集中しての呪力を探れば、いつの間にか元いた場所から移動している。
彼女の気配を真下にある自販機近くに感じた五条は、すぐに資料室の窓から飛び出した。
彼女に近づいている人物の気配も感じ取ったからだ。だがその瞬間――「ひゃぁぁ」というの悲鳴を聞いて、五条の心臓が大きな音を立てた。
もちろん五条とて後輩の七海がストーカーだと思ったわけじゃない。
ただ怯えて蹲っているの体へ七海が触れようとしているのを見た時、着地と同時に走りだしていた。ついでに首を絞めたのは、まあ悪ふざけでもあったのだが――。
おかげで更に面倒な先輩だと思われたらしい。
怪訝そうな顔を隠しもせず、校舎に入って行く七海を見送っていた五条は「やりすぎたかな」と苦笑を漏らした。
ただの顔色が悪いことも気になり、何があったのかと事情を聞けば案の定だった。
「もしかしたら……のストーカーは高専関係者かもしれない」
怖がらせるつもりでそんなことを言ったわけじゃない。だけど知らないよりは知っていた方が警戒してもらえる。五条はそう考えた。
「ま、まさか……」
「でも同じ視線を感じたんでしょ?それにあり得なくもない話だし」
動揺するを見て、ハッキリ言いすぎたかとは思ったのだが、ここは隠していても危険なだけだ。
「オマエも狙われてるってことを自覚して警戒しろ。僕や伊地知以外の男は全員警戒するくらいの気持ちでいて」
若干、私情が入った感はあれど、とりあえずそう言い放つと、の目にじわりと涙が浮かぶ。
その頼りなさげな泣き顔は反則だろ、と五条はこっそり溜息を吐く。
せっかく突き放してるというのに、その努力が無駄になりそうなほど、胸の奥がぎゅうっと締め付けられてしまったせいだ。
ほんの少し手を伸ばせば抱きしめられるのに――。
そう思いながら、伸ばしかけた手を強く握りしめた。
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
