12-信じられないだけだから
せっかく気持ちのいい陽気も地下へ潜れば台なしだな。
すっかり温くなった激甘の缶コーヒーを口にしながら背もたれに頭を預けると、天井で煌々と部屋を照らす蛍光灯を見上げる。五条の口から何度目かの深い溜息が洩れたのは無意識だった。
「ちょっと五条」
重苦しいその溜息が気に障ったらしい。それまで黙々とパソコン作業をしていた家入は、キャスター付きの椅子をぐるりと回転させた。普段はくりっとした可愛らしい瞳も、今は半分にまで縮小され五条を睨んでいる。
これ以上、作業の邪魔をしてくれるな、という苛立ちがありありと現れていた。
「ここは相談センターでもないし、私は相談員でもないから」
「別に何も言ってないよね、僕」
「でも言いたそうな空気を出してるでしょーが」
「え、そう?僕はただ、早く関係者の素行を調べて欲しいなーと思って待ってるだけだけど」
シレっとした顔で言う五条の態度に、家入は手にしたカップを投げつけてやりたい心境だった。
突然やって来たかと思えば「高専関係者の過去の素行データを調べて欲しい」と言われ、専門でもないのにデータへアクセスしようと頑張っている。なのに頼んできた相手がやる気のない溜息ばかりを吐いてるのだから、家入としては文句の一つも言いたくなるのは当然だ。
「だいたい高専の関係者の中にストーカーがいるってマジなのそれ」
「うん、多分」
「たぶんん゛~~っ?」
「ってか、それを調べたいから硝子に頼んでんだろ」
額をピクピクさせる硝子を呆れ顔で見ながら言い放つ五条に、家入は過去何度も言ってきた「クズ」という二文字をぶつけ、机の上に置いてある煙草へと手を伸ばす。
苛立った時の家入の癒しと言えば、悔しいかな、煙草しかないのが現状だ。
学生時代から「五条よりも最強の男と付き合ってクズの性根を叩き直してもらう」という野望はあったものの、未だに叶えられていない。
カチッとライターの音がして、ふわりと煙草独特の香りが室内に広がった。未成年だった昔とは違い、今は堂々と吸える年齢に達したことで、最近は校内でも喫煙タイムを楽しむことができるのは幸いだ。
「そもそもの話。高専関係者のデータと一口に言っても、私が見られるのはせいぜい健康診断の結果くらいだし、素行調査のデータはまた別口だよ」
国が、というよりは呪術界総本部が牛耳るこの世界は、当然働く者も厳選されている。
高専関係者ならば入学時や就職時にほぼ個人データが揃い、身元もハッキリしてるのでその後に詳しい調査は行われない。ただし問題行動を起こした人間の素行調査となると、これまた別案件だった。
「だいたい素行調査を受けた人間が今も高専で働いてるとは考えにくいし、もし今回の件が初めての犯行なら、過去に調査対象すらなってないかもしれないでしょ」
「それは調べてみないと分からない。人を殺したとかならそうかもしれないけど、上層部が小さな案件だと思ったなら、クビにしなかった可能性だってある……ってか、タバコ吸うなら換気くらいしろよ」
紫煙をふぅーと吹きかけられた五条は、徐に顔をしかめて手を左右にぱたぱたと動かす。
それでもお構いなしに家入は煙草の煙を吹かした。
「ここは私の部屋なんだし指図される覚えはないわ。嫌なら出てけばー」
「……ハァ。やっぱ呪術師の女は可愛くない」
「あ゛?」
「いや、違うな。同じ呪術師でもとは大違い――」
と言った五条の方へ、何かが凄い勢いで飛んできた。それはオートにしたままの五条の術式に弾かれ、足元へカシャンと落ちる。どうやら家入の使用していたライターらしい。
「もの投げんなって」
「文句あるなら出てけ」
「えー。調べるの手伝ってよ。は可愛い後輩なんだろ?」
「ぐ……っ」
家入もそこを突かれると痛い。早くストーカーを捕まえたいのは家入も同じ気持ちだからだ。
「……ったく。だったら少しは謙虚な態度でいろっての」
「何か言った?」
「別に!っていうか、そのはどうしたの?さっきまで見張ってたんでしょ」
「あー……とりあえず教室に戻るって。もうすぐ伊地知も戻るみたいだし、高専内じゃ万が一ストーカーがいたとしても無茶なことはしないだろ。念のため、また異変を感じたなら速攻で電話するようには言ってある……って、何その顏」
ふと顔を上げれば、家入がさっきと打って変わり、今はニタニタと不気味な笑みを浮かべていた。
「別にぃ。ってか、その後どうよ」
「どうって?」
「と何か進展あった?いや、アンタのその様子じゃないか」
「あ?」
「さっきまで溜息ばっかだったもんねー」
矢継ぎ早に飛んでくる言葉の刃に、五条の表情が険しくなっていく。今はあまり触れて欲しくはない内容だった。
「だから何だよ。ってか進展って別に僕とはそんなんじゃないし」
「ふぅん?」
「何だよ、その顏」
「ハァ。素直じゃないねー。相変わらず」
「は?何が」
と言ったところで、家入とは付き合いも長い。自分でもよく分からない心の内を、家入は何となく察してるような気がした。どんなに惚けても、自分の意志とは別のところで生まれてきてしまったものを簡単に消すことも出来ない。
「まあ、私の頼んだ件がキッカケになったんなら責任もあるし、相談くらいは乗ってやってもいいよ」
「……だから何の――」
「意識、しちゃってるんでしょ?五条も」
「……僕、も?」
何とも都合の良い幻聴が聞こえた気がした。入り方が間違えてるから自分でも認めたくはなかったはずなのに、もう誤魔化せないところまできてることは、五条も薄々気づいている。その初めての感覚は戸惑うばかりで、どう応えて良いのかも分からない。そんな五条の反応を見ていた家入は「気づいてないんだ」と軽く笑って煙草を灰皿へ押し付けた。
「もアンタのこと意識してるようだったから、五条だけはやめとけって言っておいたんだけどね」
「……って言うな、そういうこと!」
五条のツッコミに家入が笑う。とことん同級生をからかって楽しむつもりらしい。
でも家入が可愛い後輩にそう忠告したくなる気持ちも分かっている。過去の自分は確かに女の子と誠実とは無縁のような付き合い方をしてきた。五条も家入の立場だったならば同じことを言っただろう。それに――。
「もしが僕を意識してたとしても、それはあんなことがあったからで、別に僕への好意があるからとかじゃないでしょ」
「どうかな。もともとアンタに憧れてたって話だし」
「……え?」
「それが例え異性としてじゃなく術師としての感情だったとしても、くらいの年頃ならそれだけで十分な理由になるんじゃない?」
ま、アンタはあの行為がキッカケとは認めたくなくてを突き放してんだろうけど、と家入は苦笑交じりで肩を竦めた。とことん勘の鋭い嫌味な同級生だと苦々しく思う。
ただ、がどこまで自分を意識してるかは分からないが、彼女のそれは一時のものでしかない。恋人でもない男に自分の秘めた部分を曝け出したのだから、五条を男として意識してしまう気持ちは理解できる。だが、そのあとに生まれたものが愛情とは限らない――。
「何かゴチャゴチャ考えてるようだけど、先輩だからーとか後輩だからーなんて面倒なことは考えずに、一度くらい素直になってみたら?」
「……いちいちうるさいよ、硝子」
出来ることなら面倒な思考なんてすべて無視して突っ走れば楽なのかもしれない。だけど――。
「僕は自分のことが信じられないだけだから」
「ああ……なるほど」
これまで異性に対して、そこまで真剣に向き合ってこれなかったのは自分が一番分かっている。なのに一時の想いで後輩に手を出すのは、さすがに五条でも出来なかった。
なのに他の男が彼女に近づくたび、イライラしてしまうんだから矛盾してる、とは思う。
「ハァ……アンタも少しは大人になったと思ったけど、女の子のことに関しちゃまだまだガキだねぇ」
「うるせぇな。二年やそこらで変わるかよ」
「あ、また口悪くなってる」
「……チッ」
家入のツッコミに舌打ちで返しつつ、五条はケータイを取り出した。
「誰に電話すんの」
「伊地知ー。もうそろそろ帰ってくるらしいし。アイツにもデータ探すの手伝わせる。パソコン詳しいらしいし」
「まーた後輩をアゴで使うのか」
「あ、伊地知ー? オマエ、今どこ。え? もう校舎にいる? んじゃーちょっと地下に下りて来いよ。そう、医務室あるとこ。硝子がオマエにどうしても頼みたいことがあるの……って言ってるから。ほら例のストーカー案件でさぁ――」
「……ちょ、人の名前使うなっ」
適当なことを言いながら家入をダシにしている五条を蹴飛ばしてみても、邪魔な無限に阻まれ、今度は彼女の口から舌打ちが出る。
あげく電話を切った五条は満面の笑みで振り向き「今すぐ来るって」とピースしてみせた。完全なる詐欺罪かもしれない。
「もう……伊地知くんを何だと思ってんの」
「よく出来た使えるコーハイ」
呆れ顔の家入に対し、五条はヌケヌケと言いのけた。
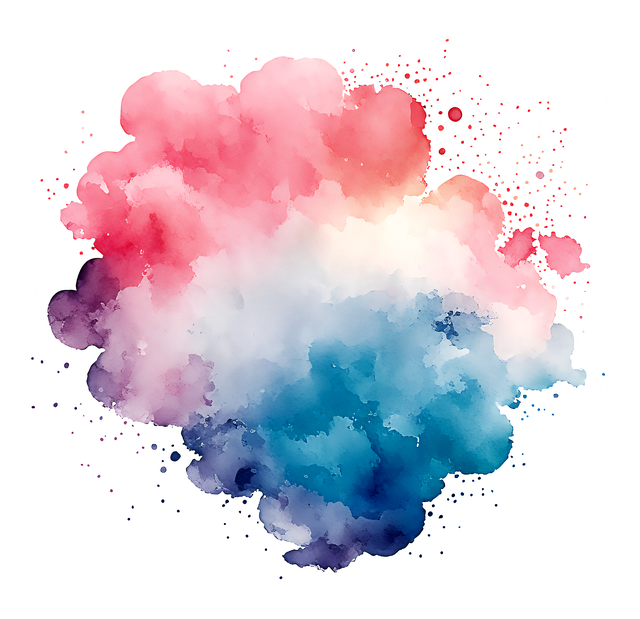
「ちょ、ちょっと私、行かないと」
任務の報告書を書こうと教室に向かっていた伊地知は、五条との通話を終えて顔が緩むのを隠すように咳払いをしながら足を止めた。
五条からの着信に気づいてげんなりしつつ出たのだが、まさか家入から頼まれ事をするなんて、と一気にウキウキしてくる。我ながらなんて単純なんだとは思うが、憧れの家入から頼られたとあれば、どんなに疲れていても駆けつけなければと思った。
「どうしたんです?」
浮かれた様子の伊地知に気づき、任務に同行していた補助監督の渡久山も足を止めて振り返る。渡久山も任務後の雑用をする為、事務室に向かっていたところだ。
「今、ストーカーがどうとか言ってましたけど」
「えっ? あ、い、いえ……何でもありません。えっと五条先輩から呼び出されまして……任務報告書はあとでキッチリ出しておくので行ってもかまいませんか?」
「五条術師に? それはかまいませんけど……何か僕に手伝えることは?」
「え」
渡久山の申し出をありがたい、と思いつつ、ふと五条の最後の言葉を思い出す。
『絶対、誰にも言うな。特に補助監や事務の奴らには』
理由は分からないが五条に言われた以上、守らなければどんな目に合わせられるのか分からない。伊地知はごくりと喉を鳴らし、ぶんぶんと頭を振った。若干クラっとしたが。
「い、いえ。これは内密にとのことなので私だけで行きます」
「内密……? そう、ですか。分かりました」
キリッと眼鏡を直しつつ応える伊地知を怪訝そうに見ていた渡久山だったが、最後は笑顔で頷いた。特級呪術師である五条悟が言うのであれば仕方ないといった顔だ。
「よく分かりませんが頑張って下さいね。あと報告書は明日までにお願いします。その他諸々は僕が片付けておくので」
「はあ、すみません。私から頼んだことなのに」
今日も渡久山から補助監督の業務について教わる予定だった伊地知は、心から申し訳なさそうに頭を下げた。
「いえいえ。僕の指導なんていつでも出来るんだし、また次の機会にでも。それじゃ」
穏やかな笑みを浮かべた渡久山はのんびりと事務室へと歩いて行く。その背中に向かってもう一度頭を下げた伊地知はくるりと踵を翻して、五条の言う地下へと走った。
「家入さん、私にどんな頼み事をしてくれるんだろう」
スキップでもしそうなほど軽やかな足取りで走りながら、ついつい鼻歌を歌ってしまう程度に伊地知は浮かれていた。
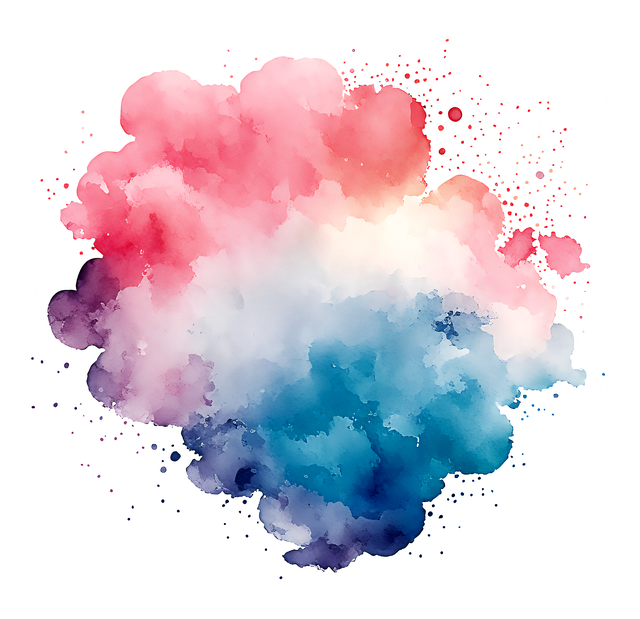
一方、『そろそろ着きます』というメールを受け取っていたは、なかなか戻らない伊地知を待ちながら「どうしたんだろ」と首を傾げた。延々と一人で資料を読み漁ることにも飽きたは、伊地知が戻って来たらコンビニまで付き合ってもらおうと思ったのだ。そこで連絡をしたら先の返事が届いたので教室で待っているところだった。
「もうすぐ着くって話だったのに。何かあったのかな……」
まさか伊地知が五条から家入の名で呼び出され、浮かれていそいそ向かったこと、おかげでへの連絡をすっかり忘れているとも知らず、ケータイの時計を見ながら溜息を吐く。
「電話してみようかな……」
と思ったものの。自分の都合で急かすのも申し訳ない、とケータイを机に置いた。もしかしたら渋滞に巻き込まれて予定より遅れてるのかもしれない。
「一人で行けたら苦労はないんだけどな……」
窓際に歩いて行ったは、窓を全開にして外の空気を吸った。先ほどより生ぬるい風が頬や髪を撫でていく。
午後になると一気に気温が上昇したようだ。今は蝉の声すら聞こえない。
――オマエも狙われてるってことを自覚して警戒しろ。僕や伊地知以外の男は全員警戒するくらいの気持ちでいて。
午前中は青かった空に少しずつ雨雲が広がっていくのを見上げていると、不意に五条から言われた言葉を思い出す。
まさか高専の関係者の中に犯人がいるなどと想像すらしていなかった。
安全だと思っていた場所が、実は一番危険なんだと知らされた時の不安や恐怖は言葉で表せない。つい五条に縋りたくなった。でも、それさえ出来なかった。
――ここで襲うほど相手もバカじゃないでしょ。そこまで怖がることないからオマエは普段通りの行動をしてて。僕も敷地内にいるし。
淡々と事務的な言葉で言われればはただ頷くしかなく。とても傍にいて欲しいとは言えなかった。
「やっぱり……素っ気なくなったのはわたしに幻滅したからなのかも」
湿った風を肌で感じながら、弱気な言葉が零れ落ちる。すっかり曇天に様変わりをした空は、まるで今の彼女の心を映したかのようにどんよりとしていた。
「誰が誰に幻滅するんです?」
「……ひゃ」
突然背後から声が聞こえて、は驚きのあまり肩を揺らした。
「あ……渡久山、さん?」
聞き覚えのある声に振り向くと、そこには穏やかな笑みを浮かべた補助監督の渡久山が立っている。彼がいるということは伊地知も戻ったということだ。ホっと息を吐きながら「お帰りなさい」と声をかけた。
「ただいま。それで、誰に幻滅されたら困るのかな?」
「え?あ……いえ、あの……誰とかじゃ……」
苦笑交じりで歩いて来る渡久山を見上げながら笑って誤魔化しておく。独り言を聞かれたなんて恥ずかしすぎるからだ。
「もしかして何か悩み事でもあるの?」
「え?」
どきりとして顔を上げると、どこか心配そうな渡久山と目が合う。伊地知と似たような眼鏡の奥の優しい眼差しは、大人の男ならではの落ち着きがある。以前はよく任務での悩みを聞いてもらったりしていた。
「ほら最近は体調もすぐれないようだったし任務も休みがちだったから心配してたんだ。何か悩んでるなら僕に話してごらん」
「え、えっと……」
いくら信用してる相手でも自分に起きたことは話せない。それに五条にも自分や伊地知以外の男を信用するなと言われたばかりだ。どう誤魔化そうか、と考えながら、そこで伊地知が一向に教室へ顔を見せないことに気づいた。
「あ、あのそれより伊地知くんはどうしたんですか?一緒に戻ってきたんじゃ……」
「ああ、彼なら先ほど五条術師から電話で呼び出されたとかで、どこかへ向かったようだけど」
「え、五条先輩に……?」
「うん。何か急用だったみたいだよ」
「そ、そうですか……」
なら連絡くらいくれてもいいのに、と思いながら、出来れば一緒に行きたかったという寂しさがこみ上げてくる。
五条にどれだけ素っ気なくされても、傍にいたい。ふと自然にそう考えている自分がいた。
(わたし――五条先輩のことが……)
どくん、と大きく心臓が脈うつ。気づけば五条のことを考えてるのも、顔を見れば安心するのも、幻滅されてたら、と苦しくなるのも――全部同じ心から生まれてくるものだ。
(五条先輩に会いたい……)
余計なことを考えずに素直な気持ちだけを残したら、答えは簡単に出てきた気がした。
「あ、あの渡久山さん。伊地知くんはどこへ行くって言ってましたか?」
「ん?ああ、いや……そこまでは聞いてないな」
「そう、ですか……」
なら、もう一度伊地知に電話をして聞いてみようとケータイへかけてみたのだが、直留守になってしまった。
「繋がりませんか?」
「はあ……。どこに行っちゃったんだろ」
「あれ、そう言えば伊地知くんに聞いたんだけど、コンビニへ付き合ってもらいたかったんですよね」
「え?あ、はい。まあ……」
そう言えばそんな話をしたんだったっけ、と思い出す。
「良ければ僕が付き合いますよ。買いたい物もあるし」
「え?」
にこにこと笑顔で申し出てくれた渡久山に、今更もういいです、とも言えず、は「じゃあ、お願いします」と答えた。五条から忠告されてはいたものの、渡久山は入学時から知っている信頼出来る補助監督だ。彼なら大丈夫だろうと思った。
それにコンビニへ行きたかったのは事実だ。伊地知と五条を探すのは帰ってからにしよう。
そう思い直し、「じゃあ行きましょうか」と渡久山に促され、は教室を後にした。
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
