15-そういうとこ
生まれて初めて恋に落ちた。
でもそれをおかしなことだとも思わず20年近く生きてきた。
恋愛なんてしなくてもキスをしたりセックスをすることは出来る。必要になったら適当な子を適当に抱いて欲を吐き出せば終わり。その行為に意味を見出すこともなく、またのめり込むこともなく。
それでいいとさえ思っていたし、男女なんて最終的にはそんなもんだろうと思っていた。今までは。
なのに、たかがデートに誘われただけで、こんなにも浮かれるものなのかと、五条自身が驚いていた。
「は? デート?」
「うん、そう」
乾いた声で返事をして振り向くと、ソファの背もたれに両手で頬杖を突きながら、何故か満面の笑みを浮かべている同級生。
その端正な顔に未曾て見たこともない幸せオーラを放っている。
この同級生に対して愛はないが、美を愛でる心は持っている。後光でも指す勢いの五条を見た家入は、あまりの眩しさにぎゅぅっと目を細めた。
「へえ。良かったじゃん。ちゃんと告れたんだ」
「いや、告ったわけじゃないけど」
「は? 違うの?」
今度こそ椅子ごと振り返った家入はどこか呆れ顔だ。せっかくお膳立てしてやったのに、と言いたいんだろう。
特にへの気持ちを家入に話した覚えもないが、五条のこれまでにない態度を見て薄々……いや、ハッキリとバレているというのは感じていた。
「そんな流れにならなかったんだよ。、泣き出すし」
「泣いたって何で」
「……いいだろ、別にそこは」
うっかり手を出しそうだったから対策として素っ気なくしてたら、に「幻滅したからだ」と変に誤解されていた。
そんな説明をわざわざするのも面倒で、五条は言葉を濁した。
とりあえず、その辺の誤解は解けたこと。そこからお詫びと称したデートになったことは、まあ五条にとっても嬉しい誤算だ。
「初めてのデートは五条先輩がいいって、めっちゃ可愛くない?アイツ」
「げぇ。何それ。惚気?五条から惚気られる日が来るなんて思ってなかったわ。だいたいは素直だし自分のこと助けてくれたアンタに一時の気の迷いを起こしてるだけじゃないの」
「あ?気の迷いって何だよ。こんなナイスガイを捕まえて」
「どこがナイスガイ……っていうか、惚気に来ただけなら帰ってよ。私、まだやることあんの」
「はいはい。悪かったよ」
再びパソコンに向き直る家入を見て、そこは素直に立ち上がる。これ以上話していても暴言を吐かれるだけだ。それにこれ以上、家入に惚気て今までの素行を突っ込まれたくもない。
今までの自分とは大きく変わったことなど、五条自身が一番感じている。
「あ、そういや、処分の方はどうなった?」
五条が出て行きかけた時、家入が思い出したように問いかけてきた。独断で渡久山を祓ったことや、に起きた問題を高専側へ報告しなかったことについてだろう。
散々聞く時間はあったのに今かよ、と苦笑しながら、五条は足を止めた。
五条が勝手に動いた件を上層部は問題視したらしいが、そこは夜蛾が上手く立ち回ってくれたようだ。家入にもそう説明するとパーティション代わりの棚の向こうから「良かったじゃん」という声が聞こえてきた。
そもそもストーカー問題に五条を引き込んだのは家入なので、多少は気にかけてたらしい。
「実際問題、僕が処分なんてことになれば五条家が出張ってくるしね。お爺ちゃん達もめんどくせーって思ったんじゃない?渡久山の危うさに気づかなかったのは高専側の怠慢でもあるし」
「まあ、そう言われるとそっか。その怠慢のせいで未来ある生徒の心身を傷つけたことは間違いないし……」
家入の声には憤りみたいな音が交じっている。いくら問題を解決したところで、が受けた傷は消えない。それは五条と家入にも分かっているからこそ歯痒かった。
五条は溜息を吐き、ドアを開ける。でも出て行きかけてもう一度だけ振り向いた。
「あ、硝子~」
「……何よ。まだいたの?」
「とのデート、どこへ行けばいい思う?」
「知るか!勝手にどこでも行け!」
医者になる為の勉強に忙しく、デートも出来ていない家入にこの手の話は地雷だったようだ。五条は笑いを噛み殺し、静かにドアを閉じた。
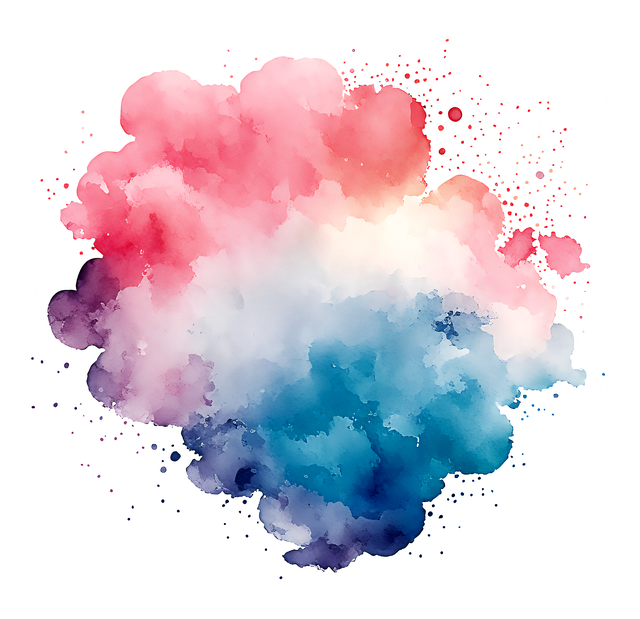
とのデートはどこへ行こうと散々考えた結果。何一つ思いつかなかった。
映画や食事も定番すぎるし、二時間弱で終わってしまう。このクソ暑い残暑の中、海や遊園地も違う。最後はキャンプや旅行まで考えたが、付き合ってもない女の子と初デートで行くのも重すぎて何か違う。
これまで会ってた女の子とはどうしてたっけ?と考えたが、その場合、ほぼ遊びなので軽く食事をした後はホテルへ直行コースだった。それも基本、向こうから誘ってくるので、五条から誘ったことすらなかった事実に行きつく。
本命の子とデートなんてものをしたことがない五条には、東大受験をするよりも難問だったらしい。
家入には「勝手にどこへでも行け」と言われ、後輩の七海にそれとなく聞いてみたが、Gでも見るかのような目で睨まれたあげく「何故私が五条さんのデート先を考えなくちゃいけないんです?」と、真冬のような底冷えのする声で言われてしまった。今は夏の終わりと言っても気温が30度もあるのに、五条の心が震えた瞬間だ。
あとは夜蛾や、先輩の冥冥、日下部などにも尋ねてみたものの、何故か真剣に応えてもらえない。歌姫に至っては「僕だけど」の一言で電話を切られる始末。
いや、ケータイに名前出るんだし切るなら最初から出なければよくね?とさすがの五条も腹が立った。その後、歌姫から着信拒否されるまで鬼電をするという暴挙に出たのは言うまでもない。
そうして周りの人間に迷惑をかけつつ、行き先も決まらないまま迎えたデート当日。高専の門扉付近で待ち合わせをした五条は、直接に尋ねてみることにした。彼女が行きたい場所へ行けばいい、という簡単なことをすっかり忘れていたらしい。
「どこでもいいんですか?」
「いいよ」
むしろ言ってくれた方が助かると思いつつ、そんな顔はおくびにも出さず頷くと、は少し照れ臭そうに「じゃあ……」と考える素振りをしてみせた。
が映画を観たいと言えば観るし、遊園地に行きたいと言えば連れて行く。自分で考えたプランよりも、本人の望む形を叶えてやりたいと思った。こんな風に思ったことすら初めてだ。
「……水族館とか」
だから彼女がはにかんだ顔で言った時、五条はすぐに「いいよ」と答えていた。そして内心、その手があったか、と思う。
水族館なら暑さもしのげるし、彼女が負担に感じることもない。
五条が即答すると、は細胞のひとつひとつに喜色を浮かべたような明るい笑顔で喜びを現わした。あまりの可愛さに自然と五条の頬も緩む。
普段の制服姿とは違い、は明るい色の裾がふわりと長いワンピースを着て足元は涼しげなミュールを履いてる。夏っぽくて可愛いじゃん、と褒めると、照れ臭そうに俯く姿にもきゅんとさせられ、五条は軽く咳払いをした。
「……じゃあ行こっか」
「はい」
二人で高専を出ると、まずは駅に向かう。彼女の希望で移動は電車ですることになっていた。
五条も高専生だった頃は、仲間や後輩達と電車で移動し、都心部へ遊びに出掛けていたこともある。でも色々なことが起きてからは遊びに行く気分でもなく。また休みはないに等しかった五条にとって、こうしてのんびり移動するのも久しぶりだった。まして女の子と二人で電車に乗るのも初めてだ。そこに気づいた時、何とも言えない新鮮さを感じた。
車窓から見える景色を楽しみつつ、他愛もない話を交わしながら30分。新宿で電車を乗り換えて10分ほどで目当ての水族館に到着した。
「でも何で水族館だったわけ?」
平日の昼間でも人は多く、混雑している雑多な街並みをの歩幅に合わせて歩く。五条は見えてきた水族館を眺めつつ、ふと疑問を口にした。
「えっと……何となく五条先輩も好きかなと思って」
「え、僕そんな話したことあったっけ」
建物の中へ入りながら、五条は考えつつ首を傾げた。普段から適当に適当なことをペラペラと話してるだけに記憶がない。
でもに「前、沖縄で水族館に行ったって話してたから」と言われて「ああ」と頷いた。
あれはまだ親友の夏油がいた頃、護衛の任務で行った場所だ。夏油が離反するキッカケの一つになった、初めて二人が失敗した任務でもある。
「沖縄が凄く楽しかったって、前にチラッと言ってたのを思い出したんです。ダメ、でしたか?」
「いや……そんなことないよ」
エントランスホールで案内を眺めながら、五条は笑みを浮かべた。言ったことに嘘はない。あの短い時間が唯一、あの任務で言えば楽しい時を過ごせた。
「わー可愛い。カラフルな魚」
一瞬、水槽に張り付いて笑みを浮かべるの姿が、あの日の少女と被って見えた。不意に感傷がこみ上げたのは、自分にも大切な存在が出来たからかもしれない。あの時とは違う痛みがかすかに走る。
「テングハギはサンゴ礁の浅い場所に生息して強い光を好むらしいよ。そのオデコの角が特徴」
「え、五条先輩、詳しい。さかなクンみたい」
「え……それって、僕もぎょぎょぎょって言わなきゃダメなやつ?」
おどけて言えばは楽しげに笑いだす。その明るい笑顔にホっとさせられる。同時に彼女を救うことが出来て、改めて良かったと思った。出来れば彼女だけは危険な目に合わせたくないし、可能な限り守ってやりたいとも。
「え、でも先輩、魚に詳しいの?ちょっと意外」
「沖縄に行った時、地元の人に聞いたの覚えてただけだよ」
「そうなんだー。わたし、沖縄は行ったことないなあ。やっぱり海綺麗?」
「うん、凄く」
ひとつひとつ水槽を覗きながら、あの日に見た澄んだ海を思い出す。照り付ける日差しと、どこまでも濃い潮の香りまで。
「こっちの海って潜っても暗いんだけど、沖縄の海は潜っても明るい。海面から光が届いて、その中を色とりどりの魚が泳いでて幻想的なんだよね。ただ静かな時間が流れてて、こんなに澄んだ世界があるんだーって感じだったな」
「……」
は黙って五条の横顔を見つめている。ふと我に返ってぎこちない笑みを浮かべたのは、自分が今、情けない顔をしてたという自覚があるからだ。あの頃のことを思い出して胸が締め付けられるのは、確かにいたはずの存在が、今はもういないのだという現実を思い出してしまうから。
その時、館内放送でイルカショーや、ペンギンと触れあえるという放送が流れた。
「イルカ見られるかも。いきましょー五条先輩!」
が笑顔で五条の手を引っ張る。その元気な笑顔に釣られて五条も微笑んだ。繋がれた手が熱い。
(何でなんだろうな……)
繋がれた手の体温を感じながら、とくんと心臓が音を立てる。これまでも色んな子と肌を重ねてきたはずなのに、一度もこんな気持ちになったことはない。
といると、元気も、癒しも、愛しさも、与えられてる気がした。
「あ、先輩、見て!ナマコ」
触れあい広場を通った時、はその不気味な物体をいとも簡単に手で掬って五条へ見せてきた。一瞬、目が点になる。それは前に五条も触れたことのあるものだったからだ。
――キモ!キモなのじゃ~!
再びあの日の明るい笑顔が、目の前のと重なってみえた。同時に楽しかったことまで鮮明に思い出し、ふっと笑みが漏れる。
そう言えばあの時もあのあと――。
もう一つ思い出しかけた時、の手の上でナマコがどろどろに溶け始め、「あぁ!」と慌てている様子に小さく吹き出した。
「ど、どどどうしよう!殺しちゃった?!」
涙目で慌てる彼女の頭を撫でながら「落ち着けって」と苦笑する。
「これは外敵から身を護る手段らしいから。ただ溶けただけで生きてるよ」
「え……そうなの?」
「前に沖縄で天然のナマコを掴んだら同じ状態になった。でも海へ戻したら元に戻ったから大丈夫だって」
五条の説明を受け、は「良かったぁ」と安堵の表情を浮かべた。本気でナマコを心配してたらしい。変わったやつ、と笑いを噛み殺しながら、ナマコを戻す彼女の手を設置してあるタオルで拭いてあげた。
「あ……ありがとう御座います」
たったそれだけで頬を染めて目まで潤ませる。無防備すぎだって言ってんのに、と文句を言いたくなったのは、この顔を自分だけじゃなく他の男にも見せるんじゃないかと心配になったからだ。
そんな想いがつい赤く染まった彼女の頬をむぎゅっと抓る行動に現れてしまった。
「い、痛いです、五条先輩」
何故抓られたのか分からないといった顔で見上げてくるは容易く五条の情緒を壊しにかかってくる。キスしたい衝動に駆られ、慌ててそっぽを向いた。まだ何も伝えられてないのにそんなことは出来るはずもなく。うるさい心臓を鎮めるのに五条は先に歩き出した。ここが水族館で良かったなと思う。もし誰もいない空間ならばうっかり抱きしめてしまいそうだった。
「……先輩?」
「イルカ……見るんだろ?」
視線を合わせないまま言えば、は「あ、そうだった!」と無邪気な声を上げた。
「ショーが始まっちゃう!行こう、五条先輩」
「はいはい」
五条に追いついたに再び手を引かれて素直について行く。子供みたいな仕草も全てが可愛く見えて、静まりかけた心臓が少しずつ速くなった。繋がれた手を僅かに握り返しただけで、彼女は照れくさそうに微笑む。
こんな風に手を繋いで誰かと歩いたのも、のんびりした時間を過ごすのも初めてで、ただ魚を見てるだけなのに心が不思議と安らいでいく。
「うわ、平日なのに凄い人が集まって来てる」
「みんな、と同じでイルカが見たいんだろ。でも少ない方なんじゃないの。まだ空いてる席もあるし」
イルカショーが行われるのは野外のプールで、じりじりと太陽が照り付けてくる。なのには子供みたいにはしゃいで「一番前に行こう」と言い出した。いや、それ絶対濡れるやつ、と五条は思ったものの、そこはの希望通り最前列へ座る。
「ここなら良く見えますね」
「濡れても知らないよー」
「大丈夫!暑いしすぐ乾くもん」
そんな会話を交わしてる内に調教師とイルカが登場して、客達から歓声が上がった。も当然キャーキャー言いながら可愛いと連呼してジャンプするイルカを楽しんでいる。
可愛いと大騒ぎしてるの方が可愛い、と思いつつ、五条は必死で笑いを堪えていた。
ただ――案の定というべきか。イルカが水の中を縦横無尽に泳ぎながらパフォーマンスを始めた途端、水しぶきが無遠慮に飛んでくる。当然、一番前を陣取っている客達は全員、髪から服からびしょ濡れ状態だ。
「やっば!こんな濡れると思わなかったんだけど!意識して無限使っとけば良かった……」
最近は術式をオートにしてある為、意識して止めなければ危険性のある攻撃に入らない水しぶきは普通にかかってしまう。おかげで他の客同様、濡れ鼠と化してしまった。
「あははっ五条先輩、シャワー浴びたみたい」
「いや、オマエもだろ――ってか透けてるし!」
「え?」
見れば着ているワンピースの胸元が水で濡れ、薄っすら下着の線が見えている。最悪なのは太陽に照らされた明るい場所だとやけに目立つことだ。
慌てた五条はTシャツの上から羽織っていたシャツを脱いで、すぐに彼女へ着せた。それすらびしょ濡れではあるが応急処置みたいなものだ。
「あ、ありがとう御座います……」
「ったく……ちゃんと確認しないとダメだろ。そういうとこが無防備すぎだって言ってんの、僕は」
「う……ごめんなさい……」
五条に叱られ、すぐにシュンと落ちこむ姿は可愛いが、普段通りの説教をしてしまったことでふと我に返る。せっかくのデートで落ち込ませてどうする、とばかりに「いちいち落ち込むなって」と濡れて額にくっついた彼女の前髪を指で直してやった。しかし今度はポっと音がしそうな勢いでの頬が赤くなる。可愛い……と油断したそばから頬が緩みそうになったところで、五条はイルカへと視線を戻した。可愛いにプラスされてちょっとエロい時の顔に見えてしまったせいだ。
髪が濡れてるのも良くなかった。一瞬、あの時のの映像がまたしても音声付きで流れそうになったところでイルカに救われた形だ。
そう、じわじわとこみ上げてくるものを誤魔化すには、癒し系の王者、イルカを見てほんわかするしかない。
……とはいえ――。
服は透けて髪も濡れて頬も赤い彼女をこのままにしておくわけにはいかない。周りの男全てがにエロい目を向けてるのでは、と思えてきた。被害妄想もいいところだが、自分も男なのでそういう心理を想像出来てしまうのが悲しいところだ。
「これ終わったら……」
「……え?」
「着替え買ってやっから」
「着替え?」
「売店に色々売ってたろ」
「い、いいです、そんな……」
「だーめ。僕が嫌なの」
つい本音を口にしてしまった。がどきりとした顔で見上げてくる。
「え……五条せんぱ」
「ってか……あれってこういう時用に売ってんのか?ちゃっかりしてんなー水族館」
誤魔化すように言いながら、パンフレットを捲って売店にある衣類をチェックする。
「先輩ってば大げさだよ……これくらいで。イルカショーは水がかかるの覚悟してたし」
「いや、笑ってる場合じゃないでしょ。だって透けてんだから。だいたい覚悟するくらいなら透けない服を着とけよ」
「……う、そ、そうですね」
失敗したかも、と五条のシャツで前を隠すと、もパンフレットを見ながら「わー色々あるし他のも見たいです」と言い出した。
売店には水族館のロゴ入りTシャツやら、イルカのマークが入ったパーカーなどの他にヌイグルミやらキーホルダーといった定番商品が売っているようだ。
「あ、このヌイグルミ可愛い」
「いや、そんなものより着替えね」
暑さで渇くなどと言ってる場合じゃなく、今すぐ着替えさせないと心配で仕方がない。
イライラしながら突っ込むと、イルカショーが終わった時点で、五条はを連れて速攻で売店へと向かった。
「わー見て下さい、イルカのTシャツ可愛くないですか?」
「……ハァ。何で僕まで……」
だけを着替えさせようと思ったはずが、「五条先輩も透けてますっ」と言われ、渋々同じTシャツを買い、着替える羽目になった。さすがにこの可愛らしいTシャツを着て外を歩く勇気は出ない。
と言っても、ワンピースの上からイルカのTシャツを着ているが可愛いのは間違いないが。あげく――。
「五条先輩とお揃いだし嬉しいな」
「……」
イルカTシャツのお揃いは嬉しくないが、お揃いを喜ぶは可愛い。今度はイルカの泳ぐ大きな水槽へ張り付いてる姿に、五条の胸の辺りがぎゅうっと締め付けられた。
二回目のショーが始まったことでフロアに客はなく、やけに静かだ。水槽の前に立つと海の中にいるような感覚になる。
「……気持ち良さそうに泳いでる」
ぽつりと言いながら、は数頭のイルカを見上げた。その横顔が綺麗で、つい見惚れてしまう。
長いこと彼女の先輩をやって来たのに、どうして気づかなかったんだろうと今では不思議で仕方がない。
もちろん可愛い後輩だと思っていたし、可愛がってもきた。でもそれはあくまで先輩という立場であり、個人的に踏み込もうとまではしてこなかった。
(ま……それだけ忙し過ぎたってことか……)
親友が高専を離反し、自分がするべき目標を見つけ、そのことばかりを考えて今日まで突っ走って来た。
心のどこかで置いて行かれた寂しさを払拭できないまま、今もあの背中を追い続けてる気がして止まれなかった。いや、止まれなくなった。
自分がやらなければ――と、その一心だったから。
だけど今こうしてと楽しい時間を過ごしていると、いかに自分が疲れていたのかが分かる。
「あ、そうだ。わたし、来週から任務に戻れることになったんです」
「……来週?」
「はい。今までサボってた分、きっちり働かないとですね」
明るい笑顔で言うは本気でそう思っているようだ。あんな事件に巻き込まれて傷ついてないはずはないのに、何もなかったかのように振る舞う姿が健気に思えて、五条は「無理しなくてもいいのに」と、つい先輩らしかぬ言葉を吐いていた。
それでもはにこっと微笑む。その笑顔を見てたらたまらなくなった。
「無理なんかしてませんよー。もう大丈夫――」
と、先を歩きだしたを追いかけると、その小柄な体へ腕を伸ばして後ろから抱きしめる。一瞬、彼女の息を呑む気配が伝わってきた。久しぶりにの熱を腕に感じて、これまで堪えてきた想いが溢れ出す。
「好きだ」
「せ……せんぱ、い?」
「が好きだよ」
生まれて初めてその言葉を口にした時、ずっと胸につかえていた重荷が、少しだけ軽くなった気がした。
ひとこと送る
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回まで
現在文字数 0文字
