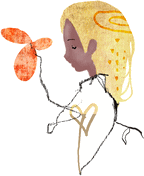2007年元旦――。の姿は久しぶりに五条家の離れにあった。現当主から年末年始は顔を出すよう言われ、五条と共に昨年末の大晦日、五条家へ戻って来たのだ。五条は「面倒くせぇ」とブツブツ言っていたが、は久しぶりに兄や彩乃に会えるのが嬉しかった。しかし今回の帰省の目的は当主からに話があるとのことで、家について早々だけ当主の部屋へ呼ばれた。内容は二週間ほど前に誕生日を迎え17歳になった五条についてだった。
「来年悟は18歳を迎えるのと同時に五条家の当主となる。五条家との当主となれば今以上に力をつけねばならない。君のおかげで早々に術式を完全に自分のものにしたが、まだ一つ足りないものがある。そこで君に提案なんだが…」
当主はに対し、あるお願いをしてきた。それはが引き受けてもいいし引き受けなくてもいい"お願い"だった。当主からその話を聞かされたは動揺し、また答えに困った。誓約としてある以上、無下には出来ないが今すぐ分かりましたとも言いにくい。
"悟が当主になった暁には、交わりの儀をしてもらいたい"
当主に言われた言葉を思い出し、の口から自然と深い溜息が洩れる。ついでに経験のないその行為を思うと、じわりと体温が上がり、額に汗が浮き出て来る。最初にここへ連れて来られた際、制約内容は聞かされていたものの、あの頃はまだ理解がそこまで及ばなかった。でも今は違う。鬼として目覚め、先祖の意識が記憶に色濃く残っている。経験はなくとも、何となくだが肌が覚えているような妙な感覚があった。
(悟と…交わる…)
以前なら冗談じゃないと突っぱねられたかもしれないが、今のは五条に仄かな想いを寄せている。五条の為だと言われれば、強く拒否できない。誓約だからとはいえ、平常心で行為に及べるのかどうかも分からない。それに五条の方はどうなのかという不安もある。
「でも…いつか六眼を生み出すには避けられない道なのよね…」
当主の言い分は理解出来た。数百年という気の遠くなるような年月の中で、現代に五条悟が生まれ、そして鬼姫である自分が生まれた。この機を逃したくないという当主の願いは当然のことだろう。
「あと11ヶ月と7日か…」
「…何がだよ」
「ひゃぁっ」
猶予のことを考えていた時、不意に背後から声がしたことではその場に飛び上がった。振り向かずとも誰かは分かったが振り向かずにはいられなかった。
「もう悟!気配殺して近づかないでよっ」
後ろで苦笑いしながら立っている五条を睨みながら、は一気に飛び跳ねた心臓を落ち着かせようと一つ息を吐き出す。離れの扉は去年の台風で壊れて新しくしたのだが、以前のように開く際、鼠の鳴き声のようなキーッという音が鳴らなくなったのも災いしたようだ。
「オマエがブツブツ言ってっから頭でもおかしくなったのかと思ったんだよ」
「う…き、聞いてたの…?」
「いや。聞き取れねえから近づいた。で、何が11ヶ月と…何だっけ」
「な、何でもないっ」
そこは聞かれてたのかと頬が一気に熱くなる。誤魔化すように五条へ背中を向け、再び窓の外を眺めた。夏の頃には鮮やかな色の花が咲いている庭も、この時期はあまり色がない。
「何だよ。せっかくコレ持って来てやったのに」
「え?」
もう一度振り向いてよく見ると五条の手にはケーキの乗った皿がある。が不思議そうに首を傾げると、五条は「彩乃がオマエの為に焼いたんだと」と言いながら皿をテーブルへと置いた。彩乃はの帰省をいたく喜び、毎日のようにの好物を作ってくれている。どうやら今日は苺のケーキらしい。
「え、美味しそう!苺がたっぷり乗っかってるね。一緒に食べよ?」
「運んでやったんだから当然だろ」
ケーキが四つに切り分けられているところを見れば、五条も食べる気満々だったようだ。は笑いながらミニキッチンへフォークと小皿を取りに行った。さっきまでの憂い顔とは違い、今はニコニコと機嫌が良さそうではある。五条はこっそりとの表情を観察した。父である当主から帰省しろと言われた時点で五条はその思惑を何となく察していた。自身が17歳を迎えてすぐだったというのもある。五条は生まれた時から18歳で当主になることを認められた存在だ。その若さで五条家の時期当主になることを定められたのは、五条が六眼持ちだからこそ。特別なのはもちろんのこと、運よく鬼姫と同じ現代に生まれたのなら、いつの世かまた六眼を生み出すために鬼姫との交わりは絶対でなければならない。それを先日父である当主から聞かされたばかりだ。正式な誓約ではない為、これまではハッキリとした物言いはされなかったが、息子が17歳になったのを機に、遂に当主も口火を切った。と交わることを頭に入れておけ、と。
"今日まで奔放にさせて来た。しかし来年からは当主として五条家の未来についても責任を負うことになる。肝に銘じておけ"
父からの一方的な物言いに五条は苛立ちを覚えたが、ここは我慢だと怒りを腹のうちに収めた。あと1年我慢すれば五条家が手に入るのだ。当主になった時、五条は父の、いや一族の言いなりになるつもりはさらさらなかった。今とて五条悟ほど無下限呪術を使いこなせる術師など一族の中には誰ひとりとしていないのだ。その気になれば全ての人間を支配出来る力が、五条悟には備わっている。しかし、父の言うように足りないものはまだある。だからこそ、五条は父に言われたことを全否定出来なかった。五条家の未来の為にを利用することは避けたいはずなのに、全てを否定しなかったのは最強であることを渇望する自分がいると知っているからだ。父への怒りはそのことへの苛立ちも含まれていたであろうことは五条も気づいていた
「はい、悟。紅茶もね」
「おう、サンキュー。気が利くじゃん」
フォークと小皿、そして淹れたての紅茶をテーブルに置いたは、えへへと嬉しそうに笑みを零した。その笑顔を見ていると、五条の胸中に渦巻いていた黒い感情が和らぐ。
「んー美味しい。彩乃さん天才」
「クリームふわっふわ。彩乃はマジで料理とかスイーツ作りがうまいよな」
「今度教えてもらおうかなぁ…」
はケーキをパクつきながら何やら悩んでいる。人間として生きていた頃は天夜が家事をしていたし、その後は五条家に入り、彩乃に色々と世話をしてもらっていたは家事全般をしたことがない。そろそろいい年頃になったことで料理のひとつもでも覚えたいと思った。それは五条に手料理をふるまいたいという健気な恋心でもある。
「そうしろよ。オマエ、料理も出来ないんじゃ嫁の貰い手がないかもしんねえし」
「……む。結婚なんてまだ先のことじゃない」
「そうやって呑気にしてっと、アッと言う間に適齢期になるぞ。まあ鬼は人間より歳とんのも遅いし今から始めれば間に合うんじゃねぇの」
五条は言いながら笑ってるが、は笑えなかった。心のど真ん中に居座っている五条への恋慕が消えない限り、他の男との結婚など考えられない。しかし例え万が一、五条がを受け入れてくれたところで、鬼と呪術師、しかも五条家当主の妻になどなれるはずもないのだ。
「何だよ。食わねぇの?」
の手が止まっていることに気づいた五条が、頬杖をつきながら溜息を吐く。はケーキにフォークをさした。色々胸中は複雑だけれど、ケーキに罪はない。再びケーキを食べ始めたを見て、五条はふと笑みを浮かべながら、紅茶を一口飲む。久しぶりにふたりで過ごす平穏な時間だった。

寒い冬が過ぎ、温かい日差しを振りまく春も終え、鬱々とする梅雨が明ける頃、五条は親友の異変に気づいた。どこか顔色が悪く、覇気がないのは去年の星漿体任務を失敗した後にもあることにはあったが、時間と共に普段の夏油に戻って行ったことで、五条も家入も安堵したものだった。しかし今年に入ってあの時のように時々物思いにふける光景を何度か目にするようになった。食欲もないのか、日に日に痩せていくような気もする。急に暑くなったことで夏バテだと本人は説明したが、すぐに納得した五条とは違い、家入だけは腑に落ちないといった顔をしていた。
「なーんか元気ないのよねぇ、夏油のヤツ」
この日も五条は朝から地方へ旅立ち、夏油も都内での任務へひとりで向かった。それを見送った家入はその足で二年の教室に顔を出し、に「お昼一緒にどう?」と誘った。いつも七海や灰原と食べていたのだが、今日はふたりも東京郊外での任務が入り不在だった。はひとり教室で自習をしていたので、喜んで家入の誘いに乗ることにした。いつも食堂で済ませていたのだが、久しぶりの女同士ということもあり、家入は最寄りの駅前までを連れ出すと、その辺では一番まともな料理を出してくれる洋食屋へ入った。昼時ということで少々混んではいたものの、ふたりは無事に窓際の席を確保する。それぞれ好きな料理を選び、食前に紅茶を頼んだ。
「傑、どうかしたの?」
少し薄目のレモンティを飲みながら、はふと顔をあげた。家入はコーヒーを飲んでいたが、溜息交じりで窓の外へ視線を向けると、困ったように首を傾げる。
「どうって聞かれると特にハッキリした答えはないんだけど…少し元気がないってくらいだし」
「夏バテって言ってたけど、傑ってそんなに暑さに弱かったっけ」
「うーん…最近は災害が多かったじゃない?だから今の繁忙期はめちゃくちゃ忙しいから疲れてるだけって言われるとそうなのかって思うんだけどね」
「硝子ちゃんが違和感あるなら、やっぱり体調悪いんじゃない?大丈夫かなあ…。今日もひとりで任務行ったんでしょ?」
「本人は大丈夫って言って笑顔で出かけて行った」
家入は先ほど顔を合わせた夏油を思い出しながら溜息をつく。何が?と聞かれると上手く説明は出来ないし、この場合なんとなくとしか言いようがない。
「まあ…重病じゃなければいいけどね」
家入はそう言いながらも早く繁忙期が過ぎればいいと思っていた。人間の鬱々とした感情が渦巻くこの時期は、現場に行かなくとも何となく気分が滅入るのだ。
「それより…は今日任務なしだったんだね。七海たちについて行かなかったの?」
「それがその場所、女人禁制の男子校みたいで、先方が男の人だけでって指定してきたみたい」
「へえ、なら仕方ないか。男子校なんて女に飢えた男しかいないだろうし、みたいな可愛い子が行ったら皆、浮き足立っちゃうもんね」
「梢子ちゃん、凄い偏見だよ、それ」
家入の言葉にが明るく笑う。の元気な笑顔を見ていると、何故か家入はホっとするのを感じた。そこへ注文したハンバーグセットとオムライスが運ばれてくる。お腹の空いていたふたりは「美味しそう」と互いに言いながら早速食べることに専念した。田舎の駅前にある洋食店にしては、なかなかに美味しいので、高専の生徒も時々ここまで食べに来ることもある。
「ところで最近は五条と上手くいってるの?」
「えっな…なな何が…?」
ハンバーグをアッと言う間に半分は食べ終えた家入が、何の気なしに質問をするとは目に見えて動揺した。
「何がっていうか…ケンカとかせずにって意味だけど…」
「あ…ああ…うん…ケンカは…してない」
は笑って誤魔化すように言うと、再びオムライスを食べ始めた。その様子に小さな違和感を覚えて家入は首を傾げた。
「…他に何のことだと思ったの?」
「え?えっと…べ、別に…ほんとに何か分かんなくて聞いただけ」
「そう?」
「うん…」
家入は特に追及するでもなく、の言葉をそのまま受け取り、食事を続けた。一方、笑顔で頷いたの心臓はバクバクと大きく脈打っていた。不意打ちで五条の名を出されると、こんなにも焦るものなのかと思う。一瞬、自分の想いがバレてるのかと勘違いしそうになった。出来れば家入にも知られたくない。鬼が術師に想いを寄せるなど、愚かとしか思われないだろう。
(…今夜は…久しぶりに交換の日だ…)
はふと今朝、任務に行こうとしていた五条に会った時のことを思い出した。五条はのところまでやってくると、不意に身を屈めて「今夜、寝る前に部屋に行くから」と小声で耳打ちしてきた。以前は一週間に一度だったそれが、今は一ヶ月に一度へ変わったことで余計に緊張する。期間が開くからだ。でもしないわけにはいかない。喉の奥の渇きにも似た飢えは自分でも抑えられないのだ。
「どうしたの?まで食欲ない?」
「え?あ、ううん。美味しいよ」
生気不足になると人間の食事が随分と味気ないものに感じる。今もその感覚があり、普段よりは喉を通らない。家入に合わせて美味しいとは言ったものの、やはり身体は正直だと思った。家入も鬼のそういった変化は知っているが、はあまり鬼の方の食事のことは話さないようにしていた。鬼の食事イコール五条との接吻に繋がるので単に恥ずかしいといった理由だ。
(悟…何時ごろ帰って来るのかな…)
最近は五条も任務が忙しいようで毎日あちこち飛び回っている。今日も東北地方へ出張へ行ったはずだ。いつもは泊りになるその出張も、交換の儀がある日は必ず日帰りしてくれている。かなりハードスケジュールをこなしている五条だが、反転術式を上手く活用しているので疲れは殆ど感じないと話していた。
(今日は早めに準備して待ってようかな…)
は胸の高鳴りを殺しつつ、最後のオムライスを口へと運んだ。

その日の夜、五条がの部屋のドアをノックしたのは深夜近い時間だった。遅くなりそうとメールを貰っていたは少し前まで起きていたのだが、ついベッドに寝転がっているとウトウトしてしまった。雑誌を広げたまま、そこに突っ伏すようにして寝ていたが、小さなノック音でハッとしたように目を開けて身体を起こした。
「悟…?」
ノックに気づいたはベッドから飛びおりると急いで鍵を外した。すると静かにドアが開き、五条が室内へ滑り込んで来る。七海や灰原といった他の生徒に気づかれないよう、交換の儀の時はいつもコッソリ訪ねて来るのだ。これも密会してるようでドキドキする。
「わりぃ…遅くなった」
「ううん…お帰りさない」
五条は入るなり制服のジャケットを脱ぐと「涼しー」と言いながらエアコンの下で冷風を浴びている。梅雨開け後の気温の高い暑い夜だった。
「どうだった?出張」
「んあーいつも通りかな。でもド田舎だったし移動の方が時間かかったわ…」
「そっか…」
「ああ、これ。お土産ー」
「え…?」
五条は手にしていた袋の中から箱を取り出すと、それをの方へ放り投げた。が慌ててキャッチすると、包みにはラブリーパイと書かれている。
「何?」
「林檎パイ」
「え、何それ。美味しそう。食べていいの?」
「あ、でも俺の分も残しとけよ。あと他のヤツには買ってねぇから内緒な」
「うんっ」
自分にだけくれたんだと思うと嬉しさがこみ上げる。そもそも五条が自分以外にお土産を買うことは殆どないのだ。でも時々こうしても好きそうなものを買って来ては分けてくれるのが嬉しかった。
「あ…そうだ…」
箱からパイを出して袋を破ろうとした時、ふと思い出した。生気不足の今、これを食べても本来の美味しさが分からない。
「どうした?」
「あ、うん…やっぱり明日食べる…寝る前だし…歯も磨いちゃったし」
「ああ、そっか。んじゃー俺だけ食おう」
五条はの隣へ座ると箱からパイを出して徐に袋を開けた。途端に林檎の香りがふわりとの鼻腔を刺激する。しかしやはり想像している美味しそうな匂いとは程遠い。
「んま」
五条はパイにかぶりつくと美味しそうに食べ始めた。も内心食べたい気持ちはあれど、どうせ食べるなら美味しく味わいたい。誘惑に負けそうになりながら、そこはぐっと我慢していると、五条がふと「ああ、そっか」と何かに気づいたように笑みを零した。
「、生気不足だから食わねえのか」
「う…うん…」
自分から催促するのも恥ずかしいので待っていたのだが、五条は気づいたようだ。すぐに最後の一口を食べ終えると、ペロリと唇を舐めながらの腕を引き寄せた。
「にはお土産より先にコッチの方が良かったな」
「そ、そんなこと――」
と言いかけた時、サングラスを外した五条に顎を持ち上げられて鼓動が跳ねた。何かを言う前に互いの唇が重なり、五条の熱がそこからじんわりと脳に到達した時は、自然に生気を喰らっていた。先ほどまで感じていた渇きが次第に消えていくのが心地よく、夢中で唇を合わせているとかすかに五条が食べていた林檎パイの味がした。
「…ん…」
を抱き寄せていた五条の手が動き、首の後ろを支えたことで長い指がの耳に触れる。そのくすぐったさで身を捩ると、ゆっくりと唇が離れた。全身を強いエネルギーが流れる気怠さに、とろんとした眼差しで見上げれば、複雑な顔をした五条と目が合う。
「…そういう反応されると困んだけど」
「……ん?…」
気まずそうに目を細めている五条の言葉が理解できず、は眠たそうな目を何度か瞬かせた。それでも睡魔が寄せては引いての繰り返しで、自然と瞼がくっついてしまう。交換の儀の後は決まって襲ってくるもので、五条もそれをよく分かっている。子供みたいに眠そうにしているを見て、五条は苦笑交じりで溜息をつくと、前髪を指で払って額にも軽く口づけた。
「ったく…人を煽るだけ煽っていつも寝るんだよなぁ、は…」
「……な…に…?」
すでに瞼はくっついたまま、口元でむにゃむにゃと呟くは半分寝かかっている。
「何でもねぇよ…いいから寝とけ」
「ん…」
多少反応はするものの、はすでに夢の中だ。その顔を見ていたら五条までが眠たくなってきた。何せ朝早くから青森まで行き、任務をこなしてとんぼ返りしてきたのだ。疲れることはなくなったが、こうして鬼の妖力を喰らった後は五条とて気怠くなってそれが睡魔へと繋がっていく。腕の中でぐったりとしているを抱き上げると、起こさないようそっとベッドへ寝かせて、五条も隣へ潜り込む。小さく欠伸を噛み殺しながら身体を横に向ければ、は気持ち良さそうに寝息を立て始めた。さっきの余韻でしっとり濡れているの唇に誘われ、軽くキスを落とすと「お休み」と呟き、五条も静かに目を閉じる。彼女の体温を感じていると、久しぶりに安眠できるような気がした。
ちょっとした合間のお話💋そろそろ後半の序章あたり…