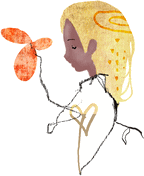灯された行灯が薄ぼんやりと静かな室内を照らしていた。ほんのりと漂う古典的な伽羅のお香は、昂った気持ちを静めてくれるようだ。五条家の離れにある寝室。その場所に、以前が使っていた一人用の布団とは違う二人用の布団が敷かれていた。その前に正座しているは普段の寝間着として着ていた浴衣ではなく、絹糸で織られた薄物の白い着物を身に纏い、少し緊張した面持ちであった。先ほどまで傍にいて世話や準備をしてくれていた彩乃も本邸宅へ戻ってしまい、は少々心細さに襲われて膝の上に置いた両手でぎゅっと着物を握り締めた。
(大丈夫――大丈夫。後悔はしない)
心の中で同じ言葉を何度も繰り返す。想定外のことが起きたのだ。少し早かろうと自分の想いには一欠けらの迷いもない。そう、迷いはないが覚悟が出来ていなかっただけ。その微小とも言える漠然とした未来が、思ってもみなかった事態でハッキリと目の前に突き付けられた時、一気にの覚悟を拡大した。
「…大丈夫。私は――」
言葉に出来ない想いは、喉の奥に痞えて飲み込まれた。
一方、五条は本邸宅から薄暗い庭をゆっくりと歩いていた。雲一つない夜空を見上げれば、空の鏡とも呼ばれる秋の名月が白く淡い光を放っていて、五条はふと足を止める。儚い月光を浴びながら何故こんなことになったのだろうと幾度も浮かべた言葉を懲りずにまた、浮かべてしまう。元々くよくよと悩むような男ではないと自負していたはずなのに、これほどまでに破壊力のある孤独は初めてだった。
――親友、夏油の離反。
想像すらしていなかった事態に五条は憤り、愁い、また孤独を感じた。自分と肩を並べられる存在はなく、子供の頃から離々たる存在だった五条にとって、高専で出会った男は五条が背中を預けられる数少ない存在であり、自分で思っていた以上に大切だったのだと、失ってから改めて痛感した。
「…」
ふと夜空へ向けていた視線を離れに移すと、奥の部屋にゆらゆらと見える赤い影。これまで見たこともないほどに戸惑い、憂いている様を明確に表している彼女の妖力。
こんな形で奪いたくはなかった――。
五条の本音が、暗く淀む心の底に沈んだ。

それは突然だった。何の兆候もなかったように思えた。少なくとも五条は気づかなかった。親友が何を思い、何に悩み、心を痛めていたか――。
担任である夜蛾から告げられたその内容は、まさに五条にとっては青天の霹靂であった。夏油の起こしたことを夜蛾に聞かされても、なかなか脳が理解しようとはしなかった。誰よりも信頼していた男の離反はそれほどに受け入れがたいことだった。五条は高専を飛び出し、思いつく場所は全て足を運んだが夏油はどこにいない。本人の口から直接聞くまでは信じられない。いや信じたくなかったのかもしれない。もちろん夜蛾が嘘をついたとも思ってはいないし、その情報が何一つ間違っていないというのは分かっていた。ただ五条の五感全てが体内に入って来た"音"の受け入れを拒否しているかのように思考が塞がれる。ただ頭にあるのは何故――?その言葉が繰り返し流れて来るだけだ。自分よりもずっと聡い男だ。後先も考えず、理由もなく大勢の人の命を、親の命を刈り取るはずがない。何かの間違いであって欲しい――。誰よりそう信じたかったのは五条だったのかもしれない。
"君は五条悟だから最強なのか?最強だから五条悟なのか――?"
その後に家入が見つけた夏油と新宿の街中で相対した時、不意にそんな言葉を問いかけられた。五条は何を言われたのか分からなかった。以前の夏油とは真逆の持論を展開されたが、混乱した頭では到底理解できない。しかし本気であることは心が痛いほどに理解した。殺そう――と思った。
それは呪詛師に堕ちた親友をこれ以上見ていたくなかったからなのか、それとも呪術師としての使命だったのか五条には分からない。分からないまま自身の最大術式である掌印を夏油へ向けた。なのに、背を向けて遠ざかっていく親友を五条は殺せなかった。あの瞬間、五条は呪術師としてではなく、たったひとりの友を失った、ただの男だった。――失態。五条は高専に戻り、夜蛾に報告をした後、その足での元へと向かった。夏油の離反を告げる為に。

あれから一ヶ月。散々迷った五条は一つの答えを出して、今ここへ来ている。五条は静かに引き戸を開け、中へ足を踏み入れた。仄かにお香の匂いが漂って来る。離れは廊下も室内も薄暗かった。靴を脱ぎ、サングラスを外しながら暗い廊下をゆっくりと歩いて行く。かろうじて寝室の方からは行灯の灯りが洩れていた。寝室へ続く襖の前に立ち、五条は小さく深呼吸をした、その時。
「…悟?」
「ああ…」
中からの小さな声が聞こえて、五条は静かに襖を開けた。は白い着物を身に纏い、布団の上に正座していたが、五条の顔を見た途端、僅かに目を伏せた。長いまつ毛の影が頬に落ちて、蝋燭が揺れるたびその影もゆらゆらと揺れる。寝化粧を施されたのか、ふっくらとした唇が艶やかに光っていて、それが何とも言えず艶めかしい。
「悪い…遅くなって。ちょっと本邸に寄ってた」
五条は着ていた制服の上着を脱いでから、の前へ座った。は俯いたまま首を左右に振ったが、膝の上で着物をぎゅっと掴む手はかすかに震えているようだった。五条は小さく息を吐くと、のその手に自分の手を重ねる。細く小さな手がピクリと跳ねた。彼女の緊張が重ねた手から伝わって来る。
「オマエ…ほんとに大丈夫か…?」
「な…何が?」
「何がって…」
五条が困ったように頭を掻くと、は俯いていた顔を上げて真っすぐに五条を見つめた。その淡い青の輝きがこの申し出をしてきた時よりも、いっそう強い決意を浮かべているのは五条にも分かった。出会った頃よりも随分と逞しくなったなと思う。今回の件はにとっても辛かったはずだ。
「大丈夫に決まってるでしょ?私から言い出したことだもん…」
「でもオマエ、震えてんじゃん…」
重ねた手からは未だにそれが伝わってくる。しかしは「む…武者震いよ」と言ってから弱々しく微笑んだ。五条の手が無意識に合わせた手を握り締める。前以上に細くなったの手に触れていると少し痩せたな、と五条は思った。
夏油の離反を伝えた時、は五条と同じような反応を見せた。聞こえているが理解できない。そんな表情を浮かべていた。やがてその話が事実なのだと理解したのだろう。は急に泣き出した。これまで見せたこともないほど泣きじゃくった。まるで子供が親に見捨てられた時のような嘆き方だったように思う。
そう言えば五条家に連れて来られた頃、が最初に懐いた相手こそが、夏油だったことを思い出す。訳も分からず連れて来られ、軟禁されたの元へ、家入や夏油が何度か様子を見に来てくれたことがあった。夏油の提案で家入と差し入れもよくしてくれた。夏油は女の子の好むものが分からないと言いながらケーキやフルーツの他に、退屈しないようにと本などを持って来て、がとても喜んでいた。五条と打ち解けて来た時でも、どちらかと言えば夏油の言うことを良く聞いていた。だからこそも混乱し、また悲しみに暮れた。しかし慕っていた男がこの世界の敵側に行ってしまったのだと理解した時、は五条のやるべきことすら理解したのだろう。ある日の交換の儀の後で、の方から五条に切り出した。
"悟。私と交わって欲しいの"
これには五条も驚いた。当主から言われていたことだとしても、五条はまだ決心すらついておらず、ともその話は一度もしたことがなかったからだ。当然、五条は一笑に付したが、思っていたよりもは真剣だった。
「オヤジに何て言われたのか知らねえけど…無理すんなよ、ガキのクセに」
ついそんな素っ気ない言葉で返してしまうほど、五条は動揺していたのかもしれない。けれど、はいつものように食ってかかるでもなく真面目な顔で「悟が当主になったらどっちにしろすることでしょう?私はそのつもりだったけど」とあっさり言いのけた。
「少し…考えさせてくれ」
五条のその言葉に、は頷いた。それが一か月前の話だ。五条にとって鬼姫と交わるのは時期当主としての使命なんだろうな、とは思っていた。しかし代々続いて来た鬼族との制約でも酷く曖昧なものが交わりの儀だ。互いに似たようなメリットがあるのだと聞いていたし、そこに何かしらの情があっても、またはなかったとしても割り切ってしまえばいいもの。前の五条ならここまで悩まず、力を求めて即決していたかもしれない。けれど今は違う。の気持ちがなければ無理強いをしたくはないと考えていた。それは当主からこの話を持ち出された時から思ってたことだ。なのに、当の本人から言い出したことで、五条は余計に混乱してしまった。
結局長いこと悩み、出した結論がと同じだったのは、やはり夏油の離反が大きかったかもしれない。この世界は思いもよらぬことが起こる。最強と言われていても予想外の敵の出現に命を落としかけたこともあった。あの屈辱は忘れていない。これからは微塵ほどの油断も失敗も許されない。ならば自らの力を更に完璧な形へ近づけたいと思った。だからこその申し出を承諾したのだ。
その後は当主にその旨を伝え、今夜ふたりは交わりの儀を行う運びとなった。
「本当に…いいんだな?」
の手を握り締め、五条は再度確認した。男の自分とは違い、は女であり、男女の性交渉は未経験だ。本来なら最初は好きな男と経験した方がいいんじゃないのかとも思ったが、は別に好きな人はいないと言う。
"好きな人が出来て私がそういうこと経験するまで儀式を待つのは無理でしょ?"
は笑いながらそう言っていた。その言葉に甘えた形になっているのは否めない。五条の中にまだ迷いはあった。けれど、は五条の問いに頷き「悟がいい…」と一言呟いた。その思いもよらぬ返答に、五条の心臓が音を立てる。
「オマエ…ほんと…」
「え…?」
「いや…」
胸の奥の疼きを打ち消すように、五条は首を振った。これは儀式であり、普通の男女がするようなものとは違う。そう言い聞かせながら握っていたの手を一度引き寄せ、その身体を布団の上に組み敷いた。軽く結っていたの雪の如き白い髪が広がり、17歳の少女とは思えぬ美しさに五条の喉が小さく鳴った。行灯の灯りでふたりの影が揺れる中、の頬が仄かに染まる。五条の手が熱を帯びたその頬を撫で、の肩がピクリと跳ねた時。ふたりの唇が重なり、深夜の帳は欠けていく――。
ふたりの関係に変化が…
夏油の離反の話は流れとして書いたので掘り下げずに終盤へ入ります。
夏油の離反の話は流れとして書いたので掘り下げずに終盤へ入ります。