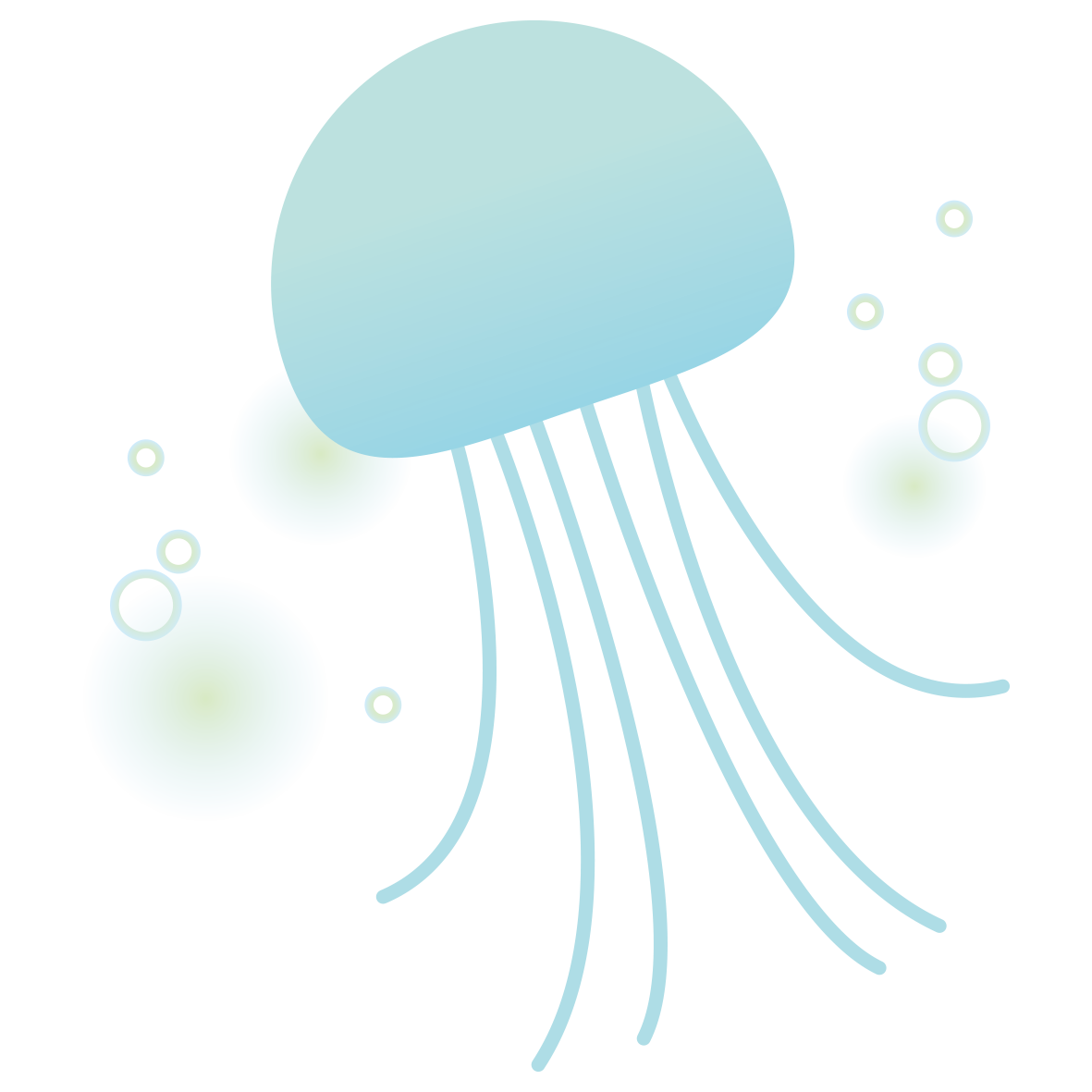青い炎が舞い、辺りにいた呪霊数体が一瞬にして燃え尽きたのを見て、七海は自身の武器をしまった。ホっと口から洩れた白煙のような吐息が、冷え切った空気に溶け込んでいく。
初冬――。恒例である寺院での祓徐はこれで今年最後となる。
「お疲れさま」
空中に浮かんでいたが地上へ下りたつのを見た七海がねぎらいの言葉をかけると、彼女も「お疲れ様、七海くん」と笑みを浮かべた。今日この寺院に来ているのはと七海のふたりだけだ。初めてここへ来た頃は引率で五条と夏油が、そしてもうひとりの同級生である灰原がいた。しかし夏油は高専を離反し、灰原は任務中に殉職した。皆で何度か訪れた場所には思い出が多すぎる。だがと七海はそれぞれの想いを抱えながらも、それを口にすることはなかった。
「さんもかなり力を使いこなせるようになりましたね。もうひとりで十分なのでは?」
「そんなこと…。ただ…最近は鬼の力がだんだん戻って来てる気がするの」
「そうでしょうね。妖力が以前の倍に満ち溢れているのが私でも分かる。何かあったんですか?」
七海はそう言いながらの表情を伺った。しかしは僅かに視線を逸らすと「別に何も。そろそろ帰ろうか」と七海に背を向け歩き出した。彼女の背中になびく雪の如き白い髪を見つめながら、これ以上探るのは野暮か、と七海は失笑した。
妖力の変化以外でも、ここ最近はやけに大人びて、女性の色香さえ漂わせる同級生に何があったのか。それは色恋沙汰に疎い七海でも大方の察しはついた。
(そう、彼女は恋をしている――。相手はきっと…)
けれども、彼女が変わったのはそれだけじゃない、と七海は悟った。鬼と五条家が交わした制約のことは知っていても、詳しい内容はさすがに聞かされていない。故に七海は双方の間にある"特例"のことは知らなかった。知っているのは生気交換の儀があるということのみ。しかし七海は何となく気づいていた。己の先輩術師である五条悟との間に、男女の関係が結ばれたのだと。それはふたりの会話であったり、視線を交わす時の雰囲気であったりと漠然としたものではあるが、明らかに前のふたりとは違う空気が流れる。ただそれが普通の男女の恋愛とは少し違う気がして、七海の中に違和感をもたらしていた。
(まあ…あのふたりに何があろうと私には関係ないが…時々見せるさんの悲しげな表情が気になりますね…)
七海は先輩であり、呪術界最強となった五条のことを信用しているし信頼もしている。しかしあの性格故に尊敬はしていない。そんな五条が、今は七海の唯一の同級生となったを悲しませているのだとしたら、と考えると、七海もいささか気分は良くない。とはいえ男女の色恋に他人が口を挟むのは野暮、と思っているので敢えて聞かないでいる。そんな状態が続いていた。
(灰原くんがここにいれば…あの持ち前の明るさで彼女を励ましてたんでしょうかね…)
かつての仲間を思い、七海は青く澄んだ空を見上げた。そこにはあの明るい笑顔を思い出させるような、冬の太陽が光り輝いていた。

次の日、の姿は京都にあった。昨晩、任務から帰ると夜蛾から次の任務を言い渡され、急遽出張が決まったのだ。
「悪いな。本当は悟が行くような任務なんだが、あいにくアイツは今、東北へ出張中で戻るのは明日の夜だ。そこでに頼みたいんだが…行けそうか?」
そう言われてしまえば断わるわけにはいかない。他に受けられる術師がいないから回ってきたのだろう。はすぐに京都行きを承諾した。幸い場所もそこまでへき地でもなく、早く終われば日帰りが可能なくらいの町だった。
京都府にある加茂町は奈良時代の一時期、都が置かれたという歴史があり、海住山寺や浄瑠璃寺、岩船寺など多数の史跡文化財がある。特産品は襖紙、茶、椎茸などで里山には茶畑が広がっているのどかな場所だ。
「こんな場所までご苦労なことやねえ。特級ともなるとひっきりなしに任務に行かされるんやろ?」
窓の外の景色を眺めていると、隣に座る男が話しかけて来た。京都駅でを出迎え、強引に車に乗り込んで来たのは二年前、京都校との交流戦で出会った禪院直哉だった。
京都に出張となった際、京都校の方からをサポートする補助監督をつけてくれることになった。東京校は補助監督不足に加え、術師の補助以外の仕事も山ほど請け負っている為、万年の人不足。そこで京都校が協力をしてくれるとのことだったのだが、の前に現れたのは京都校の補助監督だけではなく、何故か直哉も一緒について来たのだ。
"久しぶりやねぇ。元気やった?鬼姫ちゃん"
直哉は相変わらず嫌な笑みを浮かべつつ「オレが目的地まで案内したるわ」と言い出した。
「直哉くんも準一級術師でしょ?私について来ていいわけ?」
「今から行く小学校の任務、元々はオレが行こう思てたもんやねん。せやのに学長のアホが東京校へ話を持っていきよった。完全に舐めとんねん、あの老いぼれ」
相変わらず辛辣な言葉を吐く直哉に、は内心溜息をついた。散々「私だけで行く」と直哉の同行を断ったというのに、半ば強引について来てしまったのだ。一緒にいた補助監督も直哉には逆らえないのか、にこっそり「すんません…直哉さん、ああいうお人やから」とすっかり恐縮していた。
「特級相当て言うても、たかが小学校に沸いた呪霊なんぞ、オレでも祓えるっちゅーねん」
「…それはただの呪霊じゃないの。だから私か悟に話が回ってきたのよ」
「どういう意味や?」
散々悪態をついていた直哉も興味が湧いたのか、ふとへ視線を向けた。
「特級呪物って言えば分かるでしょ?今から行く古い小学校には昔ながらのやり方でソレが祀られてた」
その名を聞いて直哉はぎょっとしたように目を剥いた。
「特級呪物やてっ?それの中身は?」
「両面宿儺の指。私が今、集めてるもの」
「…宿儺」
直哉も当然その名前は知っている。1000年以上前に実在した人間ではあるが、その力は強大で他の術師も及ばず、戦わずして敗れたという逸話があった。死後も20本の指の屍蝋が特級呪物として残されたが、当時の術師達はそれらを封印することしか出来ず、後に散逸したと聞いている。その指がこの町にあると聞いて、直哉は当然好奇心をそそられた。
「へえ…確かに鬼にとっても宿儺は宿敵やったし…そら放置もできひんわな」
「それ以前に封印の力が年々弱まって来てるようで他の呪霊を呼び寄せてしまうらしいの。そういう被害報告が少しずつ増えてる」
「あーそれで回収して回ってるんか。ご苦労なことやね」
「回収は誰でも出来るけど、万が一何かが起こった場合、対処できるのは私か悟しかいない。だからよ」
はそう言いながら直哉を睨んだ。明らかに楽しんでる風の態度がの神経を逆なでしてくる。そういうところは二年前と少しも変わっていない。
「見えてきました」
その時、運転していた補助監督が車のスピードを緩めた。窓の外へ視線を戻せば、前方に昔ながらの木造校舎が見えて来る。の眼にはすでに校舎の周りを囲む淀んだ空気と大小様々な呪霊の姿が映っていた。
「ではここで待っていて下さい」
車を降りて、は補助監督にそう告げると、ひとりで校舎に向かって歩いて行く。その後を直哉も追うようについて来た。
「待っててって直哉くんにも言ったんだけど」
「…舐めた口利きはるなあ、相変わらず。オレが足手まといや言いたいんか?」
「そういう意味じゃない。これは私が受けた任務なの。直哉くんには関係ない」
「ここまで来て引けるかいな。その特級呪物とやらを拝むくらいええやろ」
直哉はそう言って笑いながら校舎へ入って行く。これ以上問答しても無駄だと判断したは、溜息交じりでその後から歩いて行った。

"ソレ"は奇怪な声を上げる人型呪霊だった。しかし生まれたばかりだったのか、予想よりも弱くの力で難なく祓えた。跡形もなく燃え尽きたその後に、ポツリと焼けただれたような不気味な指だけが残されている。はそれを拾うと布で包み新たに封印札を貼り付けた。
「これでよしと…」
後はこれを高専に持ち帰り、夜蛾へ渡すだけとなる。が宿儺の指を回収したのはこれで二度目だ。直哉に話した通り半年ほど前から宿儺の指にまつわる事案が増え、悪さをする呪霊が増えて来たことで、残りの指も探すよう進言したのはだった。記憶の奥深くに残る宿儺の脅威が、このまま放置をしておくと危険だと訴えていたからだ。
「"無事、回収"っと…」
ケータイで夜蛾へ報告メールを送り、時計を確認する。午後3時。これから京都市内へ戻れば最終の新幹線には余裕で間に合う。
「悟の方はもう終わったかな」
昨日から東北出張へ出向いている五条は今夜東京に戻るはずだ。が帰る頃には寮に戻ってるだろう。
(会いたい…)
ふと思い出すとそんな想いが溢れて来てしまう。この一ヶ月はお互いに忙しく、あまり顔を合わせることもなかった。ちょうど明日、交換の儀があるので久しぶりにゆっくり会えるかもしれない。そう思うと胸の奥が自然と疼く。
以前のように定期的な儀はしているが、その中に交わりの儀も時々含まれる。そのせいなのか、この一年で五条は更に強い力を得た。互いの身体を通じ合うことで生まれるエネルギーは、五条に力をもたらし、は鬼の本来の力を高める効果がある。おかげでも最近はひとりで任務をこなせるまでに強くなった。もちろん、それなりの体術を身につけられたのは五条や七海、そして先輩術師の特訓のおかげだ。力をつけることで任務も増え、着実に経験をつめたことはにとってもプラスだった。こうして宿敵であった宿儺の指の回収を任せられたのも、そう言う理由からだ。
「はあ…お腹空いて来た…早く帰ろう」
特急呪霊と戦ったことで、鬼としての空腹が早まったようだ。少し渇きを覚え、はすぐに古い校舎を出ようと、薄暗い廊下を歩き出した。
「あれぇ、もう終わったん?」
そこへ直哉が歩いて来た。が特級呪霊を探して戦闘している間、直哉は校舎全体に湧いている呪霊と戦っていたらしい。
「間に合わんかったかー」
「…お疲れ様でした」
不本意ではあったが、邪魔な雑魚を相手にしてくれたことは助かった。がお礼を言うと、直哉は満足そうな笑みを浮かべて「素直やん」と笑っている。
「真意はどうであれ、任務を手伝ってもらったことは事実だから」
「へぇ、ほならその礼に何してもらおうかなぁ」
「……今お礼は言いましたけど。――お待たせしました」
直哉を一瞥してからは待たせていた補助監督に声をかけると「京都駅まで送って欲しいんですけど」と車へ乗り込む。
「え、もう帰らはるんですか」
「はい。今日中には高専につきたくて」
「京都観光して行かはったらええのに。今時期の京都も風情があっていいですよ?」
「そうそう。観光ならオレが案内したるけど?」
隣に乗り込んで来た直哉も補助監督の話に乗っかり、ニヤニヤしながらの顔を覗き込んで来る。それにはそっぽを向いて「お断りします」と返した。有耶無耶になってはいるが、交流戦の時に直哉がしたことを五条から聞かされ、は少しばかり腹を立てているのだ。
「二年前のことでも私は忘れてないから」
「あらら。随分と嫌われてもーたなぁ」
「ということで京都駅までお願いします」
「そうですか?ほなら駅まで向かいますね」
補助監督は納得したように頷くと、すぐに車を発車させた。
「なーんや、つまらんのー」
直哉は苦笑交じりでボヤきながらシートへと凭れ掛かった。は何も応えることなく、窓の外へ視線を向ける。陽がだいぶ傾き、山間をオレンジ色に染め上げていくのどかな風景はどこか高専を思い出させた。
早く帰りたい―――。
まるでホームシックの如く、そんな思いがこみ上げた。高専へ帰れば五条に会える。丸一日以上も顔を見ていないと恋しくて仕方なくなるのは、五条に抱かれる幸せを知ってしまったからなのかもしれない。流れる景色を見ながら、ふとそんなことを思う。もう少しだけ、今の幸せを手にしていたかった。

「じゃあ、ありがとう御座います」
京都駅につき、は車を降りると一日ついてくれた補助監督にお礼を言った。
「いえいえ、また京都に来られたら微力ながらサポートさせてもらいます……って、直哉さん?」
補助監督の驚いた様子を見たが慌てて横を見ると、直哉までが車から降りて来た。てっきり補助監督の車で戻ると思っていたは訝しげに眉を寄せる。
「ホームまで送るわ」
「…結構です」
「そんな冷たいこと言わんでええやん。――ああ、帰りはタクシーで帰るし、アンタは先に戻ってええで」
「え、しかし――」
「ええ言うてるやろ」
愛想笑いから一転、鋭い目つきで補助監督を睨みつける。補助監督の男はビクリと肩を跳ねさせると「ほな…私はこれで」とに頭を下げて、すぐに車を出して行ってしまった。
「いつもあんな態度で接してるの…?」
「何が?」
「補助監督の人達は術師のサポートをしてくれてるのに」
高専の補助監督たちは寝る間も惜しんで術師の為に色々なサポートをこなしてくれている。学生ながらにはそんな姿を見ていて毎回頭の下がる思いだった。そんな彼らに対して上から目線の直哉を見ていると不愉快な気分になるのだ。しかし直哉はの言葉を聞いて鼻で笑った。
「ちゃうやろー?アイツらは"サポートしか"出来ひんから補助監督してんねんで?」
「…そういう考え方なんだ。じゃあ私と直哉くんは合わないね。さよなら」
「ちょー待ちぃな。やっぱ夕飯くらい付き合うてや」
京都駅に入ろうと歩き出したの腕を直哉が掴み、強引に歩き出す。それにはギョっとして掴まれた腕を振り払おうとした。
「放してよっ。私、早く帰りたいんだからっ」
しかし、直哉は更に強い力で腕を引き寄せると、の耳元へ口を寄せる。
「それは…はよぅ悟くんに会いたいからか?」
「…っ?」
「気づいてるで。ちゃん、今…空腹やろ」
「…な…」
ニヤリと笑みを浮かべる直哉の言葉が、の心臓を僅かに跳ねさせた。
「さっき特級祓うのに力を使ったせいなんちゃう?何やえらい顔が赤なってるし呼吸も微妙に乱れてはるやん?具合でも悪いんかなー思たけど…ちゃうやんなぁ?」
直哉の指摘には言葉を詰まらせた。そこまで見抜かれてるとは思わない。確かに宿儺の指を摂りこんでいた特級呪霊を祓うには、それなりの妖力を使う。これが普段の日なら問題はなかっただろうが、そろそろ生気不足だったこともあり、いつもよりは早めに空腹感が襲ってきている。それに一級呪術師である直哉が傍にいたせいで、生気の匂いが濃い分、それに刺激されたのも事実だ。
「…っ放して」
「ああ、オレから生気のええ匂いでもする?さっきより呼吸が荒いで」
「そ、そんなわけないでしょっ。早く放してってば!前と同じだと思わないで…」
「あ~アカンアカン。確かに以前よりも強なってるけど、こんな人通りの多い場所で鬼の力、使う気か?」
直哉の言うことは最もだ。鬼の力を使えば直哉を振りきれるが、周りには大勢の人間がいる。こんなところで暴れるわけにはいかない。
「オレはええで?」
「……何が」
「ちゃんに生気、あげても」
「……っなに…言ってるのっ?」
更に腕を引き寄せ、唇を寄せて来る直哉に慌てて顔を背ける。それこそこんな場所で最悪な男と唇を合わせたくもない。
「我慢せんでもええやん。東京まで戻るのに時間もかかるやろうし、それまで持たなかったら、それこそ新幹線に乗ってる人間を皆殺しにしてまうかもしれへんし、オレはそれが心配なだけや」
「そ…そんなことしない…」
「鬼の食欲は相当やて聞くし、その誘惑には抗えんやろ」
「しないったらしない…っ!私は…っ」
人間を殺したりなんかしない――!
そう叫ぼうとした瞬間だった。凄い勢いで直哉が引きはがされ、吹っ飛んでいくのを、は唖然とした顔で見ていた。目の前に立ちはだかったのは長身の男。月の光を思わせる月白色の髪が風に揺れているのを見上げた時、の碧眼が驚きで見開かれた。
「…さ…悟?」
東京にいるはずの五条が何故ここ京都にいるのか分からずに、は混乱した頭で愛しい人の名を呼んだ。しかし五条はの方を振り返らずに、目の前で驚きながら自分を見上げている直哉の胸倉を徐に掴んだ。
「に近づくなって言ったよなぁ、直哉…」
「さ…悟…くん…何で…」
自分を見下ろすアパタイトブルーの双眸が、恐ろしいまでの殺気を放っていることに気づき、直哉は身震いした。本気だ、と本能で理解した。
「一度目は許したけど…二度目は許さない。今、ここで―――オマエを殺してやろうか」
「……っわ、分かった…!彼女にはもう近づかへんて!ちょっとした冗談やし…っ」
恥も外聞もなく、直哉は心の底から降参したとばかりに叫ぶ。五条の手から解放されると、後ろを見ずに慌てて走って行く直哉を見て、五条は深い溜息を吐いた。そして後ろで未だ驚いているの表情に気づき、小さく吹き出した。
「何だよ、その鳩が豆鉄砲的な顔は」
「だ…だって…何で…?」
ゆっくりと目の前に歩いて来る五条を見つめながら、白昼夢でも見てるのではないかと何度か目を擦る。あまりに会いたいと思っていたから、都合のいい夢を見てるのだと思ってしまう。でも、こつんと額に五条のゲンコツが当たり、目の前にいるのが本物の五条だとやっと脳が理解した。
「本物…」
「当たり前だろ。こんなことじゃないかと思って迎えに来たんだよ」
「え…?」
「今日の夜に東京着く予定だったけど早く終わってさ。昼頃には高専に戻ったんだ。でも入れ違いでが京都に出張に行ったって言うし、京都校の補助監督がサポートに入るって夜蛾センセーから聞いて何となく嫌な予感がしたっつーか…」
そこまで話すと、五条はの腕を掴み、不意に歩き出した。
「え、さ、悟…?駅あっち…」
「帰る前に寄り道~」
「よ、寄り道って…」
何も応えず、ずんずんひとりで歩いて行く五条の手に引かれながら、は未だに夢を見ているような心地だった。直哉など今の自分なら何とか振り切れた。しかし、そこへ五条が助けに入ってくれたことが素直に嬉しい。あんなに怒りを露わにし、あの直哉が震えるほど殺気をまとっていたのは、自分を守る為だと思えたからだ。期待してはいけないと思いつつも、やはり好きな人から守られれば、また想いが募ってしまう。
(それにしても…悟ってばどこに行くの…?)
と思いながら前方を見ると、大きな高級ホテルが見えて来た。五条は迷うことなくホテルの方へ向かっている。
「え…ホテル…?」
「腹、減ったんだろ?」
「……え」
「んなもん顔見りゃだいたい分かんだよ」
苦笑交じりで応えると、五条は豪華なロビーを抜け、サッサとフロントで手続きを済ませてキーを受けとった。スタッフの案内を断り、を連れてエレベーターへ乗り込む。いきなりの展開にの頭がついて行かない。確かに空腹ではあるが、こんな出張先でしたことはない分、緊張してきた。五条は慣れた足取りで廊下を歩いて行くと、自分達の部屋を見つけてカードキーを差し込んだ。その様子を見ていたは「ここ、泊ったことあるの?」と尋ねる。何か話していなければ落ち着かない。
「ああ、京都出張の時にな」
「そ、そうなんだ…。こんな高級ホテルでも経費で落ちるんだね」
なるべく明るく言いながら豪華な廊下のオブジェを眺めていると、繋がれていた手が強く引き寄せられた。
「さ、さと―――」
名前を呼ぶ暇もなく、部屋に連れ込まれた瞬間、唇を塞がれ、は驚きで目を見開く。それは交換の時の接吻とは違うものだったからだ。豪華な調度品も、窓から見える京都の街並みも見ることなく、五条はの唇を貪るように何度も角度を変えて口付けた。
「…ん…ぅ」
壁に押し付けられ、深く交わるほどのキスをされ、すぐさま強引に唇を割って舌が差し込まれる。あまりの性急さに驚き、逃げようとした舌を絡み取られ、軽く吸われると背筋がゾクリと粟立つ。
いったい、どうしたというんだろう――?
交換の儀をする為に来たはずなのに、今、五条にされているのは普通に男女がするものと同じキスという行為で、生気など吸う余裕もないくらいに口内を愛撫されている。
「ん、」
その時、長い長いキスが終わり、乱れた呼吸を整えるように空気を吸い込みながら顔を上げる。しかしその瞬間にの身体は抱えられ、奥のベッドルームまで連れて行かれた。
「さ…悟…?」
慌てて五条の首にしがみつきながらも、未だ状況が把握できないは、皺ひとつなく綺麗に整えられたベッドの上に寝かされた。同時に五条が覆いかぶさって来たのを見て、慌てて手で制止する。
「ど…どうしたの…?悟…」
「どうもしない。ただ…を抱きたいだけ」
「……っ?」
「いや?」
の顏の横に手をつき、上から見下ろしてくる青い双眸は、今の言葉を裏付けるかのように情欲の色を孕んでいた。それに気づいて戸惑いながらも、五条から求められていると思うと、の鼓動は一気に速まる。
「い、やじゃ…ないけど…」
そう、これは交わりたいという意味だ。速くなる鼓動を沈めるように、冷静に今の言葉の判断をする。ただ初めて交わった後も定期的に抱かれて来たが、こんな風に強引に事を進めようとしてくるのは初めてだった。だからこそ驚き、多少の戸惑いを感じてしまう。
「…悟…どうか、した?何か…いつもと違う…」
制服のボタンに指をかけた五条に、つい問いかけた。しかし五条は応えないまま、ボタンを器用に外していくと、の首筋へ口付ける。その甘い刺激にピクリと肩が跳ねた。
「…嫌だった」
「……え…?」
はだけていく場所に唇で触れながら、五条がポツリと呟く。
「他の男に触れられてんのが……嫌だったんだよ」
「……悟…」
ゆらゆらと揺れる碧眼が不愉快そうに細められるのを見て、の心臓がいっそう速くなった。情欲の孕んだ双眸に嫉妬の炎ともとれる熱が垣間見える。
「は……僕のものじゃないのにな…」
悲しげに微笑む五条の顏が、の胸を痛くさせた。
直哉は完全にかませ犬的な扱いで終わる…笑