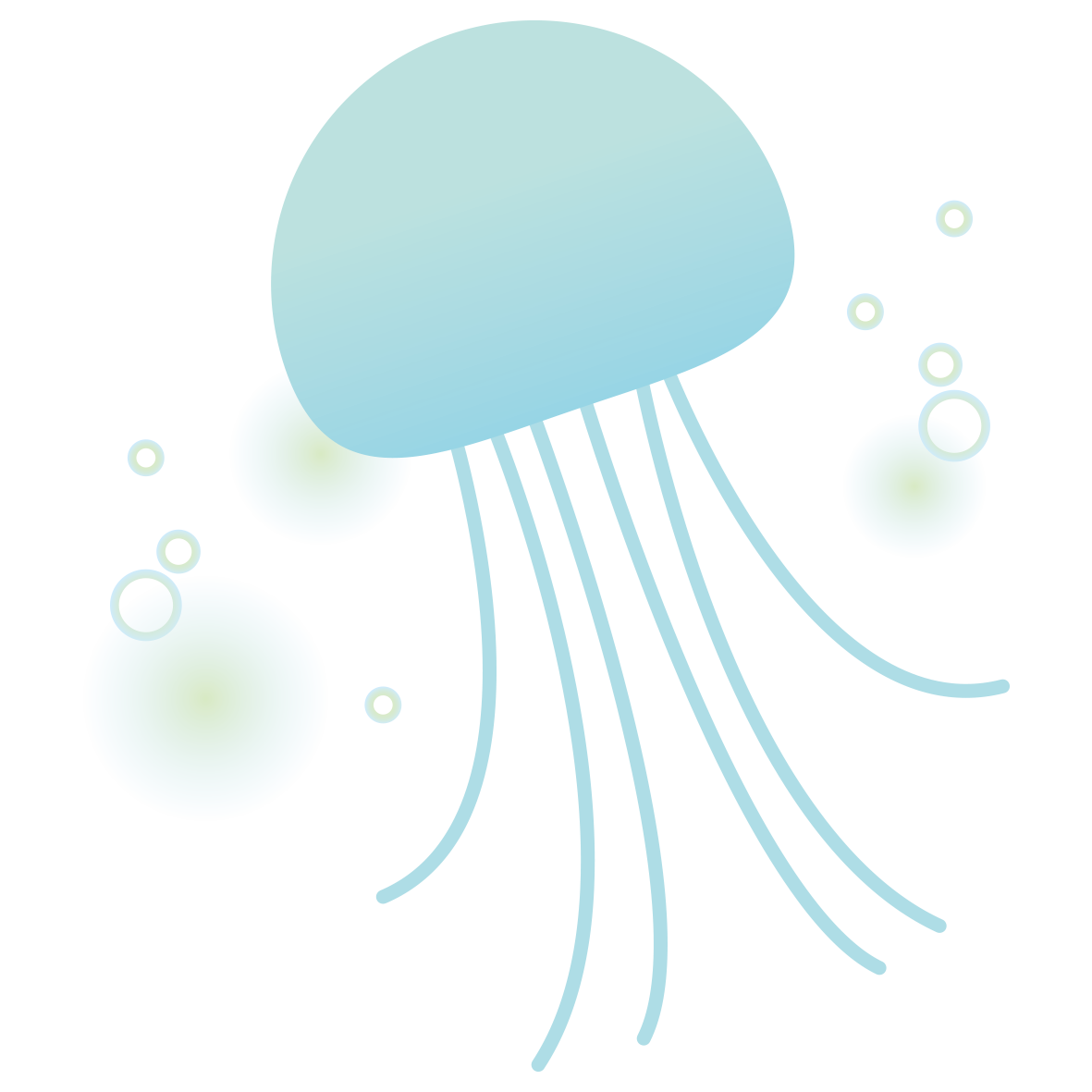「あっちか…」
僅かながらの妖力の残穢を見つけて五条はそれを追うように歩き出す。それは海がある方向だった。その時――五条の六眼が不思議な光を捉えた。
「あれは…」
海のある方向が青白く光って見えることに気づき、五条は一気に走り出した。
(あれは――鬼火だ!)
前に何度も見たことがあるの鬼火だと気づいた五条は更に走る速度を上げていく。嫌な予感がした。
(紅葉は…どうやって死んだ?海に身を投げたんじゃなかったか?まさか…まさかも――?)
紅葉のことを記した文献にも彼女がその後にどうなったのかは書かれていなかった。遺体が見つからなかったからだ。紅葉が本当に死んだのか、それともどこかで生きているのか分からないとされてきた。しかし生きていたのなら生気を喰らわずに生きて行けるはずもない。その痕跡が見つかったという文献は五条家にもなかった。
(ならやはり紅葉はすでに死んでいる。もしその記憶がの中に刻まれているならこの場所に引き寄せられてもおかしくはない…)
と紅葉の共通点。それはまさに――自分。六眼だ。
「クソ…!紅葉と共鳴したってことか…」
間違いない。は僕を――。
五条は街中を抜け、青い光のある方へ走った。街の人々が不思議な青い光に気づき始めている。騒ぎになる前に早くを見つけなければならない。
(500年前と同じ結果にはさせない…僕は…ここにいる)
海沿いを全力疾走しながら、青く光っている場所を六眼で確認した。
「あそこだ」
"蒼"を使い、一瞬で浜辺を移動すると、冷たい海へ入って行く。沖合いの辺りには幻想的なほどに綺麗な、青い鬼火がふわふわと浮いていた。
「…」
五条はそのまま冬の海へ一気に潜った。無限のおかげで濡れることもなく泳いでいける。夜の闇はの鬼火が照らしてくれている。あとは六眼での妖力を目視出来た。
(いた――!)
暗い海の底。ゆらゆらと漂う白い髪。少しずつ距離を詰めると五条はの方へ腕を伸ばした。指先がかすかに触れる。しかし波のせいであと少しが届かない。
(蒼で詰めるか…?)
だが海の中で術式を使えば余計に波が荒れてしまう。五条は少し考えると無限を解除した。そのまま一気に速度を上げての手を掴むと自分の腕の中へ納める。だが思っていたよりも深く、息が続かない。肺が押しつぶされそうなほどの苦しさを感じ、再び無限を発動した五条は鬼火を頼りにを抱えたまま"蒼"を発動し、一気に水面に向かって上昇していった。
「…はあぁぁぁ…疲れた…」
空中まで飛び上がった五条は深い息を吐き出し、腕の中のを見下ろした。冬の海に沈んでいたせいで全身が青白く、息をしていない。五条はすぐに浜辺へ下りると、そっとを横たわらせ、軽く頬を叩いた。
「…!」
頬に触れると氷のように冷たい。五条は軽く息を吸い込むと、の鼻を軽くつまんで人口呼吸を施した。同時に生気も送り込む。何度か繰り返していると、不意にが激しくむせ始めた。
「ゴホッ…ゴホゴホッ」
「…!大丈夫か?」
「…ん…さと…る…?ゲホッ…」
水を吐き出しながら、は朦朧とした目を五条に向けた。自分がどこにいるのか分からないようで、何度か瞬きを繰り返している。
「こ…ここ…」
キョトンとした顔のを見て、安心したのと同時に五条の中に怒りが突如湧いて来た。
「何やってんだ、オマエは!紅葉みたいに死ぬ気だったのかっ?」
「…もみ…じ…?」
怒鳴られたことでビクリと肩を揺らしたは、ハッとしたように身体を起こすと、後ろに広がる海を見つめた。どうやら自分がどこにいたのかを思い出したようだ。五条は呆れたように息を吐くと、その場に大の字になって寝転ぶ。真冬に海へ潜った寒さよりも、今は精神的な疲労の方が酷かった。
「はあ…ったく…どんだけ僕を心配させれば気が済むんだか…」
「悟…何で…」
「何でじゃない。が高専に顔も出してないって夜蛾先生から訊いて探したんだよ。まさかこんなとこまで来てるとは思わなかったけどね」
「………」
五条の言葉には悲しそうな顔で俯く。ほんの少しひとりになりたかっただけだったのに、知らないうちに大ごとになっていたようだ。
「…鬼火も消えたな」
「え…?」
「あそこに鬼火が浮いてたからのいる位置が分かったんだよ」
五条の指す方向へ視線を向けたが、今は何も浮かんでいない。暗闇に波の音がするだけだ。そこで自分がずぶ濡れだということに気づいた。
「ックシュ!」
「はあ…マジで風邪引く…つーことで行くよ」
「え…さ、悟…?」
突然、の腕を引っ張り、歩いて行く五条についていきながら、はどういう顔で向き合えばいいのか分からず「待って」と声をかける。しかし五条はイラだったように「待たねえよ」と言っての腕を引き寄せた。
「オマエ、死ぬ気だったのか?」
「え…?」
「紅葉と同じように、飲まず食わずで海の底で灰になりたかったのかよっ?」
「ち…違う…っそんなんじゃ…」
は必死に首を振りながら、どう説明しようか迷っていた。この海へ来た途端、自分の意識なのか、それとも紅葉の意識が乗り移ったのか分からなくなった。そして引き寄せられるまま、海の中へ紅葉の影を追いかけたのだ。その時のことをどうにか説明すると、五条は更に目を吊り上げた。
「あ?紅葉の影って…」
「い、いたの、ほんとに。私には見えた…」
「だからって普通冬の海に入るか?鬼だから生きてたものの、普通の人間だったらとっくに死んでる!」
「ご…ごめんなさい…でも…見つけたの…」
「……何を?」
「これ……」
そう言いながらはポケットの中から細い針のようなものを出した。それは錆びついてはいるが、まだはっきりと形状を保っている。
「これ…簪…か?」
「うん…紅葉さんの」
「は?」
さすがの五条も目が点になった。数百年も前の簪が形を保っていることもさることながら、それがずっとこの海の底にあったという事実に唖然としてしまう。
「これね…紅葉さんが六眼の人に貰った大切なものだったみたい」
「…それは…紅葉の記憶か?」
「うん…。きっと私がここに来たことで彼女の想いが私をそこに連れて行ったんだと思う。でも、だから死のうとしたわけじゃなくて…」
「………」
の説明に、今度こそ五条は盛大に息を吐いて項垂れた。五条からすればそんなものの為に海の底へ潜ろうとは思わない。だがは紅葉の切ない想いを感じ取り、共鳴して無意識にやったことだろう。
「あの…ごめんね…悟」
いつにも増して機嫌の悪そうな五条に気づき、は謝った。こういうところは素直なんだよな、と内心呆れつつも、つい苦笑いを浮かべた五条は項垂れているの頭にそっと手を置いた。
「何で…この街に?」
「え…?」
「僕には寮に戻るって言ったよな。なのには高専に帰らず、呑気に鬼の地巡りって。何の為?」
「な…何でそれ…」
「そりゃすぐ分かるよ。調べる方法はいくらでもあるし」
「………」
まさか自分の足取りが全てバレているとは思っていなかったは困ったように目を伏せた。何故?と聞かれたら、それはやはり――。
「で、何の為?」
「あ、あの…」
この前あんなに五条の想いを拒否するようなことをしておいて、今更ツラかったとは言いにくい。どう説明しようか迷っていると、再び鼻がムズムズとして「ックシュン!」と盛大なクシャミが出てしまった。
「あー…お互いずぶ濡れだしこのままじゃ風邪引くか…」
「…ぐす…ご、ごめんね、悟まで濡れちゃってるし…」
「まあ…水の中だと無限が邪魔になることあるから仕方ない。ってことで…行くよ」
「え…?」
五条はの手を取ると、そのまま公道の方へ向かって歩いて行く。こんな初冬にずぶ濡れで歩くふたりは相当目立つのか、近くを歩いている人達からジロジロと見られてしまった。ただでさえさっきの鬼火のせいで人が集まって来てるのだ。
「え、青い光ってどこ?光ってなくない?」
「うそー!UFOだったのかな?見逃したー」
そんな会話が聞こえて来て、はしまったという顔をしている。どうやら意識して出した鬼火ではなかったようだ。けれど、その炎のおかげで五条はの居場所が分かったのだから、結果的に良かったとは思う。ふたりはそのまま人目を避けるように公道を渡ると、五条は近くに見えた旅館のような建物の方へ歩いて行く。
「あ、あの悟…どこに…」
「こんな濡れたままで帰れないだろ。まずは体をあっためなくちゃ風邪引くし。服はホテルで乾かしてもらおう」
「え…」
原因を作ったに決定権などなく、そのまま五条の手に引かれてホテルへ入る。浜辺の宿と書かれた暖簾をくぐると、純和風な空間が広がったロビーだった。受付で部屋があるか尋ねると、ちょうど一室空いているという。五条はすぐにその部屋を取った。

「うん…大丈夫。まだ詳しい話はしてないけどね。だから硝子も心配しないで。うん。ああ、それと夜蛾センセーにお礼言っておいて。ああ。じゃあ…」
五条はそこで電話を切った。風呂から上がったが浴衣に着替えて戻って来たからだ。はどこか気まずそうに入口のところに立っている。五条は部屋に設置されたポットで温かい紅茶を淹れると「座れば」とを促した。
「温まった?」
「…うん。悟は?」
「温泉に浸かったら復活した。冬に海で泳ぐもんじゃないな」
そう言いながら苦笑すると、はまたしても泣きそうな顔で「ごめん」と呟く。だが五条はに謝ってもらいたいわけじゃない。
「…で?さっきの話の続きだけど…は何でこの街に来たの」
「………」
は紅茶を一口飲んだ後、ふと顔を上げたものの、またすぐに俯いてしまう。五条は小さく息を吐いて「そろそろ本音を言えよ」とを見つめた。
「ほ、本音って…?」
「この前が言ったこと…あれ全部嘘だろ」
「……ど、どうして…」
「さっきオヤジにも電話をしてに何を言ったか聞いた」
「……っ?」
そこでが顔を上げた。戸惑うように揺れる瞳を見れば、やはりそうか、と五条も苦笑する。自分の意志じゃないことは、その顔を見れば一目瞭然だ。
「もういいよ」
「……え?」
「もう五条家の未来のことなんて、は考えなくていいって言ってんの」
「な…別に私は――」
「今大切なものを手放して一族が潤ったところで…僕は嬉しくない」
「悟…」
「だからオヤジにもそう言った。そんなに未来の五条家が気になるなら今のうちにぶっ壊す。鬼族との制約も全て白紙にする。何もかも消えてしまえば心配することもないだろ」
「な…何それ…」
めちゃくちゃだ、とは唖然とした。仮にも五条家の当主である男が言う台詞ではない。そんなことをしたら数百年も続いた関係が壊れてしまう。
「そ…それは困る…」
「困る?」
「だ、だって…制約が全て白紙になってしまったら…鬼族はどうすればいいの?また人を襲って生きろって言うの?」
「そんなはずないだろ。そこは何も変わらない。これまで通り皆には交換の儀を続けてもらう。でも制約に縛られることはない。そうだろ?」
「で、でも…」
「…制約なんかなくたって鬼族はもう人間の脅威じゃない。今は数も減って全ての鬼が五条家の元で働いてる。普通に暮らしていけてる。それは今後もずっと続いていくよ」
五条の顏は真剣だった。嘘をついている感じでもない。もし五条の言うように制約を全て白紙に戻し、今まで通りの生活を続けられるなら、それは鬼族にとってもいいことなんだろうか。そんなことになれば自分のように相手に想いを寄せてしまう者達が増えるだけなんじゃないのかという心配はある。それは人間と鬼の子が出来てしまう確率の高さを現わしているからだ。
「そんなこと…やっぱり無理だよ、悟…」
「何で?」
「だって…」
「もしかして子供のこと言ってる?」
「そ、それだけじゃないけど、でもそれが一番まずいでしょ?お互いの脅威になるような子が生まれたら…」
「別にいいんじゃない?出来たら出来たで」
五条はシレっとした顔で言いながら、紅茶を飲んでいる。は驚いて何も言えなかった。
「だって誰ひとり産んでもいないのに何をそんなに恐れる必要があるんだよ」
「そ、それは…そう、だけど…」
「別に生まれた子が鬼の力を持っていようが、要は教育がちゃんとしてれば問題ないと思うけど」
「そ、そんな簡単に…」
「簡単なことだよ。それに鬼女が人間の子を産んだなら、多分その子は鬼の力が弱いはずだ」
「弱い…?」
「そう。血が混じることで鬼の力も次第に弱まっていく。そのうち人間に近づく。元々人間から生まれた存在だからね」
「元は…人間…」
はよく分からなくなった。この世では異質な存在だと思っていた自分にも、人間の細胞は混じっている。ならば鬼とはいったい何者なんだろうと疑問に思う。人の形をしているのに人とは違う存在。それはまるで――。
「そもそも呪術師だってこの現代じゃ化け物扱いされるよ。そういった意味で言えば似た者同士だと僕は思うけど」
五条は当然のように言った。術師として人を救う立場にある男が、自分は鬼と似た者同士だと言い切った。他の呪術師が聞いていたら激怒するかもしれないことを、五条はそんなものは大した問題じゃないとでも言うように笑う。それはにとっての救いの言葉でもあるように思えた。最強と恐れられている五条も、この世では異質な存在なのかもしれない。そしてそれを自分でも自覚しているのだ。ただ五条の言ったこと全てを五条家の人間が納得するかどうかは別の話だ。けれども、は五条が自分の意志を押し通すつもりでいることも、分かっていた。
「……悟ってほんと強引で我がまま」
が呆れたように言えば、五条はただ笑うだけだった。どこまで本気なのかも分からない。
"悟と添い遂げたいわけじゃないだろう?"
五条の父にそう問われた時、は何も言えなかった。これまで通り、鬼と呪術師という関係でいて欲しいと頭を下げられれば、はいと応えるしかなかった。
"息子を一族の裏切者にはしたくない"
その親の願いを聞いてしまえば、自分の恋心など隠し通せばいいだけのことだと、思ってしまった。なのに当の本人は自ら裏切者になろうとしている。親の心子知らずとはよく言ったものだ。
「…この前も言った通り、僕はオマエが好きだよ。大事に思ってる。これからも僕のそばにいて欲しいと思ってる。でも今の鬼姫と六眼という関係だけじゃなく、ちゃんと僕をひとりの男として見て欲しい」
「悟…」
「僕は裏切者になっても、親不孝だと言われても、が欲しい」
五条の素直な言葉に頬が一気に赤くなる。嬉しくないはずがない。ずっと心の中で想って来た。それでも互いの立場を考え、諦めようとしていた相手から好きだと言われたのだから。
ただには分からなかった。
「何で…そこまで…?」
ただ儀を行って来た関係だ。いくら触れ合って来た回数が多いとは言っても、それだけで愛情が育つものでもない。いったいいつから五条はここまで想ってくれるほど、自分のことを好きになってくれたんだろう、と不思議だった。
の問いに、五条はふっと笑みを浮かべた。
「僕はといると楽しい」
「…え?」
「一緒にご飯やケーキを食べたり、映画を観たり、仲間とバカみたいにはしゃいだり。そういうありふれた時間をと過ごしている時が、僕は一番楽しい」
「悟…」
そんなことは鬼じゃなくても出来る。普通の人間でも出来ることなのに――。
真っすぐ、真剣な眼差しで想いを伝えてくれる五条に、これまで抑えていたものが溢れそうになった。何故こんなにも惹かれてしまうのか分からなかった。でも紅葉の想いに触れ、やっと分かった気がする。古の頃から鬼姫と六眼は細胞で繋がっているのだ。呉羽と六眼から始まった物語は、現代の今も強く深いところで繋がっている。だからこそ、こんなにも懐かしく、切なく、恋しい。
そして五条の言うように、時間を共にしている時、も間違いなく楽しかった。何度もケンカをして、そのたびに仲直りをした。そんな人間臭い時間を過ごすことが出来たのは五条のおかげであり、更に言えば五条といる時だけは自分が鬼でもいいんだと思えるからだ。何を隠すでもなく、ありのままの自分を見せられるのは、五条だけだった。
「で…の答えは?」
「わたし…は…」
悟が好き――。
今日まで言えなかった秘めた想いを伝えたい。そう思った時――突然静かな部屋にぐうぅっというのお腹の音が鳴り響いた。
「………」
「………」
まず五条の顏がデフォルメされるのと同時に、の顏は徐々に赤みを帯びて、最後は耳まで真っ赤になっていく。まさかこんな大事な場面で腹の音が鳴るとは思わない。だがよく考えてみれば、前回の"食事"から一ヶ月は経っている。そのことを思い出した五条は思わず「ぷっ」と吹き出してしまった。
「……だから……腹…鳴らすなって…はははっ」
「わ、笑わなくてもっ」
「だ、だって……派手にぐぅーって鳴ったし笑うでしょ、フツー」
「…仕方ないでしょ!空腹だったんだからっ。さっきから悟がいい匂いさせるから…っ」
マンションを出た後でそのことに気づいたものの、あんなことを言った後にのこのこ戻れるはずもなく、何となく考えないようにしてこの二日間を過ごしていたのだが、やはり普通の人間よりも遥かに濃い生気を放つ五条がそばにいると、甘い匂いに釣られてしまうようだ。一度思い出してしまった空腹は収まることなく、逆に膨らんでいくばかりだった。
「じゃあ…が本心を言ってくれるなら、食べさせてあげるよ」
「…な…ズルい!」
肩を震わせながら笑いをこらえている五条を見て、が真っ赤になる。しかし五条は一歩も退かないという姿勢で首を振った。
「ズルくない。僕はちゃんと伝えたし」
「……う…」
「早くしないとまたお腹鳴っちゃうだろ」
ニヤニヤしている五条を睨んでみたところで、絶対に言わないとダメな空気になっている。気づけば向かい側に座っていた五条がの隣に座っていた。余計にいい匂いが漂ってきて、ゴクリと喉が鳴ってしまう。
「わ…わたしも…」
「うん」
「悟が……す…好き…」
言った瞬間、顔の筋肉がおかしなことになった。恥ずかしくて両手で顔を覆うと、その手を強く引き寄せられる。
「悟…」
「よく出来ました」
五条はサングラスを外して微笑むと、ゆっくりと唇を近づけ、の唇を塞ぐ。だが何度も角度を変えながら啄むそれは、交換の儀ではなく――。
「ん…さと…る?」
「まずは…僕の方を満たしてもらわないとね」
驚くの唇にちゅっとキスを落とし、五条は妖しい笑みを浮かべて呟いた。
残り一話…