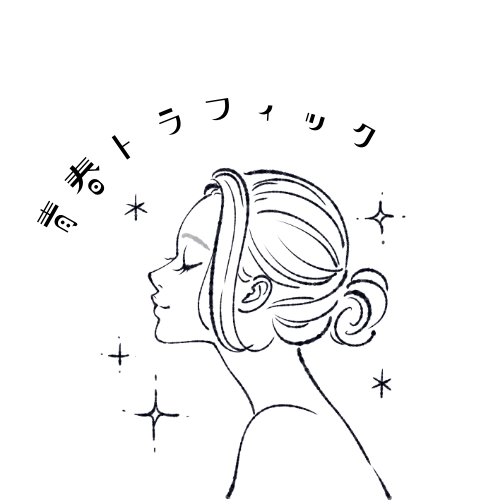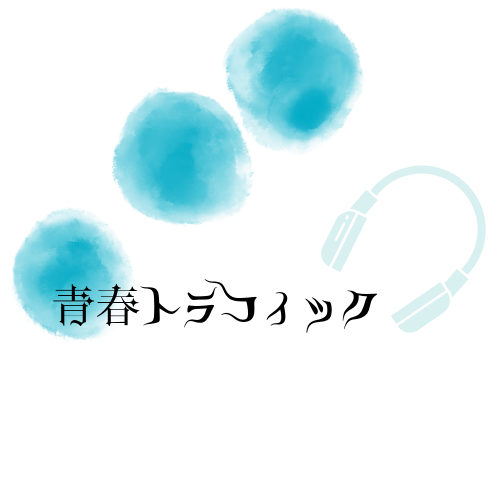
炎天下の下、白いシャツの肩先で伸びた髪が弾むように揺れる。
子供の頃からずっとショートだった僕の幼馴染が、いつの間にか髪を伸ばすようになっていた。
隣の家に住むは、僕が僕だと自我を持った頃から傍にいて、隣にいるのが当たり前な存在だった。
互いの家に行き来するのも日常で、夕飯なんかはどっちの家で食べる?なんて会話が成立するくらい自然なこと。
学校へ行くのも一緒だし、帰りも時間が合えば一緒に帰る。常に僕の隣にいたのがだった。
ただ、小学校までは良かったけど、中学に上がると僕らの関係を変に邪推するヤツも出てくる。
「いっつも一緒にいるけどお前らデキてんじゃねーの」なんて、からかわれるのも日常茶飯事。
だけど僕はのことを異性として意識したことは一度もなかった、と思う。
だっては子供の頃から髪は短いし、口は悪いし、すぐ男子とケンカする。男の僕より男の子みたいなヤツだったからだ。
そんな彼女が中学に入って乱暴な言葉遣いが減ってきた。同じクラスの男子から「可愛いのにもったない」と言われたとかで、そこから女としての自覚を持ち始めたんだと思う。
クラスのヤツに言われたくらいで変わるなんてらしくない。だいたい普通のテンションで女子に「可愛い」とか言える男ってどうなの。
どんなヤツだとのクラスまで見に行ったら、どうってことない男だった。身長も低いし、特別カッコいいわけじゃない。無駄に明るいだけが取り柄みたいなヤツ。
何であんなヤツに言われただけで言葉遣いを直したのか全く理解できなかった。
「アイツのこと好きなの?」
あの時は何故か悶々とした気分になって一度だけそう尋ねたこともあったけど、は「え、別に普通」と言うから、ちょっと拍子抜けした。
でも何となく。それ以来、無駄に元気で明るいだけが取り柄みたいなヤツが苦手だ。(ああ、そういや今のバレー部にも似たようなのいたっけ)
で、今の高校に入ったら入ったでショートだった髪が伸びて、今朝はポニーテールをしている。毎日会ってたのと、今まで下ろしてたから気づかなかったけど、髪を縛ったらガラリと印象が変わって見えて死ぬほど驚いた。
「おはよー蛍!」
「……」
いつも通り早く家を出た方が迎えに行くという流れに沿って、今朝はの方が僕の家に来た。
朝食を食べたあと、部屋で着替えていたらインターフォンが鳴って、下から「ちゃんが迎えに来たわよー」という母さんの声。でもその直後「あらあら、ちゃん?可愛い~!」なんてはしゃいだ声がして何事かと思いながら下りて行ったら、そこには――僕の知らない女の子が立っていた。
「え、?」
「そうだよー。やっと縛れるくらい伸びたからポニテにしてみたの。どう?似合う?」
明るい笑顔で僕を見上げてくる顔は、僕の知ってるのようでいて、初めて会った女の子のようでもあった。
僕が鳥野高校へ入学したらも当然のように鳥野へ入学。だから子供の頃から続いている一緒の登下校は今も健在だけど、今朝は知らない女の子と歩いてるみたいで、やけに気持ちが悪かった。
「あ、そうだ。今週末、買い物に付き合ってよ」
いつものように隣を歩くが、僕のシャツをくいくいっと引っ張ってくる。それも普段と同じ。
でも彼女の雰囲気だけが違う。
「……何で」
「ほら、来週は合同合宿あるでしょ。だから色々と必要なもの買いに行きたいの」
旅行か何かと勘違いしてる?と突っ込みたくなるくらい、はそれを楽しみにしてるようだ。清水先輩から「マネージャーやってみない?」なんて誘われて、お試しとして音駒との練習試合についてきたは今じゃすっかりその気になってる。高校入ったら部活には入らないで青春を謳歌する!なんて豪語してたクセに、もう自分で言ったことを忘れてるらしい。
僕が「高校でもマネージャーやれば」と言った時は秒で断ったクセに。
「買い物って合宿行くだけなのに何をそんなに買う必要あんの」
「あるよー。女の子には色々あんのー。男の蛍には分かんないだろうけど」
「あっそ。ってか女の子ってどこ?」
わざとらしく手を翳してキョロキョロしてやると、僕よりもかなり小さいは「ここにいるでしょーが」と腰の辺りを殴ってくる。馬鹿力だけは見た目が変化しても健在らしい。
「いちいち殴んないでくれる」
「いちいち蛍が失礼だからだよ」
「すぐ暴力に訴えてくるヤツって頭悪いんだよなぁ、だいたい」
「む……」
あースネちゃった。唇をむぅっと突きだした時はの機嫌が急降下した証だ。僕の嫌味なんて今に始まったことじゃないんだから、本気でスネなくてもいいのに。
は歩く速度を上げて、どんどん先へ歩いて行く。その後ろを着いて行きながら、何を言えばの機嫌が良くなるか、今日までの膨大な過去データの中から一つ一つ探していく。
その間、彼女の背中で揺れるポニーテールを眺めていると、やっぱり知らない女の子のように感じて意味もなくイライラした。
「おい、――」
買い物、どこに付き合えばいい――?
そう聞くつもりで声をかけた。過去のデータではそういう言葉でコイツの機嫌は直るはずという答えが導きだされたからだ。なのにそれを言う前にの方から「あ、今度の合宿なんだけど――」と声をかけてくるから言いそびれてしまった。
「音駒の黒尾先輩も来るよね」
「……は?」
随分と乾いた「は」が僕の口から零れ落ちた。今、何でその名前がの口から出てくるのかサッパリ分からない。そりゃ前に練習試合をした時、も清水先輩に手伝いを頼まれて参加してたから音駒の選手と顔は合わせてるけど――。
「蛍?聞いてる?」
固まったまま立ち尽くしてると、がひょいっと顔を覗き込んでくる。その時ポニーテールがふわりと動いた。いきなり女の子っぽい仕草をするから、僕の脳内でシステムが誤作動したみたいに思考がまとまらない。
まさか急にが色気づき始めたのって、そういうことか?
別に何を言われたわけでもないのに、僕の脳内ではがあのトサカヘッドの先輩とキャッキャウフフしてる光景がエンドレスで流れ始めた。同時におかしな動悸がしてきたけど何これ、気持ち悪い。
「ねえ、蛍ってば」
「……聞いてるよ」
どうにか脳を再起動をしようと冷静を装い歩き出す。は「待ってよ」と追いかけてきた。
「あの人が来たらなんだっていうのさ」
「ん?」
「黒尾って人。何か用でもあるわけ」
「あーうん、まあ……ちょっとね」
えへへ、と変な笑い方をしながらが僕から目を反らす。それを見てたら胸の奥がずーんと重たくなるのは何なんだ。
「で、来るかな。黒尾先輩」
「……そりゃ来るんじゃない。主将だし」
「あ、そっか。主将だっけ」
「何。そんなことも知らないで訊いてきたわけ――」
言いながらジト目を向ければ、は何やら熱心にスマホを弄っている。人に話を振っておいてスマホ弄るとか失礼な奴だ。今度は僕が「、聞いてる?」と尋ねる番だった。
「え?あ、ごめん。友達にね。黒尾先輩も来るって教えてあげてたの」
「……友達?」
「そう。希子ちゃん」
「……」
希子ちゃんというのはの中学時代からの女友達で、確か女子バレーをやってた子だ。この流れで何で彼女の名前が出るんだろうと思っていると、その答えはが教えてくれた。
「希子ちゃん、黒尾先輩のファンらしくて、もし合宿で会えたら写真を撮ってきてって頼まれたんだあ」
「……へぇ」
「え、何で笑ってんの、蛍ってば」
「別に~。っていうか急がないと遅刻するし行くよ」
「あ、待ってよ、蛍」
自分でもよく分からないけど自然と口元が緩んでくる。さっきまでの重苦しい気分がやけに軽くなった。
何だ、そっか。友達に頼まれただけなんだ。
その事実が僕の中では顔が緩むくらいホっとさせてくれた。何でそうなるのか、もう僕の中で答えは出てる。さっきバグったデータの中に、それはあった。
男勝りで口が悪くて、全然女の子って感じじゃなかったのに、僕にとってはずっと女の子だったってこと。
彼女が急に見た目まで変わって焦ったのは、その裏に僕にとって不都合な理由があるんじゃないかって危険信号を発したせいだ。
でも今回、それのおかげで自分の気持ちを自覚することが出来た。なら、そこから先は僕次第だ。
「それで……買い物ってどこに付き合えばいいの」
隣を歩くへ尋ねると、彼女は心底嬉しそうな笑顔を僕に向けてくれた。
のポニーテールが可愛く揺れても、僕の心はもう変に揺らぐことはない。
今なら過去一、素直になれる気がしたから。
「その髪型、似合ってんじゃん」