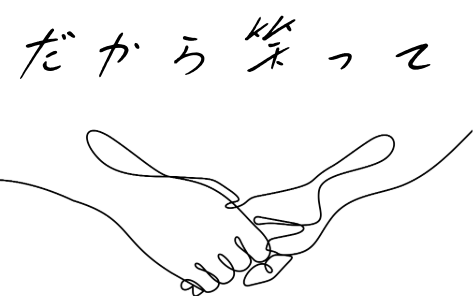決して油断をしてたわけじゃない。ただ守るべき仲間を守っただけ。その為に負った傷なら、なんてことはなかった。
なのに彼女は俺が怪我をするだけで、いつも大げさに泣きわめく。それは学生の頃から何も変わらない。泣いたって何も変わらないのに。無駄な行為だと何度言ったところで、この同級生は毎回同じように傷ついた俺を見ては涙をこぼす。
「もう……何で無人くんはいっつも自分を犠牲にするのかな!」
「犠牲にしてるつもりはないが」
「してるでしょ!自覚なさすぎだよっ」
めそめそと泣きながら、駄々をこねる子供のように地団駄を踏むも、彼女は俺の為に血蝕解放をして治療を始めた。彼女の血には治癒能力がある。これはもう一人の同級生、花魁坂京夜の鬼の回復力を上げる力とは少し違う。
文字通り、彼女の血は肉体細胞の治癒を促す効果があり、血蝕解放は"可逆性"。例えば欠損した部分も肉体の情報を読み取り元通りに修復できるから、援護部隊でも重宝されていた。ただし、強力な力ゆえに大怪我を負った鬼なら治せるのは今のところせいぜい一人か二人というところらしい。当然ながら即死した者に効果はないが。
本音を言えば、彼女の貴重な血を俺なんかに使うのは無駄な行為だと思っている。治療せずとも、時間を置けば今回の怪我くらいなら自分の回復力でそのうち治るからだ。なのに彼女は「無人くんが守ったおかげで他に怪我人いないんだから治したっていいでしょ」と言う。
断ればまた泣きだすのは目に見えてるし、俺もそこは頷くしかなかった。
「いつまで泣いてるつもりだ?」
彼女のおかげで俺の怪我は見る見るうちに治っていってる。それなのにときたら未だにぐすぐすと鼻を啜りながら泣いていた。彼女が泣き虫なのは嫌と言うほど知っている。だけど、だんだんイラついてくるのは、今、この瞬間にも彼女を泣かせているのが俺なんだと思い知らされるからだ。
「最近はあまり泣かなくなったと思ってたのに、何でお前は俺の治療の時だけそんなに泣くんだ」
溜息交じりで睨みつけると、逆に涙でべしょべしょの目を吊り上げて睨み返された。以前の彼女なら俺が睨むだけでビビってたクセに、いつの間にこんなにも強くなったんだろう。
いや、元々芯の強い子だった。泣き虫だけど泣き言は言わず、自分のやるべきこと、または何が出来るかを常に考えてる。学生の頃より随分成長したなと思う。
……ただ、少々生意気にはなったかもしれない。
「そんなことも分からない無人くんはバカなの」
「俺はバカじゃない」
「じゃあ鈍感」
「……それはだろう」
「む……わたしのどこが鈍感なの?」
「自分で鈍感だと気づいてないところが鈍感だ」
「……だからそれ特大ブーメランだと思う」
「……(ブーメラン?)」
お互い譲らないとでもいうように暫し睨み合う。一瞬だけ治療室の中がしんっと静まり返った。
廊下では仲間の誰かしらがバタバタと走ったり、大声を張り上げたりと賑やかなのに、この部屋だけ時が止まったかのように静かだった。東京杉並支部の管轄であるこのアジトは、都心に近いこともあり多くの鬼が集う場所だ。なのに不自然なほど、誰一人として入って来ない。この場に流れる不穏な空気を感じてるんだろう。部屋に近づく気配はあれど、扉が開くことはなかった。
だけど流れる静寂を破ったのはやっぱり彼女で。ふと合わせていた目を伏せ、肩の力を落として俯く。
「……もう一人で無茶しないでよ」
「無茶なんかしていない」
「してるでしょっ!いっつも!無人くんだけなら無傷で済むはずなのに――」
「ならは仲間を見捨てろと言いたいのか」
つい売り言葉に買い言葉。そんなことが思うはずもないのに言ってしまった。
彼女は一瞬言葉を詰まらせて、やっぱりぽろぽろと涙を零して泣き出した。自分の愚かさに溜息が出る。
今のは完全に俺の失態だ。
「悪い……今の言葉は取り消す」
彼女の治癒能力が強力なのは、それだけ誰かを癒したいという思いが強いからだ。鬼の血は本人の趣味嗜好が色濃く反映されて血蝕解放に至る。の場合、それは自分の為の力ではなく、自分以外の為のもの。
常に誰かを守りたいと思ってるのは俺じゃない。彼女の方だ。
「ううん……わたしもごめん。無人くんはみんなを守ってくれたのにわたしはいつも文句ばかり言っちゃう……」
「だから泣くな」
傷の癒えた手を彼女の頭へ伸ばす。軽く撫でてやると、ゆっくり顔を上げた彼女の目は真っ赤に充血していた。学生時代、初めて同じ班になった時の、必死で泣くのを堪えてた瞳を思い出す。どう動いていいのか分からないといった様子であとをくっついてきた彼女に、俺自身も戸惑っていた。ずっと一人で生きてきたせいで、自分以外の存在とどう接していいのか分からなかったから。
「……兎みたいな目になってるぞ」
「う、兎は可愛いからいいの」
「可愛いかどうかは別として……に泣かれるのは困る」
頭に置いていた手を外すように動いた彼女は、俺の肩に顔をくっつけた。柔らかい髪が俺の頬に触れる。
「泣かせてるのは無人くんだもん……」
「そうだな……」
だけど俺だって泣かせたいわけじゃない。出来れば彼女の泣き顔は見たくないから。
でも彼女を泣かせてしまうのは、昔も今も俺なんだという自覚はある。あの頃より強くなったつもりでいたのに――。
「まだまだだな、俺も」
「え?」
「……何でもない」
心の奥に隠したものを言葉にするのは苦手だから、代わりに彼女の頭へぽんと手を添える。
からはいつもの消毒液の匂いがした。
「今日の無人くん優しい……どうしたの?」
「……やっぱり鈍感なのはの方だな」
「何でよ」
むぅっと唇を尖らせて見上げてくる彼女の瞳は、まだ涙の名残がある。この顔に俺がとことん弱いというのを、彼女は知らない。言葉に出来ない俺の心の内すら何一つ、気づいてない。
これを鈍感と呼ばずして何と呼ぶんだろう。
彼女が俺の傷つく姿を見て泣くのと同じで、俺だって彼女が泣く姿を見れば悲しくなるというのに。
こういう気持ちを教えてくれたのは、他でもないだった。
「無人くん?どこか痛い?」
「いや……」
ジっとの顔を見つめていたら怪訝そうな顔をされたが、最終チェックを済ませた彼女はホっとしたように「良かった。完治したよ」と微笑む。さっきまでびーびー泣いてた奴と同一人物には思えないくらいの明るい笑顔。この顔が見たかった。
彼女の笑顔が俺にとっての救いであるように、他の仲間にとってもきっとそれは同じで。にはなるべく元気に笑っていて欲しい。
彼女の泣きはらした目を見ていたら、やっぱりそう願わずにはいられなかった。