
それは不死川が食事中をしてる時、または風呂へ入っている時。はたまた自宅の庭先で訓練をしている時、常に感じていた。
今日は久方ぶりに早いうちから家路につくことが出来た不死川は、夕飯の時刻まで庭で刀を振るっていた。
鬼殺隊、特に柱ともなれば常に強い鬼と命の獲り合いをしなければならない。腕が鈍らぬよう、少しでも余裕があれば、こうして刀を振るのが常だった。
しかし、そんな時に必ずと言ってもいいほど、例の視線が突き刺さる。今日も今日とて、背後から熱い視線を感じて、ピタリと動きを止める。しかしパっと振り向けば、その視線を送ってきているであろう人物も素早く植え込みに身を隠す為、その姿を初手で見ることは出来ない。
だが不死川はその正体に当然気づいている。
「ハァ……おい、……いい加減それやめろォ」
刀を納め、未だにコソコソと視線を送ってくる人物の名を呼びつつ。汗を拭こうと縁側に置いてある手ぬぐいへと手を伸ばす。その瞬間、物凄い速さでそれを奪いとられた。と思えば、目の前に手ぬぐいが差し出される。
「お疲れさまです。実弥さま♡」
「……お、おう」
にこにこ可愛らしい笑みを浮かべる彼女を見ながら呆気に取られつつ、手ぬぐいを受けとった不死川は額から流れる汗を拭いた。そして水を飲もうとした瞬間、またしてもギリギリのところでコップを奪われる。
「お水、どうぞ♡」
「……」
先ほどと同じようにが差し出す並々と水の入ったコップを受けとる。
その際、不死川は何かを言いかけたが、目の前で期待を込めた純粋な瞳を向けてくるを見ていると、毎回何も言えなくなるのだ。その気持ちが深い溜息となって零れ落ちた。
「い、いかがされました?実弥さま!お疲れなら今すぐお風呂を――」
「あ~いい!いいから少しは落ち着けェ!」
走って行こうとするの腕を掴んで引き寄せれば、やっと大人しく腕の中に納まった――かのように見えたが、その体は軟体動物のようにクタリと後ろへ折れ曲がり、不死川の腕から崩れ落ちそうになっている。
それはが失神寸前なほど頭に血が上り、顔全体まで茹蛸みたいになってしまったからだ。
彼女の異変に気付き、不死川はギョっとした。
「おいっ!寝るなァ!」
「ね、ねね寝てません……!」
ハッと我に返ったはワタワタとしながら頭を元の位置へ戻す。しかし今度は目の前に不死川の顔があることに気づき、再び顔から火を噴いた。
……何、ということはなく。不死川のことが好きすぎるあまり、単に照れているだけだった。
「ったく……いちいち失神しかけんじゃねぇっ!」
「す、すすすみません……っ」
一瞬気が遠くなりかけたところをギリギリで踏ん張り、彼女はぐっと意識を保つ。そして"今日も怒鳴っている実弥さまは素敵だわ♡"と心の中で思うのだ。
この二人――先月めでたく祝言を上げたばかりの正真正銘、新婚夫婦である。
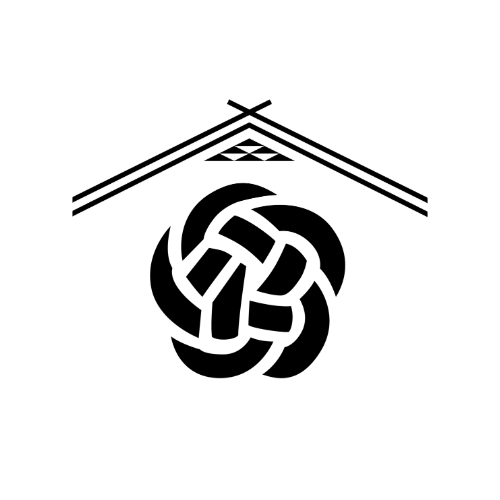
二人の出逢いは去年の冬。若い女ばかりが消えるという噂を聞きつけ、鬼殺隊の柱、不死川実弥はとある街へとやって来た。この街を荒らしているのは十二鬼月という報告を受けたからだ。
特に大きくもなく、しかし小さくもない街は、鬼にとっては格好の餌場となりやすい。
鬼の存在は隠しつつ、消えた女達の動向などを慎重に聞き込みしたものの、初日は何の手がかりも得られなかった不死川は、当然のようにこの街で一泊することにした。
運よく街には"藤の家"があり、世話になるべく不死川が訪問した際、出迎えたのが彼女――だった。
最近は鬼の噂を聞きつけた鬼殺隊の訪問が増えたらしく、忙しい祖母のお手伝いをしているという。
鬼殺隊、それも柱を出迎えるのは不死川で3人目だと教えてくれた。皆が十二鬼月を探しにこの街へ来ては見つけられずに帰って行くらしい。聞けば燃えるような闘志を持つ男と、逆に静寂を纏う御仁だったと聞き、不死川は炎柱と水柱の顔を思い浮かべた。大方、噂を聞いて来たはいいが、鬼に出会わず、更には他の任務でも入って飛んで行ったんだろう。
それを聞いた不死川は誰よりも先に、必ず十二鬼月を見つけて俺が頸を切ってやると決心した。
何せ自分は特殊な体質、鬼が好むと言われている"稀血"の持ち主なのだから、他の柱よりも鬼を引き当てる確率は高い。
不死川はその日から"藤の家"に泊まり込み、十二鬼月が現れるのをひたすらに待っていた。
その間の不死川の世話はが担当してくれていた。
彼女は18歳と若く、美しい娘だった。この街でも評判の美人ということもあり、夫になりたがる男は大勢いるらしい。
しかし当のはどんな男から言い寄られても絶対首を縦に振らない。それは自分が心底惚れた相手でなければ結婚しないと決めていたからだ。
故にどんな男からの求愛も全て断ってきたので、難攻不落の藤姫さまとまで言われるようになっていた。
そんなが初めて恋をすることになったのは、寒い冬の夜のことだった。
毎晩、十二鬼月を探して回る不死川を労おうと、温かい夕飯を用意して帰りを待っていた。しかし鍋に入れる薬味を切らしていたことに気づき、慌てて買い物へ出る。店が閉まる10分ほど前という時刻、は急いで夜道を駆けていく。鬼がうろつく街で、彼女のこの行動はあまりに軽率だった。
案の定、夜道を駆けるの前に、醜い異形の化け物が突如として現れる。それを見た時、彼女は一瞬、ぽかんとしてしまった。
呑気な人間なら誰しも思う「まさか自分が――」というやつである。
闇から姿を現した鬼は、悲鳴を上げる間も与えずを抱えて連れ去った。
そこで彼女はやっとそれが鬼だと気づいたものの、抗う術は何もなく、非力な女の身ではどうすることも出来ない。
祖母に「夜は出歩くな」とあれほど言われていたにも関わらず、言いつけを守らなかった自分を責めながらも、せめてこの鬼を探していた不死川に知らせたいと思った。
(そうだ……不死川さまは柱。彼らは血臭には鼻が利くと聞いている。風に血の匂いを乗せれば気づいてくれるはず)
幸い今夜は北風の強い日だった。は喰われるのを覚悟で自分を抱えて走っている鬼の頭頂部目がけて拳を何度も振り下ろした。ついでとばかりに自由の効く両脚をもバタつかせる。ただでは喰われてやらんという一心だった。
「放して!下ろしなさいっ。このバカ鬼!」
「コイツ……っ!大人しくしろっ!鬼狩りに気づかれるじゃねえか!」
その鬼は異様に警戒心が強く、さらった人間は必ず自分の塒へ連れて行ってから喰っていた。鬼殺隊が血臭に敏感なのを知っているのだ。しかしの暴れっぷりに我慢ならなかったのか、鬼は街から抜けた辺りでを地面に放り投げる。まずは瀕死にしてから運ぼうと考えたのだ。
「いったぁ……」
「へへへ……言われた通り下ろしてやったぞ」
力任せに地面へ落とされたは腰をしたたか打ち付けてしまった。痛みで身動きのとれない彼女の肌を、今まさに鬼の爪が切り裂こうとした、その時。一陣の風と共に飛んで来た攻撃が、鬼の頸を一撃で斬り落とした。
「ひぃっ」
地面に這いつくばっていたの目の前にごろごろと鬼の頭が転がってくる。先ほどまでは怯えた様子もなかった彼女ですら、それには悲鳴を上げてしまった。その鬼の瞳には下弦の文字。
十二鬼月とは言っても、どうやら下弦の方だったらしい。それを確認した直後、鬼の頭は塵へと変わり、風に吹かれて消滅した。
ホっとしたのもつかの間。その怒号はすぐに飛んできた。
「……何してんだ、テメエはァ!」
「し、不死川さん……?」
いつ来たのかすら気づかないほどの速さで現れた不死川は、動けなくなっていたをその腕に抱きかかえた。しかしその顔はいつもの不機嫌そうな……いや。普段より更に不機嫌極まりないといった顔で、額にはいくつもの筋が浮き出てピクピクとしている。相当ご立腹のようだ。
「こんな時刻にフラフラしてっから攫われるんだろーがァ!ババァに言われなかったのかよっ?」
「ご、ごめんなさい……」
お怒りはごもっともだとばかりに慌てて謝罪を口にしたのだが、自分を怒鳴り散らす不死川を見て何故かの頬が朱に染まる。胸がドキドキとうるさく、そのあとにキュンキュンと小さな音が追いかけてくるこの感覚は何なのだろう?
不思議に思いながらも、未だに怒鳴っている不死川を見つめては、また頬をポっと赤らめる。
実はこの、男に怒鳴られたのは後にも先にも不死川が初めてだった。
これまで言い寄ってきた男達は皆が優しく、彼女に対して誰より紳士的に接してくれていた。なので男は皆がこうなのだろうと大いなる勘違いをしていたらしい。
だから、というわけではないのだが、不死川の遠慮のない物言いで逆に心が動かされてしまったようだ。
この日からは不死川に対し、熱烈な恋慕を抱くことになってしまった。
別の任務で泊まりに来るたび不死川にベッタリと張り付いて、祖母からは「いい加減にせえ!」と叱られる始末。ついでに不死川にも「くっつなァ!」と叱られてばかりいたのだが、余計に想いを募らせていた。
だがしかし。そんな不死川もまた、滞在中に甲斐甲斐しく自分の世話をしてくれた彼女にどんどん惹かれていき、結果、の押しの一手(?)で二人は無事に結婚する流れに至った。
というわけで、二人は現在、絶賛新婚中の幸せ真っ盛り――のはずだったのだが。
不死川には一つだけ、重大な悩みがある。それは――。
「……」
夜になり、夕飯と風呂を済ませ、二人で寝室へ入る。夫婦なので当然、一つの布団に二人で横になった。
いくら普段は克己的で後輩の隊士達に厳しい不死川ではあっても、好いたおなごと結婚をしたのだから、やはり夫婦の営みは致したい。
それを実行をするべく、任務がなく家にいる時は必ず挑戦するのだが、寝床へ入り、いい雰囲気を作り、まずは口付けから……と唇を寄せると――。
「さ、実弥さ……まっ」
腕に抱いたの体が不意に脱力するのを感じた不死川は、深い深い溜息と共にがっくりと項垂れた。
「……またかよっ」
今夜こそ、と思っていただけに、不死川の落胆する気持ちは計り知れない。
というのも、毎度毎度不死川が触れるだけでの脳内が爆裂照れ状態に陥り、失神。こうなると、彼女をどんなに揺さぶろうが、必死に名を呼ぼうが、そのまま朝までグッスリという流れになってしまうのだ。
愛されすぎるというのも問題かもしれない。
「一体全体、いつんなったら俺とはまともな夫婦になれんだァ……?」
腕の中でスヤスヤと気持ち良さそうに眠っているを見下ろしながら、ふと苦笑を漏らす。その眼差しは殊の外、優しい。
「ったく……このまま襲っちまうぞ、コラァ」
ボヤきつつの鼻を軽くつまむ。すると寝顔が僅かに綻んだ。
「う~ん……さね、みさま……だい、すき……むにゃ、」
「……」
寝たまま愛の告白をされ、不死川の頬がほんのり赤く染まった。少し変わってはいるものの、可愛い妻であることに変わりはなく――。
「はあ……ったく、人の気も知らねえで」
頭を掻きつつ、溜息交じりで言いながら、不死川は寝ているの唇にそっと優しい口付けを一つ。
「しっかし……すっかり元気になっちまったコレ、どーすんだァ……?」
己の下半身を見下ろしながらボヤきつつ。今夜も腰が疼いて眠れずに、悶々とした夜を過ごす不死川だった。
