
冬の朝は夜より寒い、というのを実感しながら彼女は誰より早く寝床を抜け出した。
連日、鬼殺隊の霞柱、時透無一郎の元へやって来る隊士達の為に朝食を用意しなければいけないからだ。
――柱稽古をやる。
鬼殺隊、岩柱である悲鳴嶼行冥が口火を切り、決定した柱稽古はすぐに開始された。それはいいのだが、何せ初の試みとあって何かと準備不足。特に稽古中の無一郎、そして隊士達の世話をする者は絶対に必要だ。
それぞれの柱が話し合った結果、世話係は非戦闘員の手を借りるという話になったところで、無一郎から白羽の矢をたてられたのが"隠"として鬼殺隊に所属している彼女だった。
普段から無一郎の担当を任されることも多く、無一郎が鍛冶の里へ行く際も最後の道中を任されるのは彼女である。
無一郎から柱稽古の補佐を頼まれた時は何で私?と驚いたのだが、柱に頼まれてしまえば断るに断れない。
鬼の出現が極端に減ったからこその柱稽古であり、その場合、当然ながら隠の彼女も暇になるのだから。
しかし、それにしても、だ。
彼女は首を捻る。
「時透さまの様子がおかしい……」
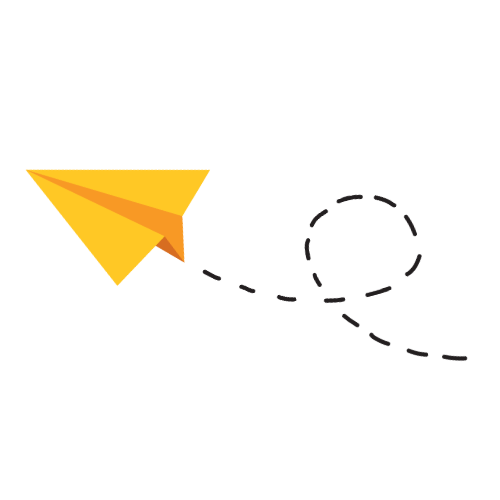
合理的主義で辛辣な言葉しか吐かないあの霞柱が、時透無一郎の様子が、どうもおかしいと気づいたのは、刀鍛冶の里から無一郎を連れ帰って少し経った頃だった。
上弦の鬼と激しい戦闘を繰り広げた無一郎達の体はボロボロで、当然のように蟲柱、胡蝶しのぶの住む蝶屋敷へ運んだのだが、その際も予兆はあったかもしれない。
というのも、治療の最中に意識を取り戻した無一郎は自分を蝶屋敷まで運んでくれた、かつ傍についててくれた彼女に対し「……ありがとう」という言葉を口にしたからだ。
これまで何度も無一郎と接しているが、そんな言葉を言われたのは初めてで、彼女はかなり驚いた。
最初は死にかけたことで何かの後遺症(!)かと思われたが、それ以降も変わらず。刀鍛冶の里、襲撃事件の前と後では天と地ほどの差があるくらいに人格が変わった、ように思う。
今回の件を頼まれた時、また塩対応をされる毎日なのだろうと予想していたのだが、柱稽古が始まって二日。未だ前の無一郎へ戻る様子もない。
いや、稽古を受ける隊士達には相変わらずなのだが、言葉の端々に何となく以前のような険がないのだ。キツい言動はむしろ本気で隊士達を鍛えようとしているように見えた。
それは彼女に対しても同様で、皆の世話をする彼女に対し、「ご苦労様」などと優しい言葉すらかけてくる。よって、塩対応の嵐を覚悟していた彼女も少々拍子抜けしていた。そして必ずそのあとに変な不安がこみ上げてくる。何が、とは上手く言えない、これまで感じたことのないそれはやたらと心臓を攻撃してくるので、何かの病なのでは……とそっちの方も心配だった。
「それにしても……最近の時透さまは優しすぎるのでは」
これは近々冬の嵐でも来そうだな、と失礼なことを思いながら、彼女は寝ぼけ眼を開ける為に両頬をパンっと叩く。
「よし……今日も頑張るか」
無一郎から与えられた一室で隠用の隊服を着こみ、頭巾と口布で顔を覆う。別に稽古の合間は家事などのお手伝いをするだけ。任務とは違うため顔を隠す必要もないのだが、いつも付けているモノなので習慣となっていた。
まだ少し薄暗い外へ行き、井戸から汲んだ水を樽へ移していく。ついでに口布を外して顔も洗った。真冬の井戸水は氷水のような冷たさで、睡魔も吹っ飛んでいく。
汲んだ水は米を炊くのに使用し、残りは洗濯用と訓練中に喉を潤せるよう台所へ。あとは味噌汁を作るのに使い、朝食の準備をしていく。
彼女は若いながら家事全般が得意な方であった。母親を早くに亡くし、幼い妹の面倒みるのは長女の役目だったからだ。しかし妹や父を鬼に殺され、剣士を目指して鬼殺隊へ入隊。親を殺した鬼を倒すという目標を掲げ、日々訓練に勤しんだ。
ただ悲しいかな。最終戦別で生き残りはしたものの、彼女に剣と呼吸の才はなく。どう頑張っても剣士になれないと悟った彼女は、隠という援護部隊へ配属と相成って今に至る。
「ふぅ……暑い」
黙々と働いていると次第に体も温まってきて、彼女は再び外へ出た。何だかんだと使用していたら水が足りなくなったのだ。再び井戸から水を汲もうと桶を手に歩いて行くと、空がだいぶ白み始めていた。そんな中、井戸の方から水音がしてふと足を止める。そこには上半身を曝け出して汗を拭く無一郎がいた。
「時透さま……?今戻られたんですね」
惜しげもなく逞しい肉体を晒しているため、少々目のやり場に困りつつも彼女はいつも通り無一郎へ声をかけた。
「あ、。おはよう」
無一郎は彼女――に気づくと、手を止めて柔らかい笑みを浮かべた。前の彼では考えられない常識的な態度と挨拶だ。
(やはりおかしい……あの時透さまがわたしに微笑みかけている!)
内心驚きつつ、そんな態度はおくびにも出さずに「おはよう御座います」と挨拶をする。
「また柱同士で手合わせですか?」
無一郎の痣らだけの体を見ながら訪ねる。柱稽古が始まって少し経った頃、無一郎は深夜に出かけることが増えた。聞けば風柱、蛇柱とで稽古をしているらしい。やはり格下の隊士達相手では準備運動くらいにしかならないようだ。
あれほど重傷だったにも関わらず、もう他の柱相手に稽古とは、と聞いた時は彼女も驚いたものだった。
「うん。は朝食の準備?」
「はい。もう終わります」
「いつも朝早くからありがとう」
「……いえ」
一瞬言葉に詰まったのは、やはりおかしいという思いが再び湧いたからだ。前の無一郎ならお礼なんか言わなかったし、こんな柔らかい笑みを浮かべることもなかった。
霞柱、時透無一郎という人物は常に無表情、無感情で、あまり他人を気にすることはない人だと思っていただけに、どういう顔で接していいのか分からない。
彼女は前の無一郎も決して嫌いではなかった。弱者には辛辣で、思ったことを全て口にしてしまうところはあれど、それは柱としての責任からくるもの。そう理解していたからだ。
自分よりも後に鬼殺隊へ来て、さほど変わらぬ歳でありながら柱となった無一郎が、今日までにどれほど鍛えてきたのかも分かっている。だからこそ信頼できるし、少しでも彼の役に立てるよう隠になった後は微力ながら援護をしてきた。
幸いにも彼女は無一郎から辛辣な言葉を向けられたことはない。常に全力投球で任務に励み、特に柱の関わるものであれば鬼も強く、いつも以上に慎重に隠としての仕事をこなしてきたからだ。
無一郎の気に障ることはせず、空気のように彼を陰ながら支えてきたつもりだった。
けれど、それに対し優しい言葉も、今みたいに労いの言葉をかけてもらったことも、ない。
だからこそ無一郎の大きな変化に戸惑い、困惑していた。
――最終決戦が近い。
最近では先輩の隊士達がよくそんな話をしている。しかしはあまりピンときていなかった。長きにわたる鬼との戦いに終止符を打つのは、自分がこの世から消えた後だろうと漠然と考えていたからだ。
ただ、今の無一郎を見ていると、その予想は間違っているのかもしれないと思う。もうすぐ彼が遠くへ行ってしまうような、そんな予感が彼女の胸に不安という名の小さなシミを刻んでいく。そこからもやもやとしたものが、大きく膨らんではち切れてしまいそうだ。
いつもと違うこと。それがは――心底怖かった。
よほど態度に出ていたんだろう。彼女の様子がおかしいと無一郎も気が付いたようだった。
「……?どうしたの。何か元気ない」
「いえ、そんなことは――」
と俯いていた顔を上げた時だった。無一郎の手が彼女の顔へ伸びたと思った瞬間、ぷちっと何かを外す音がした。それは口元を隠していた布。はらり、と口布が落ちたせいで、彼女の顔の全貌が無一郎の目に映る。素顔は以前も見られたことがあった。しかし無一郎の突然の行動が理解出来ず、彼女は小さく息を呑んだ。
「ほら、やっぱり泣きそうな顔してる」
「そ、そんなことは……」
「どうしたの?僕のせい?」
無一郎の眉がへにょりと下げられるのを見てハっとしながらも、その問いに答えることが出来なかった。無言を肯定と取った無一郎は「ごめん」と唐突にその言葉を口にした。彼が誰かに謝罪してる姿をは一度も見たことがない。だからこそ余計に胸が抉られるように感じた。
「な、何故謝られるのですか……」
「だって……が元気ないのは僕のせいみたいだから」
「ち、違います……っ。い、いえ、違わないですけども!でも時透さまが謝る筋合いではないことです」
「そんなことないよ。これまで僕はに対して酷い態度をしてきたっていう記憶はあるし、自覚は……なかったけど、でもきっとを傷つけたよね……いつも人一倍頑張ってくれてたのに……ごめん」
無一郎は神妙な顔つきでを見つめた。どうやら本心から言ってるようだ。
深い湖の底を思わせる無一郎の青みがかった瞳にジっと見つめられると、彼女の心臓がまた攻撃を受けたかのように激しく動き出す。不安、焦り、そして謎の動悸。色々と混乱した感情に振り回され、よく分からない思いがこみ上げる。
以前とは違う無一郎に接すると、最近は特にこういった現象が多くなっていた。
そもそも彼女は無一郎に傷つけられたと感じたことはない。酷い態度といっても素っ気ないだけで、あとは少々無茶ぶりされたり、我がままを言われたりした程度。そしてそれを確実に実行してきたに対し、無一郎は無駄な暴言を吐いたことはなかった。だから謝罪される筋合いはないと思ったし、そう言った。
今、無一郎に対して何かを思っているとしたら、それは完全に彼女自身の問題だ。
「わたしは時透さまのなさることで傷ついたことなんてありません」
「……え」
「もし……わたしがそう見えるのなら、それは個人的な感情です」
「個人的って……?」
「えっと……だからそれは……ですね……」
最近、時透さまが優しすぎて心配だ、と口にするのはどうなんだろう?と、は言葉を詰まらせた。
いや、優しいのに越したことはないのだろうが、あまりに変化が大きすぎて気持ちがついていけてない。そもそも、最終決戦が近いと言われる今だからこそ、おかしな心配をしてしまうのだ。無一郎が死を覚悟し、もう自分達の元へ戻るつもりがないのではないか――と。
そして自分はそのことに対し、不安を感じているのだと自覚した。それは自分で思っていたよりもずっと、大きな不安だということも。
「と、時透さまが以前と……だいぶ変わられたので、その……心配になったと言いますか……」
「心配……?僕のことが?」
無一郎はあまり自分が変わったという自覚はないのだろう。軽く小首を傾げて不思議そうな顔を見せた。
「僕はのことが心配だよ。顔色が悪いし元気がない。いつもの君じゃない」
「……わ、わたしだって元気ない時くらい……あります」
「もしかして疲れてる?毎日、朝から晩まで僕や隊士達の世話をしてくれてるもんね」
「い、いえ、わたしは――」
「そういうのは本来、隠の仕事じゃないって分かってるんだけど――」
と言いながら、無一郎は僅かに目を伏せ、でもすぐに彼女へ視線を戻した。どこか慈愛のある温かい眼差しは、彼女の鼓動を更に早くしていく。
「でも今回の柱稽古が決まった時、手を貸して欲しいと思ったのは君で、どうしても僕はが良かったんだ」
「え……」
「今日まで地味な仕事でも手を抜かず、いつも全力で僕らの手助けをしてくれてたのを知ってる。小さい体で僕を運んでくれた時も驚かされたけど、こっそり鍛錬してた姿を見て納得した。そんな風に自分の仕事をきちんと完璧にこなしてるを見てきたからこそ、今回も協力して欲しいって思ったんだよ」
「時透さま……」
まさか、そこまで自分のことを見ていてくれたとは思わない。これまで感謝の言葉など言われたことがなかったから。
無一郎の言った通り、は小柄で最初はあまり筋力もなかった。でも剣士として役に立てないのなら裏方として全力で戦おうと決めた。筋力がつくように鍛錬も欠かさなかった。刀鍛冶の里へ行く時もそうだけれど、万が一任務先で大怪我をした場合、無一郎を背負って走れるくらいにはなりたかったから。
その一つ一つを見ていてくれたことが、こんなにも嬉しいものなのか、と目頭がじわりと熱くなる。
それから無一郎は今の自分が前とは違う理由を「多分」と前置きをして彼女に語ってくれた。
元々、鬼殺隊へ来た時は過去の記憶がなかったこと。いつも頭のどこかに霞がかかっていたこと。その間の自分の言動も曖昧だが、今思えば亡くなった兄を真似ていたのかもしれないということ。
全てがの知らない話だった。長い期間、無一郎の傍で任務をこなしてきたにも関わらず、彼にそんな悲しい過去があったことを、彼女は初めて知った。
無一郎は変わったのではなく、記憶を取り戻して本来の彼の姿へ戻りつつあるのだと、今度こそ理解した。
順を追って彼女へ説明したあと、無一郎は小さく息を吐き出した。何故彼女に全てを話そうと思ったのかは自分でも分からない。でも前と違うことが心配だと言われた時、聞いて欲しいと思った。これまで自分の傍で支えてくれていたであろう彼女に。
「何か緊張する。自分のことを話すって案外、難しくて照れ臭いものなんだね」
家の前の長椅子へ並んで座りながら話をしていた無一郎は、苦笑交じりで隣に座るの顔を覗き込む。そして――目が点になった。
「……う……ひっく……」
「え、何で泣いてるの」
無一郎が全てを話し終えた時、は何故か大粒の涙を流していた。可愛らしい顔をべしょべしょに濡らし、嗚咽を漏らしながら鼻をずずず、と啜っている始末。まさに号泣状態だ。
普段はしっかり者で仕事もテキパキこなす彼女の涙を、無一郎は初めて見た。
戦闘後、隠が事後処理をしている際、新たな鬼が出現し、自分が襲われかけた時でさえ、彼女は泣かなかったのに。
「だ、だって……理由を知って安心したの……と、お、お兄さまを亡くされて、記憶まで失くしてたなんて……ひっく……」
「泣かないでよ。もう、その辺の気持ちは整理ついてるから。それに家族を失ったのはも同じだろ」
「そ、そうですけど……うう……すみません……わたし、てっきり時透さまは死を覚悟して戻ってこないつもりでいるのかと……」
「え、どういうこと?」
ぐすぐすと泣いているの言葉に、今度は無一郎が呆気にとられる。
「そう言えば……僕が変わったことで心配してたって言ってたけど……そういうこと?」
「う……す、すびばせん……!死を覚悟した人間は急に周りの人間に対して優しくなることがある、と聞いたもので……勝手に勘違いしてただけですぅ……うう」
今度は別のことでメソメソしだした彼女を、呆気にとられた様子で見つめていた無一郎は小さく吹き出した。自分のことを心配して心を痛めてくれたからこその号泣なんだと、今の無一郎なら分かる。
元々は柱と隠という関係であり、そこには上下関係があった。しかし今はもう、どちらが重要な存在かなんて考えることもない。
前線で戦う剣士も、後方で支援する隊士も、刀を打ってくれる鍛冶職人も、みんなが同じ目標を持ち、全員で戦ってるのだと、今はちゃんと分かっている。
自分を支えてくれている人達へ、感謝をする心を取り戻したからこそ、の流した涙の意味を知り、また改めて無一郎は感謝をした。
「、泣かないで」
隣で身を縮こませながら泣いている彼女の頭へそっと手を置くと。涙でいっぱいの瞳が無一郎を見た。鼻を真っ赤にして泣く姿はまるで幼子のようだと、無一郎は笑みを浮かべた。
「多分、そう遠くない日に鬼舞辻と戦うことになると思う。だから必ず戻るなんて約束は出来ない。だけど僕も死ぬつもりで戦いに行くわけじゃないから、そこは心配しないで」
「……時透さま……」
「生きて帰れた時、には笑顔で迎えて欲しいから」
「は……はいっ」
鼻を啜りながらも元気よく答える彼女を見て、無一郎は軽く頷いた。そして昇る朝日を見据えて僅かに目を細める。
「だけど、もし……」
「え……?」
「もし、僕が帰って来れなかったとしても、には笑顔で僕の魂を見送って欲しい」
そう告げた瞬間、隣で小さく息を呑む気配がした。それでも無一郎は構わず言葉を続ける。
「きっと辛く苦しい戦いになると思う。僕だって挫けそうになるかもしれない。でも絶対に最後まで諦めないと今ここで誓うよ」
「時透さま……?」
「鬼に殺された人達全ての無念を晴らす為に、今を生きる人々の未来の為に、僕らは鬼舞辻無惨を必ず倒す。例え僕に出来なかったとしても、必ず他の誰かがやり遂げてくれると今なら信じられるんだ」
昇る朝日を真っすぐ見つめる無一郎の横顔は、これまで以上に凛としていて美しい。惚けて無一郎を見つめていたは、ふと我に返って頬を染めた。これまでに感じたことのない温かいものが胸の奥を駆け巡る。
この世に生まれ落ちてから今日まで、鬼のいない世など一度もなかった。親を亡くし、兄弟を亡くし、世間で言う幸せな日常というものすら送ったことはない。故に彼女は恋も知らない。家族とはまた別の愛情を男の人に持つという経験をしたことがない。
だから、今この胸に芽生えた無一郎への温かい感情が何なのかは分からなかった。けれど、もしこの想いに名をつけるとするなら、それはやはり恋なのだろう。
決して叶うことのない恋に落ちた瞬間から、別れの予感すら覚悟しなければいけない現実を、は心底呪いたくなった。
それでも無一郎が優しく微笑んでくれたので――。
「わたしも……信じてます」
湖の底のような碧い瞳を真っすぐ見つめ返しながら、は涙を拭って心からの笑顔を無一郎へ向けた。
もし、無一郎が自分を思い出してくれることがあるならば、泣き顔ではなく笑顔を思い出して欲しい。
心から願うその想いは間違いなく、生まれたばかりの小さな恋の欠片だった。
