灰谷家のアルバイト②
「え?!時給10万?!」
「うん」
「うっそー!いいなぁ、それ!しかも灰谷兄弟の家でなんて、私が働きたいくらいだよ!」
リカちゃんは身を乗り出して瞳を輝かせている。蘭さんからバイトをしないかと言われ、それも最高の好条件を教えると、リカちゃんは酷く羨ましがった。
あの兄弟に憧れているらしい。いやリカちゃんだけじゃなく。あの高級ソープ店で働く女性たちは全員があの二人に抱かれたいと思っている、とのことだった。ちょっとビビる。
「で、蘭さんと竜胆さんの家ってどんな感じ?やっぱり素敵なんでしょ?」
「え?あ、いや、それが……昨日の今日だしまだ行ってないの」
「そっかー。でも行ったらどんな家だったか教えてね」
「う、うん」
今日はリカちゃんがお休みで、前にも来たことのあるバーで飲んでいた。何故、預貯金ワンコインのわたしがこんな高い店に飲みに来れてるかというと、昨日バイトを引き受けた時点で蘭さんが契約金という名のお金を支払ってくれたからだ。春ちゃんへ返す分と今月の生活費。
しめて100万円!奇しくも違う意味で「100万円の女」なってしまった。
このお金はバイト代ではなく、あくまで引き受けてくれたことへの報酬だそうで、時給とはまた別だということだった。何かわたしばかり得してる気分だ。
「でもいいなぁ、家に出入り出来るならいつだってそういう雰囲気に持っていけるし」
「……そういうって?」
「だからぁ。エッチに決まってるじゃない!」
「……エッっ?!」
「私がちゃんなら家に入れてもらった時点ですぐ迫っちゃうんだけどなー。色んな技でメロメロにさせる自信あるし」
「ちょ、ちょっとリカちゃん……?!」
さすが有名人からも指名の多い高級ソープ嬢。言うことがいちいち大胆だ。そりゃリカちゃんに迫られたら、いくら女経験豊富なあの二人もメロメロになるに違いない。……スケベだし。
「あ、そーだ。この際だからちゃんもバイトついでに二人のどちらかと脱ヴァージンしちゃったら?」
「……は?!なななな何を言ってるの、リカちゃん!」
ギョっとして思わず腰を浮かしかけたわたしは、気分を沈めるのにビールを一気に飲み干した。焦ったせいで気管に入りそうになる。そんなわたしを見てリカちゃんはリカちゃんは呑気に笑っていた。
「だって早く処女捨てたいって言ったのちゃんじゃない」
「そ、そうだけど……」
「優しい人がいいんでしょ?だったら経験豊富なあの二人が適任だと思うけどなあ」
「ててて適任って……蘭さんも竜胆さんもわたしの上司だし――」
「上司とデキちゃうOLなんて世の中に腐るほどいるでしょ」
「そ、そうかもしれないけど……」
「あれ、ちゃんはあの二人のこと嫌い?」
「え、ま、まさか!嫌いじゃないよ……」
そう、決して嫌いじゃない。というかあの二人を嫌う女はいるんだろうか。銀座のお姉さま方まで惑わすくらいだし。
ただわたしの場合、二人ががあまりにグイグイ来るから逃げ腰になってしまうだけだ。あとは沼りそうで怖い。
「じゃあいいじゃない。この機会に」
「こ、この機会にって言われても……」
「え、じゃあちゃんはどっちが好み?」
「えっ?」
「わたしはどっちもなんだー。大人な蘭さんと濃厚なセックスもしてみたいし、可愛い竜胆くんには色々あんなことや、こんなことを教えてあげたいし」
「へ、へえ……(リカちゃんってば欲張り!)」
というか処女のわたしには少し刺激が強い話だ。いや、日頃からリカちゃんを筆頭にお店のお姉さまから濃厚な話や失敗談、変態なお客様の話はたらふく聞かされてるから、そういう知識だけは豊富にあるけども。
「ちゃんは?」
「えっと……あまりどっちとか考えたことがないというか…」
「そうなの?じゃ考えなよ」
考えなよと言われても困ってしまう。どう応えようかと思っていると、突然ケータイが震動しだした。
「あ、蘭さんからだ。メッセージだけど」
「え、嘘!もし暇なら飲みに来ないかなあ」
「あ……でも呼び出しみたい」
「え?あ、さっき言ってたバイト?」
「うん。何か今から来いって……」
メッセージにはその一言しかない。とりあえず高い報酬を貰った手前、呼ばれたらすぐ行くことにはなっていた。
「ごめん、リカちゃん。わたし、行かなくちゃ」
「いいよ。適当に飲み友でも呼び出すから。でもまた詳しい話、聞かせてね」
「うん。じゃあ行って来るね」
「行ってらっしゃーい」
リカちゃんは笑顔で送り出してくれた。きっと後日蘭さん達の家のことを根掘り葉掘り聞かれそうだ。
とりあえず蘭さん達の新しいマンションはこのバーからも近い。徒歩五分ほどで目的地のマンションが見えて来た。
「この前見た時も思ったけど……でか」
六本木の街にドーンと建っているタワマンを見上げて、首が痛くなった。このマンションの最上階ってどんだけ景色がいいんだろうか。
「えっと……4501だっけ」
エントランス前に行って部屋番号を入れていく。インターフォンを鳴らすと『おー早いじゃん』という声が聞こえてきた。蘭さんだ。
蘭さんはすぐにオートロックを外してくれる。そのまま中へ入ると高級ホテルも真っ青な広いロビー。そしてフロントに立っているコンシェルジュがにこやかな笑みを浮かべながら頭を下げてきた。
「すご……どんだけするんだろ、このマンション」
芸能人も住んでるようで、なかなかに警備も厳重だ。最上階に着くまでに3つほどオートロックがあって、その都度インターフォンを鳴らさなければいけない。面倒くさすぎる。
「つ、ついた……」
最上階に到着した頃にはすでに疲れてしまった。
「、コッチ」
「え?」
エレベーターを降りた瞬間、目の前に蘭さんが歩いて来て、わざわざお迎えに?と驚いてしまった。でもよく見れば、そこはエレベーターホールというよりはエントランスホールといった雰囲気で、まさかの"エレベーター降りたら灰谷家でした"――状態だった。
「こ、ここ……もしかして玄関、ですか」
「おーこのフロア全部が家だからな」
そう言いながら蘭さんは笑ってるけど、それってなかなかに凄いことだ。というか、こんな広い家をわたし、一人で掃除しなくちゃいけないの?とそっち方が心配になった。
「リビングはこっち」
蘭さんはわたしの手を引いて案内してくれる。呆けてエントランスを見渡していたわたしは慌ててついて行った。
というか蘭さんのスーツ以外の姿は初めて見る。ゆったりとした白のトップスに、同じく白のパンツスタイルはシンプルなのに凄く似合っている。というか妙な色気まで醸し出してて少しドキっとしてしまった。
(リカちゃんが変なこと言うから意識しちゃうんですけど……)
引かれている手がやけに緊張してしまう。竜胆さんは不在なのか、気配がしなかった。ということは……蘭さんと二人きり?
「あ、あの。今日はどんな仕事すれば……」
「え?仕事?」
無駄に広いリビングの、これまたお尻にフィットするふかふかの高級ソファに座らされつつ。ふと思い出して尋ねると、蘭さんは不思議そうな顔で振り向いた。
「何か仕事して欲しくて呼んだんですよね」
「あーそうだっけか」
「はい?」
「まあ、いいじゃん。オレがに会いたくなったからってことで」
「は?」
その返しに唖然としてると、蘭さんは手にビールとグラスを持って戻って来た。
「今日の仕事はこれってことで」
「え……これ、とは」
「オレの酒の相手」
「……は?」
「こういうのは……ダメ?」
隣に座った蘭さんは蠱惑的な笑みを浮かべて顔を覗き込んでくる。たったそれだけのことなのに何故か頬が熱くなった。二人きりの状況と、このシチュエーションはヤバい。
「そ、それはいいんですけど……ただ一緒に飲むだけで時給あんなに払ってくれる気ですか」
「まあ、そういうことになるか。、すげーじゃん。オレと家飲みするだけで銀座のホステスより稼ぐことになるし」
「ハッ!そ、そう言われれば……確かに」
「ってことでカンパーイ」
蘭さんはビールを注いだグラスをわたしに持たせると、自分のグラスをカツンと当ててくる。お酒が嫌いじゃないわたしには何て美味しいバイトなんだと少し感動してしまった。
「い、いただきます……」
言いながら冷えたビールを一口飲むと、少しだけ緊張も和らいでいく。やっと室内を見る余裕も出来て、ぐるりと見渡してみた。想像した通り、シンプルな部屋にポイントとして高級家具やオブジェが飾られている。全体的に壁が黒くて、ウォールライトがやけに映えるカッコいい空間だった。
「何か……掃除する必要もないくらい綺麗」
「ああ、ここに来た時、一回掃除してもらったからなー。後は普段そんなに帰ってこねーってこともあるけど」
「あ、そっか……忙しいですもんね、蘭さんも竜胆さんも」
そういながらビールを飲んでると、目の前に何かを差し出された。視線を向けると変わった形の鍵が揺れている。
「これ、渡しておくわ」
「え?」
「この部屋の合鍵」
「あ……合鍵って」
蘭さんはその鍵をわたしの手に落として「ないと不便だろ」と笑った。
「も通って来て分かったと思うけど、ここは警備システムが厳重だから、いちいちオートロックのたびインターフォンを鳴らすはめになる」
「確かに……そうだったかも」
「ってことで今度からは自分で開けて上がって来いよ」
「……はあ。分かりました」
合鍵の意味が分かって素直に受け取ると、蘭さんは不意にわたしの顔を覗き込んでニッコリと微笑んだ。
「まあ、寝込み襲いに来てもいいけど」
「……き、来ませんっ」
蘭さんの含みのある笑みを見ていると、この何とも役得なバイトを引き受けたことが、少しだけ無謀だったかなと心配になってくる。
"二人のどちらかと脱ヴァージンしちゃったら?"
その時、ふとリカちゃんの言葉が頭に浮かんで慌てて打ち消す。その時、蘭さんがソファから立ち上がった。
「次は――何を飲む?」
そう訊かれただけなのに、何故か頬が熱くなった。
|||
「やっぱオマエに頼ったのかよ……」
春千夜は軽く舌打ちをしながら、目の前でニヤつく蘭をじろりと睥睨した。
「急に金返して来たからそんなこったろーとは思ったけど」
「せっかく、あんな芝居売って無駄遣いやめさせようとしたのに残念だったなァ、三途」
「あ……?」
「来月、金返さなかったら処女もらうってやつー?」
「……チッ」
蘭の指摘にまたしても舌打ちをしながら、春千夜はソファにどっかりと腰を下ろす。
の散財癖は昔から変わらないので春千夜もよく分かっていた。だからこそ、あんな脅しをして無駄な散財をやめさせようと思った。それを蘭に見抜かれてたのは誤算だったとしか言いようがない。まあ盗み聞きされたので仕方はないが。
「それくらい言わねえとの散財癖は直んねーんだよ」
「へえ、良く知ってんなァ?さすが幼馴染ってわけだ」
「うるせぇな……。つーかアイツをあんま甘やかすんじゃねえ。つけ上がるから」
「いいだろ、別に。可愛い子はとことん甘やかすことにしてんだよ、オレは」
「は?嘘つけ。オマエは女を甘やかすような男じゃねーだろ。どうせをからかって遊んでんだろーが」
「それがそうでもねーんだよな~」
「は?」
ニヤリと笑う蘭を見て春千夜は眉間を寄せた。この男がこういう顔をしてる時はだいたいろくなことを考えていない。春千夜も何だかんだ蘭とは付き合いも長いので良く分かっている。
「もしが中身サイテーで金の為に誰とでも寝るような尻軽ならからかって終わってたけどな」
「……は中身サイテーだろ。欲しい物の為なら男に甘えればいいって思ってるような女だぞ。キスだって平気でするしな」
「ああ、でもありゃガキのおねだりと同じだろ。他の女がやってんのと枠が違うんだよ、オレから言わせると。三途も分かってるクセにとぼけんなよ」
「……チッ。うぜぇな、相変わらず」
「図星~」
春千夜が思い切り顔をしかめると、蘭は楽しそうに笑いながら立ち上がった。
「だいたい処女って時点で身持ちは固いってことだろ?キス魔なのに処女っていいじゃん、可愛くて」
「あ?オマエ、にちょっかい出すんじゃねーよ!女に困ってるわけじゃねえだろが」
「だーからは他の女と全く違うって言ったろ。オレから見れば可愛くて仕方ねーの。だから口出すなよ」
「あ?!テメェ、アイツに手ぇ出したらぶっ殺すぞ!」
「そん時は受けて立ってやるよ」
蘭はヒラヒラと手を振りながら部屋を出て行く。その後ろ姿を見ながら春千夜は浮かした腰を下ろし、盛大に溜息をついた。
「何でアイツは昔から厄介な男に惚れられるんだよ……。どんなフェロモンまき散らしてんだ……?」
その中に自分も含まれるという事実には、気づいていない春千夜だった。
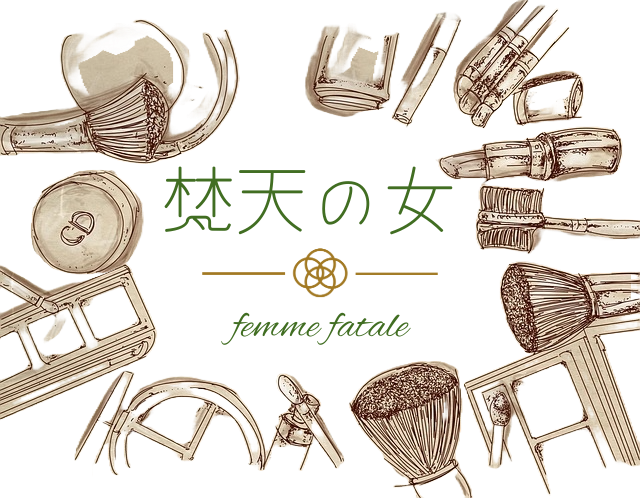
メッセージは文字まで、同一IPアドレスからの送信は一日回までひとこと送る
