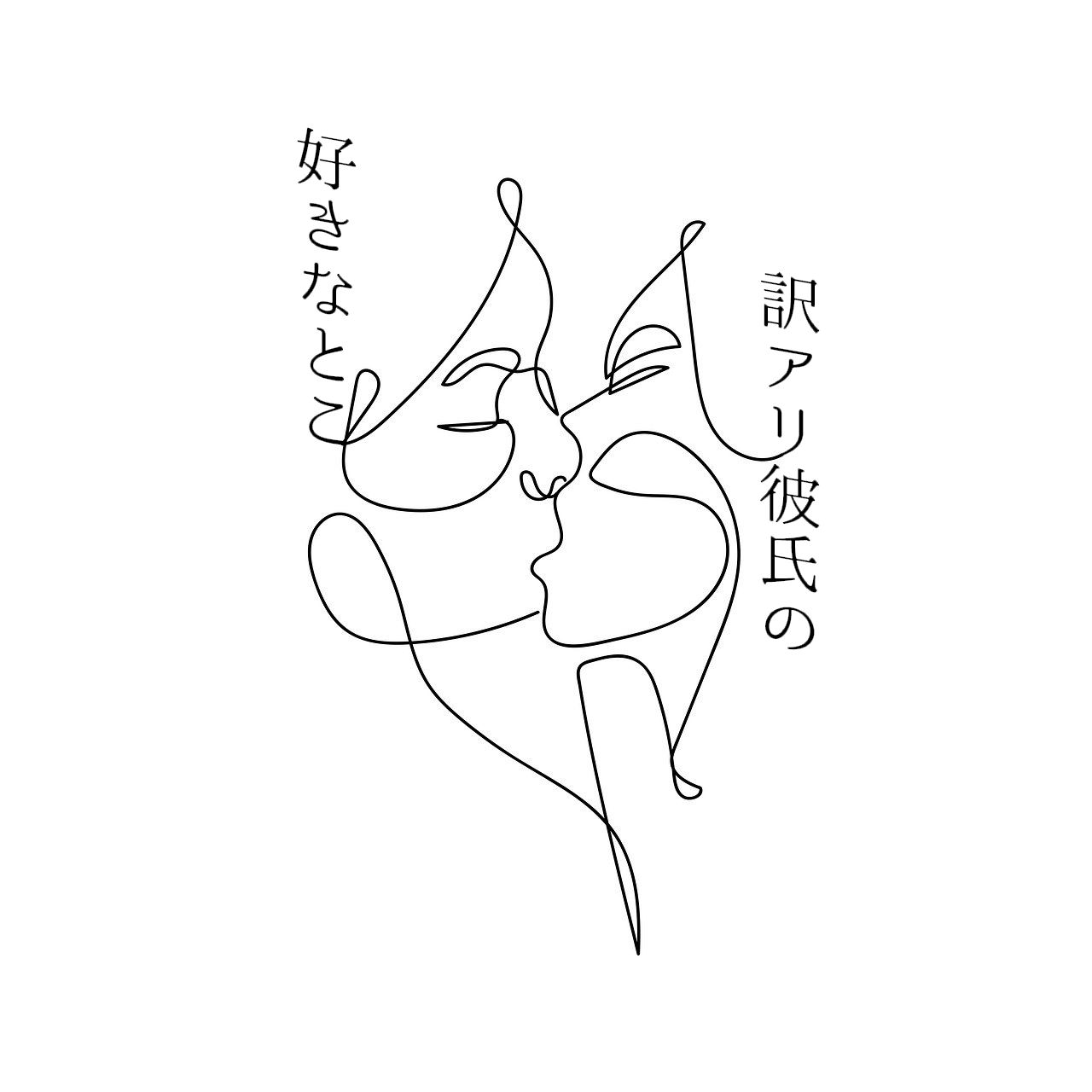訳アリ彼氏の好きなとこ
ちゅんちゅんと窓の外から雀の鳴き声が聞こえて、ゆっくりと頭の中が覚醒していく。
「ん……」
目を擦りながら、ふといつもの自分の部屋の匂いじゃないことに気づいた。
(あ…そっか…わたし、夕べは一虎くんの家にお泊りして…)
そこで更に気づいた。背中があったかい。恐る恐る振り向いた時、一虎くんがわたしの背中にくっついて眠っていた。
「…っどわっ?!」
一虎くんの寝顔の威力がヤバすぎて、寝起きなのにとっても変な声が出ました。
*
一虎くんが起きてから一緒にコンビニに行くと、チャラい男二人に声をかけられそうになった。でもそこに一虎くんが来てジロリと睨みつけると、男達はそそくさと逃げていく。一虎くんは目で相手を殺せるらしい。
「ったく。もボーっとすんなって。隙ありすぎ」
「う、うん…ごめん」
ぐりぐりっと頭を撫でてくれる一虎くんは、わたしにとっては凄く優しい人だ。今日はどこに行きたい?と聞かれたけど、一虎くんの家でのんびりしたいと言ったら、何故かいつものお勉強を教えてくれることになった。
「の成績さえ上がればイジメっ子も文句言わねえんだろ?」
そうやっていつも気にかけてくれる一虎くんは、ほんとにわたしの救世主だと思う。ホントは映画の続きを観たかったけど、一時間だけ勉強を教えてもらうことにした。
「何か分かんないとこあったら言って」
一虎くんは勉強を教えてくれる時だけ眼鏡をかける。視力はそんな悪くないみたいだけど、眼鏡をかける方が集中できるらしい。わたしは一虎くんの眼鏡をかけてる姿も好きだ。あとは鼻筋が通ってるとことか、優しい匂いとか、低い声も好き。あとは――。
「あ…ここ、ちょっと分かんない」
「ん?どれ」
この「ん?」の優しい声も好き。
「え、何?」
心に好きが溢れて腕にぎゅぅっとしがみついてしまったから一虎くんに驚かれちゃったけど、おかげでパワー補給が出来て分かんなかったところもシッカリ頭に入れることが出来た。
勉強が終わってからは一虎くんと一緒にお昼ご飯を食べようってなって、わたしが簡単にお母さん直伝のナポリタンを作ってみた。
「ん、うま!何、この懐かしい味」
「ほんと?良かった。このケチャップに秘密があってー」
「へえ、はいい奥さんなりそー」
「えっ」
あまりにサラリと言うから何となく照れ臭くて耳まで真っ赤になったのが分かる。ジンジンと熱を持ってるからだ。別にプロポーズされたわけじゃないのに赤くなるのは恥ずかしい。一虎くんはギョっとしてわたしを見てたけど、不意に真顔になった。
「は?何その顔。クソ可愛いんだけど」
「え…っ」
一虎くんの顏がググっと迫って来たから、更に恥ずかしくなって顔が燃えたのかと思ったくらい熱い。ついでに言うとこんな至近距離で見ても、一虎くんの顔は綺麗だなと思ってしまう。
「ん?何?」
ついジっと見つめてしまって、一虎くんが首をかしげてくる。そのせいでピアスがリン…と鳴る音も好きだし、一虎くんの首を傾げる顏も好き。
「いや、あの…顔良すぎじゃない……?」
「…は?」
その「は」って顔も可愛い。好きになり始めた頃から一虎くんの背景がキラキラして見えるんだから不思議だ。そう言えば一虎くんはどんな顏の子が好きなんだろう。
「一虎くんは好きな芸能人とかいないの?この子の顏が好きーとか…」
さり気なくリサーチしてみようと、前から気になってたことを尋ねると、一虎くんは「芸能人…?」と更に首をひねっている。普段あまりそんな話はしないから一虎くんのタイプを知るいい機会かもしれない。
「えー?う~~~~ん…あんまいねぇかも…」
「え、そうなの?珍しいね」
「ってか、の顏は好き。自然体のカワイイ系」
「えっ!」
「ほら、オレの周りケバイのしかいねーし。だから最初見た時から可愛いと思ってたんだよなー」
「………」
まさかの答えが返ってくるからドキドキしてしまった。顔の熱が一向に冷めてくれない。
(ん…?でも待って。最初に一虎くんに会った時のわたしって……)
数か月前の自分を思い出して、ちょっと驚いてしまった。一虎くんと会った頃は、毎日が憂鬱で早く死にたいってそればっかり思ってたのに。
「最初って…あの死にそうな顔してる時でしょ…?」
「え?あーうん」
「………(あれのどこで可愛いと思ったの…?)」
一虎くんの可愛いの基準がよく分からない。毎日あちこち傷を作って、顏にだって絆創膏ばかり貼ってたのに。
「最初はさー。好みの顔と一発ヤレればいっかなーくらいだったんだけど…」
「…な…」
「もう今はちゃんの虜よ、オレ…」
困ったように眉を下げてわたしを見る一虎くんに、ついジトっとした目を向けてしまう。最初の頃、軽そうとは思ってたけど、まさかそんなことを考えていたとは思わない。
「……」
「あれ、スベった?のツボ分かんねー」
「過去の一虎くんの不節制なとこに引いてるんです」
「げっ引くのなし。ダメ」
むぅっと口を尖らせていると、一虎くんは意外にも慌ててわたしの隣に座った。「虜なのはホントだから」とわたしの膨れた頬にちゅっとキスをしてくれる。それだけで心が落ち着くんだから、わたしもたいがい単純すぎる。
「じゃあ聞くけどさー。はオレのどこが良くて付き合ってくれたわけ?」
「…えっ」
「ん?言ってみ?」
「………」
目の前で首をかしげて顔を覗き込んで来る一虎くんにキュンっと胸が鳴ってしまう。これはやっぱり反則だと思う。
「え、えっと…だから…」
さっきまでいっぱい出て来たのに、いざ本人に聞かれると言うのが恥ずかしい。でもふと思い出した。イジメられて苦しい時、いつも一虎くんに助けてもらってたことを。
「あの、ね」
「うん」
「一虎くんに会った頃、毎日ツラくて消えたいって思ってたの」
「…うん」
「でも、そんな時に一虎くんがバイト先のコンビニに来ては話しかけてくれて、愚痴を聞いてくれたり、他愛もない話に付き合ってくれたりして…凄く救われたの。っだから……あ、あれ…」
あの頃のことを思い出してたら、不意にツラさまで蘇って涙が零れ落ちた。泣くつもりなんかなかったのに、体中が痣だらけだった自分を思い出したら、どうしようもなく泣けてくる。慌てて涙を拭って「ご、ごめん」と謝ったら、一虎くんはポンと頭に手を乗せて、それからわたしに向かって両腕を広げた。
「、おいで」
「……か、一虎くん…」
一虎くんの優しい顔を見てたら無性に甘えたくなって素直に抱き着くと、背中に腕が回ってぎゅっとされた。ふわりと一虎くんの優しい香りがして、ホっと安堵の息が洩れる。
「オレの元気わけてやるよ」
「え、ん」
顔を上げた瞬間、くちびるにちゅっとキスが落ちてくるから、恥ずかしさのあまり涙が引っ込んでしまった。
「元気出た?」
「…う、うん……」
「あれ、まだ足りねえ?じゃあもっかいしてやるよ」
「い、言ってない…っ」
がしっと両頬を掴まれたから慌てて首を振ったけど、一虎くんは顔を傾けて今度はやんわりとしたキスをしてくれた。軽く啄まれるだけでも恥ずかしい。
だけど一虎くんは、いつもわたしに沢山の元気をくれる。そんな彼が、わたしは大好きなのです。