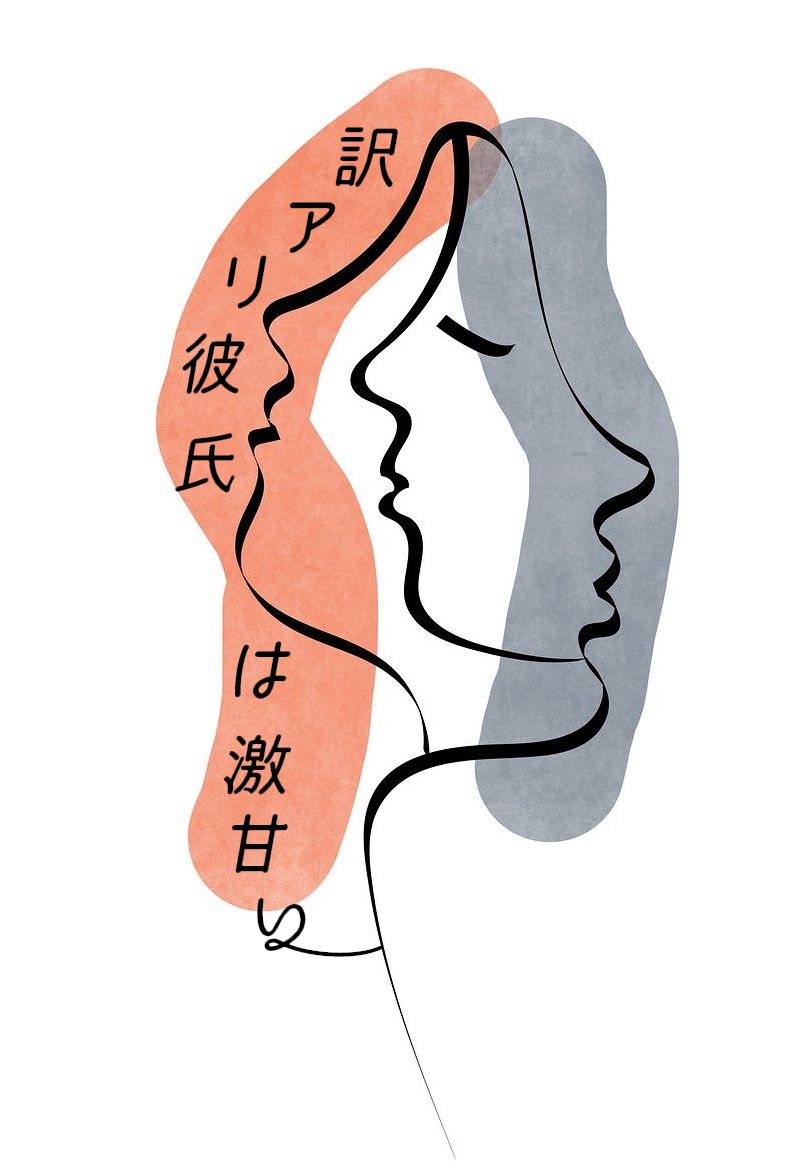訳アリ彼氏は激甘い
先週の誕生日、一虎くんがわたしの欲しいと思ってたワンピースをプレゼントしてくれた。デート中、わたしがそのワンピースをジっと見てたことに気づいたらしい。でも一番嬉しかったのは、プレゼントの袋にコッソリ入れられていたメッセージだった。
"、お誕生日おめでとう。いつも好きって言ってくれるの嬉しい。こんなオレを頼ってくれてありがとう。生きててくれてありがとう。これからもしんどい時は頼っていいからオレにだけは我慢すんなよ。一虎"
家に帰ってからメッセージカードに気づいて、読んだあとは嬉しくて大泣きしちゃったけど、一虎くんと出会った時の自分が死ななくて良かったと心から思った。あの時のわたしが死ぬことを怖いと感じて良かった。心から、そう思う。
そして今日はお休みだから一虎くんとデートの約束をしていた。一日一緒にいられると思うと、単純なわたしは嬉しさのあまり朝から早起きして可愛くなるための準備に余念がない。プレゼントのお礼にと夕べ作ったチョコなどを袋に詰めながら、一虎くん食べてくれるといいなと思った。でもシャワーから上がって髪を乾かしている辺りで、少しずつ寒気を感じるようになって風邪かなと思うと憂鬱な気分になる。でも熱を測っても平熱だし、あまり気にしないことにした。髪をブローして一虎くんからプレゼントされたワンピースを最後に着れば、我ながら可愛く仕上がった。
「あら、一虎くんとデート?」
「うん。だからご飯いらない」
階段を下りていくと、リビングからお母さんが顔を出した。
「あらいいわね~。今度ウチにも連れて来てね。イケメンの一虎くん」
「うん」
お母さんはわたしよりはしゃいだ様子で呑気に笑っている。わたしの両親は前に一虎くんにも話した通り、少しのほほんとしている。特にお母さんは彼氏が出来たと話した時も「どんな子?カッコいい?」なんて大騒ぎするくらいミーハーで、写真を見せると「その辺のアイドルよりカッコいいじゃない!」と何故か大喜びしていたし、黒金の派手な髪色や首のタトゥーを見ても「お洒落ね~!」と言うくらいだった。そして一番大切なこと。一虎くんが少年院上がりだということもきちんと伝えてある。でもその話をしてもお父さんとお母さんは「私達はを信用してるから。だから今度ちゃんと紹介しなさい」と言うだけだった。
「が好きになった子なら大丈夫」
という変な自信があるらしい。その話を幼馴染の一馬に話したら「どんだけ親ばかなんだよ、おじさんもおばさんも」と笑ってた。わたしも少しそう思わないでもなかったけど、一虎くんがわたしを凄く大切にしてくれてるのを見てもらえれば大丈夫だと思う。
「ちゃんと起きてるかなぁ…」
家を出てバイト先のコンビニ近くにある一虎くんのマンションにやって来た。バイト先を挟んで、我が家から一虎くんのマンションまでは徒歩13分ほど。遠いのか近いのかよく分からない距離にある。そのだいぶ慣れた道のりを歩いて来たわたしは、マンションエントランスに入ったところで自分の身体の異変に気づいた。
(う…何か…お腹痛い…)
インターフォンを鳴らしてオートロックを解錠してもらったものの。エレベーター内に設置された鏡に映る自分の顔を見て少し驚いた。薄くメイクを施したにも関わらず、真っ白というか血色が悪い。要は随分と具合が悪そうな顔色だった。それに首筋辺りがゾクゾクとしてきて、さっきよりも寒気がする。どうしよう、と思ったものの、せっかくのデートなのに帰る気分にもなれず、わたしは一虎くんの部屋のインターフォンを再び鳴らした。
「おー!可愛い」
ドアが開いた瞬間、一虎くんは歯ブラシを咥えたまま顔を出し、満面の笑みを浮かべて褒めてくれた。
「…ほんと?」
「うん。思った通り、良く似合ってる。あ~ちょっと入って待ってて。あと3分で出れる」
「う…うん……(上半身ハダカ…)」
着替えてる途中だったらしい一虎くんは上半身裸だったから、目のやり場に困ってしまう。細身でほぼ筋肉しかないのでは?と思うくらい引き締まった身体に若干頬が熱くなる。普段は隠れている首のタトゥーの下部分は肩や胸の辺りまで入っていて、全容を見たのは初めてだ。普通なら怖いと思いそうなそのタトゥーは、一虎くんによく似合っていて、むしろ綺麗だと思った。
(あ…まただ…)
玄関に入ったところで、下腹部の辺りがチリチリとした不快な痛みを訴えて来る。その独特の痛みを感じた時、イヤな予感がした。
「…トイレ借りるね」
「おー」
洗面所にいる一虎くんに声をかけてから靴を脱いですぐにトイレへ向かう。そしてあることを確認した時、わたしの顏から更に血の気が引いた。
「ごめん。お待たせ。もう行ける」
フラフラとトイレから出たところで一虎くんが服を着て歩いて来た。でもわたしは絶望感そのままにその場へズルズルとしゃがみこんでしまった。
「……しんじゃう」
「は?!どした?」
アレだと分かった途端、痛みが酷くなってくるのは何でなんだろう。
「いたい~…」
驚いて目の前にしゃがんだ一虎くんにしがみつき、べそべそ泣きつく。ショックだったのはせっかくプレゼントしてくれたワンピースを少しだけ汚してしまったことだ。
「…ワンピに血がついちゃった…ごめんなさい~…ぐす…」
「あ……(生理か…)」
一虎くんは何かを察したらしい。「今なったん?」と聞いてきた。
「う…うん…ストレスで不順だったから……ハッキリ分かんなくて…ひっく」
「そっか。じゃあ薬も持ってねーよな。あ~泣くなって」
「…う…ごめん…」
「分かった。じゃあこれ脱いでオレのヤツ着て寝てな。どれ着てもいいから」
一虎くんはテキパキとした様子でわたしを部屋に連れて行くと、クローゼットを開けて「なるべく身体冷やさねえ服選んでな」と言いながら薄手のアウターを羽織った。
「薬局に行って来るからケータイにいつも飲んでる薬とか送っておいて。あと他に欲しいもんとかも。下着は何でもいい?」
「え…っ?」
まさか買いに行ってくれるとは思わなくてビックリしてしまった。でも一虎くんは普通に笑いながら「は動けねえだろ?」と言ってくれた。
「で、でも…」
「いいから。下着のサイズは?」
「え…S」
「ちっさ。色とかは何でもいい?」
「う、うん……あ、あのっごめんね…」
出て行こうとする一虎くんの服をつい引っ張ると、彼は「気にすんなって」と笑顔で頭を撫でてくれる。その優しさが胸に沁みて止まりかけてた涙がまた溢れて来た。
「泣かないで。ほら早く着替えて横んなってろって。腹痛いんだろ?」
「…う…んう、ん」
「じゃあすぐ戻って来るからいい子で待ってて」
一虎くんはそう言い残すとすぐに出かけて行った。凄く恥ずかしいけど、女物の下着とかナプキンを買う彼の方がきっと恥ずかしいはずだ。心の中で申し訳なく思いながら、ドアの閉まる音を聞いていた。なのに腹痛は容赦なく襲ってくるから、せっかく着て来たワンピースを脱ぐ。小さなシミを見て悲しくなったけど、すぐにお湯で軽く洗ってクリーニングに出せば綺麗に落ちるはずだ。
(それにしても一虎くん…いつもだったら"紐パンにするわ"とか言いそうなのに、こういう時はふざけないんだよなぁ…。そういうとこも好き…)
情緒不安定なのか涙が溢れてくるのを堪えながら、どうにか一虎くんのトレーナーとパジャマ代わりにしてた短めのズボンを借りる。腹痛はだんだん酷くなって下腹部を色んな角度で攻撃してくるから、フラフラとベッドへ上がってころんと横になる。どうしても痛みがあるから体を折り曲げてしまうのはいつものことだ。でも何も一虎くんとデートの日になることないのにと思う。クラスメートの二人からイジメられるようになってからというもの、ストレスでだんだんと生理不順になっていった。だから予測が立たなくて、いつもはナプキンと下着のセットをこっそり鞄に持ち歩いてたのに、今日に限って小さなバッグだし邪魔になるからと入れてなかったのが仇になった。
(一虎くんは男なのに、あんなもの買いに行ってくれるなんて驚いた…普通なら嫌な顔しそうなものなのに…優しいな…)
とりあえず言われた通り、必要なものをケータイで送信してから横になっていると30分後、一虎くんが帰宅した。手にした大量の袋に驚いたけど、お礼を言って受けとると、まずはトイレに移動して下着やナプキンを手早く身に着ける。その後に痛み止めを飲んで一虎くんにくっついてたら気づけば眠っていたようだ。ふと腰の辺りを擦られた感触が脳に伝わって、わたしはゆっくりと目を開けた。
「あ…起きた?」
「……っ?」
目の前にわたしを心配そうに見下ろす一虎くんの顏が合ってギョっとした。何故かわたしは一虎くんの膝の上に頭を置いて寝てたらしい。
「薬、効いてきた?」
「…うん」
わたしの腰を擦りながら、一虎くんは「良かった」とホっとしたように微笑む。
(もしかして…腰、ずっと擦っててくれたのかな……ほんと優しい)
一虎くんの優しさが身に沁みて、ついでにデートをダメにしてしまったことが悲しくて、また涙がじわりと浮かんでしまう。
「今日…ごめんね」
「いいって。気にすんなよ、こんなことで。デートはいつでも行けるだろ」
大きな手が優しく頭を撫でてくれて、ちょっと感動してしまった。彼を好きになって良かったと改めて実感する。
「ん?起きる?」
「…ん」
小さく頷いたものの、膝枕をしてもらってた体を起こすと、何となく離れるのは寂しい。胡坐をかいてた一虎くんの脚の間に横向きに座って、両腕を背中に回すとぎゅっと抱き着いた。
「やっぱり…あと10分」
「…うん」
わたしの身体にも一虎くんの腕が回ってすっぽりと納まってしまった。こうして密着してるだけでお腹の鈍痛も和らぐ気がするから不思議だ。胸に顔を押し付けていると、一虎くんの鼓動の音が少し速くなっているのが分かる。
「…ドキドキ聞こえる」
「そりゃー好きな子に抱き着かれたらそーなるんじゃねえ?」
「え」
コッチまでドキっとしてしまう台詞を言われて顔を上げると、一虎くんが照れ臭そうにそっぽを向いた。そんな顔を見てしまえば、わたしもドキドキしてしまう。くっついてるせいで一虎くんの香水の匂いがさっきから鼻腔を刺激してくるのも原因の一つだ。
「腰、ツラくねえ?」
「ん、平気」
そう応えながらも、そこで何となく疑問に思った。さっき突然生理になった時、一虎くんはテキパキしてたし、するべきことをよく分かってた。男の彼が何でそんな機転が利いたんだろう。
(もしかして…元カノとかにもこういうことしてたのかな…)
思い当たるのはその辺しかない。過去のことだけど、やっぱりそこは嫌な気持ちになってしまう。こんな風に思うのは我がままだって分かってるのに。わたしは一虎くんが何もかも初めてだけど、一虎くんは違う。わたしの前にも彼女がいて、きっと今のわたし達の関係よりも深い間柄だったんだろうし、ナプキンくらい買いに行くのはわたしが考える以上に平気なことなのかもしれない。
「…どした?」
背中に回した腕の力を緩めると、一虎くんが心配そうに眉を下げた。
「また痛くなってきた?」
「………」
黙って首を振ると、一虎くんは怪訝そうな顔でわたしの顔を覗き込む。その金色の綺麗な虹彩に、彼の過去に嫉妬したブスなわたしが映っていた。
「何だよ…どした?」
「……うん」
「…何かあるなら言えって。言わなきゃ分かんねえだろ?いつものらしくねえじゃん」
わたしの表情を見て何となく気づいたのか、一虎くんは優しい声色でわたしを諭す。これ以上心配かけたくないし、この胸のモヤモヤを残して家に帰るのも嫌だから、ここは思い切って吐き出すことにした。
「あのね…こういう状況、一虎くん慣れてるなあと思ったの…」
「え?」
「だから前の彼女の時もこうだったのかな…って思ったら…ちょっと嫉妬しちゃっただけなの。ごめんね」
「…」
正直に話すと少しだけモヤモヤが晴れた気がする。一虎くんは少し驚いた顔でわたしを見つめてたけど、でも突然ぎゅぅっと強く抱きしめてくるからビックリした。
「か、一虎くん…?」
「……ヤキモチとか…可愛すぎ」
「えっ」
腕の力を少し緩めた一虎くんは、嬉しそうな顔をしてわたしを見下ろした。
「…でも彼女とかじゃなくて母親」
「お…母さん…?」
どういう意味だと思ったら、一虎くんはちょっと笑ってわたしの額に口付けた。
「母親が結構重たいタイプの人でさ。で、毎月なるたびに動けなくなって、だからオレがよく買いに行かされてただけの話」
「あ…」
苦笑いを浮かべながら説明する一虎くんを見て、そういうことかと腑に落ちた。家族の話は殆ど教えてくれないから、そこまで考えられなかった。なのにバカみたいに嫉妬したりなんかして、急に恥ずかしくなってしまった。
「ご、ごめん…」
「何で謝んだよ。嬉しかったけど?からのヤキモチ」
「え…嬉しいって…」
ニヤっと笑う一虎くんはわたしを抱え直すと、身を屈めて触れるだけのキスをくちびるへ落とした。
「そりゃー嬉しいじゃん。からヤキモチ妬かれるの。でもまあ…心配させたくねえから言うけど、オレがこんな風に世話した女はだけだから」
「…わたし…だけ…?」
「オレ、これまでテキトーな女の子とテキトーな付き合いしかしたことねーし…だからこんな風に心配したり世話焼いたりしたこともねーんだよ。幻滅した?」
その問いに慌てて首を振ると、一虎くんはホっとしたように微笑んだ。でもわたしも今の話を聞いてホっとしたから、思い切って言ったのは良かったかもしれない。こんな風にしてくれるのがわたしだけなんて、そんなの幸せすぎる。
「少し良くなってきたようだな。まだ体温はたけーけど」
「…痛みはだいぶ楽になった」
「そっか。あーじゃあ腹減らねえ?つっても、まだ夕飯タイムでもねーか」
ふと時計を見れば夕方の4時になるところ。そこで持って来たものを思い出した。
「あ、チョコレート持って来たの…食べる?」
「え、…何でチョコ?」
「えっと…だから…」
バレンタインデーはとっくに過ぎてるけど、その時はこうして過ごせなかったから、ワンピースのお礼に何か手作りしたいなと思ったのがチョコだったのだ。
「こ、この前のプレゼントのお礼もかねて…作ったの」
「え、の手作り?」
「うん。あ、でも甘い物が苦手なら無理しないで――」
「いや待って!めっちゃ食う!」
「え…大丈夫…?無理しなくても…」
「食う!」
「ア、アレルギーとか――」
「ない!」
「味の保証は出来ないょ――」
「いい!」
「……めっちゃ食い気味だし、顏怖いよ、一虎くん…」
グイグイ来る一虎くんにちょっと笑いながら、紙袋に入ったチョコを取り出す。一口サイズのチョコをつまんで「じゃあ、はい」と口の中に入れてあげると、一虎くんの綺麗な瞳がキラキラ輝きだした。
「ちょーーーー美味いっ!」
チョコをもぐもぐしながら感激している様子の一虎くんを見てたら少し呆気にとられてしまった。そこまで感激されるとは思わない。
「えーすげえ!が作ったんだろ?天才!」
大げさなことを言いながら、一虎くんは両腕を広げて「ん」とこっちに来ての合図をするから、再びその腕に納まるようにくっついた。
「もう一個ちょーだい」
「はい。(…可愛い)」
口を開けておねだりしてくるのが可愛くて、もう一つチョコを口の中へ入れてあげる。すると一虎くんは歯と歯の間にチョコを挟んで、膝立ちしてるわたしをふと見上げた。
「こへ、あえう」
「へ…?」
これあげる、と口を突き出され、顏が赤くなった。これはわたしに口移しで食べろということだろうか。
(待って…こんなの上級者向けすぎない?)
チョコを咥えてジッと見上げて来る一虎くんは犯罪級にカッコいい。耳まで熱くなって固まっていると「はーあーくー」と目を瞑って催促してくる。可愛すぎる。ハッキリ言って、それはわたしに早すぎでは?と思わないでもなかったけど、このままだと食べるまでこの状態かもしれない。腰を抱き寄せられたままの体勢を思えば、これも恥ずかしい。
「じゃ、じゃあ…」
と覚悟を決めて、一虎くんの口に納まっているチョコめがけて口を近づけた。
「あ…っ」
でもくちびるが触れてしまって慌てて離す。自分からキスしたみたいな形になって、かぁぁっと顔が赤くなるのが分かった。
「ご、ごめん…くちびる当たっちゃった…」
「…………(きゅん)」
言った瞬間、後頭部に一虎くんの手が回ってぐいっと引き寄せられた。
「…ん」
くちびるを塞がれたと思えば、今度は口をこじ開けるようにされた。そこへ柔らかいものがチョコをわたしの口へと押し込むように侵入してくる。その柔らかいものが一虎くんの舌だと気づいた時、心臓が大きく跳ねてしまった。やっぱり素人のわたしには上級すぎて、軽く眩暈がしてしまう。
「…んっ」
舌が出ていくのと同時に、口内のどこかを舐めていくから、ビクっと肩が跳ねた。ビックリして目を開けると、一虎くんはいたずらっ子のような笑みを浮かべて「べ」と舌を出す。
「お味はどーですか?」
「わ……わか…わかんな…い…(ベ、ベロが…ペロって…口の中舐められた…!)」
ぎゅっとわたしを抱き寄せながら訊いてくる一虎くんは、確信犯的な笑みを浮かべている。やっぱりわたしよりも数倍は一虎くんの方が大人だ。
「…、首まで真っ赤じゃん。かわいー」
「か、からか…わないで…」
初めて他人に口の中を暴かれた恥ずかしさに目が回りそうだけど、この日の一虎くんも激甘だったのは間違いない。