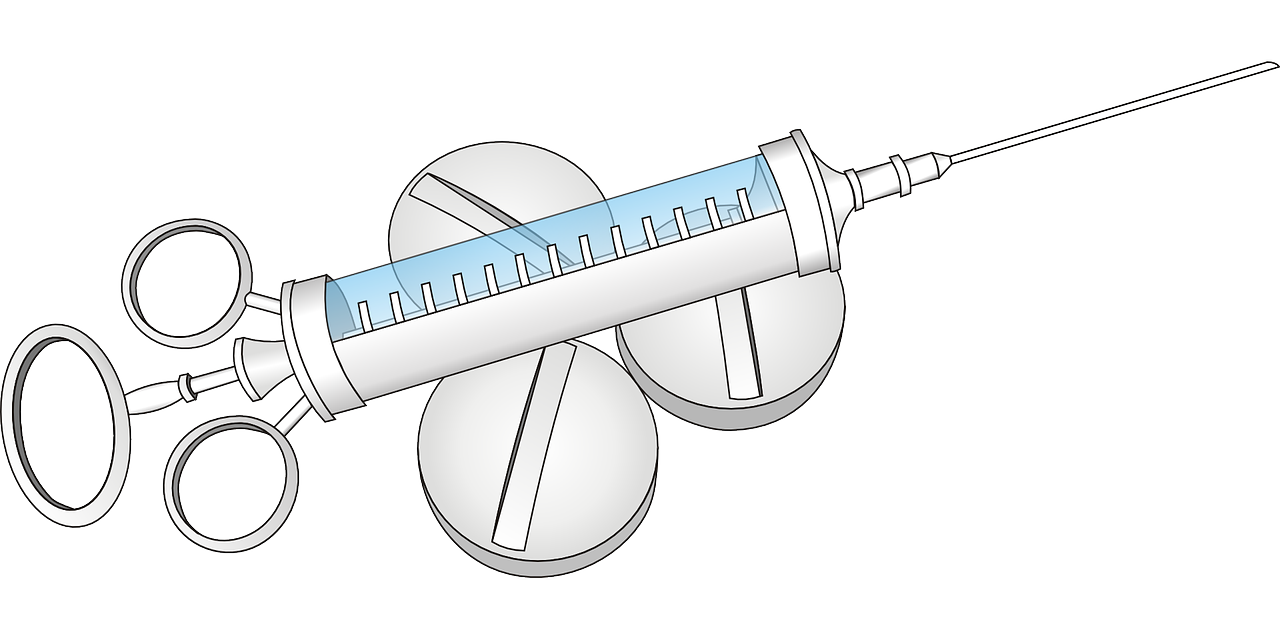空気が冷たい――。
少し前からはそう感じていた。花冷えの頃は過ぎ、そろそろ五月。ついでに言えば今日は朝から快晴で、ちょうどいい気候だった。なのにリビング内の室温はやけに寒々しい。
ただ――そう感じているのはだけだったかもしれない。
(いったい何なの…?)
先ほどから全身にビリビリとした視線が刺さっている。その視線の送り主はイザナを迎えに来たであろう、灰谷蘭だ。
イザナに食事をさせている間、蘭はソファにふんぞり返りながら、何故かジトっとした目つきでを見ている。いや、睨んでいるといった方が正しい。
蘭はイライラした様子で、落ち着きなく組んだ足をぷらぷらと揺らしていた。
(わたし、何か悪いことでもしたっけ?)
一瞬そう考えたものの、全く記憶にない。むしろ彼らのボスを治療し、こうして食事の世話までしているのだから感謝してもらいたいくらいだ。
そう思いながら、最後の一口をイザナの口へ運ぶ。
「はい、終わり。じゃあ、お薬出すから、それ飲んだら帰って下さい」
器をキッチンへ運び、すぐに水と薬を用意する。しかしイザナは徐に顔をしかめて振り返った。
「犬用の薬なんか飲めるかよ」
「大丈夫よ。動物が口にできるものなんだから市販薬より安全…だと思うし」
一瞬考えてから応えるを見て、イザナの頬が引きつった。
「だと思う…?てめぇ…ハッキリ分かんねえもんオレに飲ませるつもりか?」
腰を浮かせたイザナが薬を持ったの手首を掴む。その力の強さに顔をしかめながらも、キャンキャンうるさい大型犬だと内心苦笑した。
撃たれた次の日にこれだけ怒鳴れるなら、もう大丈夫だろう。
「平気だってば。動物の体は人間よりもずっと繊細なの。内臓だって小さい。そういう子達の体に悪い影響が出ないよう調合されてる薬なんだから」
「…そういう問題かよ。オマエ、医者のくせにテキトーすぎじゃね?」
「悪かったわね。いいから早く飲んで。こっちが抗生剤で、こっちが痛み止め。言っておくけど、人間の薬が欲しければちゃんと人間用の病院に行って。それが一番いい。最も…その傷を見られたら即通報されるとは思うけど」
「…ぐ…」
強気の態度で薬を突き出され、さすがのイザナも言葉に詰まる。出来れば犬用の薬など飲みたくないのが本音だ。だが傷口はジクジクと痛み、そのせいか少し熱っぽい。それに夕べは治療の際、動物用の部分麻酔をすでに打たれているらしい。(後で聞かされた)今更か?とも思った。幸い渡された錠剤は人間のものと殆ど変わらない形状だった。
「…チッ。分かったよ…足元見やがって」
腹立たしいがの言い分は正しい。イザナは薬の入った袋を乱暴に受け取ると、言われた錠剤を水と一緒に流し込んだ。
「良く出来ました」
「うるせえな」
まるであやすように言われ、カチンときた。こんな口を利かれたのは初めてだ。蘭が話してた通り生意気な女だ、と思った。だが裏腹に――どこか懐かしいものを覚えた。
遠い昔、育った施設でヤンチャをしてはこんな風に説教されてたのを思い出す。
「はい、じゃあ二人とも早く帰ってくれる?」
自分のやるべきことは終わった。は早く一人になりたかった。せっかくの休日を、こんな男達の為に潰したくはない。
すると、それまで不機嫌そうに二人のやり取りを見ていた蘭が立ち上がった。
「おい、」
「な、何よ…」
馴れ馴れしく呼ぶなと思いながら後ずさる彼女の前に、蘭が相変わらず不機嫌そうな顔で歩いてきた。
「イザナの傷はもう大丈夫なんだろうな」
「…ちゃんと治療はしたし…あ、でも毎日さっきの薬は飲んだ方がいい。完全に傷が塞がるまでは細菌感染しないとも言い切れないし。だから念のため毎日ここに来て。薬は今渡すけど、他にも消毒したり包帯を取り換えたりしたいから」
「は?毎日…?」
驚きの声を上げたのは問いかけた蘭ではなく、イザナの方だった。
「そうよ。早く治したいならね。あの傷じゃ早くて全治2か月…ってとこだと思う」
「マジかよ…」
予想していたよりも長かったらしい。体に穴が開いたのだから当然だ。イザナはげんなりしたように項垂れた。
その様子を眺めながら、綺麗な顔立ちはしかめっ面でも綺麗なんだな、とは変なところで感心していた。
「めんどくさい…」
「でも医者ならみんな同じこと言うと思うけど」
「…チッ」
「……(舌打ち?)」
大きな瞳を半分にまで細めながら舌打ちをするイザナを見て、今度はの頬が引きつる。親切で言ってあげてるのになんだその態度は、と言いたかった。もちろん反社組織のトップに対して絶対に言えないが。
「だったら…オマエが来い」
「…はい?」
不機嫌から一転、どこか得意げな笑みを浮かべたイザナは「オマエがオレのとこに来いっつってんの」ともう一度繰り返した。
「な、何でわたしが…」
「通うの面倒だし。オレらの本部は隣のビルだ。近いし問題ねえだろ」
「……(なら自分が来ればいいのに)」
内心そうツッコんだものの、やはり本人には言えない。そもそも理屈が通用する相手じゃないのは、普段から蘭を相手にしてるのでよく分かっている。
「…分かった。でも仕事があるから行くのは夜になるけど…」
「あ?オレが必要だと思った時に来いよ。電話したらソッコーでな」
「な…そんなこと出来るわけ――」
「あ?文句あんの」
「う……(この我がまま犬め…)」
端正な顔立ちが意地悪そうに微笑む。イザナは命令することに慣れているようだった。チラリと蘭の方を見れば、彼もイザナの言動に慣れているのか「諦めろ…」と苦笑いを浮かべている。
「わ…分かったわよ。行けばいーんでしょ?行けば…。ったく…自己中を絵に描いたような男ね…」
「あ?何か言ったか?」
「別にっ」
面倒な仕事がまた一つ増えた。何とも腹立たしいが逆らうことも出来ず、は溜息を吐いた。
「んじゃー戻るか、蘭」
気が済んだのか、イザナがエレベーターの方へと歩いて行く。それを見てホっとしたのもつかの間。
「ああ…ってかオレも包帯だけ変えてもらうわ」
今度は蘭の相手をする羽目になった。
◆◇◆
イザナを見送ってから戻ると、不機嫌丸出しの女医が待っていた。
「じゃあ先に傷の消毒をするから座って」
諦めたような顔で包帯や消毒液などを準備しはじめたを眺めながら、蘭は再びソファへ腰をかける。せっかくの休日を邪魔されたことを根に持っているのか、彼女の表情は相変わらず仏頂面だ。それでもお構いなしに蘭はジャケットと仕立てのいいシャツをを脱ぎ、怪我を負った腕をの方へと突き出す。彼女は蘭の隣に座ると、慣れた手つきで古い包帯を解いていった。
「痛みは?」
「もうねえよ」
「そう。まあ…傷口もくっついてるし、あまり動かさなければ来週には完全に塞がると思う」
淡々とした様子で話しながら、消毒液で浸したコットンをピンセットで摘まみ、それを傷口にあてていく。冷やりとした感触が蘭の肌を湿らせていった。
(静か…だな…)
二人だけの室内は何の音もない。時折、開け放された窓の外から車の走る音や、歩道を歩く人々の話し声が聞こえる程度。合間にふわりと柔らかい春風が吹いて、の長い髪を揺らしていった。普段は一つに縛っている髪を下ろしているせいだ。窓から入る日差しを浴びて、綺麗な髪は艶々と光っていた。
(こうして見ると、まあ普段よりは女に見えるな)
消毒を終えて、今度は包帯を巻きだしたを眺める。休日だからだろう。彼女の顔はいつも以上に化粧っ気はない。だが真剣な顔で包帯を巻いている姿は、蘭の目に少しだけ眩しく映った。
(すげー色白…竜胆も言ってたが、昔は勉強ばっかしてたんだろーな)
彼女の肌は陽の光が当たると透き通るほど白く見えて、蘭は内心苦笑した。プールや海で肌を焼いたことがあるならこうはいかないはずだ。
(恋愛そっちのけのガリ勉タイプってのは間違いなさそうだ)
勝手な分析をしながら、ふとこの堅物女の気を引ける男がいるならどんな奴なんだろうと首を捻る。先ほどイザナに食事をさせていたとこを見れば、世話を焼くのは好きそうだ。と言って、彼女からすればイザナは大きな犬と同じだったのかもしれないが。
「はい、出来た」
「おーサンキュ」
包帯を巻き終わったが顔を上げた時、不意に目が合った。彼女は何故か驚いた様子で瞬きを繰り返している。その表情が幼い少女のそれと似ていて、蘭は吹き出しそうになった。
「何だよ、その間抜け面は」
「む…。だって…急にらしくもなくお礼なんて言うから…ビックリしたのっ」
「ハァ?オマエ、オレのこと何だと思ってんだよ」
「何って…自己中で横柄で狡賢くて――」
「は…てめぇ、ディスりすぎだろ」
「いた…っ」
好き勝手に言われ、蘭がの頭を軽く小突くと、彼女の首が思った以上に後ろへ反れる。どんだけ軽いんだと少しだけ驚いた。
「…もう…痛いなあ…首が折れたらどーするの?暴力的も追加しとこ…」
「あ?別に殴ってねえじゃん」
「殴られてたら今頃わたしは全身骨折で死んでるでしょうねー」
「何だそれ」
遠い目をしながら棒読みで言い切るを見て、蘭は思わず吹き出した。いつもの憎まれ口のように聞こえて、少し違うノリにも感じる。まるで古い友人を相手にしているようだ。
「オマエは大事なウチのお医者さまだからな。そんなことで殺すはずねえだろ」
「…それは…どーも」
今度は複雑そうな顔で言うと、は包帯や消毒液を片付け始めた。その横顔を眺めながら、ふと先ほど感じた苛立ちを思い出す。
彼女がイザナの世話を焼く姿が何となく気に入らなかったのだ。
(ってかあんなことで何でオレがイライラしなくちゃなんねーの…?)
自分でもその辺はよく分からないが、明らかに自分への態度と違ったのが癪に障る。利用価値があるただの債務者に独占欲を覚えるなどおかしな話だ。
(コイツは組織の為に利用してる…それだけの女だ)
まるで自分に言い聞かせるように納得していると、不意にが振り向いた。
「…他に用がないなら、そろそろ帰って。貴重な休みを無駄にしたくないの」
「…チッ。人を厄介者みたいに…」
処置が終わり、蘭がシャツとジャケットを着こんでいると、またしてもゴキブリを見るような目つきで睨まれてしまった。他の債務者からこんな態度をされたことは一度もない。当然、女からも。
(初めて会った時はビビって震えてたくせに…)
ふと初対面の日のことを思い出した。
父親の借金のことを初めて知ったらしい娘は、血の気の失せた顔で、蘭に言われるがまま書類へサインをしようとした。だが直前、持っていたペンを静かに置いてこう言ったのだ。
――この内容じゃサインは出来ません。
それは楽勝だと余裕をかましていた蘭を少なからず動揺させた。
――この土地は…いえ、土地はどうでもいい。でもこの病院だけは続けさせて下さい。借金は働いて絶対に返します。
そう言い切った時のの目は驚くほどに真剣で、本気で億単位の金を返そうとしている。蘭にはそう見えた。
元々土地を奪うと脅して、ついでに医者と病院を手に入れようとしていた蘭には好都合だったとも言えるが、本気で父親の負債の責任を取ろうとしている彼女の意志の強さに驚かされた。
どんな人間も桁違いの借金額を見れば、まず返済できるとは考えない。どうにか他の方法でチャラに出来ないかを考える。そこで初めて組織にとって都合のいい方法を提示すれば、相手は簡単に言うことを聞く。それがどんな犯罪行為であっても。
なのには迷うことなく「絶対に返す」と言い切った。まだ24の若さで、親の借金の為に自分を犠牲にする人生を選んだのだ。
借金額を見て震えていた女は、もうそこにはいなかった。
覚悟を決めると女はこうも豹変するものなのかと驚かされたのを思い出す。
(いや…女が、じゃない。コイツがそういう人間ってことだ)
結果、目的通りに契約をさせられなかったものの、急遽交換条件を出すことで組織の為に働くことを承諾させることには成功した。だが、それは彼女にとっても都合のいい話だったのかもしれない。
自分の病院を守る――。彼女にしてみれば、その希望だけは消えていないのだから。
(実際の借金額が数百万だと知ったら…さすがにコイツも驚くだろーな)
未だ早く帰れと言いたげに睨んでくるを眺めながら、ふと失笑が漏れた。
「なに笑ってんのよ…」
「…いや、別に」
不意に笑い出した蘭を見て、は怪訝そうに眉を潜めている。今、ここで真実を教えたら、彼女はいったいどんな反応をするんだろう。見てみたい気もするな、と蘭は思った。
元々の父親が借りたのは400万弱。現在の借金額はそれに膨大な利子を加算しただけの適当な金額だ。真っ当な金融会社ではないのだから、その辺は自由に設定できる。そして最初に貸し付けた金額は彼女の父親がとっくのとうに返し終えていた。その事実をだけが気づいていない。九井が作った書類に記された金額を素直に信じているからだ。
(そこはまだまだ青いよな…先生も)
反社の人間が言うことを簡単に信用なんてするものじゃない。そう警告してやりたくなる。
(ま…それは出来ねえけどな…父親がどこにいるのかってことも含めてバレねえようにしねえと)
彼女にはもう少し"都合のいい存在"でいてもらわなければならないから。
「じゃあお望み通り帰るわ。ああ、明日イザナのとこに行くの忘れんなよ」
「…分かってるってば」
は不服そうに、それでも素直に頷いた。彼女のこういうところは蘭も嫌いじゃない。かすかに笑みを浮かべると、手をヒラヒラと振りながら部屋を後にした。