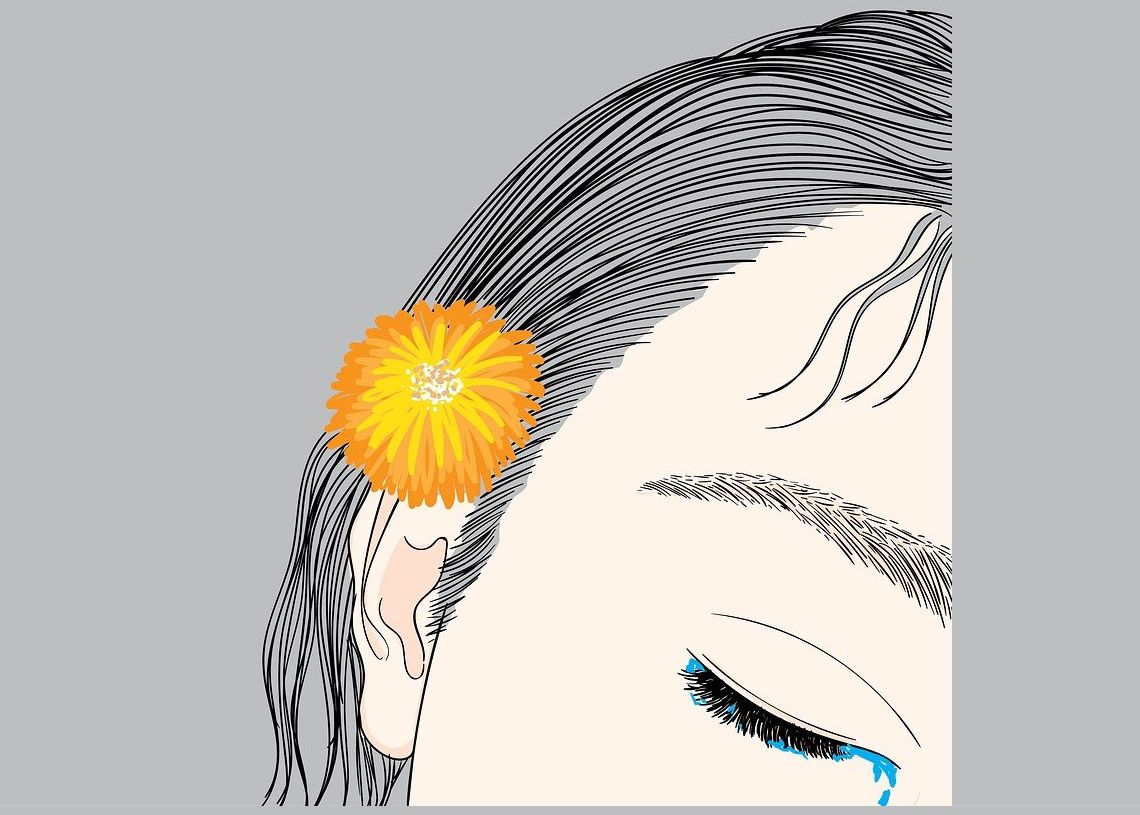
I knew
第二十一幕:未来を思う
引っ越し祝いのパーティが二日後に迫った今日。
担当の新人作家さまが休暇中ということもあり、ここ最近は通常の勤務で落ち着いていたわたしは仕事の合間にいい感じの美容室やネイルサロンを検索してすぐに予約をしておいた。
竜ちゃんや蘭ちゃんの昔馴染みだという仲間の人に初めて対面するのだから、竜ちゃんの彼女として相応しい程度に着飾りたいという女心だ。
普段のわたしはそこまでメイクにも服装にも気を遣ってないし、先生の締め切り前なんかはその辺のオッサンと変わらないくらいにズボラな恰好をしてると思う。
出版社勤務の編集者…なんて、聞こえはいいかもしれないけど、実情は外見に気を遣ってられるほど余裕はなく。ファッション誌ならともかく、わたしのような作家担当の編集部は特に適当だったりする。
これまで竜ちゃんと会う時はそれなりに気を遣って女の子らしい恰好やメイクをしてたけど、それでも足りなかったと思う。
なのに竜ちゃんはいつ会う時でも「可愛い」なんて言ってわたしを甘やかすから、これでいいのかな…なんて思い始めてたけど、やっぱり甘えは良くない。
(竜ちゃん達のお友達、みんな派手だったもんね…)
前に仲間だという天竺メンバーと写した写真を見せてもらった時、わたしの知らない世界の人達ばかりで度肝を抜かれてしまった。
頭の横にタトゥーが入ってた人もいたし、やたらとガタイのいい人とか、めちゃくちゃ美形な人までいて、とにかく目立つ人達ばかりだった。
あの中にわたしが入っていいんだろうか、と心配になって、だから余計にアレコレと予約を入れてしまったのもある。
(当日はメイクもお願いしちゃおうかなぁ…自分でやって失敗するのも嫌だし…。あ…服!服はどうしよう)
帰り支度をしながら一番肝心なことを思い出して手が止まる。パーティってどれくらいの規模なのかは分からないけど、普段デートで着てるようなワンピースとかじゃ地味かもしれない。
(帰りに買いに行こうかな…)
そう思いながら時計を確認すると、すでに午後5時すぎ。今から渋谷まで買いに行くのも怠いけど、明日は美容室などを予約したから、行くなら今日しかない。
「急がなくちゃ」
仕事用のノートパソコンをバッグに詰めて、靴を履き替えるとすぐに編集部を飛び出した。だいぶ薄く進化したノートパソコンでも地味に重く。これを抱えて買い物に行くことすら疲れてしまうけど、明後日は早く上がる為に終わらせたい仕事があるから仕方ない。家に持ち帰ってやらないと間に合わないかもしれないからだ。
――家に帰ってまで仕事すんの?
なんて竜ちゃんに呆れられそうだけど、パーティの為だと言えば大目にみてくれるはずだ。
そう思いながらエントランスロビーに出た時、わたしのスマホが鳴りだした。竜ちゃんかも、と思いながらポケットに突っ込んだスマホを出す。いつも時間があれば、このくらいの時間帯に『迎えに行こうか?』という電話が入るからだ。でも今夜は別の相手からだった。
『おー、もう仕事終わったー?』
「蘭ちゃん?今ちょうど会社を出るとこだけど…どうしたの?」
まさかの蘭ちゃんからでちょっと驚いた。電話がきたことじゃなく、蘭ちゃんがこの時間に起きてるなんて珍しいからだ。
『いや、今日竜胆のヤツ、仕事で迎えに行けねえっつーから暇なオレが行こうかなーと思って。わりと早くに目が覚めちゃったんだよ』
「そっか…って、え…?蘭ちゃんが来てくれるの?」
『まーオレじゃ不満だろうけどー』
なんて言いながら蘭ちゃんは笑ってる。釣られてわたしまで吹き出してしまった。
「不満なわけないでしょ。嬉しいよ」
『そ?なら…早く出て来いよ。もうオマエの会社前にいるし』
「え、ほんとに?」
驚いて電話を繋げたまま会社のビルを出ると、目の前にはド派手なスポーツカーがドンっと止まっている。蘭ちゃんの愛車のポルシェだ。しかも鮮やかなバイオレットカラー。こんなオフィス街にそんな目立つ車が止まっているせいで歩行者がみんな蘭ちゃんの車を振り返っている。
前にも何度か迎えに来て貰ったことはあるけど、相変わらずの存在感だ。
「、こっちこっち」
わたしが突っ立っているのを見つけた蘭ちゃんが、窓を開けて声をかけてきた。
どこのモデルだと突っ込みたくなるような、これまたカッコいいスーツを着こなしている。
歩道を歩く帰宅途中らしきOLさん達が一斉に色めきだったのが、わたしの目にもハッキリと伝わってくるんだから笑ってしまう。
"罪な男"…という言葉は蘭ちゃんの為にあるような言葉かもしれない。
とにかく、これ以上ここにいたら目立って仕方がない、とわたしは促されるまますぐに助手席へと滑り込んだ。
何度も乗せてもらったことはあれど、相変わらずの車体の低さと高級な革張りの座席は緊張してしまう。
竜ちゃんのベンツは車体が高いからなおさらだ。
「~今日も一日お疲れ~♡」
「ひゃ」
乗った瞬間、蘭ちゃんの腕が伸びてきてギュッとハグをされた。その後は頭に頬ずり攻撃とホッペにチューのサービスまである。完全なるマーキングだ。
これは蘭ちゃんがわたしを迎えに来てくれた時のお約束で、"竜胆には内緒"という蘭ちゃんとわたしの間で暗黙のルールがあったりする。
その理由は蘭ちゃん曰く「竜胆がヤキモチ妬くから」だそうだ。
何でも「を迎えに行ってくれんのは助かるけど、ぜってー手ぇ出すなよ?」と毎回クギをさされるらしい。
今日のお迎えは起きてた蘭ちゃんが言い出したみたいだけど、しっかりクギはさされたようだ。
「今日は竜胆が企画したイベントのことでスタッフと打ち合わせ入ってて遅くなるみたいだわ」
「あー…そう言えば昨日寝る前にそんな話をチラっとしてたかも」
夕べ、早く終われば迎えに行けると竜ちゃんは言ってたけど、やっぱり終わらなかったようだ。
クラブのイベントは毎回大規模なものになるし、有名人を呼んだりするから、細かな打ち合わせと入念な準備が必要だと蘭ちゃんが教えてくれた。
「まあ明後日は貸し切りパーティあっから、それまでにだいたい終わらせたいんだろ、アイツも」
「そっかー。でもわたしもそんな感じなんだ」
言いながらパソコンの入ったバッグをポンと叩く。
蘭ちゃんは「家でも仕事すんのかよ」と竜ちゃんみたいなことを言って苦笑した。
「まあ、でも飯くらいは食うだろ?」
「え?あ、まあ…っていうか…買い物してないかも…」
蘭ちゃんの言葉でふと思い出した。お互い忙しくて食材を買いにいく暇がなく、家にはインスタントラーメンすらないかもしれない。家に帰る前にコンビニでも寄ってもらおうかと思った時、服を買いに行こうとしてたことも思い出す。
「いけない…!蘭ちゃん、わたし服を買いに行きたくて…」
「服~?何で?あー…もしかしてパーティの時に着るやつか」
「う、うん…わたし、恥ずかしながら碌な服持ってないから」
「んなの普段の恰好で十分可愛いのに」
「そんなわけ…」
ニッコリしながら褒めてくれる蘭ちゃんは、やっぱり竜ちゃんのお兄さんだなあと思う。
わたしを甘やかす天才だ。
「でもまあ…が変なこと気にせず100%楽しんでくれるなら買いにいくかー」
「え…?」
急にハンドルを切った蘭ちゃんに驚いて顔を上げると「オレがに似合う服を選ぶわ」と言いだした。
「え…それは助かるけど…蘭ちゃん忙しいでしょ?いいの?」
「言ったろ?今日のオレは暇人だから。それに可愛いの為に服を選んでやりたいの」
「…蘭ちゃん」
「なにウルウルしてんだよ。子犬か」
わたしが感動してると、蘭ちゃんは笑いながら頭をワシャワシャ撫でてくる。出来ればハンドルから手は離さないで欲しいと思いつつ、お洒落な蘭ちゃんが選んでくれるなら凄く助かると思った。
「んじゃーサッサと買い物して、その後はディナーデートでも行くとするか。どうせ腹も減ってんだろ?」
「え、いいの?」
「オレがとデートしたいからいいんだよ。ってか竜胆のヤツ、仕事なんてかわいそ~」
そんなことを言って笑ってるけど、ちゃんと竜ちゃんに報告電話を入れる辺りが蘭ちゃんらしい。
ほんとに仲のいい兄弟だと思う。
そう思いながら何となくジーンとしてた時だった。
蘭ちゃんが竜ちゃんに電話をすると『はぁ?!何でオレを差し置いてとデートすんの?!』とキレられてたから思わず笑ってしまった。
竜ちゃんが帰ってきたら散々文句を言われるだろうなぁと思いつつ、たまには蘭ちゃんとのデートも悪くないかもしれない。
なんて思ったのは内緒の話だけど。
「は~マジで竜胆、ヤキモチ妬きだなー」
電話を切った後で蘭ちゃんが苦笑している。隣で竜ちゃんの怒鳴る声は聞こえてたからちょっと恥ずかしい。
「まあでも何とかお許し出たから大丈夫だろ」
「うん」
「まー帰ったら熱烈にお帰りのチューでもしてやりゃ機嫌も直んじゃねえの」
「…え」
ニヤニヤしながら言われて更に顔が熱くなった。
確かにお帰りのチューはいつもしてるけど、蘭ちゃんにはバレバレみたいで照れ臭い。
その時、スマホが軽く振動してメッセージが届いた。確認するとケーコ先輩からで、やっぱり何を着てけばいいのかという相談だった。
そこでふと思い出す。
「あ、そうだ。あのね、ケーコ先輩のとこに新しくアシスタントが入ったんだけど、その子もパーティに呼んでいい?ほら、他に暇な子いたら誘ってって言ってたでしょ」
「アシスタント?ああ、初めてがうちのクラブに来た時、やってたような仕事?」
「うん。その子はバイトみたいなんだけどケーコ先輩が可愛がってて」
「へえ、じゃあ呼べよ。こっちも男ばっかだから女の子呼べってうるせえのがいんだよ。だから大歓迎」
「良かった~。じゃあケーコ先輩にOKって送っとくね」
服装のことを返信がてら、そのことについてもメッセージを打っていく。とりあえず今夜は蘭ちゃんとデートするなんて話したら怒られるから内緒にしておこう、なんて思いながらケーコ先輩にメッセージを送信した。
「これでよし、と」
「で、その子って可愛いの?」
スマホをバッグにしまっていると、蘭ちゃんがニヤつきながら訊いてくる。やっぱりその辺は男性陣も気になるところなのかもしれない。
「うん、凄く可愛いよ。何かウチの会社にはいないようなお洒落な子で、華やかさがあるっていうか。美人って言うよりは可愛いアイドルタイプかなぁ」
先日ケーコ先輩に紹介してもらった子を思い出しながら説明すると、蘭ちゃんが「へえ、じゃあ班目辺りが喜びそ~」と笑っている。
「みんな、可愛い子に飢えてっから」
「そーなの?」
「まあ、アイツらモテねえからなー。オレらやイザナと違って」
「またそんなこと言って」
と笑ったものの、実際蘭ちゃんはモテるから自意識過剰なんて言葉は当てはまらないのは分かってる。
「蘭ちゃんは美人系の人がタイプだもんね」
「あ?オレ~?オレは別にそんなん決めてねえけど。オマエより可愛いとか思う女はいねえしなー」
「え…嘘ばっかり…」
蘭ちゃんのリップサービスとは分かっていても、そんな風に言われるとやっぱり照れ臭い。
わたしがジトっと睨むと蘭ちゃんは「嘘じゃねえよ」と軽く吹き出した。
「まあ弟の彼女って、他の女とは比べもんにならねーくらい特別っていうか…無条件で可愛いもんなんだよ」
「…そうなの?ああ、それって孫を可愛がるおじいちゃん的な…?」
「あ?テメェ、オレをおじいちゃんにすんなよ」
「いたっ」
素朴な疑問を口にしただけなのに、蘭ちゃんはあたしのホッペをむぎゅっとつねってきた。でもこれもいつも通りのじゃれ合いで、わたしからすれば楽しい時間の一つだったりする。
彼氏のお兄さんからこんなに思われるのは、何だかんだで幸せなのだ。
「あ~早くがほんとの妹になんねーかなぁ」
蘭ちゃんがシミジミ言うから思わず吹き出した。
それはわたしと竜ちゃんが結婚するということだから、何気ないその一言は、わたしにとって凄く嬉しい。
本当に、そうなれればいいのに。
この時のわたしは、そんな先の未来を想像するだけで幸せだった。