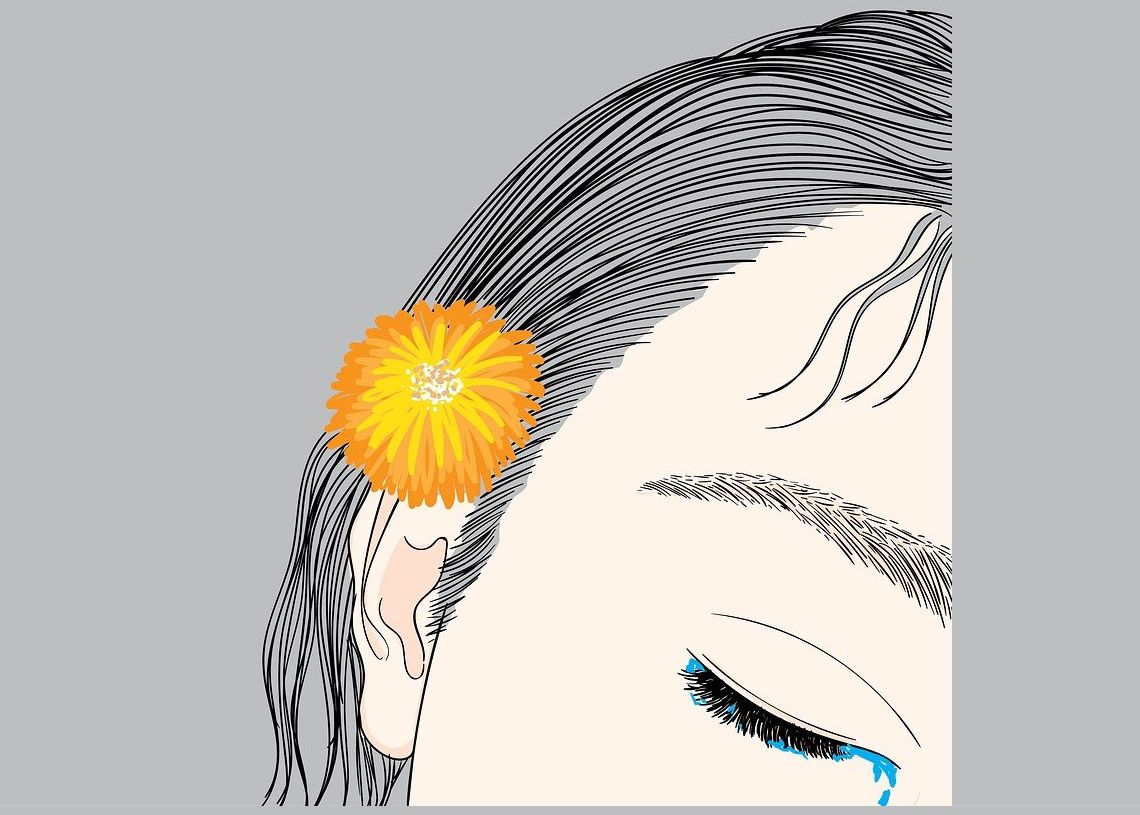
I knew
第二十二幕:予感
挫折をしたことがない人間は、最悪の未来を想像できない。
そう言ったのは誰だったか――。
まさに正論だと思ったのは、今のオレが確実にソレだからだ。自分の手の中から大切なものが零れ落ちていくなんて、想像すらしてなかった。
『ツーツーツー』
コールどころか、永遠に話し中を知らせるノイズが、空しく鳴り響く。かけ慣れた番号に何度かけても、一度も繋がることはなかった。
何とも分かりやすい着信拒否だ。
どうしてこんなことに――。
何百回と考えたところで過去は変えられないし、この悲惨な結末を迎えた理由も至極簡単。
オレがどうしようもないほど愚かだったからに他ならない。
夕べが家を出て行った。一緒に暮らし始めてから約半月足らずで破局を迎えるなんて、誰が想像できるだろう。
全てはあの日が元凶だ。引っ越し祝いと称した仲間内のパーティ。
本当なら、楽しい一日になるはずだったのに――。
▽▲▽
パーティ当日、夕方には家を出て、会場になるクラブへ顔を出すと、ある程度のセッティングはだいたい完了していた。普段は寝坊助の兄貴が、今日は張りきって昼から準備をしてくれたおかげだ。
「うわー。豪華な料理がいっぱい」
繋いでいた手を放して、がはしゃぎながらホールへと走っていく。慣れないヒールを履いてるから、転ばないかと心配で、オレも後から追いかけた。って、子供を心配するお父さんか、オレは。
「見て、竜ちゃん!ピンチョスプレートがあんなにある!お洒落で可愛いし、これ絶対蘭ちゃんの好みだよね」
設置された長いテーブルの上には、が言うようにズラリと豪華な料理が並んでいる。ピンチョスを初め、お洒落で見た目の良い高級スイーツなんかも、全て兄貴が見立てたメニューだろう。兄貴は不良なんてやってたわりに、女の子が喜ぶような物を選ぶのが上手いから、任せて正解だったなと思う。
「早く食べてみたいなー」
がワクワクしたように言うから、つい笑ってしまった。こういう無邪気なとこもクソ可愛いんだから困る。
それに今日のは更に可愛さ増しましだった。兄貴に選んでもらった――それはちょっとイラっとしたけど――某ハイブランドのタイトワンピースは、体のラインを強調するから普段のを少しだけ大人っぽく見せるデザインだ。花を象った襟元と、肩の辺りは胸元までシースルー、彼女にしては珍しいタイトなスカートも膝上という短さで、オレもドキリとさせられた。でも色は優しいピンクベージュだからか、大人すぎず、でも子供っぽくもない、エレガントな雰囲気がによく似合ってる。
まあ、多少の露出は気になるとこだけど、が着ると変な厭らしさがない分、オレの許容範囲ギリギリを攻める辺り、さすが兄貴といったところだろう。
「あと30分くらいで始まるから、そしたら好きなだけ食えよ」
「あ、ダメだよー髪に触っちゃ…崩れちゃう」
「あ、そうだった」
つい、いつもの調子で頭を撫でようとしたら、が慌てて離れていった。髪も服装に合わせて美容室でセットしてもらったから、普段はストレートの髪も、今はふんわり巻いてアップにしてある。それもめちゃくちゃ可愛いんだけど、触れないのは何か悲しい。
「わたし、スタッフさんにも挨拶してくるね」
「オレも行こうか?」
歩きかけたに声をかけると「子供じゃないんだから一人で行ける」と、あっさりフラれてしまった。
オレとの関係を客に知られないよう、は殆どここに来ることがないから楽しいんだろう。苦笑交じりで見送っていると、いきなり後頭部にゴツンという衝撃。ついクセで「いてーな」と文句を言えば、案の定ニヤついた兄貴が立っていた。その隣にはさっき到着したばかりのイザナくんまでいる。更にホール内でフライングの如く酒を飲み始めた鶴蝶やモッチーも、すでにには紹介済みだ。
「な~に捨て犬みてーな顔で見送ってんだよ」
「んな顔してねえし」
「いや、してた」
「イザナくんまで勘弁してよ」
二人はカジュアルなスーツでキメていて、こうして並んでるとホストにしか見えない。そう言ってやったら「オマエもだろ」と突っ込まれたけど。
「噂通りめっちゃ可愛いよなあ、竜胆の彼女」
「だろ?」
「予想以上に良い子すぎてビビったけど」
今は鶴蝶やモッチー相手に談笑しているを見ながら、イザナくんは「あの子がよくオマエを選んだな」なんて失礼なことを言って笑っている。
でも、それはオレが一番思ってるかもしれない。あんないい子が、オレのことを本気で好きになってくれるなんて奇跡だって。
「大事にしろよ」
「当然そのつもりだし」
「竜ちゃーん!もうすぐケーコ先輩も着くって」
笑顔で手を振ってくるに手を振り返しながら、迷うことなく応えると、兄貴もイザナくんも「何かムカつく」と理不尽なことを言いながらどついてきた。いや、何で?と聞きたくなったけど、地味に似た者同士の二人に勝てる気がしないから、そこはスルーしておく。
「女の子、到着だって?」
耳ざといイザナくんが期待した目でオレを見た。イザナくんはモテるんだから、何も身内だけのパーティで女を狙わなくてもいいのに。
「まあ、女の子…って呼んでいいのか分かんないの先輩と、そのアシスタントは…若いって話だけど」
「へえ。そうなんだ」
「…手ぇ出すのなしの方向で。の知り合いだし」
「生意気」
ゴンっという音と共に、またしても後頭部に衝撃が走った。でもイザナくんは笑ってるから、口で言うほど怒ってるわけじゃなく、今のは「了解」って意味だと思う。ただ、いちいち殴るのやめて欲しい。まあ手が早いのは昔からだけど。長年、イザナくんの下僕をしてる鶴蝶に、少しだけ同情してしまった。
「あ、そーだ。竜胆、裏からビールとグラス、受け取ってきて。最初の乾杯用」
「えー…スタッフに頼めよ」
兄貴から指令が出て、ついそう言ったけど、スタッフは別の準備で手が回らないらしい。まあ兄貴の理不尽な注文に、裏では色々大変なんだろう。仕方ねえな、と溜息を吐きつつ、に声をかけてから厨房へ向かう。
その時、ホールの方から「あ、ケーコ先輩。こっち」という明るい声が聞こえてきた。
△▼▽
その女を視界に捉えた時、何の悪ふざけかと思った。
「あ、蘭さん。今日は内輪のパーティなのに招待してもらっちゃってありがとうー。お言葉に甘えて若い子も連れてきたの。この子は最近アシスタントで雇った――ちゃんです」
ケーコというの先輩が何やら話してたが、オレの耳には全く入ってこなかった。それもこれも、目の前で挑発的な笑みを浮かべてる、その"アシスタント"のせいだ。
「どうも。お久しぶりです、蘭さん」
女はわざとらしく協調した物言いで、オレに嘘くさい笑顔を振りまいた。しかも普段着るようなギャル服でも厚化粧でもなく、今はキッチリとしたスーツを着て薄めのメイクを施している。一見してあの女と同一人物には見えないが、オレの目は誤魔化せない。
この女が、と同じ出版社でアシスタント?悪い冗談だ。全く笑えねえ。
「え、蘭さんのこと知ってるの?」
「ええ、まあ。ちょっと。ねえ?蘭さん」
最悪だ――と、そう思った。この状況、含みを持つ笑み。この女はの素性を知っている。どうやって調べたのかは知らないが、竜胆との関係を知ってて、コイツはここにいる。あげく同じ会社にバイトとして潜り込み、の先輩のアシスタントにまでなっていた。
自分と竜胆との関係をケーコって先輩にも隠して今日まできたんだろう。それもこれも、こういう状況になるのをひたすら待つため。そうとしか思えない。
「え、蘭ちゃん、この子と知り合いだったの?凄い偶然!」
「……っ」
先輩の隣にいたまでが、驚いたようにオレを見る。その刹那、自分でも顔が引きつったのが分かった。この女の目的は知らないが、嫌な予感しかしねえ。
「ちょっと来い」
「え…蘭ちゃん…?」
ひとこと言って女の手を掴むと、が困惑したような顔でオレを見る。本当なら、いつもみたいに笑顔を見せて、上手くはぐらかして、さらりとその場を立ち去れば良かったのかもしれない。でもこの時のオレは、そんな余裕がなかった。目の前の爆弾を、一分一秒でも早く、の目の届かない場所へ、捨てたかった。
そうしないと、いけなかった。なのに――。
「あれ、兄貴?その子、誰だよ」
「―――ッ?」
オレの言いつけ通り、飲み物とグラスを受けとった竜胆が、何も知らずに戻ってきたのを見て、俺の顏から今度こそ血の気が引いた。
掴んでいた手が、あっさりと振り払われる。
竜胆はこの女が、例のヤツだと気づいていない。見た目がだいぶ違うせいだ。だから呑気に「早速ナンパすんなって」と笑ってる。
そして、女はオレが制止する前に、竜胆の方へと歩き出す。
この後の展開は、嫌でも想像できてしまった。
「来るな、竜胆!」
「え…?」
咄嗟に怒鳴ってしまったオレを見て、竜胆の笑顔が固まる。それを見計らったかのように、女は愉悦を含んだ笑みを、その顏に浮かべた。
「竜胆くん、会いたかった」