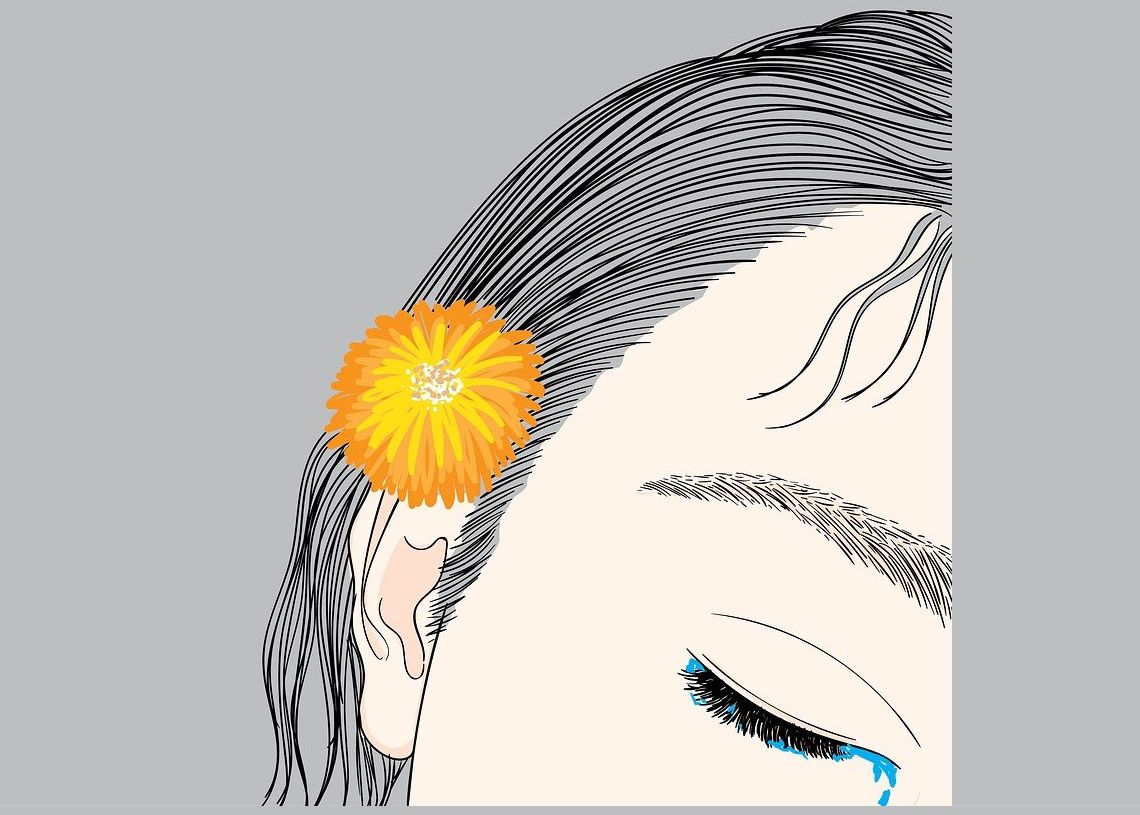
I knew
第二十三幕:優しさに触れる
あの夜のことが忘れられない。
――竜胆、来るな!
蘭ちゃんの叫ぶ声と共に始まった、悪夢の夜だ。
グラスが割れる音。誰かの怒号と悲鳴。そしてあの子が竜ちゃんに見せた、挑発的な笑み。
今も頭にこびりついて、離れない光景。
ケーコ先輩のアシスタントだった女の子は、あの夜以降、ぱったり会社には来なくなったという。きっと、目的を果たしたんだな、と思った。
わたしは何も知らなかった。知らないまま、竜ちゃんと付き合って、自分を幸せだと思い込んでたらしい。道化もいいとこだ。
いや…違う。本当は、いつかこんな日が来るんじゃないかって、どこかで怯えてた。竜ちゃんに女の影を感じても、見てみぬふりをしてきた。小さな違和感を覚えても本人に確認することもなく、わたしは忙しさにかまけて、本来の彼を見ようとしてなかったんだと思う。
――竜胆くん、会いたかった。
あの夜、彼女はそう言って竜ちゃんに駆け寄った。何故、ケーコ先輩のアシスタントの子が竜ちゃんを知ってるんだろうと、不思議に思ったけど、あの時の竜ちゃんの凍り付いた表情を見て、すぐにどういう関係なのかを察してしまった。それでも、わたしと付き合う前のことなら、と思おうとした。だけど、そんな小さな望みも、すぐに打ち砕かれてしまった。
竜ちゃんに駆け寄った後、彼女はわたしを見て、ひとこと言った。
――あんたと付き合ってる裏で、竜胆くんが何をしてたか教えてあげる。
彼女はそう言って、バッグから出した写真をその場でばらまいた。勝手に足が震えて、視界に飛びこんできた写真の数々に、心臓が抉られたのかと思うような衝撃を受けた。
それは知らない女の人を膝に乗せてキスをする竜ちゃんの写真。他にも別の女の人、それも上半身裸の人とキスを交わす写真。どれもこれも、わたしの知らない竜ちゃんが写っていた。ご丁寧に日付まで載っている。どれも全て今年のものだった。わたしと付き合う前のものじゃない。
蘭ちゃんや、他の誰かが何かを叫んで、あの子を強引に店から連れ出すのを感じながら、わたしは言葉もなく、竜ちゃんを見つめてた。何かを言ってくれるのを期待した。全部あの子の嘘だって、そう言って欲しかった。なのに竜ちゃんはわたしから目を反らして――。
――ごめん、…
そんな言葉が欲しかったんじゃない。そう叫んでわたしは店を飛び出した。わたしの名を呼ぶ色んな人の声も無視して、ただ前だけを見て外に飛び出した。そこからあまり細かい記憶はない。混乱した頭と、胸の痛み以外、覚えてない。何も考えたくなかった。
気づけばマンションの前にいて、わたしは決心する前に行動してたように思う。自分の服を詰めるだけトランクに詰めて、竜ちゃんと一緒に住み始めたばかりの部屋を飛び出した。ここを出る時はあんなに幸せだったのに、これからもそれが続いていくと信じてたのに。なんて呆気ない幕引き。
それが一カ月前の出来事だ。
「久しぶり…。元気そう…ではねぇな」
そして今日、あの夜以来、初めて蘭ちゃんと顔を合わせた。
マンションを飛び出したわたしは、しばらくホテルを転々として過ごした。スマホの設定も拒否にした。竜ちゃんや蘭ちゃんからの電話は自分でも気づかないようにしたかった。でも自分にも責任を感じてたケーコ先輩が、蘭ちゃんから頼まれたらしい。
「今日蘭さんと会う場をセッティングしたから、せめて顏くらい見せてあげて。凄く心配してるの」
そう言われて最初は悩んだけど、これ以上ケーコ先輩に責任を感じて欲しくなくて、蘭ちゃんだけなら、という約束で、わたしは指定されたラウンジへとやって来た。蘭ちゃん御用達の個室がある店らしく、店内に入ると、高級店らしいスーツを着たスタッフから丁寧に部屋へと通された。
「…今…どこにいんだよ」
気まずくて俯いたまま、紅茶から上がる湯気をボーっと見ていたら、蘭ちゃんが身を乗り出して、わたしの頭へそっと手を乗せるのが分かった。その手は前と変わらず優しくて、つい泣いてしまいそうになる。でも今ここで泣けば、きっと蘭ちゃんを困らせるから、どうにか耐えて笑顔を見せた。
「ケーコ先輩のマンションに居候してる。しばらく会社近くのビジネスホテルを転々としてたんだけど、ケーコ先輩がうちに来なって言ってくれて」
「…そっか」
きっとその辺の話は蘭ちゃんも先輩から聞いてるんだろう。それ以上深くは聞いてこなかった。
「ちゃんと…仕事は出来てるんだな?」
「…うん。わたしが抜けたら作家先生に迷惑かけちゃうもん。ほら、わたし、仕事はきっちりするから先生にも頼られてるし」
あまりに蘭ちゃんが心配そうな顔をするから、少しでも場を明るくしようと軽口を叩く。でもそんなの蘭ちゃんには全てお見通しみたいだ。「無理に笑うなって」と苦笑されてしまった。
でもね、蘭ちゃん。不思議なことに、時間が過ぎていくたび、わたしは笑うことも出来るようになったし、仕事だって前と同じく出来てる。無理をしてるのかは分からないけど、どんなに傷ついても、悲しくても、わたしの時間は進んでいくから、仕事も待ってはくれないから、明日は必ずやってくるから、生きてる以上、海の底に沈んでばかりもいられないんだ。
ただ、隣に竜ちゃんがいない寂しさは簡単に埋められなくて。マンションを飛び出して、一カ月は過ぎたというのに、心はまだあの夜を彷徨ってる気がする。何一つ言い訳すらしてくれなかった、竜ちゃんの「ごめん」と共に。
「…は…どうしたい?」
「え…?」
しばしの沈黙の後、蘭ちゃんが切り出した。顔を上げると、いつになく元気のない蘭ちゃんと目が合う。わたしもだけど、蘭ちゃんも少し痩せたように見えた。
「簡単に許してやってくれ、とは言えない。でもオレは竜胆の兄貴だから…アイツが落ちてく姿は見てらんねぇし、それを抜きにしてものこと可愛いからさ。このまま会えなくなんのは…すっげー嫌なんだわ…」
「…蘭ちゃん…」
まだ、そんな風に言ってくれるんだと思うと泣けてきた。わたしは話し合うこともせずに、蘭ちゃんの大事な弟から逃げ出したのに。
「ご、ごめんね…蘭ちゃ…」
「ハァ…何でオマエが謝んだよ…100パー悪いのは竜胆だろ。まあ…オレも知ってて見逃してたとこもあったし、言ってみりゃ同罪だ。だから…謝んな」
「…ん。そうだね」
「…って、おい!」
溢れた涙を拭きながら頷くと、蘭ちゃんは前のようにわたしのオデコを軽く小突く。こんなやり取りすら、懐かしくて死にそうだ。
「やっと笑顔が見れたな」
ここへ来た時よりも、少し表情が柔らかくなった蘭ちゃんは、ホっと安堵の息を漏らした。その顏を見ただけで、今日まで物凄く心配かけたんだと分かる。もしかしたら竜ちゃんも…と、そこまで考えて、すぐに打ち消した。今は竜ちゃんのことを考えたくない。
「なあ…やっぱ竜胆と会うの、嫌か?」
少し温くなった紅茶へ口をつけると、少しして蘭ちゃんが訊ねてきた。出来れば会って話し合った方がいいのは分かってる。まだ竜ちゃんからは何も聞いてない。どんな気持ちであんな酷いことをしてたのか、聞きたいことは山ほどある。だけど、まだ顔を合わせる勇気がない。今の竜ちゃんがどんな気持ちでいるのかも分からないから、色んなことが怖い。
「…そうか」
わたしの言葉に、蘭ちゃんはへこんだように溜息を吐いた。
「まあ…まだ時間が足りねえのは分かってんだけどさ…。竜胆のやつ、マジで死にそうなんだわ」
「……え?死にそう…って…」
本当なら今は竜ちゃんの近況を聞きたくはなかった。わたしがこんなに苦しいのに、竜ちゃんだけ、いつもと変わらない生活をしてると聞いてもツラいだけだから。竜ちゃんも落ちこんでるかもしれないけど、人前に出ればそうはいかないだろうし、何だかんだと前のように仕事をしてる気がしていた。
でも――そんな予想を超えて「死にそう」と言われると、やっぱり心配になってくる。
蘭ちゃんは深い溜息を吐きながら、ゆったりとしたソファに凭れ掛かった。
「言葉の通り。飯も殆ど食わねえで酒ばっか飲んでる。仕事には顔出すけど、そんなんだから表の方は任せられねえし、ハッキリ言って使えねえ状態。イベントも今はオレが仕切ってんだ。今の竜胆に任せて、ゲストの前でゲーゲー吐かれても困るしな」
蘭ちゃんの話を聞いて言葉を失った。まさか、あの竜ちゃんがそんな状態だなんて想像すらしてなかった。いつも飄々としてるように見えて、今の仕事は大事にしてたし、好きだから頑張れるとも言ってたのに、それさえ出来ない状態なんて。
「そ…それは…わたしが原因…?」
恐る恐る尋ねると、蘭ちゃんは再び身を乗り出して、苦笑交じりに頬杖をついた。
「他にあるー?あの竜胆がそこまで落ちる原因。ねえよ」
「そ…そう…なんだ…」
「まあ…自業自得と言えばそれまでなんだけどさ。アイツものことだけは本気で大事にしてたから、今の状況はキツいだろ」
ったく困った弟だよ、と蘭ちゃんは笑った。でもわたしは、じゃあ何でって気持ちが湧いてきてしまう。
「……大事って…ほんとにそうなのかな」
「あ?」
お酒のグラスを傾けていた蘭ちゃんが、ギョっとしたように手を止めた。こんなこと蘭ちゃんに言っても仕方ないのに、一度溢れた気持ちを止められなかった。
「蘭ちゃんは…竜ちゃんがわたしのこと大事にしてたって言ったけど、じゃあ…何で他の子とあんな酷いこと出来るの…?」
「……」
「わたしのこと大事だって、本気で好きだって竜ちゃんも言ってくれたけど…じゃあ…何で他の子とあんなことするの…?何でっ?」
言葉に出すたび、お腹の奥の方から激しい感情が沸き上がってきて、頭に血が上ったのか顔や頬が熱い。同時に涙がポロポロ落ちて、唇や顎を濡らしていくのが気持ち悪いのに、自分の意志じゃ止められないくらい、涙が溢れてくる。蘭ちゃんは呆気にとられたような顔でわたしを見ていた。今までこんなに感情的になったこともないし、蘭ちゃんも初めて見たからかもしれない。わたしの中にもこんな激情が眠ってたのかと、自分でも驚いたくらいだ。
蘭ちゃんは黙ってわたしを見てたけど、小さく息を吐き出した後、静かに立ち上がった。そのまま隣に移動してきたかと思えば、わたしの体を丸ごと、蘭ちゃんは抱きしめた。その腕の優しさにまた泣けてきて、蘭ちゃんの胸に顔を押し付ける。この歳で、小さな子供みたいに泣いたのは初めてだったかもしれない。人の腕の中がこんなにも安心するんだと、実感してしまった。
「…ごめん…八つ当たり…」
蘭ちゃんに頭を撫でてもらってると、少しずつ気持ちが落ち着いてきて、さっき怒鳴ってしまったことを謝った。でも蘭ちゃんは「謝んなって言ったろ」と、前のようにわたしの頬をつまむ。その痛みすら懐かしかった。
「は何も悪くねえから。ただ…竜胆のバカな行動の理由を上げるとすれば…忙しいに会えない寂しさからくる甘えってしか言えねえわ」
「…え…」
驚いて顔を上げると、蘭ちゃんは困ったような顔で微笑んでいた。大きな手で、また頭を撫でられる。
「アイツ、が何もかも初めてだったんだよ。女の子をちゃんと好きになったのも、その子と会えない時間が凄く寂しいんだってことも。まあ…それまでは彼女なんて面倒なもんいらねえってアイツも思ってたから、適当に色んな子と遊んでたのは本当。でもに会って竜胆は変わった」
蘭ちゃんはそこまで言うと、自分のグラスを取って、お酒を一口飲んだ。わたしにどう伝えればいいのか、どこか思案してる顔に見えた。
「ただ…変わったけど、変われねえ部分もあっただけ。アイツ、寂しがり屋だったんだよなー。と付き合いだすまで、オレも忘れてたけどさ」
「え…竜ちゃんが…?」
「そう。ガキの頃はいっつもオレにくっついて歩いてたしな。まあ…大人になったら超生意気になったけど」
蘭ちゃんはそう言いながら笑った。わたしも小さい竜ちゃんを想像して、ちょっとだけ笑ってしまった。
「竜胆はオレと同じくらい、ホントは我がままなんだよ。でもに会いたいのに会えなくて、オマエだって遊んでるわけじゃねえから無理も言えなくて…そのどうしようもないモヤモヤを初めて経験したからさ。そういうモヤついた感情をどう消化していいのか分かんなかったんだろうな。んで…それを解消する方法として、自分に寄ってくる軽い子達を選んだ。最初は多分、を裏切ってるって感覚もなかったかもしんねえ。それまで誰とも深い付き合いしてこなかったから。でも…と会ってると少しずつ自分の間違いってやつに気づいてった」
蘭ちゃんは静かに、とうとうと話している。それはわたしも知らなかった竜ちゃんの本質。わたしが忙しくて会えない時、竜ちゃんがいつからか「寂しい」と言ってくるようになったのを思い出した。
「別にだからアイツを許してやってくれって言いたいわけじゃねえし、誤解すんなよ。これは竜胆との問題だから、オレもその辺は理解してるつもり」
「うん…分かってる」
わたしが頷くと、蘭ちゃんはホっとしたように微笑んだ。きっと竜ちゃんに代わって、竜ちゃん自身も気づいてなかった事実を踏まえて、わたしの疑問に答えてくれたんだと思う。そんな蘭ちゃんの優しさが、やけに身に沁みた。
「…ま、どんな結論をが出したとしても…オレは仕方ねえと思ってる」
「え…?」
蘭ちゃんがポツリと呟く。
「アイツの兄貴として…出来ることなら仲直りして欲しいとは思ってるけど――」
「蘭ちゃん…」
「ただ…万が一。オマエが竜胆と別れたとしても、オレとも会わないとかは絶対やめろ」
「え…?」
急に声のトーンが低くなった気がして、伏せていた視線を上げると、蘭ちゃんは頬杖をつきながらわたしを見ていた。ちょっと怒ってるかもしれない。
「この際、竜胆のバカは知らね。自業自得だし?でも、そのせいでオレが寂しー思いすんのは許せねえ」
「………」
まさか真顔でそんなことを言いだすとは思わない。呆気にとられてポカンとしてしまった。
「んだよ…。もしかして、そのつもりだったとか?」
蘭ちゃんはこれまで見たこともない怖い顔で、わたしを睨むから、思わずぶんぶん首を振る。すると「そ?なら良かった」と怖い顔が一転、いつもの優しい笑顔を見せてくれたから、心底ホっとした。
――は?兄貴が優しい?んなのにだけだって。兄貴の中でだけは特別枠なんだと。弟のオレより溺愛してるし。でも普段は悪魔と契約してんのかってくらい他の人間には怖いから。
ふと以前、竜ちゃんが言ってたことが頭に過ぎった。わたしは優しい蘭ちゃんしか知らないから、その時も「嘘だ~」なんて笑って聞いてたけど、さっきの蘭ちゃんを見る限り、竜ちゃんの話してたことは真実かもしれない。蘭ちゃんともう会わないと決めてたわけじゃないけど、もし仮にそんなことを言おうもんなら、本気で蘭ちゃんは怒るのかな、なんてことを考えた。ホッペをつねられるだけじゃ済まないかもしれない。
「んじゃあ、たまにはオレとこうしてデートしようなー?」
「う…うん」
今はニコニコしながら頭を撫でてくれる蘭ちゃんに悪魔の角が二本見えるのは気のせいだろうか。なんてバカなことを考えてたら、気持ちが少し落ち着いてきた。これも蘭ちゃんのおかげだ。
「ああ、じゃ、このまま飯でも行く?」
蘭ちゃんがスマホの時計を確認しながら訊いてきた。
「え…いいの?週末だし、蘭ちゃん仕事かデート入ってるんじゃ…」
「いいんだよ。オーナーとしての仕事は終わらせてきたし、店は竜胆が復活するまで店長にフォローしてもらってっから。あとより優先すべきデート相手なんか、オレにはいねえの」
澄ました顔でそんなことを言うから思わず笑ってしまった。蘭ちゃんはいつだって甘やかし上手だ。だから、かもしれない。もう少し気持ちが落ち着いてきたら、竜ちゃんと会って、ちゃんと話をしてみようと、ふと思った。
「つーか、オマエ少し痩せたろ。ちゃんと食えよ、マジで」
「うん…。あ、あのね、蘭ちゃん」
「ん?」
姿勢を正して、目の前の蘭ちゃんを真っすぐ見上げると、すぐに優しい眼差しに触れる。そんな蘭ちゃんを見ていたら、このまま逃げてばかりいちゃダメだと思った。
「…今すぐは無理だけど…もう少し落ち着いたら、わたし…竜ちゃんと会って話してみる」
思い切ってそう伝えると、蘭ちゃんは「そっか」と言うだけで、他には何も言わなかった。きっとそれが、蘭ちゃんを優しいと思う理由なんだと思う。
「じゃあ何食いたい?」
前と何一つ変わらない態度で誘ってくれる蘭ちゃんを見て、心の中でありがとうと呟いた。