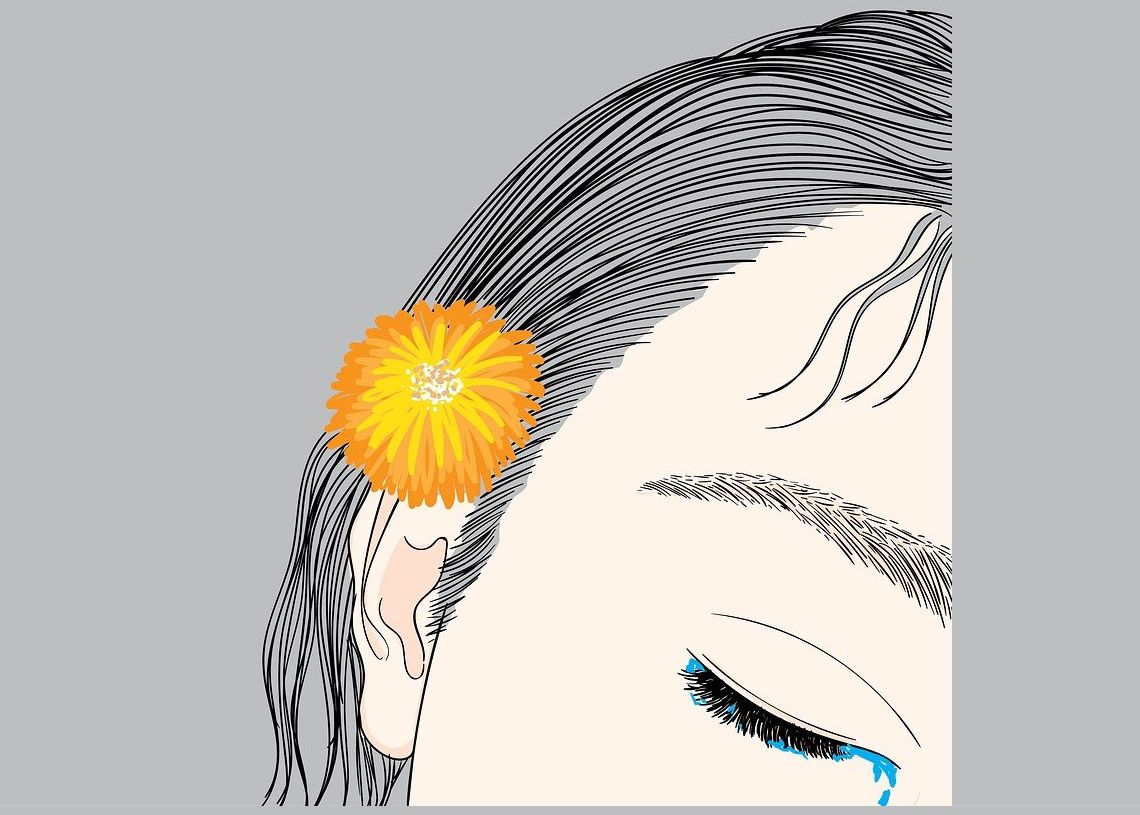
I knew
第二十四幕:堕ちる
苦しい。気持ち悪い。頭が割れる――。
自分の体なのに、意志とは無関係に襲ってくる症状に耐えかねて、腹の奥からこみ上げてくるものを一気に吐き出した。けど、もう胃液と酒しか出てこねえ。当たり前だ。食事が喉を通らなくなって、もう長いこと経つ。
――ツラいのは分かるけど酒ばっか飲むな。飯を食え、飯を。
兄貴はそう言うけど、そうじゃない。こうなってみて、心と体が直結してんのがよく分かる。重く痛みを伴う心に呼応するように、体が食事を受け付けなくなった。どうしても飯が喉を通らないから、唯一摂取できる水分を求めて、最終的にはそれが酒に代わっただけ。そしてこの吐き気は酒だけが原因じゃなく。自分のしてきた数々の裏切り行為が、今頃になって、自分への嫌悪感として襲ってくるせいだ。
「オレだって腹は減ってんだっつーの…」
すでに何も出なくなった口元を拭い、力の入らない手で水を流すと、オレは這うようにしてトイレを出た。どれだけ吐いたところで、スッキリすんのは体だけで、心は焼け付くように痛い。その痛みから解放されるのは泥酔して眠ってる時だけだ。
フラつく足をどうにか動かして立とうとしたけど、体を動かす反動で視界が一回転する。脳が溶けてんのかって思うくらい視界が揺れて、また少し気持ち悪くなってきた。
「ハァ…ムリ…」
部屋に戻るのを諦めて、玄関通路へ倒れたまま目を閉じる。頭が働く状態でもないから、自分がこれからどうすべきかなんて先のことすら考えられない。ただ一つ、揺るぐことのない思いだけは、今もオレに刻まれたまま。
「…に…会いてぇ…」
無意識にその名を口にした瞬間、彼女の笑顔が脳裏に浮かぶ。
――竜ちゃん。
記憶の中のは、優しい声でオレの名を呼んでくれる。笑顔を向けてくれる。その一つ一つが、どれだけ大切な瞬間だったのかを、彼女を失って改めて気づかされた。
最後に会ったあの夜のの顔を、忘れることが出来ない。こんなにも大切な存在をオレ自身が傷つけた。その罪の重みが、今のオレを痛めつけてくる。情けねえにもほどがあんだろ。はオレだけを見ててくれたのに、信じてくれてたのに、その想いを全て踏みにじってしまった。愛想尽かされんのは当然だ。
誰かオレを殺して欲しい――。
堕ちるとこまで堕ちたら、そんなバカな考えしか浮かばなくなった。
だけど、ふと視界に入った物を見て、また少しだけ浮上する感覚が襲う。玄関先に置かれたままの赤い傘。付き合い始めた頃、大事にしてた傘が壊れたって落ち込んでたから、オレが買ってにプレゼントしたものだ。たいして高くもねえのに、あいつは凄く喜んでくれたっけ。
――ありがとう、竜胆くん!大事に使う!あ、でもまた壊れるの嫌だから、台風の時は使えないなぁ。
――そしたら、また別の買ってやるって。
――それはダメだよ。これは初めて竜胆くんに買ってもらった物だから壊したくないの。
そんなことを言われたのは初めてで、凄く嬉しくて、純粋にいい子だなって思った。普段はそれほど化粧ッ気もない彼女が、オレと会う時は頑張ってお洒落をしてきてくれるのも嬉しかった。いつも着飾ってる子ばかり見てきたから、そういうのが当たり前だと思ってたけど、意外と女の子は大変なんだよと、気づかせてくれたのもだ。改めて兄貴を紹介するって時は、酷く緊張して借りてきた猫みたいに小さくなってたけど、結局、一緒に酒を飲んだらすぐに仲良くなってた。あの気難しい兄貴をあんなにメロメロにする子はそういるもんじゃない。そんなを本気で好きになったのはオレの方だった。
(まだ…使っててくれたのかよ…)
まるで新品のように綺麗な傘を見てたら、酔いも手伝ってか、情けないほど泣けてきた。
いや…オレは見てたはずだ。彼女があの傘を大事に使ってた姿を、何度も、何度も。なのに、いつからかプレゼントしたことも忘れて、ここへ引っ越して来た時に持って来た傘のことなんて、気にもとめてなかった。
――これは初めて竜胆くんに買ってもらった物だから壊したくないの。
その言葉通り、が今も大事に使ってくれてたんだという事実を、今更ながらに気づくなんて、オレは本当に大バカだ。
に会いたい――。
もう一度、心の底からそう思った。
その時、玄関ドアの方でピピっと解錠する電子音が聞こえた気がした。床に仰向けで倒れたまま、頭だけをそっちへ向ける。少し動かすだけで大波に揺られてるような不快さが襲うけど、霞んだ視界にドアがゆっくりと開くのが映って、もしかしたらが「竜ちゃん、ただいま!」なんていつもの笑顔で入ってくるんじゃないかと、バカな期待をしてしまった。
「…――」
「うお!」
オレが動いたからか、センサーライトが反応して廊下の明かりが点いた瞬間、中へ入って来た人物が大きな声を上げた。
「り、竜胆?こんなとこで寝てんじゃねえよ!死体かと思ってビックリしただろが!」
「…あり…き?」
倒れてるオレを恐々と覗き込んできたのはオレが望んでた人ではなく、呆れ顔で溜息を吐く兄貴だった。ってか、足で蹴るな、足で。
「ったく…生きてっかと思って様子見に来たら、また飲んでたのかよ。おら、立て」
「…わりぃ…動けらく…らった…」
舌も回らないオレの腕を掴んで自分の肩に回すと、兄貴は「動けなくなるまで飲むんじゃねえ」と文句を言いつつも、リビングまで運んでくれた。こういう時、兄貴はやっぱり兄貴だなって思う。本当ならバカな弟をぶん殴りたいだろうに、こうして世話を焼いてくれんだから。
「ほら、まずはこれ全部飲め」
オレをソファに座らせると、兄貴はボトルごと水を持ってきた。いや、2リットルは飲めねえよ、と言いったつもりだったけど、口が回ってたかまでは自信がない。酔いが酷くて視界がぼやけてるから分かりにくいが、きっと兄貴の顔は不機嫌そのものだろうことは、簡単に想像できる。
「ほら、グラス持って」
「ん…さんきゅ…」
「んで吐きたくなったら吐いて、また水飲め。繰り返してたら少しはマシになんだろ」
「…ん」
「あーそれと。今夜はもう酒飲むんじゃねえぞ」
兄貴はそう言ってから、テーブルの上にドサリと袋を置いた。半分も開かない目で確認すると、それは近所のスーパーのもので、中にはレトルト系の他にネギやら海苔だのが色々入ってる。オレに料理でも作れって言ってんのか?と、少しだけおかしくなった。昔からオレは料理なんてやったこともねぇし、兄貴もそれを知ってるのに。
けど予想外にも兄貴はそれを持ってキッチンへ行くと、「まずはお粥から食えってが言ってたぞ」と、サラリと言ってのけた。
「…え」
あまりに自然に名前を出すから、オレの聞き間違いかと思った。兄貴は何事もなかったかのように鍋に水を入れて、それをIHの上に置いている。電源の入るピっという音を聞きながら、オレは「いま…らんて?」と声をかけた。
「あー?何言ってっか分かんねぇけど、お粥はオレが用意してやっから、オマエはひたすら水飲んどけ、水を」
「い…いや…そう…じゃらくて…。ありき…今……って――」
「?ああ、今まで一緒だった」
「いや、そこオマケみてーり言うんじゃれえよっ」
シレっとした顔で応えた兄貴に、つい声を荒げる。兄貴は「はは、舌まわってねえじゃん」と呑気に笑いだすから、こっちもカチンときた。聞きたいことはあれど、確かにこれじゃまともに話も出来ねえ。まずは少しでも酔いをさますのに水を一気飲みして、ムカムカしてきたらトイレで吐くを繰り返す。その後も水で腹が膨れるくらい飲んだ頃、やっと酔いも呂律もマシになってきた。
「…おい、兄貴…」
「なあ、お湯湧いたけど、これブッ込めばいいんだっけ…」
オレの感情とは裏腹に、兄貴は呑気にお粥のレトルトパウチをひっくり返して作り方を見てる。あの兄貴がキッチンに立ってるなんてレアな光景も面白いが、それを笑う前に、オレは兄貴にのことを聞きたかった。
「それお湯で温めるだけで出来るやつな?それより兄貴…と会ってたってどういう――」
「ああ、このまま入れていいんだ。おっけ」
「って聞いてる?兄ちゃん!」
ブツブツ言いながらお粥のパウチを鍋に入れた兄貴は、「うるせーなぁ…」と言いつつ、やっとオレの方へ振り向いた。そのままキッチン台に寄り掛かると、窮屈そうなネクタイを緩めながら「からオマエに飯食わせろって言われたし、まずは優先しなきゃだろ」と、どや顔で言ってきた。どうやらと会ってたってのは嘘じゃないらしい。
「…どういうことだよ」
はオレと兄貴を着信拒否にしてたはずだ。なのに何で兄貴だけ?って思いがぐるぐる回ってしまう。その答えを欲しくて兄貴を睨むと、そこはあっさり教えてくれた。
「まあ…結論から言えば…今日、と会ってきた。例のケーコさんに頼んでと会えるようお膳立てしてもらったんだよ」
「…な…何でオレに言わねえの…?」
「オマエに話してどうなんだよ。一緒に行きたかったとでも?」
「ったりめえだろ…!」
ついカッとして怒鳴ったものの、兄貴は怒るでもなく「オマエがいたら来てくれねえじゃん」と肩をすくめてみせた。当然イラっとしたが、それはオレ自身のせいだから何も言い返せない。それに兄貴が勝手にそんな行動をとったのは、きっとオレの為でもある。まあ、半分は自分がに会いたかったんだろうけど。そこが分かるだけに内緒で会いに行ったことだけは腹が立つ。
そんな苛立ちが伝わったのか、兄貴は鍋の方をちらりと確認した後、オレに視線を戻した。意外にも真剣な顔だ。
「…ま、気になってんだろうから教えてやる。は…オマエにこっぴどく傷つけられても、ちゃんと自分の生活を送ってたよ」
「……言い方」
オレが何も言い返せないのをいいことに、兄貴は一番痛いところを突いてくる。でも怒る権利なんて、オレにはない。
「…元気だったのかよ」
一番気になったことを尋ねると、兄貴はふっと笑みを浮かべて首を振った。
「んなわけねぇだろ。無理に明るく振る舞うことも時折あったけど、無理してんのバレバレ。でもツラいからって仕事は休めねえから頑張ってんだろ?健気すぎて兄ちゃん泣けてきたわ…」
大げさに目頭を押さえて言う辺りが嘘くさいが、兄貴は本当にを心配してたから、そういう思いになったのはあながち間違ってないんだろう。不意にオレを睨むと「改めてオマエのしでかしたことに怒りが湧いたわ」と真顔で言われてしまった。これ以上、追い打ちかけんなよ、兄ちゃん。
「でもまあ…竜胆にも話さなきゃな。の気持ち。酒に溺れて可愛い弟がヘビードリンカーになる前に」
兄貴は溜息交じりでシンクに並ぶ空っぽの酒瓶をつまむと、それをダストボックスへと投げ捨てる。ガチャンっという耳障りな音が、やけに頭に響いた。
◀△▶
と一カ月ぶりに会って、色々話をした。案の定、は深く傷ついていて。彼女を傷つけた張本人の兄としては、どうしてやればいいのか分からなかった。当たり前だ。竜胆に初めて彼女が出来たということは、その彼女を慰めるなんて体験はオレも初めてだからだ。でも下手な慰めより、彼女がきっと一番疑問に思ってるであろう、愚弟の浮気の理由や原因を、正直に話すことが一番だと悟った。それを知らなきゃは前に進めない。心も動かない。
オレの説明を聞いて、がどう感じたのかまでは分からない。でも最初は頑なだった雰囲気が和らいで、気持ちが落ち着いた頃に竜胆と会うと約束してくれたのは、もしかしたら少しはオレの気持ちが届いたのかもしれない。竜胆の兄としては心底ホっとした。
その後に夕飯デートをした。の好きな鮨屋に連れて行って、そこでもまた前みたいに色々と話ができて、オレ的にはやっと少し安心することが出来た。後は時間が経てば、から竜胆に連絡がくるだろう。
そんな安堵感を抱いて、をタクシーに乗せた時だった。彼女が「蘭ちゃん、もし時間あるならちょっと買い物頼んでもいい?」と言ってきた。可愛いの頼みだと即OKすると、彼女は少し言いにくそうに「竜ちゃんにお粥か何か買ってって欲しいの」と言ってきた。
「何も食べてないんでしょ…?なら…まずは消化のいいお粥を無理やりでも食べさせて。お酒も飲むの止めて欲しい…」
泣きそうな顔でそんなことを言われたら、オレに断る理由はない。そもそもオレだって竜胆の状態は心配だった。でも、竜胆に怒ってるはずのから言われた時は、健気すぎてマジで抱きしめたくなった。自分を裏切って傷つけた弟を心配してくれるような女は、きっとこの子しかいない。の大切さを改めて実感した。出来ればオレが嫁にもらいたいくらいだ。まあ、天地がひっくり返っても、がオレを選ぶわけもねえし、竜胆の兄としては、やっぱり妹になって欲しいんだけど。
とにかく、オレは健気なのお願いを果たすべく、竜胆のマンション近くにあるスーパーにわざわざ寄って、言われた通り、お粥のレトルトを大量に買って、その足ですぐ竜胆の家にやって来た。
どうせ愚弟は酒を飲んで寝てんだろう。合鍵でドアを開ける前、そう思うことは思った。だけど、まさかトイレ前で寝てるとは思わねえよ。つい蹴っちまったわ。
「…で、今ここな」
混乱してる弟の為、簡単にここへ来るに至った経緯を話した。途中オレの主観も混ざった気もするが、そこは文句を言われる筋合いもない。そもそも可愛い弟の為に兄貴であるオレが動いて、との約束を取り付けてきたんだから。
竜胆はやっと少し酔いが醒めてきたようで、ちょいちょい話の合間に「ハァ?」だの「何でだよ」だのと突っ込みを入れてはきたが、今はポカンとした顔で、オレを見上げてる。まさかが「会って話す」と言ってくれるとは思ってなかったような顔だ。まあオレも今日そんなとこまで話が進むとは思ってなかったけどな。
「…え、マジで…がオレと会ってくれるって…?」
「ああ。でもいつになるか分かんねえぞ。気持ちが落ち着いたらってことだし」
「いや…十分…マジで…十分だわ、兄貴…」
少しは安心したのか、竜胆の顔に若干赤みが戻ってきた。さっきまでは色白通りこして死人みたいに青ざめてたし、オレとしてもホっとした。とりあえず温まったお粥を器に入れて、に教えてもらった通り、ネギだの海苔だのかけてやると、「これ食って寝ろ」と竜胆の前へ置く。竜胆も今度こそ、素直に頷いた。
「まあ、気持ち悪くなったら吐いてもいいから。まだまだあるし」
「…ん。でも…何か今なら食えそうな気がする…」
「そ?なら、ありがたく食えよ。オレが作ってやったんだから」
と偉そうに言ってみる。つかさず「温めてネギ切っただけじゃん」と突っ込まれたけど、それくらいの元気が出たならオレも安心だ。ただ食いながらも「でも自分だけ会いに行って一緒に飯食うんはずりい」と文句をたれるから、一発シバいたけど。
「アホか。ここでオレまでと縁切れたら、誰が仲介してくれんだよ」
「…まあ、そうだけど」
「そもそもが会いたくねえのはオマエだけで、オレはとばっちり受けただけじゃん」
「……結局、自分が会いたかったんだろ、それ」
「それもある。でも…オマエと仲直りして欲しいと思ってんのは本当だし、そこはいちいち嫉妬すんじゃねえ」
分かったか?と言えば、竜胆は渋々ながら頷いた。だいたい今、竜胆がに会ったとして、何をどうするつもりなのかと考える。謝っただけじゃ、の傷ついた心は戻らない。
「竜胆はさー。これからとどうしたいわけ?」
「…どうって…きちんとオレの口からも説明して、ちゃんと謝りたいと思ってるよ」
「で、出来れば前みたいに付き合いたい、と。そういうことかよ」
「当たり前だろ…。言うより難しいとは思うけど、オレはとこれからも一緒にいてえし…今更どの口が言うんだって思われるだろうけど、でもやっぱり大事だから、もう泣かすことも傷つけることもしない。絶対に」
竜胆は真剣な顔でそう言い切った。まあ、今の竜胆ならそう言うだろうというのも想定済みだ。でも、その思いを実現するには、きっと大きな問題が立ち塞がるのを、オレは知っていた。人の心はそう簡単なものじゃないからだ。特に男よりも女の方が、もっと複雑に出来てるってことを、きっと竜胆は知らない。
「オマエの気持ちは分かった。けど…とやり直すってことはそう簡単じゃねえ」
「…それは…分かってる」
「いや、分かってねえだろ」
竜胆はどういう意味だと顔をしかめたが、ここはハッキリ現実を突きつけた方がいいと思った。じゃなければ、この先、と再会したところで、必ず終わりがくる。
オレは向かいのソファに腰を下ろすと、どう説明しようか考えた。竜胆の場合、遠回しに言っても複雑な女心なんて分からないだろうから、ここはストレートに分かりやすくが一番かもしれない。
「例えば、オマエが頭下げて、反省もして、仮にそれがに伝わって、オマエのことを許してくれたとする。けどな。オマエがどんなに心を入れ替えたとしても、一度浮気したオマエをが心から信じてくれることはないと思っとけ」
「…あ?何でだよ…オレはホントにもう――」
「例えそうだとしても、だ。何気ない些細なことがキッカケで浮気を疑われる。オマエに全く身に覚えのないことでも、からすればオマエの言うことが嘘なのか本当なのかは分からないだろ。その場では信じると言ってくれたとしても、心の中じゃ嘘をつかれてるかもっていう不安を抱えることの方が多いはずだ」
「だから何で。してねえのに疑われるってことかよ。でもならきっと信じて――」
「前とは違うんだ、竜胆」
ハッキリ告げると、竜胆はハッとしたようにオレを見た。やっと現実が見えてきたらしい。
「一度裏切ったら、前と同じ信頼はすぐに取り戻せない。今回はやり直せたとしても、また騙されてるかもしれないとは常に怯えることになる。それだけのことを、オマエはにしたんだよ。好きな女に疑われながら一緒にいるのは想像以上にキツいはずだ。オマエはそれに耐えられんのか?」
竜胆は黙ってしまった。やっと自分の置かれた状況を理解したらしい。今の状態で現実を見せるのは酷な気もしたが、これを乗り越えないと二人は本当にダメになる。それでも好きだから、と一緒にいる地獄を選ぶか。耐えられそうにないからと別れを選ぶか。後は竜胆が決めることだ。しょせん、男女のことはなるようにしかならない。
「ま…今はまだ答えなんか出ねえだろうし、ゆっくり考えろ」
兄として、やれることは全てやった。竜胆の肩を軽く叩き、玄関へ向かう。
「ああ、それ。ちゃんと食えよ。が心配してくれるうちが花だからな」
買って来た食材を指して言うと、竜胆はふとオレを見た。その目にはさっきまでの陰りはなく、少しだけ光が戻ってきたように見える。
「兄貴…」
「ん?」
「……さんきゅ」
「おー」
ポツリと呟いた弟は、何かを決心したような顔でオレを見てる。オレはオレで、いつもの皮肉めいた笑みを浮かべて、竜胆の部屋を後にした。