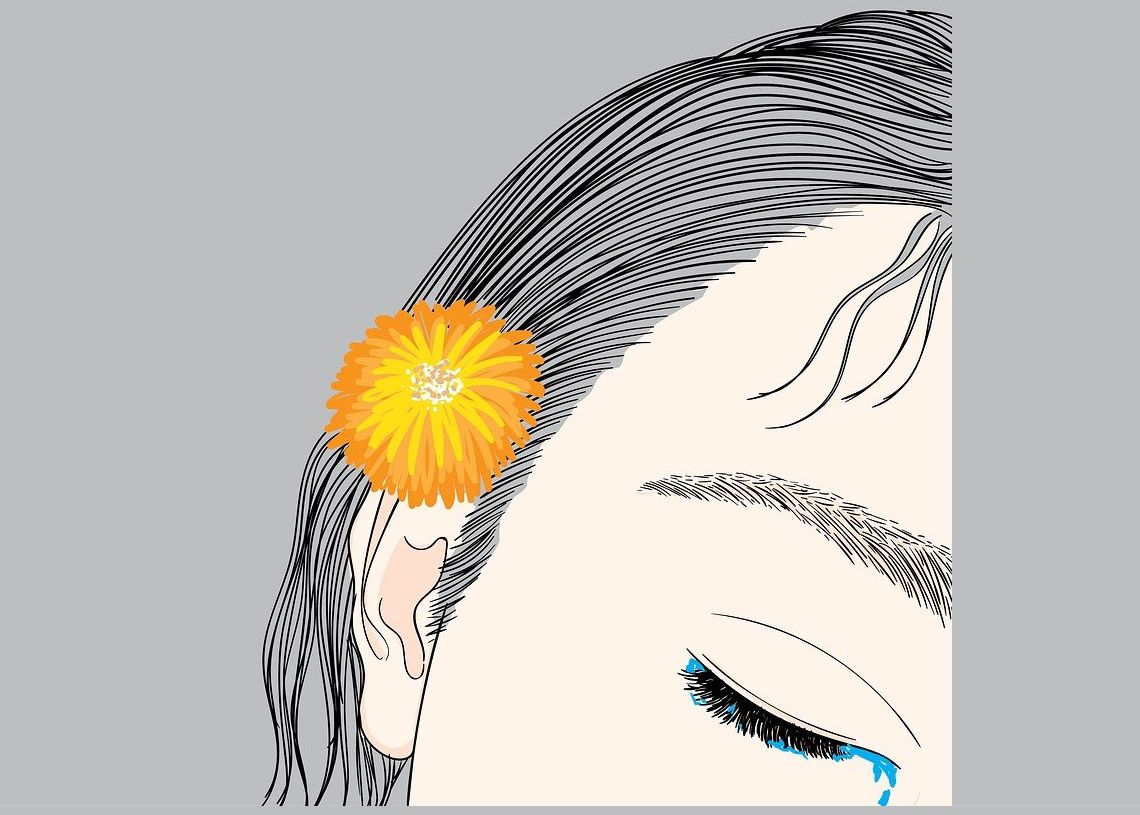
I knew
第二十五幕:浮上
蘭ちゃんと会って話をしたら、それまで鉛が入ってるみたいに重苦しかった心が、少しだけ楽になった。それは何度考えても分からなかった竜ちゃんの心の内が、ほんの少し見えてきたからだと思う。
わたしを好きだと言う裏で、他の女の子を抱いてたと知った時。何で?どうして?という言葉だけが頭の中で永遠に回っていたから、それがなくなった分、冷静に考えることができた。そしたら「が何もかも初めてだ」って言ってくれた時の竜ちゃんを思い出した。
初めてだからこそ、どうしたらいいのか分からない。その感覚はわたしも凄く理解できる。わたしも竜ちゃんと付き合って色んな"初めて"を知ったからだ。
でも会えない寂しさを、わたしは仕事の忙しさで中和できてたけど、竜ちゃんは違ったんだろう。そもそも職種が違う上に、自分の好きなように働ける環境の竜ちゃんにとっては、わたしと根本的に違ったんだ。
それに竜ちゃんの周りには常に華やかな女の子がいる。女のわたしには分からないけど、きっと男の人なら自然にそうなってしまうこともあるんだろうな、というところまでは理解できた。
それを許せるかどうかは別問題で人によっても違うだろうけど、でも、竜ちゃんが「に会えないのは寂しい」と言ってくるようになった時、わたしはもっと竜ちゃんのことを考えるべきだった。
竜ちゃんは優しいから。わたしより大人だから。そんな理由付けをして、最後には「きっと我慢してくれる」なんて。そんな甘えた思いがあったのは確かだ。
会えなくても、わたしは電話で話せるだけでも嬉しかったし、どこかで満足もしてた。会えないけど、竜ちゃんと心は繋がってると信じこんでいた。
少女漫画じゃあるまいし、なんて自分勝手な思い込みだったんだ…と愚かな自分が情けなくなった。
結局、わたしは恋に恋をしてただけの女だったんだ。そこに今更ながら気づいてしまった。
初めて本気で男の人を好きになって、ふわふわと甘い夢を見てるように、竜ちゃんのことを見てたんだろう。わたしと竜ちゃんのことは現実なのに、それを分かってるつもりでいただけ。ほんとは何ひとつ分かってなかった。
言葉にしなくちゃ自分の思いは伝わらない。どれだけ信頼しあってる相手だとしても、きちんと伝えようとしなきゃ、思いも考えも深いところまでは分かるはずもない。
超能力者じゃない限り、言わなくても分かってくれるなんてことは、現実の世界じゃありえない。人間なんだから当たり前だ。わたしにも心があるように、竜ちゃんにだって心はある。それをきちんと知ろうとしてなかったわたしも悪い。
わたしは竜ちゃんの行動に傷つけられたけど、きっと竜ちゃんもわたしのことで傷ついてた。わたし以上に寂しい思いを募らせてた。
それにもう一つ、気づいたことがある。会えないから寂しい、という思いはもちろん強かったのかもしれないけど、根本的なことを言えば、竜ちゃんの心の内は「わたしの気持ちがどこにあるか分からない」が正しいのかもしれない。
思い返せば、会う時間が少なかったことに加えて、わたしはずっと竜ちゃんに抱かれるのを拒んできた。竜ちゃんはわたしがいいと思ってくれるまで待つと言ってくれたけど、わたしもその言葉に甘えてしまったけど、本当は心のどこかで不安にさせてたはずだ。色んな要素が絡み合って、竜ちゃんはわたし以外の人に逃げたのかもしれない。
今頃になって気づくなんて本当にわたしは大バカ者だ。
でも、そこに気づいたことで、これまでの重苦しい感情が浄化するように消えていくのを感じた。絶対に許せないと、心の奥底で燻ってた怒りも、自分の非を認めたら少しずつ鎮火するように負の感情が消えていく。そしたら自然と涙が溢れてきた。
「…竜ちゃんに会いたい」
余計な感情を取っ払ったら、出てきたのはとてもシンプルな答えだった。こんな状況になって、初めて竜ちゃんのことを理解できたような気がする。
「お帰り、。どうだった?」
家に帰ると、ケーコさんが心配顔で出迎えてくれた。泣き顔になってたから「大丈夫?何かあった?」とケーコさんは慌ててたけど、彼女にも迷惑をかけてしまったから、気分が落ち着いた時に、きちんと蘭ちゃんから聞いた話や、改めて分かった自分の気持ちを、順序だてて話した。
話してるうちにまた泣けてきたけど、ケーコさんは黙って最後まで話を聞いてくれた。ケーコさんの淹れてくれたコーヒーの温かさが手から伝わってくるのも、今は凄くありがたい。
「…そっかぁ。そうだったんだね、ふたりは」
話し終えた後、ケーコさんはコーヒーを一口飲んで、小さく息を吐き出した。竜ちゃんと付き合いだした時も、付き合ってる最中も、ここまで深く踏み込んだ話を彼女にしたことはなく。だからなのか「竜胆くんとの間には何の問題もないと勝手に思ってたよ」と苦笑されてしまった。
「でも…言われてみれば、は忙しくて会えない日が続いてた時も、"竜ちゃんに会いたい!"とは愚痴ってたけど、言うほど悲壮感は漂ってなかったよね」
「だ、だって寂しいって思う時間すらないくらい仕事に追われてたし、それ以外は疲れて爆睡して、起きたらまた仕事って感じだったんだもん…」
「まあ…確かにねぇ。この業界の人なら誰でもそういう時期はあるから、そうなっちゃうか。それに比べて竜胆くんは自分の店ってこともあって、かなり自由な時間はとれる方だもんね。とは時間の流れ方が違ったんだろうなぁ、きっと」
「うん…だから竜ちゃんに寂しいって言われたりしても、きっとわたしは深く考えないで、ただそう言ってもらえたことを喜ぶくらいだった気がする。そういう時の竜ちゃんの気持ちを全然考えてあげれてなかったし、知ろうともしてなかった」
「…温度差ってやつか。難しいよね、確かに。相手の気持ちを全部理解するのは無理だし、みたいに目先の仕事に追われちゃうのも分かるからさ」
ケーコさんも同じくらい忙しい人だからか、自分も似たようなことあったなぁと呟いた。それが理由でそのうち恋人を作るのも面倒になったらしい。ケーコさんが夜な夜なクラブに行くのも、恋人は面倒だけど人恋しい時もあるからだと笑った。そんな話は初めて聞いたかもしれない。こんなに一緒にいたケーコさんの本音すら知らなかった自分にも驚く。そう伝えると、ケーコさんは「やっぱ人のことって意外と分かってないもんなのかもね」と笑った。
「でもは偉いね」
「え?どうして?」
「だって普通は浮気されたら相手や浮気相手に腹が立って、相手がどう感じてたなんて考えないでしょ。まして自分にも悪いとこがあったんじゃないか、なんて思わないって」
「…わたしも…蘭ちゃんと話すまではそうだったと思う。竜ちゃんのことが分からなくなって、信じてたのに何でこんな酷いこと平気で出来るのって…」
「それが普通だって」
「うん…でもね。そこから違ったって気づいたの。竜ちゃんのことが分からなくなったってとこからして違う」
「違う?」
「わたしは何も竜ちゃんのこと分かってなかったんだよ、最初から。確かに今回のことは凄くツラかったけど…でもそれを気づけたことだけは良かったって思って…」
わたしの話を聞いて、ケーコさんは「そっか」と、どこか安堵の表情を浮かべた。きっと彼女なりに心配してくれてたんだろう。わたしと竜ちゃんのことを、最初から見守っててくれた人だから。
「はほんとに竜胆くんのこと好きなのね。じゃなきゃ、そんな風に考えられないもん」
「…竜ちゃんのことは…あまり理解してあげられてなかったけど、でも…やっぱりわたしの知ってる竜ちゃんも本当だって、そこは信じてるから」
「お、何よ。もう惚気る?昨日までは"世界中の不幸をわたし背負ってますぅ"、みたいな顔してたクセに」
「え…わたし、そんな顔してました…?」
「してたよ~。文芸の編集長にの様子が変なんだが何か知らないかって聞かれたし」
「え、編集長に?」
まさか上司にまで気づかれてたとは思わず驚いてしまった。それくらい酷い顔をして働いてたんだろうな、とちょっと反省する。
「コーヒー淹れ直そっか」
「あ…ありがとう」
わたしが地味にへこんでいると、ケーコさんはカップを二つキッチンへ運んで、新たにコーヒーを注いでくれた。こんな風にふたりで話すのはあの夜以来だ。あの時は竜ちゃんと住んでたマンションを飛び出した後、心配して電話をくれたケーコさんが迎えに来てくれて、近くのホテルのラウンジで朝まで飲んでた。わたしは酷く取り乱して、感情的な言葉を吐きだすだけ吐き出した気がする。ケーコさんはそれを黙って聞いてくれてたっけ。
「あ、ねえ。そう言えば…あの子のこと蘭さんに訊いた?」
コーヒーを淹れ直して戻ってきたケーコさんが、ふと思い出したように言った。あの子、とはアシスタントとしてウチの出版社に潜り込んできた子のことだろう。彼女のことは蘭ちゃんからチラっと教えてもらった。
「うん…あの日…クラブから連れ出した後、蘭ちゃんもキレて、二度と竜胆に近づくなって言って追い返したって言ってた。それからはクラブにも顔を出してないって」
「そう…今はもう電話も繋がらないからどうしてるのかと思ったけど…何であんなことしたんだろ。竜胆くんに嫌われるだけじゃない?」
「…そう、だよね。でも…きっと許せなかったのかも。竜ちゃんに嫌われてもいいから、わたしのこと傷つけてやろうって思うくらい、あの子も傷ついたんだと思う」
何となくそう思って言ったら、ケーコさんは盛大に溜息を吐いた。ちょっと呆れ顔だ。
「…ほんとってお人よしすぎ。普通は彼氏の浮気相手の女のことなんか理解しようと思わないよ」
「わたしも昨日まであの子のやり方には腹が立ってたけど…でも竜ちゃんの色んなことに気づいたら、何となくあの子のやったことも、それなりの理由はあったんだろうなって思えてきて…」
「そうかもしれないけど、あの感じじゃ竜胆くんに遊ばれた腹いせに復讐しに来たってのが妥当じゃない?あ…!ごめん…デリカシーないこと言って…」
遊ばれた、と聞いてハッとした時、ケーコさんがすぐに気づいて謝ってきた。でも本当のことなんだろうから仕方ない。それに――。
「ううん…きっとそうなのかも。ただ…あの子は少なくとも竜ちゃんに対して本気だったから、あんなことしたんだよね、多分…」
「でも竜胆くんは遊びと割り切ってるような子しか手は出してなかったんでしょ?だったら、その後に何があったかは知らないけど、今更本気ですって言われても、さすがに困るでしょ、竜胆くんも」
「…うん…。でもね、わたしと一緒に住み始める前には、竜ちゃんもそういう子達と完全に縁は切ってたんだって蘭ちゃんが言ってたの。だから、あの子もその時に竜ちゃんから酷い縁切りされたのかなって。でも納得できなくて復讐してやろうって思ったのかもしれない」
「そうかもしれないけど、が気にすることじゃないって。もう終わったんだから」
「うん…そう、だね…」
そうは言ったものの、何となくあの子のことが気になっていた。あそこまでやるからには、きっと彼女も竜ちゃんのことで傷ついてたはずだ。あの子が本気だったのか、それか遊びでのことだったとしても、竜ちゃんは彼女を傷つけた。このままなかったことにするには、何となくスッキリしない。
「それで…竜胆くんと会って話す決心はできたの?」
あれこれ考えていると、ケーコさんがふと尋ねてきた。昨日までのわたしなら、まだ無理だと応えたかもしれない。でも今はちゃんと会って話がしたいと思った。
「うん。わたし…竜ちゃんと会って話してみる…」
心が決まったせいか、久しぶりに気持ちが軽く感じた。今は笑うことも苦じゃない。皮肉にも、竜ちゃんとこうなったことで、わたしも少しは大人になったのかもしれない。
ケーコさんはわたしの決心を聞くと、どこかホっとしたように、微笑んでくれた。
◀▽▶
兄貴がと会ってから一週間目の朝。だいぶ体も頭もスッキリしたオレは、前のようにクラブへ顔を出していた。に言われた通り、お粥を少しずつ食べ始めたら、次第に他の食事も摂れるようになったし、今は吐き気も襲ってこない。にオレと会う気があると分かっただけでこれなんだから、オレも相当ゲンキンなやつだと思う。
まだ、オレ達が今後どうなるか分からないのは同じだけど、少しの希望があるなら、オレはを諦めたくない。
――前とは違うんだ、竜胆。
兄貴にそう言われて、ガツンと頭を殴られたみたいにショックを受けた後、自分の置かれた状況を本当に理解した。兄貴の言ってたことは普通に考えれば当たり前のことだ。なのにオレはそこまで深く考えることもなく、安易な頭で前みたいに戻りたいとしか思ってなかった。をあんなに傷つけたのに、いい気なもんだと、また自分に腹が立ったし、調子のいいことを考えてしまったことも深く反省した。
ただ、どうしてもと別れるという選択肢は出て来なくて、疑われることを分かっていても、彼女を手放そうとは思えなかった。
きっと兄貴が言ってたように簡単なことじゃない。一度失った信頼は、やり直すことが出来ても、すぐには戻ってこないだろう。でも、何年かかったとしても、オレはとこれからも一緒にいたい。他の誰かじゃなく、がいい。ハッキリしてるのは、そんな思いだけだ。
夕べ、兄貴に電話して自分の気持ちを話したら『ほんとに大丈夫かよ』と心配されたけど、この先もしに疑われたとしても、自分の行動で示していくしかない、と覚悟を決めた、と告げた。
『一緒にいる地獄を選んだか…。ま、それでこそオレの弟だ』
兄貴はそんなことを言って笑った後、『頑張れよ』と言ってくれた。兄貴のそのひとことで、覚悟はより固まった気がする。
「あとはからの連絡を待つだけ…か」
手の中にあるスマホを見ながら溜息を吐く。本当はすぐにでも電話をかけて会いたいと言いたいとこだけど、まだ着信拒否になってたら、と思うと怖いし、向こうから連絡すると言ってるのに、こっちからするのは良くない気がして、そこは我慢してる最中だった。
あまり我慢するのは得意じゃないが、今後はもっと我慢することが増えてくだろうから、オレもここら辺で変わらないといけない。そう思った。
「あ、竜胆さん!ちょっと次のイベントのことで相談があるんスけど」
書類仕事に戻った時、部屋に店長が顔を出した。今まで休んでた分の仕事は溜まってるし、週末のイベントもあるから、今日は地味に忙しい。
「何?」
「いや、このゲストなんスけど、来る予定だったのが、事故起こして入院したらしいんスよ。だから代わりを誰にしようかと思って」
「マジ?ったく…こんなギリギリで事故ってんじゃねえよ…」
なんて理不尽なことを言いつつ、すぐに呼べるような人物を検討する。二日後という急な申し込みになるから、あまり有名なやつは無理だろう。と言って、あまり名の知られてないやつでも盛り下がってしまう為、程よく客を呼べるくらいの知名度があるのが望ましい。
「あ~…探しておくから、準備だけは進めとけ」
「分かりました。宜しくっス」
「おー」
パソコン画面と睨めっこをしつつ、店長に軽く手を上げて応えた。同時に、オレがいなかった間もちゃんと店を盛り上げてくれてたスタッフを、今度労ってやるか、と考える。こんな風に思えるようになったのは、きっとのおかげなんだろう。彼女はいつもオレ以上にスタッフのことを気にかけてくれていた。
「お…コイツのスケジュール空いてそう」
パソコンで相手のスケジュールをチェックしながら、連絡するだけしてみるか、とスマホへ手を伸ばす。だが手に取る前に、そのスマホから爆音が鳴り出した。と付き合いだしてからというもの、いつ電話が来ても取りこぼすことがないように、着信音を最大にしとくのがクセになっていたのを思い出す。こういう時に聞くと、やけにうるさく感じる。
「っせぇな…少し下げるか?」
ブツブツ言いながら、相手を確認もせず、パソコンから目を離すことなくスマホを手にする。耳に当てるだけで通話ができる設定は、なかなかに便利だ。
「もしもしー?」
どうせオレがちゃんと仕事をしてるか、兄貴が確認の為にかけてきたんだろう。そう思ってたのに――。
『……竜ちゃん…?』
通話口の向こうから、の消え入りそうな小さな声がオレの名を呼んだ。その不意打ちともいえる電話に、オレの脳が完全にフリーズした瞬間だった。