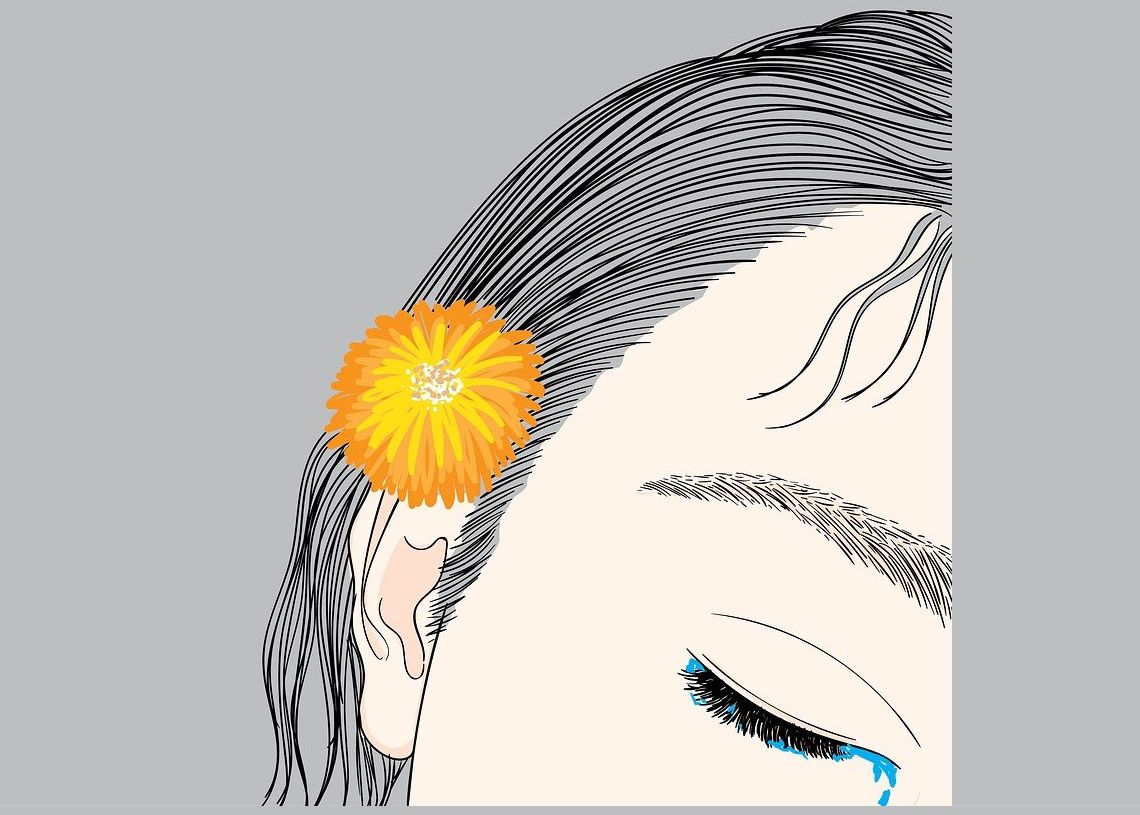
I knew
第二十六幕:くちづけ
その日は朝から大変だった。がいなくなってからというもの、我が家はマジで荒れ放題。洗濯物は溜まるわ、使った食器は洗わずキッチンにそのまま重ねてあるわ、あげく適当に買って来た弁当の入れ物だとか、飲み散らかしてたビールの空き缶、バーボンのボトルなどなど、その辺にわんさか放置されてた。それらを全て片付けるために、オレは一日がかりで大掃除を決行した。
先ずは手あたり次第、ゴミは分別しながらゴミ袋に突っ込んで、汚れた食器は洗浄機にブッ込む。脱ぎ散らかしたままの洗濯物は三回に分けて洗濯機へ突っ込んで回しっぱなし。
そこから今度は窓枠、棚、テレビ台、オーディオ機器、テーブルなどの埃を払っていく。その作業にはが愛用してたクイックルワイパーなる物を使ってみたけど、これがマジで便利だった。
そんで最後は部屋中、掃除機をかけてまわる。が良く言ってた「掃除は上から下が鉄則なんだよ、竜ちゃん」という言葉に倣って、その通りにやってみると、確かにそのやり方が一番理にかなってたのすげえ。前にが働く出版社から"掃除の達人"という本を出した主婦に教えてもらったそうだ。
生まれてこの方、これほど掃除に時間を割いたことはなかったけど、これを日々やってる主婦の人はマジで尊敬する。
「よし…綺麗だな」
次の日、最終チェックで全ての部屋をチェックしておく。昨日めちゃくちゃ頑張った甲斐もあり、あんなに荒れ放題で淀んで見えてた部屋たちが、今日は心なしかキラキラ光って見えるんだから、掃除するってほんと、めちゃくちゃ大事だと実感する。
ホっとしたところでキッチンへ行き、と選んだコーヒーメーカーで新しくコーヒーを淹れる。一緒に住み始めてから、彼女がハマりだした生クリームもちゃんと用意して。
そもそも――何で不精のオレが季節外れの大掃除をやったのかというと、話は一昨日まで遡る。
その日、仕事に復帰してたオレの元に、突然から電話がかかってきたのだ。兄貴からもオレと会うことを約束してくれたとは聞いていたものの、それが明日なのか、一週間後、はたまた半年以上も先なのかは全く分からなかったから、オレも長く見積もって半年くらいを想定して、彼女からの連絡を待つ覚悟をしてた。
だから一昨日、から急に連絡が来た時は心底ビックリして、だいぶ声が上ずってしまったように思う。
――竜ちゃん…元気?
最初に彼女はそう訊いてきたけど、オレは「あー」だの「うー」だのと全然言葉が出て来なくて、オレってマジでヘタレの情けない男だったんだな、と改めて落ち込んだ。でも少し気分も落ち着いてきた頃、彼女の方から「明後日、時間ある?」と切り出してきた。
――ちゃんと…話がしたい。
――…オレも。
そんな短い会話の後、どこで会おうかと尋ねると、は「家がいい」と言ったから、じゃあ明後日の午後三時と時間も決めて電話を切った。
ただ、その後もしばし放心して、今の電話はオレの妄想じゃないよな?なんて何度も着信履歴を確認してしまったのは兄貴にも内緒だ。
――え、マジで?、明後日家にくんの?!
ふと我に返った後は、すぐに兄貴に連絡を入れた。から電話が来たことを伝えると、さすがに兄貴も驚いてたけど、最後は良かったな、と言ってくれた。そして――。
――ああ、それとが来る前に部屋は全部片づけておけよー。今の汚部屋を見られたら、それこそ幻滅されっかもだし。
な~んて、最後の最後にそんな釘を刺されたオレは、自分の部屋の状態を思い出して一気に青ざめたというわけだ。まあ、おかげで早々に綺麗にすることが出来て、今はホっとしながらを待ってるものの、約束の時間が近づいてくるたび、胃の辺りがキリキリと痛みだした。
今日、どんな話になるのか想像もつかない。が許してくれる保証もない。最悪、今日、彼女と別れるなんてことになったら…と悪い方へ考え出すとキリがないけど、でも考えずにはいられなかった。
ただ、万が一に別れると言われても、すぐに引き下がるつもりはない。オレも変わっていかなきゃいけないんだ。兄貴の言ってた通り、前とは違うんだから。
そんなことを考えてると、気づけば約束の時間が迫っていた。オレは淹れたてのコーヒーをカップに注ぎながら、気持ちを落ち着かせるために一口飲む。
その時――突如として部屋のインターフォンが鳴った。まだ少し時間に余裕があると思っていたから、思わずカップを落としそうになるほど驚いた。無意識に壁時計へ視線を走らせると、時刻は午後二時五十分。まさか、と思いながらモニターを見れば、そこにはが俯いたまま立っているのが映っていた。久しぶりに見る彼女の姿に、胸の奥が一気に熱くなっていく。心はほんと正直だ。
がここに戻ってくる。何度も夢に見た光景だった。
それにしても、部屋の前までは上がって来てるのに、合鍵で入って来ない辺りが彼女らしい。
『竜ちゃん…?わたし…』
「うん。今、開けるから」
応答した後、すぐに玄関のキーも解錠すると、あの夜以来ぶりに会うがそこに立っていた。いらっしゃいと言うのも変だし、ここでコンニチハもないだろうから、どう声をかけようか迷う。でもそんな心配はの一言が打ち消してくれた。
「ご、ごめんね。早く着いちゃって…」
「いいって。オレも落ち着かなかったし」
なるべく自然に話しながら、ふたりでリビングに向かう。そこには四人掛けほどの大きなソファ。でもまだシングルソファは置いてないから、必然的に並んで座ることになった。その前に、と先ほど淹れたコーヒーをのカップに注いで、彼女の前へと置く。はそのカップを懐かしそうに指でなぞりながら、一言「ありがとう」と言った。
「あ、あとこれもな」
そう言って生クリームを絞った小皿を出すと、の顔が僅かに和らいだ。コーヒーのアレンジ動画を見て、これが一番美味しそうだったと、早速次の日買ってきたもので、コーヒーに浮かべると程よい甘さになるから美味いらしい。
「ありがと。覚えててくれたんだ」
「当たり前だろ」
そんな返しをしながら、今度こそソファに座る。でも前と違うのは、並んで座っていても彼女との間に確かな距離があることだ。
オレは――この距離を埋めることは出来るんだろうか。
「美味しい…」
カップを口に付け、彼女がホッとしたように息を吐き出すと、コーヒーから立ち上る湯気がふわりと室内へ流れて消えた。それを見つめていたオレは、意を決して彼女の方へ体を向ける。同時にきっちり頭も下げた。こんな風に人に頭を下げたことは一度もなく。きっと後にも先にも、彼女にだけだろう。
「…オレが全て悪かった」
「竜ちゃん…」
不意に謝罪したオレを見て、の声がかすかに震えたのが分かる。オレの腑抜けた心臓がキュっと縮こまったように苦しくなった。でもこんな痛みより、の心の方が痛かったはずだ。
「オレは…を傷つけた。何をどうしても過去は変えられねえけど…でもオレはもう二度と、オマエを裏切るつもりはないから」
顔を上げて、真っすぐ彼女を見つめる。今のオレは言葉でしか伝える術はないし、彼女にしてみれば全て嘘くさく聞こえるかもしれない。だけど、どんなにこの先に疑われようと、その傷に向き合っていく。これからの行動で示す。その気持ちは自分で思ってた以上に硬い。
そんな思いを言葉にしてへ伝えたところで、ふっと息が漏れた。知らず知らず、緊張していたらしい。
は何も言わずにオレの話を聞いてくれていた。時折、化粧っ気のない顔に、ほんの僅かながら驚きの表情が見え隠れしていたけど、今の気持ちを素直に、正直に伝えられたから、後悔はない。後は彼女の気持ちがどう動くのか、ただそれだけだった。
しばし沈黙が続く。まるで死刑宣告を待つ死刑囚みたいな気持ちで彼女の言葉を待っている間、オレの中の不安が何度も顔を覗かせたけど、決めるのはだ。オレからは何を言うでもなく、ひたすら彼女の答えが出るのを待っていた。
どれくらい経ったのか。互いのカップが空になった頃、不意にが口を開いた。
「竜ちゃんの…気持ちは分かった…」
「…ん」
「でもね…」
と、続いた言葉を聞いて、オレの心臓がざわりと音を立てる。でもね、という言葉は、さっきオレが言ったことへの拒否の意ともとれたからだ。でも彼女は真っすぐオレを見つめながら「わたしも竜ちゃんに謝らなきゃって…思ってたの」と言いだすから、驚いてしまった。何でが?と少し頭が混乱したまま彼女を見つめる。今回のことは全てオレが悪いし、彼女に非はない。なのにはどう言えばいいのか考えあぐねているように見えた。
「何で…が謝んだよ…悪いのは全部オレじゃん…」
沈黙が耐えられず、ついそんな言葉を口にすれば、は慌てたように首を振った。
「…何が違うんだよ」
「だって…わたしも竜ちゃんのこと全然理解出来てなかったし…会えない日が続いても、わたしは仕事に追われて竜ちゃんの気持ちとか全然考えてあげられてなかったから――」
「そんなの…のせいじゃねえじゃん…。そもそもオレがきちんと我慢してれば良かった話で、寂しいからって他の女をオマエの身代わりにしたこと自体、オレが悪かったんだよ…」
「そ、それはそうだけど…でも原因を作ったのはわたしだし、わたしも悪かったんだよ…。忙しさにかまけて竜ちゃんの寂しい思いとか全然、理解できてなかったし…」
「だから、それは――」
と言いかけて言葉を切った。何だ、これ。お互いが自分のせいだと言いあってる。も同じことを考えてたようだ。目が合った瞬間、ふたり同時に吹き出してしまった。
「もぉ~…、マジで頑固…」
「それ竜ちゃんもでしょ?」
じゃあ似た者同士だな、なんて言いながら、またふたりで笑い合う。こんな風にとまた笑える日がくるなんて、昨日までのオレは考えてもなかった。ただ不安で、許してもらえるのかどうかも分からなかったから。
一時、穏やかに話すことが出来たおかげか、さっきまでの焦燥感や恐怖は薄れて、きちんと冷静にと向き合うことが出来た。
「オレは…のこと好きになって自分が変わったつもりでいたけど、全然だったって気づいた。会えない時のどうしようもない気持ちとか、自分の中で消化すら出来なくて、だから一時だけが好きだって気持ちから逃げてただけなのかもしれない」
「…竜ちゃん…」
「でも…を失うかもしれないって思った時、心の底から変わりたいって思ったんだよ…。今さらって思われても、また一からちゃんとやり直したいって、今日に会って、改めてそう思った。だから…今のがどう思ってるのか聞かせて欲しい…。どんな気持ちでも、オレちゃんと聞くから」
今の思いがきちんと伝わるよう、一つ一つ言葉を選びながら伝える。正直、今の彼女がどう思ってるのか知るのは怖かったけど、それを聞かなきゃ一歩も前へ進めない。この先のふたりの未来を描くことさえ、出来ない。だから、の口からちゃんと聞きたかった。この先もオレの傍にいてくれるのか――否か。
はオレの話を聞いて、僅かに俯いてしまった。だけど、次に顔を上げた時、彼女の瞳には涙がいっぱい溢れていた。
「わ、わたし…竜ちゃんが他…他の子と…そういう関係になってたって知った時…死にたくなった…」
「…うん…」
「な…何も言い訳してくれなかったのも…か、悲しかった…ひっく…」
「…うん」
「だ…けど…だけどね…」
「うん」
「り、竜ちゃんに会えなかった…今日までの毎日が…い、一番…つらかっ…た…」
彼女は泣くのを堪えながら、一生懸命、自分の思いを言葉にして伝えてくれた。その一つ一つが、オレの心に沁みていく。でも最後の言葉を聞いた時、もオレと同じ思いを抱えてたんだと、気づいた。
「だ…から…わたし…」
竜ちゃんと別れたくない――。
が涙声で紡いでくれたその一言を聞いた時、もう我慢することが出来なかった。ふたりの間にあった距離を埋めたくて、の腕を引き寄せると、力いっぱい華奢な身体を抱きしめる。その瞬間、は小さな子供みたいに泣き出した。宥めるように背中を擦りながら、抱きしめる腕に力を入れる。
こんな彼女を見てしまったら、もう一生、他の女なんていらないと思った。腕の中の彼女だけが、オレの傍にいればそれでいいんだと、今は心からそう思う。
涙でグチャグチャになったの頬を指で拭うと、恥ずかしそうにオレを見上げてくる。何度拭いても涙が止まらないから、その濡れた頬にそっと口付けた。
そして――オレ達は久しぶりにキスを交わした。