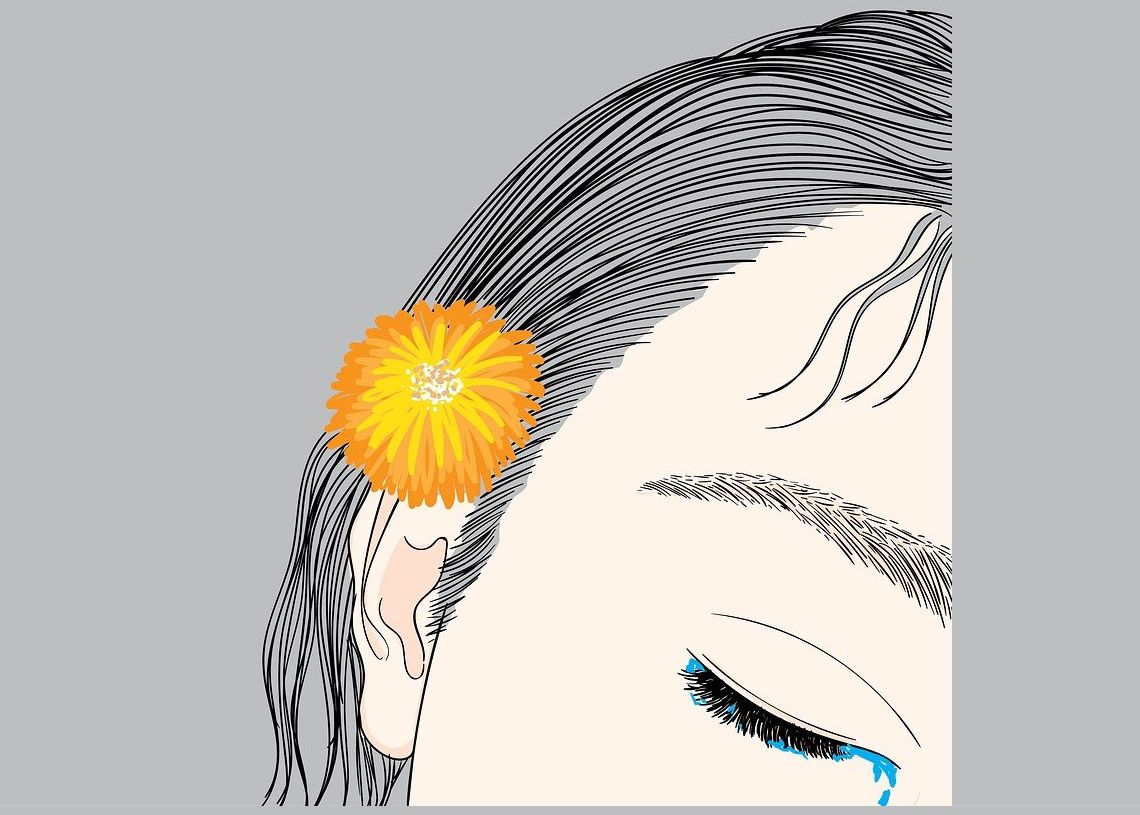
I knew
終焉:エキストラ1の女
――竜胆が女に刺された。
その嘘みたいな一報は、私が彼氏との海外旅行から帰ってきた時、遊び仲間から齎された。あの竜胆が?と死ぬほど驚いて、死ぬほど心配した。ちょっと海外に行ってる間に何でそんなことになってるのか。
とにかく竜胆の無事な姿を確かめたくて、それまで隣にいた彼氏なんかどうでもよくなった。何だかんだと言い訳をして別れたあと、すぐに竜胆が入院したという病院へ向かう。けど、そこには彼の仲間達が大勢出入りをしてたから、結局、彼の病室まで行くことは叶わなかった。
そこで私が愚かだったのは、竜胆を刺した女が例の彼女だと勘違いしたことだ。
きっと竜胆の浮気を知った普通の女が嫉妬に狂って心も病んで、竜胆を刺したんだろう。勝手にそう思い込んでいた。現に広まっていた噂では、相手の女はメンヘラのヤバい女だという話だったし、その女がまさか自分と同じような遊びの女だなんて一ミリも考えなかった。
それは竜胆が手を付けた女達が、私のように彼と割り切った関係を築いてると知ってたからだ。そんな女がバカみたいに嫉妬をして彼を刺す?あり得ない。
そんな愚かなことをするよりも、遊びでいいから彼に抱かれることを選ぶはずだ。だから刺したのは竜胆が付き合ってた出版社に勤めるOL。そう、思ってしまった。
竜胆の容体も分からず、一カ月ほど悶々と過ごしてたある日。クラブ仲間から竜胆の快気祝いをやるらしいとの情報をもらった。そこで退院したんだと心底ホっとして、安心したらやっぱり竜胆に会いたくなった。きっと長いこと入院してたんだから彼も欲求不満のはず、という下心もあった。そういう時の竜胆は絶対に私を拒んだりしない。そう思った私は、快気祝いをする日時を調べてもらって、その日の夜、久しぶりにクラブへと顔をだした。
「あれー久しぶりじゃん。何してたのー?」
「彼氏と旅行にね」
顔見知りの男とそんな他愛もない会話を交わしながら、私はすぐに竜胆が来てるかどうかを店長の健太郎に確認した。でも彼は私が来たことにあまりいい顔をせず、詳しいことも教えてくれなかった。きっとあんな事件があったあとだしピリピリしてるんだろう。そう思った私は、トイレに行くフリをして何度かVIPルームへ上がる階段の前をウロウロしていた。でもその時、ホールの方から賑やかな声が聞こえてきて、私は咄嗟にトイレに飛び込んだ。かすかに竜胆や蘭さんの声が聞こえた気がしたからだ。もしかしたら、と私の直感が働く。数人ほどの声が入り混じった会話に聞き耳を立てつつ、トイレからコッソリ通路の方を伺っていた。
「ってか竜胆、マジで回復速くね?」
「まあ、が看病してくれたし」
「げー早速惚気かよ、オマエ。ってか、よくコイツのこと許す気になったねー?ちゃん」
「え、あ、えっと…」
「だろー?オレもビビったわ」
「ら、蘭ちゃん…」
「兄貴!ってかイザナくんも余計な話をにしないで。マジで思い出させないで」
その会話を聞いて私の鼓動がどくんと跳ねた。その団体は思った通り竜胆や蘭さん達で、彼らはトイレの前を通ってVIPルームのある二階へ上がっていく。
ただ、久しぶりの竜胆の声にドキドキしたのもつかの間、という名前が出たところで、一気に冷や水をかけられたかと思うくらいに、熱が引いていく。その名前には聞き覚えがあったからだ。
「…まさか…あの時、電話で話してた…本命の彼女…?」
私の脳裏に数か月前の記憶が蘇る。あの時も竜胆はその名前を口にした。聞いたこともない優しい音で、その名前を呼んだのだ。
そこに気づいた時、思わず通路を覗き込んでいた。見覚えのある長身の後ろ姿は蘭さんと竜胆だ。そして知らない男がふたり。その中に小柄な女が交じっていた。
綺麗な長い髪を揺らし、竜胆と手を繋いでいる、見たこともない女が。
(あの女が……?あんな色気もクソもないような女が竜胆の本命…?嘘でしょ?)
初めて竜胆の彼女を見たショックの他に、てっきり竜胆を刺して捕まったと思っていた女――が犯人じゃなかったという現実に、私は打ちのめされていた。
もしあの女が犯人なら、竜胆はまたフリーに戻ったはず、という淡い夢が一瞬で消え去ったからだ。
竜胆がフリーなら、まだ私にも希望がある。そう思ったのに。
どれくらい、そこにいたのか。不意にトイレの中へ誰かが入ってきて、私とぶつかりそうになった。
「あ、すみません…」
そう言って頭を下げてきた女は、すぐに奥の個室へと入って行く。でも私はその女見た瞬間、思わず息を呑んでしまった。顔を正面から見たのは初めてだけど、すぐに竜胆の彼女だと気づく。幼い顔立ちをした女はナチュラルメイクしか施してない、本当にその辺にいるような普通の女だった。なのに今まで会った竜胆の遊び相手のどの女よりも、人を引き付けるような可愛らしい雰囲気があった。それは女なら誰もが憧れる、好きな男から愛されることで得られる、満ち足りた表情から滲み出たものなのかもしれない。
敵わない――。
そこに気づいた時、今度こそ心の底から打ちのめされた気分だった。
その時、という女が洗面台の方へ戻ってきた。つい、その満ち足りた幸せそうな顔を凝視してしまう。は私がまだ同じ場所に立ってるのを不審に思ったのか、怪訝そうな顔で手を洗っている。その際、持って来たポーチからグロスを出して塗り直し始めたけど、驚くことに彼女はたったそれだけのメイク直しで済ませて、トイレから足早に出て行ってしまった。私の中であり得ない、という言葉が浮かぶ。
「何よ、アレ…」
私なら竜胆に会う前は念入りにメイクを直す。少しでも綺麗に思われたいからだ。でもあの女はちょっとグロスを塗っただけで容易く彼の元へ戻れるんだと驚いた。それが本命の余裕のようにも思えて、圧倒的な敗北感に打ちのめされる。
その時だった。通路の方から「おい」という低い声がして、心臓が大きな音を立てた。その艶のある低音は嫌というほど知っている。
「…蘭さん」
通路に出ると、そこには案の定、竜胆の兄の蘭さんが怖い顔をして立っていた。私を見た瞬間、何かを悟ったらしい。何やってんの?と迫力のある目つきで私を見下ろして来た。
「竜胆に会いに来た?」
「……退院祝いを言いに」
私は蘭さんが苦手だった。この男は竜胆ほど甘くはない。女の下心なんてとっくに見抜かれてるだろう。現に私の言い訳めいた理由を聞いて「竜胆には二度と会いに来るな」と言ってきた。まるで死刑宣告された気分だ。なら、せめて一目だけでも、と思うことすら許されないんだろう。
でも、踵を翻そうとした時、蘭さんは「ああ、やっぱちょっと待って、竜胆呼ぶわ」とスマホで電話をかけ出した。相手は竜胆。ちょっとトイレの前に来いと言っている。驚いて振り返ると、電話を切った蘭さんは「オマエも竜胆と遊んでたクチだろ?本気だったわけ」と訊いてきた。何でそんなこと訊くんだろう。そう思っているところへ、竜胆が歩いてきた。久しぶりに見る彼は、あの子と同じような満ち足りた顔をしていた。私と会ってた頃のような、どこか寂しげで常にジレンマを抱えていた彼は、もうどこにもいなかった。
「久しぶりだな」
「…うん」
「彼氏は?上手くやってんの」
「……まあ」
「そっか」
竜胆はどこかホっとしたような顔を見せた。こんな彼は初めて見る。ちょっと驚いている私に、竜胆は「オマエにも悪いことしたな」と驚く台詞を吐いてきた。どういうつもりだと顔を上げれば、竜胆は一つ聞きたいんだけど、と前置きをしたあと「お互い遊びだと思って会ってたけどさ。オマエはどうだった?」と訊いてくる。何でそんなこと?と思ったけど、私は前と同じように嘘をついた。
「もちろん遊びに決まってるでしょ。何でそんなこと訊くの?」
「いや…万が一…オマエが本気だったつーなら…悪いことしたなと思っただけ。でもまあ…オマエは彼氏いるしな」
どこかホっとしたように笑う竜胆を見て、違うと言いたかった。でも今更そんな本心を見せるわけにはいかない。竜胆の後ろで蘭さんが壁に寄り掛かったまま、ジっとこっちを観察するように見てるのも怖かった。
「まあ、今後はもうオマエともふたりで会う気はねえし、そのこと言いたかっただけ。オマエも浮気なんてしねえで彼氏と仲良くしろよ」
「…何それ。竜胆に言われたくないんですけど」
「それな」
私の言葉に竜胆が笑った。その穏やかな笑顔を見た時、私の心臓が抉られたのかと思うほどに悲鳴を上げた。彼をこんな顔にしたのは、あの女に違いない。あの子は竜胆が抱えていたジレンマや、暗澹とした思いを、見事に消し去ったようだ。また敗北感に襲われて、竜胆を思う心が暗く沈んでいく。
「…怪我は。もう大丈夫なの?」
「ああ、もうバッチリ。心配してきてくれたんか」
「別に。旅行から帰ってきたから久しぶりに踊りに来ただけ」
「そ?じゃあ、まあ楽しんでってよ。オレは彼女と一緒だから今日は接客できねーけど」
「別にいいよ。じゃあ…ね。竜胆」
「おー。じゃーな」
竜胆はまるでただの知り合いに挨拶するように手を上げて戻って行く。その背中を見つめていたら、私の心は完全に折れてしまったようだ。もう二度と、竜胆は私を抱いてくれないだろう。そう、気づいてしまったから。
「分かった?竜胆はもうオマエのような嘘つき女に手を出すことはないから」
その場に残っていた蘭さんが、怒鳴るでもなく、ただ無機質な声でそんな言葉をぶつけてくる。分かってる。私は嘘つきだ。蘭さんはとっくに見抜いてたんだろう。竜胆さえ気づかなかった、私の本心に。
「そういうことなんで、二度と竜胆にかまうな。それが守れるならここに来るくらいは許してやるよ」
蘭さんはその言葉を最後に私の前からいなくなった。けれども、私はもう二度とこの店に来ることはない。竜胆と触れあえないなら来る意味がないからだ。
結局、私は主役になりそこねた愚かな女の一人に過ぎなかったというわけだ。
私はいつも誰かの脇役だった。
叶うことなら好きな男の隣で主役になってみたかった。
もう彼の隣で主役になれる日は、永遠に訪れない。
竜胆にとって、私は今も昔も、エキストラのひとりに過ぎないのだから。