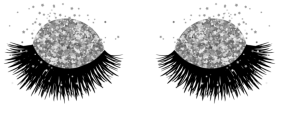「マイキーに彼女ぉ?いねぇよ。そんなもん」
そう教えてくれたのは彼の幼馴染の明司春千夜だ。春千夜と私は一年の時、同じクラスで席も隣だったから一番聞きやすかった。
中二の夏休み直前。もし佐野くんに彼女がいないなら思い切って告白しようと思ってた。
給食タイムのこの時間が最も声をかけやすかったのは、春千夜が食べ終わった後、いつも机に突っ伏して教室で昼寝をしてるからだ。
春千夜は私の質問に答えたあとで体を起こすと、大あくびをしながらガシガシと頭を掻いて怪訝そうに眉根を寄せた。何でそんなこと聞くんだよ、的な顔だ。というか案の定「何でんなこと聞くわけ」と今度は私が質問をされてしまった。この場合の答えも一応、用意してある。
「と、友達から聞いてみてって頼まれて」
「ふーん。マイキーに彼女いるかどうかって?何、オマエの友達はマイキーのこと好きなのかよ」
「さ、さあ?どうなんだろね」
私は微妙に学区違いで、佐野くん達とは別の小学校だった。だけどこの中学に入って彼のことを知った時は、あまりに私の好みドストライクで腰を抜かしそうになったくらいの衝撃を受けたのだ。
どの女子よりも色白で肌はきめ細やかだし、さらさらの髪を綺麗な金髪にしてて、佐野くんのあの端正な顔には良く似合ってる。あんなの誰だって一目惚れするはずだ。
それに地元では"無敵のマイキー"なんて通り名まであるくらい、ケンカに強いらしい。
一年の頃、東京卍會というチームを佐野くんが作ったのは噂で聞いて知ってるし、それがギャップ萌えと言わずして何と言おう。あのヤンチャっぽさが、またいいのだ。
二年になって同じクラスになったのは運命のような気がしていた。
「どーせマイキーの無敵だっつー噂とか聞いて興味持ったミーハーだろ。女ってマジでチョロい」
「何よ、春千夜。女って一括りにしないでくれる?」
ちょっと痛いところを突かれて言い返す。この場合、架空の友達に向けてのことだろうけど。
でも春千夜の言う通り、確かに自分がチョロいのは自覚してる。
顔だけで言えば、この明司春千夜もかなりのイケメンだけど、性格がキツいのがマイナスだと思う。後輩や同級生、先輩にまでキャーキャー言われてるからって調子に乗ってるし。
モテるという枠だけで言えば、きっと佐野くんより春千夜の方がモテてるんだろう。でも私は断然佐野くん派なのだ。
(でもそっか。佐野くん彼女いないんだー。意外かも)
内心驚きつつ、だったら誰かにとられる前に告白をしちゃおうか、と考え始めた時、春千夜が小さく鼻で笑ったのが聞こえた。
「でもまあ、マイキーには確かに彼女いねえけど、好きになっても無駄だからやめとけって言っとけよ。そのお友達に」
「……え?無駄って……何で?」
どきりとしながら訪ねると、春千夜は再び机に上半身を突っ伏してぎろりとした鋭い目で私を見上げてきた。さすが地元でも有名な不良だ。迫力はある。佐野くんの次に、だけど。
「マイキーは幼馴染にベッタリだから、女作る暇ねえと思うし」
「え、幼馴染ってことは……アンタもそうなの?」
「まあなー。はオレや場地、マイキーの幼馴染で、この学校の三年」
「えっ?年上?」
「年上って言ってもは鈍臭いし、何か妹みたいなやつだけどな」
春千夜はそれだけ言うと、また欠伸をしながら「もういいだろ」と昼寝を再開した。
私は小さく「ありがと」とだけ声をかけて、ふらふらと教室を出る。すでに脳内は「」という名前がぐるぐる回っていた。
学校内で佐野くんに近づく女子は一通りチェックしてたけど、三年は盲点だった。そもそも佐野くんは女子から話しかけられても素っ気ない態度で返すことの方が多かったし、普段は春千夜を初めとした仲のいい男子と一緒にいることが多い。
特に中学生のクセに頭にタトゥーを入れてる龍宮寺くんとは仲がいいのか、しょっちゅう二人でいるのを見かける。
でもその中に三年の女の子なんていた記憶はない。いたのかもしれないけど、少なくとも私は見かけたことがなかった。
「どんな人なんだろ……」
春千夜に聞けば一発なんだろうけど、これ以上詮索したら佐野くんを好きなのが私だとバレてしまいそうで聞けなかった。
佐野くんにベッタリされてるなんて、その幼馴染の先輩が羨ましい。
「でも幼馴染なんだし、ベッタリだからって別に彼女なわけじゃない……」
一瞬、失恋したかのような気分になったけど、一旦冷静になって考えた結果、そういう結論に達した。そもそも二人が特別な関係だったら春千夜がそう言うはずだ。でもアイツは「彼女作る暇がない」と言っただけで二人がそう言う関係とは言わなかった。
(そうよ。別に心配することない)
自分にそう言い聞かせて納得させると少しは気分も軽くなってくる。
それに佐野くんと私は同じクラスだし、普段からよく話しかけてるから他の子より仲がいいという自負もあった。佐野くんは嫌な顔もせず私と楽しそうに話してくれるし、きっと告白しても大丈夫、と何度も言い聞かせながら自分の教室へ戻った。
そして終業式当日。この日に告白をすると決めていた。
今日告白して、佐野くんの彼女になって、長い夏休みは佐野くんといっぱい会う。そんな野望を胸に教室へ向かうと、珍しく佐野くんの方が早く来ていた。
「お、おはよう、佐野くん」
「……おー。おはよー」
佐野くんの席は私の後ろ。いつものように声をかけて椅子に座る。佐野くんは眠たいのか、欠伸を連発していた。可愛すぎる。伸びてきた前髪を縛って後ろへ流してる髪型も可愛い。不良なのに可愛いってところが、ポイント高すぎるのだ。
前に「自分でやってるの?」と聞いたら「ケンチンにやってもらう」と教えてくれた。ケンチンとは龍宮寺くんのことで、あんないかつい顔をして佐野くんの髪を縛ってあげてるのか、と想像してちょっとだけ笑ってしまったのは内緒だ。
「佐野くん寝不足?」
「んあ?あー……夕べチームの奴らとバイクで流してたから寝不足かも……」
「へえ、楽しそうだね」
「うん、楽しかった。春千夜がバカとモメて特服が水浸しになったけど」
「え、何で?」
よくよく聞けば、いつものメンバーでバイクを走らせてたら、他のチームの男達が幅寄せして煽ってきたらしい。短気な春千夜がその挑発に乗ってしまったようだった。凄く分かる気がして笑ったけど。春千夜の短気は同じクラスの時に何度も目撃したから分かりすぎる。
それで近くの公園でやり合うことになった佐野くん達は殴り合いの最中、その公園にあった噴水に敵を蹴り飛ばしたり、突っ込んだりしたそうだ。結果、全員がびしょ濡れになったと佐野くんは楽しげに笑った。
ケンカをしたわりに、佐野くんの顏には傷一つないから、勝敗の結果だけは聞かなくても分かる。やっぱり佐野くんは無敵らしい。話を聞いてるだけでドキドキして、また惚れ直した。
もし佐野くんと付き合えたら、彼のバイクに乗せて欲しい、なんてことまで妄想してしまう。もしケンカに巻き込まれたとしても、佐野くんは絶対に守ってくれるはずだ。どうしよう。そんなことになったら惚れすぎちゃって処女を捧げたくなってしまうかも。いや、佐野くんに是非もらって欲しい、なんてことまで飛躍して考える。
もしそんなことになったら彼の黒い瞳に見つめられるだけで蕩けてしまうかもしれない。
あーもう、絶対この瞳に映りたい。そして佐野くんに好きになってもらいたい。
半分目をハートにしながら佐野くんの話を聞いていると、彼は「でもオマエ、変な奴だよな」と苦笑気味に言ってきた。
「え、変って何で?」
「ん-?だってオレらのケンカの話、めちゃめちゃ食いついてるし。フツー女って嫌な顔すんじゃん」
「え……そ、そうかな……」
それは佐野くんだからであって、決してケンカの話が好きなわけじゃない。もしその話を春千夜から聞かされたとしても「あっそ」で終わらせる自信がある。
なんて考えてると、佐野くんはふっと笑みを浮かべて「アイツもオマエみたいに寛大だったらなー」とひとこと呟いた。
「え……アイツって?」
佐野くんがあまりに優しい笑みを浮かべるから、ついドキっとして聞いてしまった。
でも「ああ、オレの――」と佐野くんが何かを言いかけた時。
「まんじろー!いるー?」
唐突に聞こえた女の子の声に、いち早く反応して弾かれたように立ち上がったのは佐野くんだった。
「!どーした?」
「……っ?」
今までとは違う弾んだ声で応えた佐野くんは、嬉々とした表情を浮かべて廊下の方へ歩いて行く。それをゆっくり視線で追っていけば、そこには一人の女子生徒がいて。彼女は佐野くんに笑顔で手を振っていた。
長い髪をポニテにした、すんごく可愛らしい小柄な女の子。一年でも同学年でもない。雰囲気で分かる。彼女は三年生だ。
佐野くんは今の今まで話していた私の存在なんか忘れたかのように、彼女の方へ足早に歩いて行く。
その姿を見た時、この人が「」という幼馴染なんだと気づいた。同時に、私なんかが告白したところで、秒でフラれるのがオチだという、最悪な結果を見せられた気持ちになった。
「万次郎、学校終わったら暇でしょ?ちょっと109に付き合ってー」
「えー何で」
「ほらぁ、この前話した――」
そんな会話をしながら彼女は慣れた動作で佐野くんの腕をぎゅっと掴む。そして彼女が話すたび、佐野くんが身を屈めて耳を口元へ寄せてあげている。その光景を見る限り、二人は幼馴染というより、彼氏彼女そのものだ。
という彼女を見つめる佐野くんの黒い瞳が、見たこともないくらいに優しい。
「あーそうだった。おっけー。じゃあ終わったらケンチン誘って行こうぜ」
「ありがとー万次郎。助かるー」
佐野くんが彼女の頭へぽんぽんと手を乗せる仕草はとても自然で、彼女が佐野くんに甘える姿も凄く自然だ。いつも二人はこんな感じなんだろうなと思ってしまった。
「じゃあ、あとでな」
そう言いながらさんという人に手を振る佐野くんの笑顔は、どう見たって彼女に恋をしている。彼の瞳には一ミリも入る余地がないのだと理解した。
学ランをなびかせ、ポケットに両手を突っ込んで歩いて来る佐野くんの顔には、さっきまでの眠そうな表情は見られない。鼻歌でも歌いそうなほど機嫌がいいみたいだ。
自分の席に座った佐野くんは徐にケータイを取り出して電話をかけ始めた。ケンチン、と言う名前が出たから相手は龍宮寺くんらしい。
「今日の帰り、ケンチンも付き合ってよ。そーそー。エマに買ってやりたいもんがあるんだって。がケンチンに選んでやって欲しいって言ってっからさ」
彼女が来た時と同様、佐野くんの声は弾んでいた。夏休みを前に受かれている子供みたいに、目を輝かせているに違いない。
上履きの踵を踏んだ足元がそわそわしてるのが伝わってくる。そういう些細な動作を見ているだけで放課後が待ち遠しいんだと分かってしまうし、彼がどういう夏休みを過ごすのかまで想像出来てしまった。
佐野万次郎の瞳には彼女――さんしか映ってない。
結局、告白したところで私は一生、彼の美しい瞳に映ることは出来ないのだと悟った。
――好きになっても無駄だからやめとけ。
佐野くんの明るい話し声を聞きながら、ふと春千夜に言われた言葉が脳裏を掠めていく。
中二の夏。私は初めての失恋を経験していた。